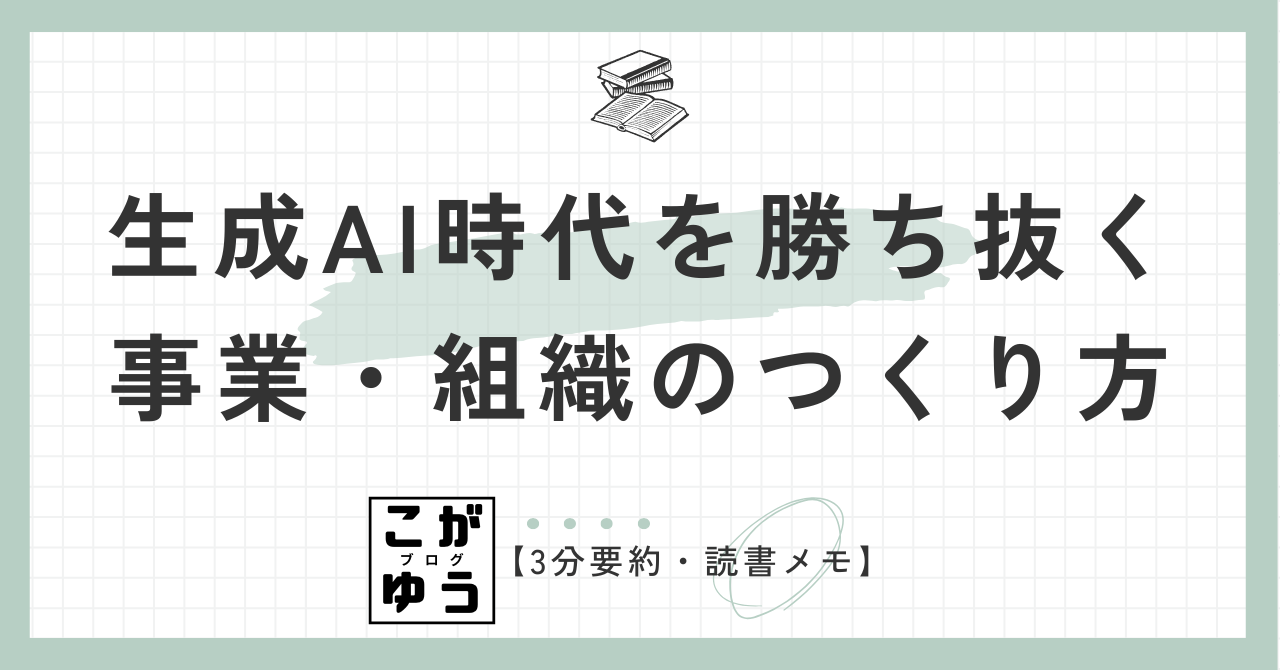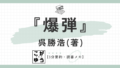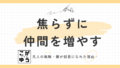ご覧頂き誠にありがとうございます。
今回は『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』についてレビューと要約の記事となります。
『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』徹底解説:AIネイティブへの進化論
1. 著者の紹介
梶谷健人氏は、生成AIのビジネス活用を専門とするコンサルタント、講演家、そして本書の著者です。新規事業開発やサービスグロースのアドバイザーとして長年の経験を持ち、自身もXR/メタバース領域のスタートアップであるMESONを約5年間経営してきました。現在は、テレビ東京やAI領域の上場企業エクサウィザーズ社をはじめとする10社以上の企業に顧問として関わり、生成AIを活用した企業成長を支援しています。豊富な実務経験と生成AI領域の深い知見を組み合わせることで、本書は数多あるAI関連書籍の中でもユニークな一冊となっています。
2. 本書の概要
『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』は、「生成AIがスゴい」という表層的な情報に留まらず、経営層や事業リーダーが本当に必要としている「生成AIを活用して事業・組織をどう成長させるか」という問いに真正面から答える実践的な指南書です。「事業づくり」「サービスづくり」「組織づくり」という3つのテーマを軸に、「現在」と「未来」という時間軸で考察を展開。具体的なフレームワーク、事例、未来予測、プロンプトテクニック、組織変革のステップなど、生成AI時代を勝ち抜くための具体的な方法論が満載です。特に、「意義」と「意味」のデザイン、そして「生成AIネイティブ」な組織への変革という概念が重要な柱となっています。
3. 本書の要約
本書は、7つの章と巻末特典で構成されており、生成AIのビジネス活用における重要な側面を網羅的に解説しています。
第1章:生成AIがもたらす変革の全体像
生成AIの現状の勢い、社会・ビジネスへの影響、各領域における最新の活用事例など、生成AIがもたらす変革の全体像を明らかにします。
第2章:成功する生成AI事業・プロダクトのつくり方
生成AI領域で成功するための鍵となる「意義」と「意味」のデザインについて解説。独自のメソッドやフレームワークに加え、生成AIで何ができるかを7つに分類して分かりやすく解説します。
- 「意義」と「意味」のデザイン:
- 意義: 顧客が本当に困っている課題を解決すること。Javelin Boardなどのフレームワークを活用し、顧客の真の課題を特定。
- 意味: 生成AIを活用する必然性。生成AIの7つの本質的な価値(①コンテンツの創造コスト削減、②自然な対話、③非構造化データ処理、④マルチモーダル化、⑤専門知識の民主化、⑥言語障壁の軽減、⑦新たなインプット手法)が課題解決に貢献するかを検討。
第3章:生成AIが描く未来予想図
マクロな視点から、今後15~20年の中長期的な未来における社会や人の在り方の変化、そして今後5~10年の比較的短期的な未来における各業界の変化について、未来予測を提示します。
第4章:生成AI時代のUXデザイン
生成AIならではの優れたユーザー体験(UX)を創造するために必要なフレームワークやベストプラクティスを紹介します。
- UX=u(便益)+e(情緒価値)-f(フリクション): 便益の最大化とフリクションの最小化が重要。
第5章:UXを変容させる5つのキーワード
生成AIによって大きく変容するUXの在り方を、「デザインの粒度」「インターフェース」「体験の主戦場」「放置系UX」「マルチモーダルインプット」という5つのキーワードで解説します。
- UXの変化:
- ①デザインの粒度が”User”から”You”へ(パーソナライズ)。
- ②インターフェースの融解(意識しないAI活用)。
- ③”OS的レイヤー”の体験(生活基盤へのAI浸透)。
- ④”放置系UX”(AIによる自動タスク実行)。
- ⑤「マルチモーダルインプット」前提のデザイン(多様な入力方法)。
第6章:生成AI時代の組織づくり
生成AIを活用して組織の生産性やアウトプットクオリティを向上させる方法について、具体的な生成AIツールやプロンプトテクニックを紹介します。
- ChatGPTプロンプトテクニック:
- ①役割定義。
- ②#変数と詳細情報付与。
- ③必要な情報をChatGPTに質問。
- ④出力フォーマット指定。
- ⑤アウトプットの自己改善。
- ⑥良いアウトプットの基準提示。
第7章:生成AIネイティブな組織への進化
従来の業務プロセスを刷新し、新たな事業価値を創出できる「生成AIネイティブな組織」への変革ステップと、経営層が見据えるべき未来予想を提示します。
- 生成AIネイティブな組織への7ステップ:
- ①上位レイヤーのコミット。
- ②ビジョンの策定。
- ③コアチームの設置。
- ④業務の特定と改善。
- ⑤メンバーの育成。
- ⑥事業への活用。
- ⑦組織・働き方の変革。
巻末特典:
- 非エンジニアにも分かりやすい生成AIの技術解説
- 注目の生成AI関連スタートアップリスト
- おすすめのAI関連ニュースレターリスト
4. ココだけは押さえたい一文
「生成AI領域で成功する事業・プロダクトをつくるには、『意義』のデザインと『意味』のデザインがカギとなる。」
この一文は、本書の核となるメッセージです。技術中心ではなく、顧客の課題解決と生成AIを使う必然性を重視することの重要性を表しています。
5. 感想とレビュー
『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』は、「生成AIがスゴい」という表層的な情報に留まらず、経営層や事業リーダーが本当に必要としている「生成AIを活用して事業・組織をどう成長させるか」という問いに、著者自身の豊富な経験と確かな知見に基づいて真正面から答える実践的な指南書です。単なる技術解説ではなく、技術をいかにビジネスや組織に落とし込み、具体的な成果に繋げていくのか、という視点が貫かれている点が大きな特徴です。特に、著者自身が新規事業開発やサービスグロースのアドバイザー、そしてXR/メタバース領域のスタートアップ経営者としての経験を持つことが、本書に深みと説得力を与えています。また、テレビ東京やエクサウィザーズ社をはじめとする複数企業への顧問経験も、本書の内容をより実践的で現代のビジネスシーンに即したものにしています。
良かった点:
- 経営層・事業リーダー視点への特化: 巷には技術解説に偏った生成AI関連の情報が多い中、本書は経営層や事業リーダーが本当に必要としている情報、つまり「いかに事業・組織を成長させるか」という視点に特化している点が際立っています。これは、著者が多くの企業から同様の相談を受けてきた経験に基づいているため、読者のニーズに的確に応える内容となっています。
- 実践的なフレームワークと具体的なテクニック: 「意義」と「意味」のデザイン、「Javelin Board」、UXの変化、ChatGPTプロンプトテクニック、生成AIネイティブ組織への変革ステップなど、抽象的な概念だけでなく、具体的なフレームワークやテクニックが豊富に紹介されています。特に、プロンプトテクニックは、すぐに業務に活用できる具体的なノウハウであり、読者にとって大きな価値となるでしょう。
- 豊富な事例と示唆に富む未来予測: 企業における生成AIの活用事例が豊富に盛り込まれているだけでなく、今後15~20年の中長期的な未来、そして5~10年の比較的短期的な未来における社会や各業界の変化についての未来予測も示されており、読者は具体的なイメージを持ちながら、生成AIの可能性を理解することができます。
- 分かりやすい構成と平易な文章: 専門用語を分かりやすく解説し、平易な文章で書かれているため、AIの専門家でなくても容易に内容を理解することができます。章立てや構成も整理されており、スムーズに読み進めることができます。
- 巻末特典の充実: 非エンジニア向けの技術解説、注目のスタートアップリスト、おすすめのニュースレターリストなど、巻末特典も充実しており、読者の学習意欲をさらに高める構成となっています。
特に共感した点
- 「意義」と「意味」のデザインの重要性: 技術ドリブンではなく、顧客の課題解決を起点に考えることの重要性を強調している点は、非常に共感できます。多くの企業が最新技術の導入自体を目的にしてしまいがちですが、本当に重要なのは、その技術が顧客にとってどのような価値を生み出すのか、なぜ生成AIでなければならないのか、という本質的な問いです。本書はこの点を明確に示しており、企業が戦略的に生成AIを活用するための重要な視点を提供しています。
- 「生成AIネイティブ」な組織への変革の必要性: 生成AIを単なるツールとして導入するのではなく、組織文化や働き方そのものを変革する必要性を説いている点は、非常に示唆に富んでいます。真の意味で生成AIの恩恵を受けるためには、組織全体で意識改革を行い、AIを活用する文化を醸成していく必要があることを教えてくれます。これは、これからの組織運営において非常に重要な視点となるでしょう。
- UXの変化に関する考察の先進性: 生成AIによってUXがどのように変化していくのか、という考察は、今後のサービス開発において非常に重要な視点となります。特に、「放置系UX」や「マルチモーダルインプット」といった概念は、今後のUXデザインのトレンドを先取りしており、非常に参考になります。
6. まとめ
『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』は、生成AIのビジネス活用を考える上で、現代の経営者、事業責任者、サービス開発者にとって必携の一冊と言えるでしょう。単なる技術紹介に留まらず、具体的なフレームワークや事例、未来予測などを通して、生成AIをいかにビジネスに活かし、組織を変革していくのか、という実践的な指針を与えてくれます。特に、「意義」と「意味」のデザイン、そして「生成AIネイティブ」な組織への変革という概念は、これからのビジネス戦略を考える上で非常に重要な示唆を与えてくれます。著者の実務経験に基づいた解説は、他のAI関連書籍とは一線を画しており、読者はすぐに実践に活かせる知識と戦略を手に入れることができるでしょう。変化の激しい時代を生き抜き、未来を切り拓くための羅針盤として、本書は大きな価値を持つと言えるでしょう。
特に以下のような方におすすめです。
- 企業の経営層、役員
- 事業部長、部門責任者
- 新規事業開発担当者
- サービス企画・開発担当者
- DX推進担当者
- 経営コンサルタント
- 生成AIに関心のあるビジネスパーソン全般
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。