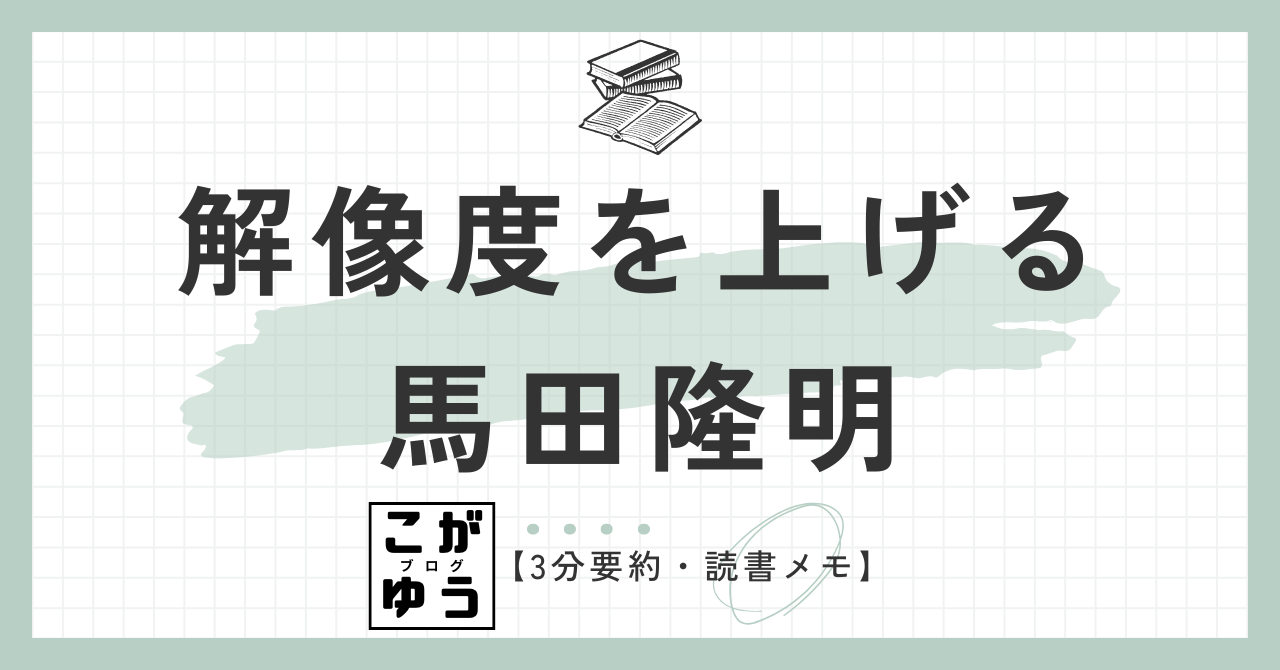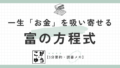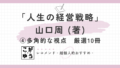ご覧頂き誠にありがとうございます。
今回は『解像度を上げる』についてレビューと要約の記事となります。
研ぎ澄ませ、思考の解像度を!『解像度を上げる』馬田隆明著 要約とレビュー
1. 著者の紹介
馬田隆明(まだ たかあき)氏は、株式会社Unlikelyの共同創業者であり、代表取締役を務める起業家です。東京大学経済学部を卒業後、戦略コンサルティング会社である株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)を経て、独立されました。
起業家としての経験に加え、コンサルタントとして数々の企業の課題解決に携わってきた実績を持つ馬田氏。その経験を通じて培われた、物事の本質を見抜く力、複雑な情報を整理し分かりやすく伝える能力は、本書『解像度を上げる』にも遺憾なく発揮されています。
著書には、前著『未来を実装する』もあり、未来洞察や新規事業開発についても深い知見を持っています。Twitter(@umeda_u)などでも積極的に情報発信されており、その思考の深さと分かりやすさに多くのフォロワーが魅了されています。
2. 本書の概要
『解像度を上げる』は、私たちが日常的に接する情報や課題、そして未来に対する理解度や捉え方の精度を高めるための思考法を解説した一冊です。著者の馬田隆明氏は、この「解像度」を、ビジネスにおけるコミュニケーション、問題解決、そして未来予測において不可欠な能力であると捉えています。
本書では、「解像度」を深さ・広さ・構造・時間の4つの視点から定義し、それぞれの視点を高めるための具体的な考え方や行動、いわゆる「型」を提示しています。単なる思考論に留まらず、「情報×思考×行動」を組み合わせることの重要性を強調し、読者が日々の生活や仕事の中で実践できる具体的な方法論が満載です。
特に、課題と解決策の「解像度」を分けて考える視点や、ともすると見過ごされがちな「課題の深さ」の重要性に焦点を当てている点は、本書の大きな特徴と言えるでしょう。若手ビジネスパーソンはもちろん、経験豊富なプロフェッショナルにとっても、自身の思考力を一段階引き上げるためのヒントが散りばめられています。
情報過多で変化の激しい現代社会において、曖昧な理解や表層的な認識では、本質を見誤り、適切な判断を下すことが難しくなります。本書は、そのような時代を生き抜くために、思考の鮮明さを高め、より良い意思決定を行い、価値を生み出すための道筋を示してくれるでしょう。
3. 本書の要約
『解像度を上げる』は、全8章で構成されており、「解像度」という概念を深く理解し、それを高めるための具体的な方法論が段階的に解説されています。
第1章 解像度を上げる4つの視点
まず、ビジネスにおける「解像度」の定義を明確にします。それは、物事への理解度や表現の精緻さ、思考の明快さを指します。解像度が高い人は、説明が的確で説得力があり、具体例を豊富に示せるというイメージで捉えられます。
そして、解像度を高めるための4つの重要な視点として、深さ・広さ・構造・時間を提示します。
- 深さの視点: 事象の原因や方法を具体的に掘り下げる力。なぜそうなったのか?どのようにすれば実現できるのか?を追求します。
- 広さの視点: 考慮すべき原因やアプローチの多様性を認識する力。一つの視点に囚われず、多角的に物事を捉えます。
- 構造の視点: 深さと広さで得られた要素を意味のある形で整理し、それぞれの関係性や重要性を把握する力。全体像を理解し、要素間のつながりを明確にします。
- 時間の視点: 経時変化や因果関係、物事のプロセスや流れを捉える力。過去、現在、未来の時間軸の中で物事を理解します。
第2章 あなたの今の解像度を診断しよう
ここでは、自身の現在の解像度を客観的に評価するための指針が示されます。「わからないことがわからない」「疑問や質問がない」状態は、解像度が低い兆候であると指摘します。
以下のような状態に当てはまる場合は、解像度を上げる余地があるとされます。
- 「それってどういう意味?説得力がない。」と言われる
- 「で、何なの?それって何の価値があるの?」と言われる
- 話がふわっとしていて、多くの事例に当てはまるようなよく聞く話である
- 安易な解決策を提示している
- 最初の一歩として何から始めればよいか分からない
さらに、自身の解像度を確認するためのチェックリストが提示され、重要なポイントを明確かつ簡潔に話せるか、自信を持って言い切れるか、ユニークな洞察があるかなどが評価項目として挙げられています。
第3章 型を意識しながら、まず行動からはじめて、粘り強く取り組み続ける
解像度を高めるためには、情報収集・思考・行動の3つを組み合わせ、反復することが重要であると述べられます。解像度が低い人に多いのは行動不足であり、情報を得たらまず行動し、思考を巡らせて情報を整理し、上司や先輩からのフィードバックを得るサイクルを回すことが推奨されます。
また、粘り強く続けることで質は向上しますが、ただ闇雲に行動するのではなく、「型」を意識して情報を整理していくことの重要性が強調されます。
第4章 課題の解像度を上げる―「深さ」
課題が正しく設定されていないと、生み出される価値に大きな差が生じると指摘し、良い課題の3条件として、大きな課題であること、合理的なコストで現在解決しうる課題であること、実績を作れる小さな課題に分けられることを挙げます。
課題の深さを追求する上で重要なポイントとして、以下の行動が挙げられます。
- 内化と外化を繰り返す: 読む・聞く(インプット)と書く・話す・発表(アウトプット)を意識的に行う。
- 言語化する(外化): 今分かっていることを言葉にすることで現状を把握する。
- サーベイする(外化): 書籍やインターネットなどから多くの情報を集めて全体像を知る。
- インタビューをする(内化): 個人の感想ではなく、事実を聞き出すことを意識する。
- 現場に入る(内化): 実際に利用者の行動を観察し、体験する。
- Why So?を繰り返し事実から洞察を導く(外化): 表面的な事象に留まらず、根本原因を深く探る。
- 習慣的に言語化(外化): 日常的に自分の考えや気づきを言葉にする習慣を持つ。
第5章 課題の解像度を上げる―「広さ」「構造」「時間」
課題の広さを高めるためには、以下の実践が推奨されます。
- 前提を疑う: 物事の前提を問い直し、より多くの選択肢を検討する。
- 視座を変える: 一つの視点に固執せず、異なる立場や視点から物事を捉える。木を見て森を見ずではなく、両方の視点を持つ。
- 体験する: 普段とは異なる環境や状況を体験することで、新たな視点や気づきを得る。
課題の構造を捉えるためには、情報を整理し、要素間の関係性を明確にすることが重要です。MECE(漏れなく、重複なく)やピラミッド構造などのフレームワークを活用し、情報を整理・構造化する「型」が紹介されます。
課題の時間軸を考慮するためには、過去の経緯、現在の状況、そして将来への影響を理解することが重要です。時間軸を入れることで、課題の本質や変化の方向性が見えてきます。
第6章 解決策の解像度を上げる―「広さ」「構造」「時間」
解決策の解像度を高めるためには、課題の解像度と同様に、広さ、構造、時間の視点が重要になります。
- 広さ: 一つの解決策に固執せず、多様な解決策の可能性を探る。ブレインストーミングなどの手法を活用し、多くのアイデアを出すことが重要です。
- 構造: 複数の解決策候補を比較検討し、それぞれのメリット・デメリット、実現可能性などを構造的に整理する。意思決定マトリクスなどのツールが有効です。
- 時間: 解決策の短期的な効果と長期的な影響を考慮する。段階的な導入計画や、将来的なリスクと対策などを検討することが重要です。
第7章 実験して検証する
高い解像度の解決策を生み出すためには、机上の空論に留まらず、実際に実験を行い、その結果を検証することが不可欠です。小さな規模から実験を始め、得られたデータに基づいて仮説を修正していくアジャイルなアプローチが推奨されます。実験を通じて、何が有効で何がそうでないかを具体的に理解することで、解決策の解像度は飛躍的に向上します。
第8章 未来の解像度を上げる
最終章では、不確実な未来に対する解像度を高めるための思考法が解説されます。過去の延長線上で考えるのではなく、複数の未来のシナリオを想定し、それぞれの可能性と対策を検討することが重要です。バックキャスティングやシナリオプランニングなどの手法が紹介され、未来に対する解像度を高めることで、変化に柔軟に対応し、新たな機会を創出する力を養うことができると述べられます。
4. ココだけは押さえたい一文
「解像度を上げるためには、情報(収集)、思考、行動という3つを組み合わせ、反復しなければならない。」
『解像度を上げる』
「情報を得たらすぐに思考し、思考したらすぐに行動し、行動をして情報を得たらまた深く思考する、これを短時間で繰り返すことが解像度を上げるコツ」
『解像度を上げる』
「顧客よりも顧客の課題のことを深く知っているカスタマーマニアになれるかどうか」
『解像度を上げる』
「書くことで自分の考えの間違いや、解像度の低さにも気づきます。書きましょう。書きましょう。とにかく書きましょう。」
『解像度を上げる』
「顧客の意見ではなく、事実を聞く」
『解像度を上げる』
「内容が不完全に感じたとしても、とりあえずメモを残す」
『解像度を上げる』
「Why so?を繰り返して、事実を洞察へとかえていく」
『解像度を上げる』
「パナソニックの創業者である松下幸之助は「百聞は「一見にしかず」だけではなく、「百聞百見は一験しかず」とも言っています。体験したからこそ視野が広がって気づける視点もある」
『解像度を上げる』
「いろいろな課題と少しずつフィットしているだけの解決策は選ばれない」
『解像度を上げる』
5. 感想とレビュー
『解像度を上げる』を読み終えて、まるで霧が晴れるように、思考がクリアになった感覚を覚えました。「解像度」という、どこか曖昧に使われがちな言葉を、深さ・広さ・構造・時間という明確な4つの視点から定義し、それを高めるための具体的な「型」を示すことで、抽象的な概念が血肉化されたように感じます。
著者の馬田隆明氏の、コンサルタントと起業家双方の視点から語られる内容は、単なる机上の空論ではなく、実践的な知恵に溢れています。特に、「まず行動する」ことの重要性を強調しつつも、「型を意識する」ことの重要性も説いている点は、多くの思考本とは一線を画していると感じました。頭の中でいくら考えていても、実際に行動に移し、そのフィードバックを得なければ、解像度は上がらないという当たり前のようで忘れがちな真理を、改めて認識させられました。
また、課題の解像度と解決策の解像度を分けて考えるという視点は、問題解決の本質を捉えていると感じました。良い解決策は、質の高い課題設定から始まる。このシンプルな原則を、改めて深く理解することができました。特に、課題の「深さ」を追求するための具体的な方法論は、日々の業務においてもすぐに実践できるものばかりです。Why So?を繰り返すこと、現場に入ること、そして習慣的に言語化すること。これらの基本的な行動を意識的に行うことで、物事の見え方が大きく変わるだろうと確信しました。
本書全体を通して、「情報×思考×行動」の反復というメッセージが強く伝わってきました。質の高い情報を収集し、多角的に思考を巡らせ、そして実際に行動に移して検証する。このサイクルを意識的に回すことこそが、解像度を高めるための王道であると改めて認識しました。
最終章の「未来の解像度を上げる」という視点も、非常に示唆に富んでいました。不確実な未来に対して、一つの予測に固執するのではなく、複数のシナリオを想定し、備えておくことの重要性は、VUCA時代を生きる私たちにとって、 不可欠な考え方だと感じました。
『解像度を上げる』は、若手ビジネスパーソンはもちろん、経験豊富なプロフェッショナルにとっても、自身の思考力を鍛え直し、一段上のレベルに引き上げるための必読書と言えるでしょう。具体的な「型」が豊富に紹介されているため、読んだその日から実践に移せる点も魅力です。情報過多な現代において、思考の解像度を高め、本質を見抜く力を養いたいすべての人に、強くお勧めしたい一冊です。
6. まとめ
『解像度を上げる』は、起業家でありコンサルタントである馬田隆明氏が、物事の理解度や表現の精緻さ、思考の明快さを意味する「解像度」を高めるための思考法を解説した一冊です。深さ・広さ・構造・時間という4つの視点から「解像度」を捉え、それぞれの視点を高めるための具体的な考え方や行動、いわゆる「型」を豊富に紹介しています。
本書の核心となるのは、情報収集・思考・行動の3つを組み合わせ、反復することの重要性です。課題の解像度と解決策の解像度を分けて考える視点や、課題の「深さ」を徹底的に追求する方法論は、問題解決能力を飛躍的に向上させるための鍵となります。
また、未来に対する解像度を高めるためのシナリオプランニングなどの思考法は、不確実な現代を生き抜くための羅針盤となるでしょう。
『解像度を上げる』は、自身の思考力を磨き、より本質的な理解、より的確な判断、そしてより良い未来を築きたいと願うすべての人にとって、必携の一冊です。具体的な「型」を意識しながら日々の業務や生活に取り組むことで、あなたの思考の解像度は確実に向上するはずです。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。