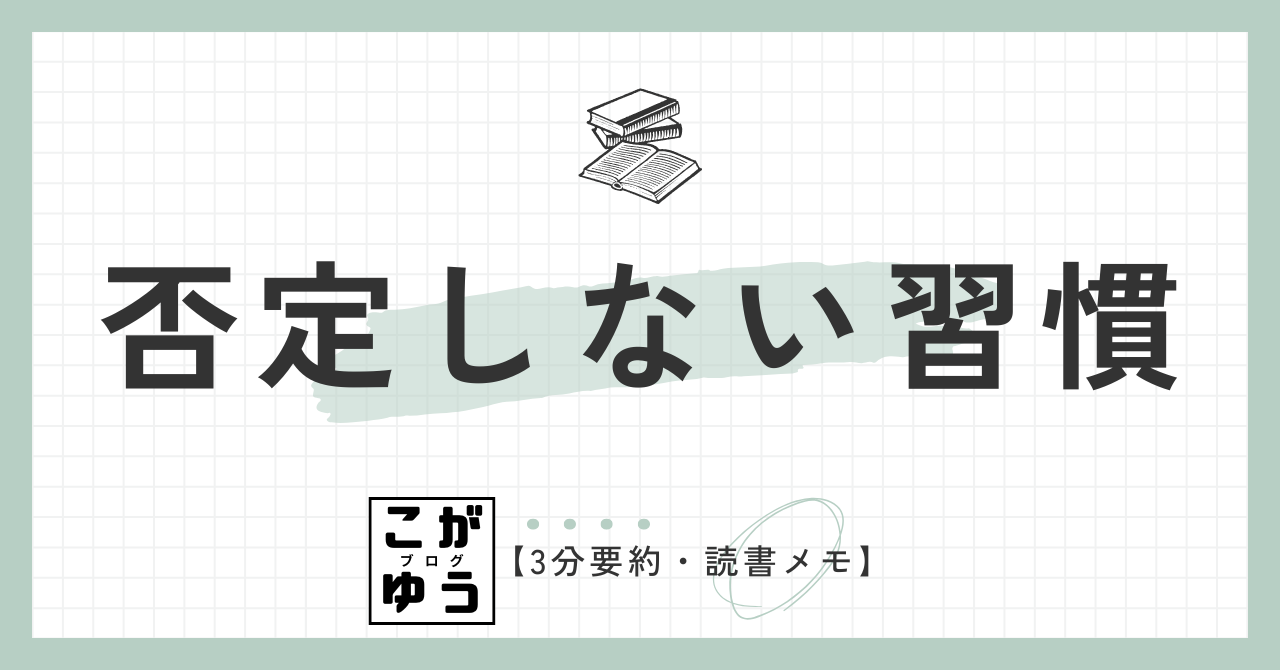このブログでは、日々の仕事や人間関係に役立つヒント、そして心地よいライフスタイルを送るための考え方を発信しています。
さて、仕事でもプライベートでも、人間関係の悩みって尽きないですよね。「なぜか人とよくぶつかる」「部下や後輩とのコミュニケーションがうまくいかない」「家族との関係がギクシャクする」…こうした悩みが、日々の幸福度を下げてしまうことも多いのではないでしょうか。
人間関係を良くする方法として、「相手を褒める」「ポジティブな言葉をかける」といったことがよく言われます。もちろんそれも大切ですが、今回ご紹介する一冊は、それ以上に効果的で、しかも簡単な、人間関係の根本を改善する習慣を教えてくれます。
それが、『否定しない習慣』 林 健太郎 (著) です!
著者の林健太郎氏は、プロのコーチとして、多くの人のコミュニケーションの課題に向き合ってこられた方です。その経験から得た、人間関係を劇的に変える秘訣、それが「相手のことを否定しない」というシンプルな習慣なのだと言います。
「え?否定しないだけで?褒めたり肯定したりしなくていいの?」と、私も最初は少し意外に感じました。しかし、本書を読み進めるにつれて、この「否定しない」ということが、いかに人間関係の土台となる「安心感」を築く上で重要か、そして私たちが無意識のうちにどれだけ相手を「否定」してしまっているか、に気づかされました。
この記事では、私が『否定しない習慣』 を読んで、これはすぐにでも実践したい!と感じたポイントを、以下の構成で、コンパクトにまとめてお伝えします。
「否定しない習慣」を手に入れることで、あなたの人間関係はどう変わるのか? ぜひ最後まで読んでみてください!
1. 著者の紹介
まず、本書『否定しない習慣』の著者、林 健太郎(はやし けんたろう)氏をご紹介します。
林健太郎氏は、プロのコーチとして活動されています。コーチングとは、対話を通じて、相手の自己実現や目標達成をサポートする専門的な関わり方です。
多くのクライアントと深く関わる中で、林氏は人間関係の質が、その人の幸福度や成長に大きく影響することを痛感されてきたのでしょう。そして、良好な人間関係の基盤には、特定のコミュニケーションの「習慣」があることを見出されたと考えられます。
本書は、林氏がコーチングの現場で培ってきた、相手との間に信頼関係や安心感を築くためのコミュニケーション技術、特に「否定しない」ことに焦点を当て、それを日々の習慣として身につけるための具体的な方法をまとめたものです。
プロコーチとして、多くの人の「話し方」や「聞き方」、そしてその根底にある「思考パターン」に触れてきた経験があるからこそ、私たちが無意識に行っている「否定」の習慣を見抜き、それを改善するための実践的なアドバイスができるのです。
2. 本書の概要
次に、本書『否定しない習慣』が全体としてどのような内容を扱っているのか、その概要を説明します。
本書の中心的なテーマは、「相手のことを否定しない」というコミュニケーションの習慣を身につけることで、人間関係を劇的に改善し、「安心感」に基づいた信頼関係を築くことです。
著者は、人間関係を良くするために「褒める」「肯定する」といったプラスの行動が推奨されがちだが、それよりもまず、相手の言葉や存在を「否定しない」というマイナスをゼロにする、あるいは徹底的に避けることの方が、はるかに効果的で、関係性の土台を築く上で重要だと主張します。
なぜなら、人間関係において最も大切な「安心感」は、「褒められる」ことではなく、「何を言っても否定されない」「話を聞いてもらえる」「失敗しても責められない」といった、「否定されない」経験によって生まれるからです。
そして、人間関係のトラブルや不信感の多くは、本人が気づいていない「無意識の否定の習慣」によって引き起こされていると指摘します。相手の話を遮る、ミスを責める、意見を頭ごなしに否定する、真剣に相談に乗らない、といった行為は、すべて相手を「否定」することになります。
本書は、こうした「無意識の否定の習慣」を、プロのコーチが実践する具体的なコミュニケーション技術と、それを日々の「習慣」にするための考え方やコツを学ぶことで、「否定しない習慣」へと変えていくことを目指します。
良い人間関係を築きたい人、相手との間に信頼関係を育みたい人、そして、コミュニケーション能力を高めたいと考えている人にとって、本書は、そのためのシンプルかつ強力な習慣術を提供してくれる一冊です。この習慣が身につくことで、職場や家庭など、様々な場面での対人関係がよりスムーズになり、心理的な安全性の高い関係性を築くことができるでしょう。
3. 本書の要約
それでは、本書『否定しない習慣』の核となる部分を、その要約としてさらに詳しく見ていきましょう。
本書が提唱する最も重要な考え方は、「良い人間関係の土台は、相手を褒めることではなく、まず『否定しない』ことによって生まれる『安心感』である」という点です。人は、どれだけ良い点があっても、致命的なマイナス(否定)があれば離れていく生き物であり、コミュニケーションにおける致命的なマイナスこそが「否定」なのです。そして重要なのは、自分が否定していないつもりでも、言われた相手が「否定された」と感じたら、それは「否定」になるということです。
本書では、この「否定」には、①相手の話や意見を打ち消す、聞かない、奪う、②相手のミス・失敗を責める、③悩みの相談に真剣に向き合わないといった、私たちが無意識にやってしまいがちな習慣があると指摘します。
これらの「無意識の否定の習慣」を「否定しない習慣」に変えるために、本書は「否定しないマインド」と「否定しない技術」を紹介しています。
まず、「否定しないマインド」の基本的な考え方は以下の3つです。
- 「事実だから否定してもいい」という思考をしない:
- 正論であっても、相手が否定されたと感じれば関係性を損ないます。重要なのは、「言われた相手が否定されたと受け取るかどうか」です。ただの会話では事実や正論より、相手の気持ちを理解し、希望を与えることが好まれます。
- 「自分は正しい」という思考をしない:
- コミュニケーションにおいて、どちらか一方が一方的に正しいことは稀です。意見の違いは「多様性」として認め、「共有する目的を見つける」ことに意識を向けましょう。相手は敵ではなく、同じ目的に向かう仲間です。
- 「過剰な期待」をしない:
- 「これくらいできるだろう」という期待は、相手ができなかった時に不平不満や否定につながります。人を思い通りに動かすことはできません。相手を否定しても結果は出ません。萎縮させたり、恨まれたりするだけです。ミスが起きたら、感情的に責めるより、「ミスが起きないようにするには?」と建設的に考えるべきです。
次に、これらのマインドに基づいた「否定しない技術」です。
最も大切な技術は、「言葉を返す前にブレーキを踏む」ことです。具体的には、相手が話し終わったと思ったら、すぐに話し始めるのではなく、最低約2秒の沈黙を置くことです。この「間」を取る意識がなければ、つい相手の話に被せてしまったり、反射的に否定的な言葉を発してしまったりするのを防ぐことができます。
「否定しない」とは、相手の言葉をすべて肯定したり、言いなりになったりすることではありません。相手の意見や考え、行動を頭ごなしに否定しないという意味です。当然、否定せざるを得ない状況もあります。重要なのは「どう伝えるか」です。
その方法として、本書はまず「相手が言ったことそのものだけを『承認する』」ことから始めることを推奨します。ここで大切なのは、相手の言った内容に同意する必要はないということ。承認するのは、「相手がそう言った」という事実だけです。一番簡単な承認の言葉は、「そうなんですね」です。相手の言うことが間違っていると感じても、「そうなんだね。そういう考え方もあるよね」のように、まず相手の言葉を受け止める姿勢を示します。
その上で、同意できない場合は、相手の意見を否定せず、別の候補を聞いたり、「例えばこんな選択肢はどうかな?」と自分の考えを提案したりすれば良いのです。「否定しない」は「言いなりになる」とは全く違います。相手の意見を尊重しつつ、自分の考えも適切に伝える技術が重要です。
要するに、本書は、私たちが無意識に行っている「否定」の習慣に気づき、相手の言葉をまず受け入れ、数秒の沈黙を置き、「そうなんですね」といった言葉で一度「承認」するといった具体的な技術を実践することで、相手に「何を言っても大丈夫だ」という安心感を与え、良好な人間関係や信頼関係を築くための習慣術なのです。
4. ココだけは押さえたい一文
本書『否定しない習慣』の中で、私が最も「これこそこの本の、そして良好な人間関係の本質だ!」と感じた、シンプルながらも深い真実を突いている一文があります。
それは、人間関係において最も大切な「安心感」がどう作られるかについて述べられている、この言葉です。
「この安心感は、『褒められる』『肯定される』といったことでは作られません。『何を言っても否定されない』『話を向き合って聞いてくれる』『ミスや失敗を責められない』といった『否定されない』ことで生まれてくるのです。」
私たちは、つい「相手を喜ばせよう」「ポジティブな雰囲気を作ろう」として、褒めたり肯定したりすることばかりに意識を向けがちです。もちろん、それは人間関係を円滑にする上で大切な要素ではありますが、本書は、それだけでは「安心感」という、関係性の最も根本的な土台は築けないのだと明確に示しています。
本当に相手が心を開き、本音で話せるようになるのは、たとえ完璧でなくても、失敗しても、あるいは自分と違う意見を言っても、「この人は自分を否定しない」という確信が持てた時なのです。褒められることによる喜びは一時的かもしれませんが、「否定されない」ことによる安心感は、その人の存在そのものを受け入れられたという深い信頼に繋がります。
この一文は、人間関係において、「何を『プラス』するか」よりも、「何を『マイナス』しないか」、特に「否定」という致命的なマイナスをいかに避けるかが、いかに重要であるかを教えてくれます。本書を読む際には、ぜひこの言葉を心に留めて、あなたが周囲の人々に対して、「何を言っても否定されない安心感」を提供できているか、自問自答してみてください。
人間関係で最も大事なことは「相手を否定しない」こと
『否定しない習慣』
その人はその人なりに精いっぱいやっている
『否定しない習慣』
私たちが否定をする一番の原因は、「相手が間違っていて、自分が正しい」と思い込んでいることかもしれない
『否定しない習慣』
ナイスなことが言えないなら、何も言うんじゃない
『否定しない習慣』
「聞いたあと」こそ、あなた自身の冷却期間が約2秒必要
『否定しない習慣』
「承認」は4種類ある
『否定しない習慣』
①存在の承認
②行動の承認
③プロセスの承認
④見解の承認
簡単にわかった気になってはいけない
『否定しない習慣』
「何を言っているか」と同様に・・・・
『否定しない習慣』
いや、もしかしたらそれ以上に「相手にどう見えているか」が重要
「今、話をしている相手は成熟した立派な大人。何か客観的なアドバイスや判断が欲しいのであれば、自分から求めてくるはず。それがないということは、黙って聞いてもらいたいのだ」
『否定しない習慣』
「合いの手」の基本フレーズ5
『否定しない習慣』
①「そうなんですね」
②「もう少し詳しく」
③「ほかには?」
④「というと?」
⑤「だとしたら?」
「ああ、それ、わかる」は嫌われる
『否定しない習慣』
「わかる」から「わかる気がする」へ
「提案があるんだけど、いいかな?」
『否定しない習慣』
あなたの提案を受け入れるかどうかの選択権は相手にある。
相手に選択権がないになら、上から目線のアドバイスか、ただの命令です。
5. 感想とレビュー
本書『否定しない習慣』は、そのタイトルのシンプルさとは裏腹に、人間関係の本質、特に信頼関係や安心感をどう築くかについて、非常に深く考えさせられる一冊でした。そして、すぐにでも実践したくなる具体的なヒントが満載です。
私自身、日々の仕事で多くの人と関わる中で、コミュニケーションの重要性は痛感しています。特に、チームメンバーが心理的な安全性を感じ、自由に意見を言い合える環境を作ることは、クリエイティブなマーケティングの仕事を進める上で不可欠です(これは以前レビューした本でも触れましたね!)。本書は、この心理的な安全性の基盤が、まさに「否定されない」ことによって築かれるのだと明確に示しており、私が感覚的に重要だと感じていたことの具体的な行動指針を与えてくれました。
本書で一番ハッとさせられたのは、私たちが無意識のうちにどれだけ相手を「否定」してしまっているかという指摘です。相手の話を途中で遮って自分の話をし始めたり、相手が何かを説明している途中で「あ、それ知ってる」と話を奪ったり、あるいは相手が困っている時に「それはあなたが〇〇しなかったからだよ」と原因や責任を追及したり…。これらは、悪気なくやってしまいがちですが、言われた相手は確実に「否定された」「ちゃんと話を聞いてもらえなかった」と感じてしまいます。本書の「あるある」事例は、まさに「うわ、自分もやってる…!」と耳が痛くなるものばかりでした(苦笑)。
特に、マネージャーという立場では、部下からの相談に対して、すぐに解決策やアドバイスを言ってしまいがちです。しかし、本書で学ぶように、まずは相手の話を最後まで聞き、「そうなんですね」と一度受け止める(承認する)こと。そして、数秒の沈黙を置いて、相手が話し終えたことを確認する。これらは、相手に「この人は自分の話をちゃんと聞いてくれている」という安心感を与えるために、非常に効果的な技術だと感じました。忙しい時ほど忘れがちですが、意識的に取り入れたいと思っています。
また、「事実だから否定してもいい」という思考をしないという点も、ビジネスシーンでは特に重要です。データや正論は大切ですが、それを振りかざすだけでは、相手の感情を無視した「否定」になりかねません。まずは相手の状況や感情に寄り添い、「そうなんですね」と受け止めた上で、「ちなみに、こういうデータもあるんですが…」のように伝えるスキルが、円滑なコミュニケーションには不可欠だと再認識しました。
「過剰な期待をしない」というマインドセットも、マネジメントにおいて本当に重要です。部下が期待通りのパフォーマンスを出せなかった時に、「なぜできないんだ」と否定的に反応するのではなく、「彼/彼女なりに頑張った結果かもしれない」「どうすれば次回はうまくいくか?」と建設的な視点に立つこと。これは、相手を否定しないだけでなく、自分自身のフラストレーションを管理する上でも役立つ考え方です。
本書は、「否定しない」というのは「言いなりになることではない」と明確に述べています。相手の意見を尊重しつつも、自分の意見や代替案を適切に提案する技術も紹介されており、一方的に我慢する関係ではないことが強調されている点も安心しました。
私のブログテーマの一つである「ライフスタイル」という観点からも、本書は非常に示唆に富みます。夫婦関係や親子関係、友人関係においても、「否定しない習慣」は安心感を育み、関係性をより豊かなものにしてくれるはずです。「褒める」よりもまず「否定しない」。このシンプルな原則は、あらゆる人間関係に応用できる、まさに「一生モノの習慣」と言えるでしょう。
総じて、『否定しない習慣』は、私たちの無意識のコミュニケーションの癖に気づきを与え、人間関係の質、特に安心感と信頼関係を築くための、具体的で実践的な習慣術を教えてくれる素晴らしい一冊です。難しい理論は一切なく、誰にでも明日からすぐに試せる内容ばかりです。
人間関係の悩みを抱えている方、コミュニケーション能力を高めたい方、部下や家族との関係を良くしたい方、そして安心感に基づいた強い信頼関係を築きたいと考えている、すべての人に心からお勧めしたい一冊です。
6. まとめ
『否定しない習慣』の核となるメッセージは、良好な人間関係の土台は、「相手を褒めること」よりもまず「相手を否定しない」ことによって生まれる「安心感」である、ということです。そして、人間関係のトラブルの多くは、私たち自身が持っている「無意識の否定の習慣」によって引き起こされていると指摘します。
本書は、この無意識の否定の習慣を改善するための「否定しないマインド」(事実や正論に固執しない、自分を正しいと思わない、過剰な期待をしない)と、「否定しない技術」(言葉を返す前に2秒の沈黙を置く、相手の言葉を「そうなんですね」と承認する)を、プロコーチならではの視点から具体的に解説しています。
私の個人的なレビューとしても、本書の指摘する無意識の否定は非常に耳が痛く、日々のコミュニケーションを見直す大きなきっかけとなりました。特に、2秒の沈黙や、内容に同意しなくても事実として「承認する」という技術は、マネジメントや人間関係においてすぐに活用できる、実践的なヒントだと感じています。「否定しない」ことは「言いなりになることではない」という点が明確なのも安心です。
もしあなたが、
- 人間関係のトラブルで悩むことが多い
- 部下やチームメンバーとの信頼関係を築きたい
- 家族や友人との関係をより良くしたい
- 自分のコミュニケーションの癖を改善したい
- 相手に安心感を与えられる人になりたい
と考えているなら、ぜひ本書『否定しない習慣』を手に取ってみてください。
本書は、あなたの人間関係を根本から変えるための、シンプルながらも強力な習慣を教えてくれるでしょう。そして、周囲の人々との間に、安心感に基づいた温かい信頼関係を築くための一助となるはずです。
この本が、皆さんの日々のコミュニケーション、そして人間関係をより豊かなものにするための一助となれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。