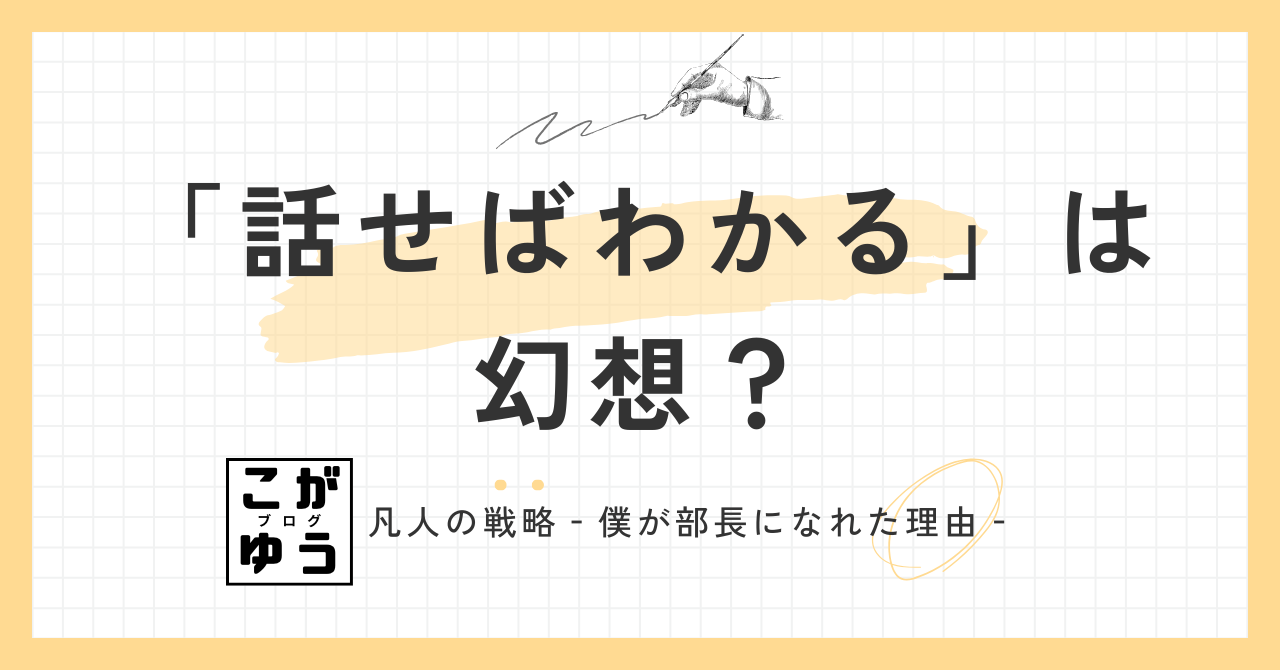日々の人間関係や仕事の中で、「なんで伝わらないんだろう…」「言ったはずなのに…」と、もどかしい思いをしたことはありませんか?
私たちはよく「話せばわかる」と言います。確かに、話し合うことは大切です。でも、残念ながら、この「話せばわかる」は、時に私たちを悩ませる「幻想」である、という現実と向き合う必要があります。
「え、どういうこと?」と思うかもしれませんね。でも、ご安心ください。この記事では、この「幻想」の正体を理解し、それでもなお、相手との真の理解を築き、より良い関係を育むためのコミュニケーションの「技術」を、皆さんにわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』 今井むつみ (著)を参考に書かせていただきました。
「話せばわかる」が幻想だと知ることは、決して諦めではありません。むしろ、そこからが、本当に効果的なコミュニケーションを学ぶためのスタートラインなのです。さあ、一緒にこの奥深いテーマを探求し、あなたのコミュニケーションを次のレベルへと引き上げましょう!
人間の記憶は非常に曖昧であり、話した内容が正確に記憶され、伝わるわけではない ~脳の不思議なフィルター~
まず、大前提として知っておいてほしいのは、私たちの「記憶」が非常に曖昧だということです。私たちは、誰かと話した内容を、録音機のように一言一句正確に記憶しているわけではありません。
脳は、膨大な情報の中から必要なものを取捨選択し、自分にとって意味のある形で再構築します。その過程で、一部の情報は抜け落ちたり、形を変えたり、時には全く異なるものに変換されたりします。
例えば、あなたが会議で重要な指示を出したとします。あなたは「〇〇を△△の期日までに、必ず□□の形で提出してほしい」と明確に伝えたつもりでも、相手の脳では「〇〇を△△の期日までに」は記憶されても、「□□の形」が抜け落ちていたり、別の解釈に置き換わっていたりする可能性があるのです。
これは、相手が集中していなかったとか、能力が低いということではありません。人間の脳が持つ、ごく自然な機能なのです。この事実を理解することから、コミュニケーションの誤解を防ぐ第一歩が始まります。
私たちは、自分の都合のいいように記憶を書き換えたり、解釈したりする生き物である ~無意識のバイアス~
さらに厄介なことに、私たち人間は、自分が持っている先入観や願望、感情に基づいて、情報を「都合のいいように」記憶を書き換えたり、解釈したりする生き物です。心理学では、これを「確証バイアス」や「自己奉仕バイアス」などと呼びます。
例えば、あなたが部下にある業務を依頼しました。部下は「よし、自分の成長のチャンスだ!」と前向きに捉え、あなたはその部下が「意欲的に取り組んでくれるだろう」と期待しました。ところが、後日、部下が「あの時、無理やり押し付けられたと感じた」と言ってきたとしたら、どうでしょう?
あなたには、そう言ったつもりは全くなくても、部下はあなたの言葉を、自身の「無理やり押し付けられたくない」という感情や、あるいは過去の経験に基づいて、無意識のうちにそのように解釈して記憶していたのかもしれません。
これは、意識的にウソをついているわけではありません。誰もが持っている、ごく自然な心の働きなのです。この「無意識のバイアス」の存在を知ることは、相手の言葉や行動の背景を理解しようとする姿勢に繋がります。
私たち人間は、相手の話した内容をそのまま脳にインプットするわけではない ~「解釈」という名のフィルター~
私たちは、相手が話した言葉を、そのまま録音機のように脳にインプットするわけではありません。むしろ、私たちは、相手の言葉を、自分自身のこれまでの「経験」「知識」「価値観」「感情」「置かれた状況」といった、複雑なフィルターを通して「解釈」しています。
同じ「早めにやってほしい」という言葉でも、
- 残業続きで疲弊している人にとっては「またサービス残業か…」というプレッシャーに。
- 時間管理が得意で、効率的に仕事をしたい人にとっては「よし、今日の午後の時間を使おう」という行動のきっかけに。
- 承認欲求が高い人にとっては「期待されている!」というモチベーションに。
…と、全く異なる意味合いで受け取られる可能性があります。
「言った通りにやってくれない」と感じる時、それは相手が悪いのではなく、あなたの言葉が、相手のフィルターを通して、あなたとは異なる意味に「解釈」されてしまった結果かもしれません。この「解釈」というフィルターの存在を理解することが、より伝わるコミュニケーションの第一歩です。
言葉を尽くして説明しても、相手に100%理解されるわけではない ~伝達の限界~
私たちは、どれだけ言葉を選び、論理的に、そして情熱的に説明したとしても、相手にその内容が100%完全に理解されることはありません。これは、コミュニケーションにおける避けられない「伝達の限界」です。
なぜなら、前述のように、相手はあなたの言葉を自分なりのフィルターを通して解釈するからです。また、言葉だけでは伝えきれない「非言語情報」(声のトーン、表情、ジェスチャー、場の雰囲気など)も、理解に大きく影響します。そして、聞き手の知識レベル、集中力、その時の感情状態なども、理解度を左右します。
「これだけ説明したのに、なぜわかってくれないんだ!」とイライラする気持ちはよく分かります。しかし、そのイライラは、この「伝達の限界」を知らないことから来るものかもしれません。
「完璧な理解は難しい」という前提に立つことで、私たちはコミュニケーションに対する期待値を適切に調整し、より効果的な伝え方や、確認の方法を模索できるようになります。
言った側と言われた側で、その情報の重要度が違う ~優先順位のズレ~
もう一つ、コミュニケーションの誤解を生む大きな要因は、言った側(発信者)と、言われた側(受信者)で、その情報の「重要度」が異なっていることです。
あなたにとっては、今日の会議で話した内容が「最重要事項」だったとしても、相手にとっては、他にも多くの情報やタスクを抱えている中で、あなたの話は「数ある情報の一つ」に過ぎないかもしれません。あるいは、もっと緊急性の高い別のタスクが頭を占めていて、あなたの話の優先順位が下がっている可能性もあります。
例えば、マネージャーが部下に「来週の月曜までに、この資料を作成しておいてほしい」と依頼しました。マネージャーは、その資料が次の重要な会議で必要不可欠なため、これを最重要視しています。しかし、部下は、他にも緊急性の高い顧客対応や、期限が迫っている別のプロジェクトを抱えていて、資料作成の優先順位はマネージャーが考えているほど高くないかもしれません。
この「重要度のズレ」は、意図しないタスクの遅延や、認識の齟齬を生み出します。マネージャーは「なんでやってくれないんだ」と感じ、部下は「他にもっと優先すべきことがあったのに」と感じるわけです。相手にとっての重要度を推し量り、必要であれば優先順位の調整を行うことが、スムーズな業務遂行には不可欠です。
ウソをつくつもりがなくても、「相手が、そして自分が、事実として正しいことを言っているとは限らない」~客観性の限界~
最も耳が痛い話かもしれませんが、私たちは「ウソをつくつもりがなくても、相手が、そして自分が、事実として正しいことを言っているとは限らない」という事実を受け入れる必要があります。
これは、「欺こうとしている」という意味ではありません。人間は、意識的または無意識的に、自分の記憶や解釈、都合の良い部分だけを選んで話したり、あるいは、その場の雰囲気や相手の反応に合わせて、事実を少しだけ「脚色」して話したりすることがあります。
例えば、過去の成功体験について話す時、無意識のうちに自分の貢献を大きく見積もったり、失敗の原因を他者に転嫁してしまったりする経験はありませんか?あるいは、相手もまた、自分の立場を守るために、事実の一部を隠したり、歪めて伝えたりすることがあるかもしれません。
これは、悪意ではなく、自己防衛本能や、承認欲求といった、人間のごく自然な心理が働く結果です。この「客観性の限界」を知ることで、私たちは、相手の言葉を鵜呑みにするのではなく、多角的な視点から情報を確認したり、自身の発言も本当に客観的か内省したりする姿勢を持つことができるようになります。
「話せばわかる」は幻想だけど、それでも「話す」価値は無限大 ~諦めずに、より良い対話を求めて~
ここまで、「話せばわかる」がいかに難しいか、その理由をたくさんお伝えしてきました。もしかしたら、「じゃあ、どうすればいいんだ…」と、少し途方に暮れてしまったかもしれませんね。
でも、安心してください。これらの「幻想」を知ることは、決してコミュニケーションを諦めることではありません。むしろ、その逆です。
「完璧な理解は難しい」という前提に立つからこそ、私たちはより慎重に、より工夫を凝らしてコミュニケーションを取ろうと努力できます。
では、どうすればこの「幻想」を乗り越え、より良いコミュニケーションを築けるのでしょうか?
- 「伝わらない」前提で話す: 相手が100%理解して当然だと思わない。重要なことは、異なる言葉や方法で複数回伝える。
- 相手のフィルターを意識する: 相手の立場、経験、感情を想像し、「この言葉は、相手にどう受け取られるだろうか?」と考える。
- 「解釈の確認」を習慣に: 伝えた後、「今の話、〇〇さんはどう理解しましたか?」「私がお伝えしたかったことは、〇〇さんの認識と合っていますか?」と、相手に確認する。
- 非言語情報を活用する: 言葉だけでなく、表情、声のトーン、ジェスチャーも意識し、メッセージに一貫性を持たせる。
- 相手の「重要度」を測る: 伝えた情報の優先順位を相手とすり合わせる。「他に優先すべきことはありますか?」「私としては、これを最優先でお願いしたいのですが、いかがでしょうか?」
- オープンな対話の場を作る: 意見や懸念を自由に話せる心理的に安全な場を日頃から築いておく。
- 「傾聴」に徹する: 自分の言いたいことばかり話すのではなく、相手の話を最後まで、遮らずに聞く。その背景にある感情や意図まで汲み取ろうと努める。
- 記録に残す: 重要な決定事項や指示は、口頭だけでなく、議事録やメール、チャットなどで文字として残し、いつでも見返せるようにする。
これらの工夫は、一見すると手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、誤解から生じるトラブルや手戻りを考えれば、はるかに効率的であり、何よりも、相手との信頼関係を深めるための投資です。
「話せばわかる」は幻想かもしれません。でも、私たちは「話す」ことを諦めてはいけません。なぜなら、話すことは、人間が互いに繋がり、理解し、共に未来を創るための、唯一の、そして最も尊い手段だからです。
この「幻想」の正体を知った今、あなたはきっと、これまで以上に効果的で、心温まるコミュニケーションを築くことができるはずです。さあ、一歩踏み出し、真の理解を目指す旅を始めましょう!
詳しく知りたい方は、『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』 今井むつみ (著))を手に取ってください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。