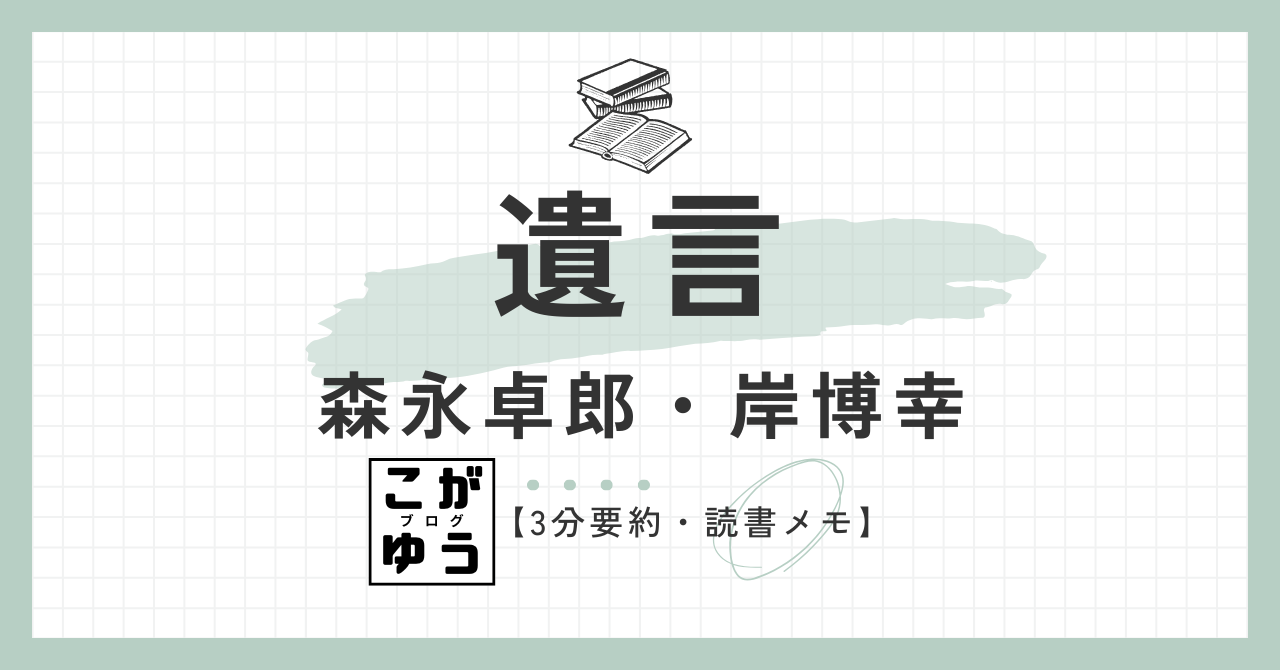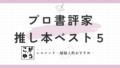ご覧頂き誠にありがとうございます。
普段、私たちは漠然とした不安や、今の日本の閉塞感を感じながら日々を過ごしていませんか?
「このままで日本は大丈夫なんだろうか…?」
「自分の将来は明るいのだろうか…?」
そんな漠然とした問いに、まさに「命を懸けて」答えてくれる、衝撃の一冊を今日はご紹介したいと思います。それが、経済アナリストの森永卓郎さんと、経済学者の岸博幸さんによる共著『遺言 絶望の日本を生き抜くために』です。
「余命宣告を受けた二人が語る『遺言』…?」
「どんな残酷な現実が語られているんだろう?」
そう思われた方もいるかもしれません。この本は、共にがんを患い、死と向き合う中で「余命宣告」を受けたお二人が、これからの日本社会、そして私たち個人がどう生きていくべきかについて、忖度なしで語り尽くした対談集です。
テレビやメディアでは語られない「国民の9割が知らない残酷な現実」。そして、その中で私たちがどうすれば「絶望の日本を生き抜く」ことができるのか。森永さんと岸さんの経験と知見、そして死生観が凝縮された、まさに「最後のメッセージ」とも言える内容になっています。
今回のブログ記事では、この重くも示唆に富んだ一冊の魅力を、以下の構成で深掘りしていきます。
今日の記事が、日本社会とご自身の将来について深く考えるきっかけとなることを願っています。ぜひ、最後までじっくりと読んでみてください!
1. 著者の紹介
本書『遺言 絶望の日本を生き抜くために』の著者である森永卓郎さんと岸博幸さんは、共に日本の経済や社会について長年深く考察し、発信し続けてきた著名な識者です。彼らは、それぞれのキャリアの中で「霞が関」(日本の官僚機構)での宮仕えを経験し、その内部事情を熟知しています。その後、それぞれの道で経済評論家や学者として活躍されてきました。
この本の最大の背景となっているのは、お二人ともがんに罹患し、医師から「余命宣告」を受けているという共通の、そして非常に重い事実です。死と真正面から向き合う中で、彼らの人生観や生き方がどのように変化したのか、そして残された時間で何を伝えたいのか――。そうした切実な思いが、本書に比類ない説得力と深みを与えています。
森永卓郎さん:異色の経済アナリスト
森永卓郎さんは、独特の視点と歯に衣着着せぬ物言いで知られる経済アナリストです。日本専売公社(現JT)や経済企画庁(現内閣府)を経て、獨協大学教授、経済アナリストとして多方面で活躍しています。彼の分析は、時に既存の経済学の枠にとらわれず、一般の生活者の目線に立ったユニークな提案や、痛烈な社会批評を行うことで多くのファンを獲得しています。
本書では、自身の「超貧困」からの生い立ちや、バブル期の体験、そしてがんとの闘病生活について赤裸々に語り、特に「トカイナカ(都会と田舎の中間)」での生き方や、悔いなき人生を送るための提言など、個人が「絶望の日本」を生き抜くための具体的なビジョンを提示しています。
岸博幸さん:元エリート官僚の経済学者
岸博幸さんは、旧通商産業省(現経済産業省)のエリート官僚として霞が関で活躍し、小泉政権下では竹中平蔵氏のブレーンとして構造改革を推進しました。退官後は慶應義塾大学大学院教授として教鞭を執りながら、経済学の視点から日本の政治・経済・社会問題に鋭く切り込む論客としても知られています。
本書では、経済産業省の内部事情や「失われた30年」の責任、そして日本がなぜ現在の状況に至ったのかについて、元官僚としての知見を交えながら冷静かつ厳しく分析しています。彼自身の「がん」との向き合い方についても語り、組織に隷属しない生き方の重要性を説いています。
異なるバックグラウンドを持つお二人ですが、「組織に隷属するのではなく、自分がやりたいことをやって生きていくことが重要だ」という点で意見が一致しており、この共通の哲学が、本書の根底に流れる力強いメッセージとなっています。死生観を共有する二人が、それぞれの経験と専門知識を融合させ、日本社会への「遺言」を私たちに残してくれた、極めて重要な一冊です。
2. 本書の要約
『遺言 絶望の日本を生き抜くために』は、経済アナリストの森永卓郎さんと、経済学者の岸博幸さんという、日本を代表する二人の識者が、がんによる余命宣告を受けたという重い現実を背景に、現在の日本社会が抱える問題点と、私たち個人がこの「絶望の日本」をどう生き抜くべきかについて、赤裸々に語り合った対談本です。
本書は、彼らの「死と向き合う」姿勢から始まり、日本の経済、政治、社会、そして個人の生き方まで、多岐にわたるテーマが本音で語られています。国民の9割が知らないような「残酷な現実」を浮き彫りにしつつ、絶望の淵から希望を見出すための「ビジョン」と「覚悟」を読者に問いかける内容となっています。
本書は以下の8つの章で構成されており、それぞれのテーマが深く掘り下げられています。
1章:さらば「霞が関」
お二人が経験した霞が関での宮仕えについて振り返ります。官僚機構の実態、そこでの経験が彼らの人生観やその後の活動にどう影響したのかが語られます。森永さんの「超貧困」からの急上昇、岸さんのエリート官僚としての道のり、そしてそれぞれの「霞が関を去った理由」が明らかになります。
2章:「がん」と向き合う
この章は、本書の最もパーソナルで切実な部分です。余命宣告を受けたお二人が、死とどのように向き合い、人生観や生き方がどう変わったのかを語ります。高額な治療費や、喫煙と「心の栄養剤」といった彼らのユニークな視点が示され、命の尊さや時間の有限性について深く考えさせられます。
3章:「失われた30年」と経済産業省
日本経済が停滞し続けた「失われた30年」の真の原因を探ります。企業が栄える一方で個人がやせ細る現状(GDP600兆円に対し、企業の内部留保550兆円、現預金330兆円)を指摘し、その責任の所在について経済産業省の内部事情も交えながら議論します。
4章:ザイム真理教
財務省が持つ強大な権力と、その政策決定システムについて、森永さんが提唱する「ザイム真理教」という独特の視点から批判的に分析します。増税が官僚の出世につながる構造など、霞が関の深部に切り込んだ本音トークが展開されます。
5章:防衛政策
日本の防衛政策、特に「対米従属」の現状について議論します。アメリカの根強い「優越思想」に触れ、日本がいつからこの路線に変わったのか、その転換点(1985年のプラザ合意や日航機墜落事件との関連性)について、お二人の異なる視点から考察が深まります。
6章:小泉構造改革
小泉純一郎元首相が行った「構造改革」が日本経済に与えた影響について、光と影の両面から徹底検証します。小泉氏、竹中平蔵氏、木村剛氏という「三大悪人」の評価や、その後の日本経済への影響について、率直な意見が交わされます。
7章:株式市場はバブルか?
現在の株式市場の状況を分析し、それが「バブル」なのかどうかについて議論します。「創造性のないAIバブル」という森永さんの見解など、現在の経済状況に対する厳しい視点が提示されます。
8章:森永流「これからの生き方」
本書の締めくくりとして、森永さんが提唱する、絶望の日本を生き抜くための具体的な「生き方」が語られます。特に「トカイナカ(都会と田舎の中間)で生きる」という提案や、首都機能移転の必要性など、従来の常識にとらわれない新しい生活様式が提案されます。
本書の要約を総括すると、『遺言』は、死と向き合う二人の識者が、現在の日本が抱える多層的な問題(経済、政治、社会構造)を徹底的に批判しつつ、その中で私たち個人が「組織に隷属せず、自分がやりたいことをやって生きていく」ことの重要性を強く訴える、未来への警鐘と希望の書です。彼らの「地に落ちた日本の経済力を再興するには、企業も人も『とことん頑張る』ことが絶対に必要だ」というメッセージは、読者に深い覚悟を促します。
3. ココだけは押さえたい一文
本書『遺言 絶望の日本を生き抜くために』の核心を突き、読者の心に最も深く響く「ココだけは押さえたい一文」として、私が選んだのは、お二人の共通の人生哲学であり、本書全体のメッセージを凝縮したこの言葉です。
「組織に隷属するのではなく、自分がやりたいことをやって生きていくことが重要だ」
この一文は、余命宣告を受け、死と向き合う中で彼らが辿り着いた、人生の真理とも言える生き方を示しています。現在の日本社会が抱える多くの問題の根底には、個人が組織や既存のシステムに縛られ、自分の意志とは異なる選択を強いられている現状がある、と彼らは暗に示唆しています。
しかし、お二人はその「絶望」の中で、それでも「自分がやりたいことをやって生きる」という選択肢を提示し、その重要性を力強く訴えかけています。これは、単なる理想論ではなく、彼ら自身が死を目前にして辿り着いた、最も本質的な「生き抜くための知恵」であり、読者への「遺言」に込められた最大のメッセージだと言えるでしょう。
4. 感想とレビュー
日々、経済や社会の動向にアンテナを張る立場として、お二人のような第一線の識者が、自身の命を懸けて語りかけるメッセージの重みをひしひしと感じました。
この本の最大の魅力は、やはり「余命宣告を受けた」という背景から語られる、お二人の一切の忖度がない「本音」でしょう。テレビやニュースでは決して聞けないような、日本の経済・政治の裏側や、官僚機構の深い闇について、彼らがこれほどまでに率直に語り尽くしていることに驚きを隠せませんでした。
森永さんの、自身の「超貧困」からの生い立ちや高額な治療費の話、そして「喫煙は心の栄養剤」と語る人生観は、時にユーモラスでありながらも、死と向き合う人間の真摯な姿を映し出しています。特に、彼が提唱する「トカイナカで生きる」というライフスタイルは、漠然と都会の喧騒に疲弊している私のようなビジネスパーソンにとって、具体的な未来の選択肢として非常に魅力的でした。
一方で、岸さんの元エリート官僚としての視点から語られる「失われた30年」の分析や、経済産業省の内部事情、そして「ザイム真理教」への言及は、日本の経済停滞の根源に鋭くメスを入れています。特に、企業が莫大な内部留保を抱えながら個人がやせ細る現状を指摘し、その責任の所在を具体的に追及する姿勢には、深く共感しました。
お二人の対談は、ときに意見が食い違う場面もありますが、それこそがこの本の面白さです。例えば、竹中平蔵氏の評価に対する森永さんと岸さんの微妙な温度差など、異なるバックグラウンドを持つ識者同士の議論だからこそ見えてくる多角的な視点がありました。それが、読者自身に「自分ならどう考えるか」を促してくれる良い刺激になります。
この本は、決して読者に「絶望」を突きつけるだけではありません。確かに日本の現状は厳しいことが語られますが、その中にも、個人が「組織に隷属するのではなく、自分がやりたいことをやって生きていく」ことの重要性という、力強い希望のメッセージが込められています。これは、私たちマーケターが、常に新しい価値を創造し、顧客に寄り添うために、既存の枠にとらわれずに挑戦し続ける姿勢にも通じるものだと感じました。
また、日本がなぜ「対米従属」の道を選んだのか、その歴史的な転換点(1985年のプラザ合意や日航機墜落事件との関連)について、森永さんが持つ独自の「睨み」と、当時経産省にいた岸さんの「肌感」が語られる部分は、まるで歴史のミステリーを解き明かすようで、非常に引き込まれました。
読了後には、今の日本が抱える課題の深さと、それに対して私たちが個人として何ができるのか、という問いが強く残りました。この「遺言」は、森永さんと岸さんという二人の知性が、命を削って私たちに残してくれた、未来への羅針盤のような一冊です。
5. まとめ
今回は、森永卓郎さんと岸博幸さんの共著『遺言 絶望の日本を生き抜くために』について、著者の紹介、本書の要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書は、共にがんを患い余命宣告を受けたお二人が、現在の日本社会が抱える多岐にわたる問題点(経済、政治、社会構造など)について、一切の忖度なく語り尽くした、まさに「命のメッセージ」が詰まった一冊です。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- 二人の著者による「命を懸けた」本音トーク:自身の闘病経験も交えながら、日本の現状を深く、時には痛烈に批判する。
- 多岐にわたるテーマ:「霞が関」の裏側、「失われた30年」の責任、「ザイム真理教」といった財務省批判、防衛政策、小泉構造改革、株式市場の動向など、多角的に日本社会を斬る。
- 「国民の9割が知らない残酷な現実」を浮き彫りにしつつ、私たち個人がどう生きるべきか、具体的なビジョンを提示。
- お二人の共通のメッセージは、「組織に隷属するのではなく、自分がやりたいことをやって生きていくことの重要性」。これが、「絶望の日本」を生き抜くための鍵として提示されている。
- 森永さんの「トカイナカで生きる」提案など、新しい生き方や価値観も紹介されている。
本書は、確かに日本の厳しい現実を突きつけますが、それは決して絶望のためだけではありません。その根底には、読者一人ひとりが現状を直視し、自らの意志で未来を切り開くための「ビジョン」と「覚悟」を促す、力強いメッセージが込められています。
もしあなたが、
- 「森永卓郎」さんや「岸博幸」さんの本音を聞きたい
- 今の日本社会の閉塞感に疑問を感じている
- 自分自身のキャリアや生き方について、新たな視点が欲しい
- 厳しい現実の中で、それでも前向きに生きるためのヒントを探している
と考えているなら、ぜひ一度、この『遺言 絶望の日本を生き抜くために』を手に取ってみてください。
きっと、あなたの日本社会への見方を大きく変え、そして、あなた自身の人生をより深く、力強く生きるための大きなきっかけとなるはずです。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。