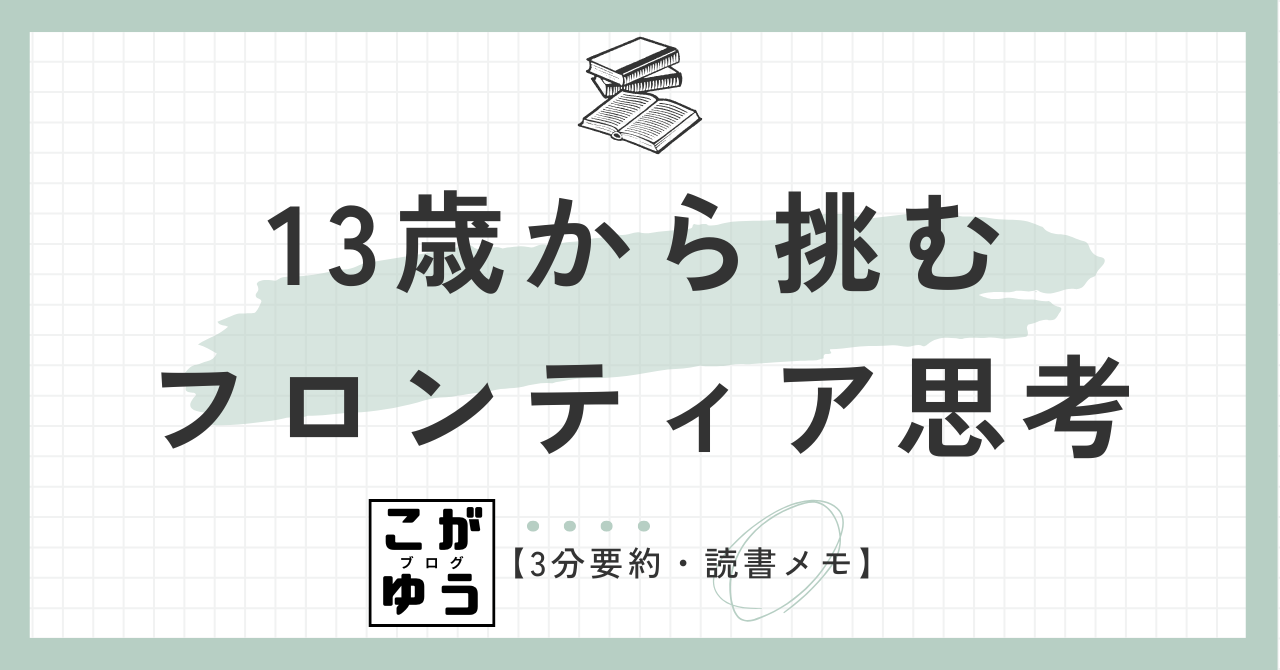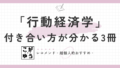あなたは「未知の課題」や「予期せぬ問題」に出会ったとき、どんな気持ちになりますか?
「困ったな…」
「どうしよう…」
「失敗したら嫌だな…」
もしそう感じがちなら、今日ご紹介する一冊は、あなたのものの見方、そして未来への向き合い方をガラリと変えるかもしれません。
今回ご紹介するのは、イグ・ノーベル賞受賞者であり、明治大学総合数理学部教授の宮下芳明さんによる『13歳から挑むフロンティア思考』です!
この本は、タイトルに「13歳から」とある通り、中学生から大人まで、誰もが分かりやすい言葉で「フロンティア思考」という新しい考え方を教えてくれます。未知の領域にワクワクしながら踏み込み、失敗さえもポジティブに捉えるための「方法論」と「心構え」が、具体例とともに詰まっています。
今日の記事が、予測不能な現代社会を楽しく、そして力強く生き抜くためのヒントとなることを願っています。ぜひ、最後までじっくりと読んでみてください!
1. 著者の紹介
本書『13歳から挑むフロンティア思考』の著者である宮下芳明さんは、明治大学総合数理学部 先端メディアサイエンス学科の教授です。
宮下教授の研究室では、最先端のメディア技術やインタラクションデザインに関する研究が行われています。特に、「味覚の電気刺激によって食べ物の味を変える研究」で世界的な注目を集め、2023年にはその研究がイグ・ノーベル賞(「人々を笑わせ、そして考えさせる」科学研究に贈られる賞)を受賞しました。この受賞は、彼の研究が持つユニークさと、既成概念にとらわれない「フロンティア思考」を体現していると言えるでしょう。
彼の研究スタイルは、まさに本書で語られる「未知の領域を探求する面白さ」そのもの。予想外の結果や難問に直面したときでも、「面白い!」「次はどうなる?」とポジティブな好奇心を持って取り組む姿勢は、多くの研究者や学生、そしてビジネスパーソンにとって大きな刺激となっています。
宮下教授は、専門的な研究活動だけでなく、一般の人々にも科学の面白さや探求することの楽しさを伝える活動にも力を入れています。その一環として、メディア出演や講演活動も積極的に行っています。
本書では、イグ・ノーベル賞受賞という彼個人の特別な経験やライフスタイルを前面に出すことはせず、読者誰もが「自分にも応用できる」普遍的な「フロンティア思考」を、身近な例を交えながら分かりやすく解説しています。専門家でありながら、その思考法を極めて平易な言葉で伝えようとする姿勢は、著者の「読者に寄り添う」という強い意志の表れと言えるでしょう。
2. 本書の要約
『13歳から挑むフロンティア思考』は、明治大学教授でイグ・ノーベル賞受賞者である宮下芳明さんが提唱する、未知の領域に踏み込むための「方法論」と「心構え」を学ぶための書籍です。タイトル通り「13歳」の読者も意識した、平易な言葉と身近な例で、誰にでも応用できる問題解決のヒントが詰まっています。
著者は、「フロンティア」を単なる国境や境界ではなく、「未知の領域」を探求するという意味で使っています。そして、このフロンティア思考の根幹にあるのは、未知の問題や予想外の結果に出会ったときに「面白い!思ってたのと違う!次はどうなるのだろう?」と高揚感を持つ、ポジティブな姿勢です。まるでオープンワールドのゲームを攻略するように、楽しみながら試行錯誤を重ねる好奇心こそが、フロンティア思考を加速させると語っています。
本書は、読者が失敗や未知の問題に出会ったときに「脳内ゲーム実況」を使うことを推奨しています。ゲーム実況者のように自分を解説し、トラブルや失敗をむしろ「おいしい展開」と捉えることで、ワクワクしながら課題に取り組む姿勢を育むことができると説きます。
本書の執筆方針として、以下の点が挙げられています。
- 「13歳」の読者を意識:難しいビジネス用語や専門用語を極力使わず、分かりやすい言葉でフロンティア思考を解説。大人が読んでも十分に有益な内容。
- 「偉人」の事例を一切使わない:著名な学者や実業家、アスリートといった特別な事例ではなく、「どんな人にも応用できる方法」をまとめることを重視。
- 著者個人の経験も紹介しない:イグ・ノーベル賞受賞までの経緯や個人のライフスタイルには触れず、読者が「自分にもできそうだ」と感じられる普遍性を追求。
- 身近な事例を多用:日常生活の中で誰もが経験したことがある場面やイベント、身近なものを例に挙げることで、読者の実感と共感を最優先。同じ事例を複数の章で再利用し、視点を変えることで新たな発見があることを実感させる工夫も凝らしている。
- 方法論と心構えの両輪:何をどう観察し、どう検証するかという「方法論」だけでなく、その時にどんな気持ちで取り組むかという「心構え」の重要性を強調。
本書は以下の7つのチャプター(章)で構成されており、それぞれでフロンティア思考を構成する要素と実践方法が具体的に示されています。
CHAPTER.01:「問題」の性質
問題の発見から「問題視」の重要性、そして日常生活が研究活動に通じることなど、問題への向き合い方の基礎を解説します。正解のある問題とない問題の違いも示唆します。
CHAPTER.02:「解」の多様性に挑む
「選べる解」がすべて正解ではないこと、解の選択肢を自分で生み出すこと、評価軸が変われば解の順位も変わることなど、多様な解の探索とその評価について論じます。
CHAPTER.03:解探索」の方法論
「そもそも?」の問いかけで目的や手段を疑うこと、実行しながら解を探索すること、生成AIの力を借りるなど、具体的な解の探し方とアプローチを提示します。
CHAPTER.04:解を「実行」する
ポジティブな「失敗」と「反省」、成功しても「失敗」と呼んでみる発想、スモールスケールでの試行錯誤、他人を「バーチャルな自分」として見るなど、実行段階での心構えと工夫を解説します。
CHAPTER.05:仲間と挑む――協力と衝突を味方に
未知の領域へ一人ではなく仲間と踏み出すこと、多様な役割を担うことの重要性など、チームでの問題解決について語ります。
CHAPTER.06:問題解決を加速させる「コミュ力」
相手を笑わせる会話、良い質問の考え方、「匿名の失敗」でダメージなく反省するなど、コミュニケーション能力が問題解決にどう貢献するかを解説します。
CHAPTER.07:フロンティア思考へのさらなる挑戦
常識を覆し、社会の枠組みまで変える視点、違和感を抱え続けることの重要性、情報収集のアンテナの張り方、異なるものの共通点を探して「つなげる」力など、フロンティア思考をさらに深めるためのヒントを提示します。
本書の要約を総括すると、『13歳から挑むフロンティア思考』は、複雑な世界で変化を恐れず、むしろ楽しんで未知に挑むための、普遍的な「思考法」と「心の持ち方」を、誰にでも理解できるように丁寧に解き明かした一冊です。読者が「これなら自分にもできそうだ」と感じ、日常の問題や新しいチャレンジに前向きに取り組むきっかけとなることを目指しています。
3. ココだけは押さえたい一文
本書『13歳から挑むフロンティア思考』の核心を突き、読者の心に最も深く響く「ココだけは押さえたい一文」として、私が選んだのは、フロンティア思考の根幹にあるポジティブな姿勢を象徴するこの言葉です。
「未知の問題に出合ったときに『面白そう』と好奇心を持って、ワクワクしながら謎解きや攻略に向かう姿勢。」
この一文は、フロンティア思考の最も重要な「心構え」を端的に表しています。多くの人が避けたいと考える「未知の問題」や「困難」に対して、ネガティブな感情を抱くのではなく、「面白そう」という好奇心を抱き、まるでゲームを攻略するかのようにワクワクしながら取り組む姿勢こそが、フロンティア思考の原動力であることを示しています。
このポジティブな視点こそが、失敗を恐れずに新しい挑戦を楽しみ、困難を乗り越えるための鍵となる、本書の最も重要なメッセージであると言えるでしょう。
4. 感想とレビュー
宮下芳明さんの『13歳から挑むフロンティア思考』は、まさに「凝り固まった頭をほぐしてくれる」、そんな気づきに満ちた一冊でした。普段、ビジネスの世界では「問題解決」というと、フレームワークを駆使したり、論理的な思考を重ねたりすることが重視されがちですが、この本は、もっと根本的な「心構え」と「楽しむ姿勢」の重要性を教えてくれます。
まず、「13歳から」というタイトルと、ビジネス用語や偉人のエピソードを一切使わないという執筆方針に、著者の「誰にでもこの思考法を届けたい」という強い思いを感じました。これが、読み手にとって非常にフレンドリーで、スッと頭に入ってくる理由だと思います。私のようなビジネスパーソンが読んでも、普段使っている専門用語を一度リセットし、本質的な「考える楽しさ」を取り戻すきっかけになりました。
特に印象的だったのは、「未知に出合うときこそワクワクする」「脳内ゲーム実況を使う」といった、フロンティア思考の根幹にあるポジティブな姿勢です。マーケティングの仕事でも、新しい市場を開拓したり、予期せぬトラブルに対応したりすることは日常茶飯事です。そんな時、「困った…」と眉間にしわを寄せるのではなく、「面白い!」「次はどうなる!?」とワクワクする視点を持つことで、停滞していた状況が動き出すかもしれない、と大きなヒントを得ました。まるで、自分が主人公のオープンワールドゲームを攻略しているように問題に取り組むという発想は、まさに目から鱗でしたね。
そして、「方法論」と「心構え」の両輪で語られている点も非常に実践的だと感じました。「そもそも?」の問いかけで目的や手段を疑うことや、「スモールスケール」で失敗を経験すること、さらには生成AIの力を借りるなど、具体的なアクションステップが提示されているので、読みっぱなしで終わることなく、すぐに実践できるイメージが湧きました。
また、「同じ事例を複数の章であえて再利用」しているという工夫も、読者にとって非常に有益です。同じ場面でも視点を変えれば、こんなに新たな発見があるんだ、ということを実感させられます。これは、マーケティングで多角的な視点を持つことの重要性や、PDCAサイクルを回す上での「反省」の質を高めるヒントにもなると感じました。
この本は、単なる問題解決のハウツー本ではありません。むしろ、変化の激しい現代社会において、いかに「未知」を恐れず、むしろ楽しんで探求し、自らの力で未来を切り拓いていくか、そのための「心のあり方」と「実践的な知恵」を教えてくれる一冊です。
もしあなたが、
- 「フロンティア思考」という考え方に興味がある
- 宮下芳明教授のユニークな視点に触れてみたい
- 仕事や日常生活で直面する「問題」を、もっと楽しく解決したい
- 失敗を恐れず、新しいことに挑戦する勇気が欲しい
- 変化の激しい時代を、ワクワクしながら生き抜くヒントを探している
と感じているなら、ぜひこの『13歳から挑むフロンティア思考』を手に取ってみてください。
きっと、あなたの「考える」ことへの意識が変わり、目の前の課題が「面白い謎解き」に思えるようになるはずです。そして、何よりも「未知」に挑む楽しさを教えてくれる、そんな素晴らしい体験があなたを待っています。
5. まとめ
今回は、宮下芳明さんによる『13歳から挑むフロンティア思考』について、著者の紹介、本書の要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書は、「人生100年時代」を生き抜くために、未知の領域にワクワクしながら踏み込むための「方法論」と「心構え」を、「13歳から」理解できるように平易な言葉と身近な例で解説してくれる一冊です。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- 「フロンティア思考」とは:未知の領域を探求する考え方で、「方法論」と「心構え」の二つの要素からなる。
- ポジティブな心構え:未知の問題や失敗を「面白い!」「おいしい展開」と捉え、ゲーム感覚で楽しむ「脳内ゲーム実況」を推奨。
- 普遍的な応用性:著者の特別な経験や偉人のエピソードではなく、誰にでも身近な事例を使い、どんな人にも応用できる方法をまとめている。
- 実践的な方法論:「そもそも?」の問いかけ、解の多様性、実行しながらの探索、生成AIの活用、スモールスケールでの失敗など、具体的なアクションステップを提示。
- コミュニケーションと協調性:仲間と協力することの重要性や、問題解決を加速させる「コミュ力」についても言及。
『13歳から挑むフロンティア思考』は、変化の激しい現代社会において、「問題」を恐れるのではなく、「面白がる」ことで、主体的に未来を切り拓く力を養うための強力なガイドブックです。年齢や立場に関係なく、誰もが今日から実践できるヒントが満載で、私たち自身の好奇心を刺激し、新しい挑戦への一歩を後押ししてくれるでしょう。
この本を読んだあなたも、目の前の「未知」を「面白いフロンティア」に変えてみませんか?
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。