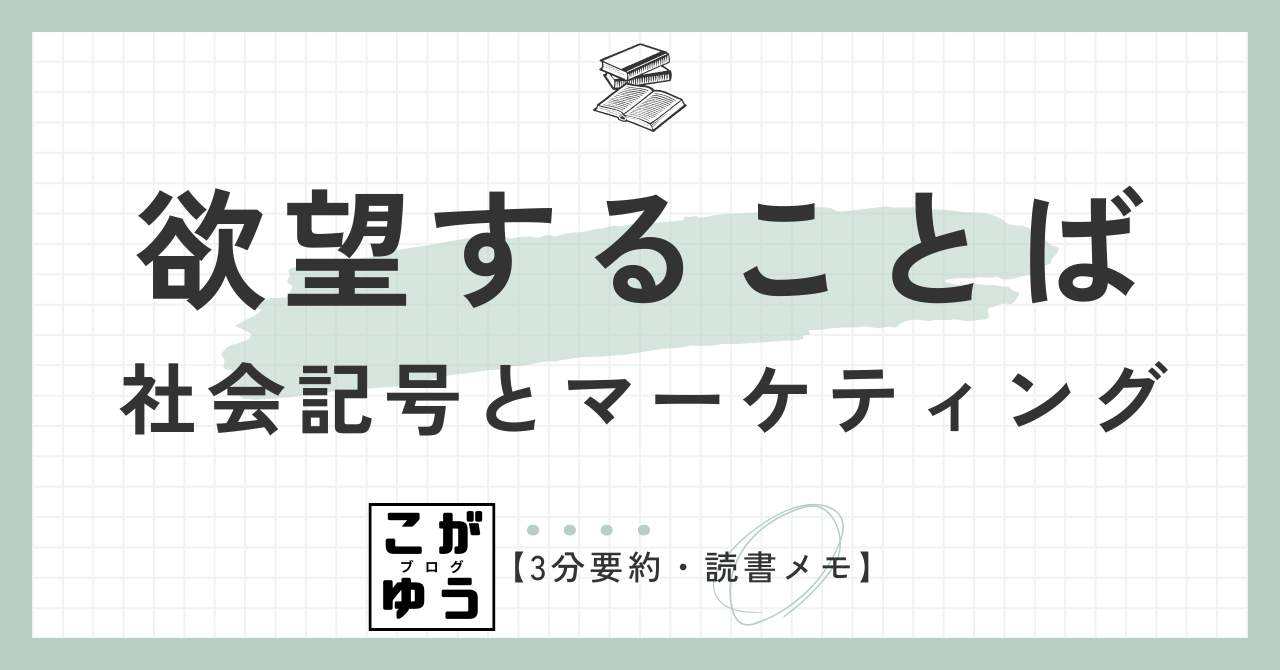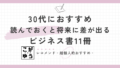あなたは最近、どんな新しい言葉に出会いましたか?
「インスタ映え」「美魔女」「おひとりさま」「イクメン」…
いつの間にか当たり前のように使われているこれらの言葉が、実は私たちの消費行動や社会のトレンドを大きく動かしているとしたら、どう思いますか?
今日ご紹介するのは、そんな「ことば」が持つ知られざる力に迫る、『欲望する「ことば」』です!
著者は、広告界のトップランナーである嶋浩一郎さんと、マーケティング研究の第一人者である松井剛さん。実務家と研究者という、異色のタッグが「ことば」と「欲望」、そして「市場」のダイナミズムを解き明かします。
この本は、私たちが普段意識しない「ことば」の奥深さと、それがビジネスや社会に与える影響を教えてくれます。
「ことば」がどのように生まれ、どんなプロセスを経て社会に定着し、私たちの「欲望」を顕在化させ、新たな市場を創出していくのか。そのメカニズムを知ることは、マーケターとして、そして現代社会を生きる一人の消費者として、非常に重要な視点を与えてくれます。
今回のブログ記事では、この刺激的な一冊の魅力を、以下の構成で深掘りしていきます。
ぜひ最後までじっくりと読んで、あなたも「ことば」の持つ知られざる力について一緒に考えてみませんか?
1. 著者の紹介
本書『欲望する「ことば」』は、広告・マーケティング業界の第一線で活躍する実務家と、気鋭のマーケティング研究者という、まさに最強のタッグによって書かれました。
嶋 浩一郎(しま こういちろう)氏
広告業界のカリスマ的存在であり、博報堂のクリエイティブ局でPRに携わった後、博報堂ケトルの共同CEOを務められています。広告ビジネスの枠を超えた幅広い活動でも知られ、2004年には「本屋大賞」の立ち上げに参画し、その成功に大きく貢献しました。また、カルチャー誌『ケトル』の編集長を務めるほか、2012年には東京・下北沢にユニークな本屋「B&B」を内沼晋太郎氏と共同で開業するなど、常に新しい文化とビジネスの接点を生み出し続けています。
嶋氏は、「ことば」をいかに世の中に広め、人々の行動を変えるかというPRの現場で長年培ってきた、実践的な知見と洞察力の持ち主です。特に、人々の潜在的な欲望を言語化し、新しいトレンドや市場を創出する「社会記号」の生みの親としての視点は、本書の大きな魅力となっています。
松井 剛(まつい ごう)氏
一橋大学商学研究科の教授で、商学博士。専門はマーケティング、社会文化学、消費者行動論と多岐にわたります。2007年から2009年までプリンストン大学社会学部客員フェローを務めるなど、国内外で精力的に研究活動を行っています。
松井教授は、特に「言葉とマーケティングの関係」について15年以上にわたり研究を続けてきた大学教授であり、その学術的な裏付けが本書の考察に深みを与えています。社会や文化の中で「ことば」がどのように機能し、消費者の行動に影響を与えるのかを、理論的かつ多角的に分析しています。
この二人の共著である本書は、嶋氏の現場での経験と洞察、そして松井教授の研究に基づく学術的な知見が融合することで、「ことば」の力が世の中を動かすメカニズムを、実務と理論の両面から深く掘り下げています。単なるビジネス書ではなく、私たちが生きる社会のあり方を理解するための、示唆に富んだ一冊と言えるでしょう。
2. 本書の要約
『欲望する「ことば」』は、広告界の第一人者である嶋浩一郎氏と、マーケティング研究者の松井剛氏が共著で、「ことば」が人々の欲望を顕在化させ、新たな市場や社会現象を生み出すメカニズムを解き明かす一冊です。
本書の中心テーマは、「社会記号」と呼ばれる概念です。著者は、「女子力」「加齢臭」「草食男子」「婚活」「美魔女」「おひとりさま」「イクメン」「インスタ映え」といった、いつの間にか私たちの日常に溶け込み、当たり前のように使われている造語や言葉を「社会記号」と定義します。そして、これらの社会記号が、私たちの世界の見え方を一変させ、さらにはマーケットを支配していく力を持つと指摘します。
本書の目的は、この「社会記号」がどのように生まれ、どんなプロセスを経て社会に定着していくのか、そしてなぜ人々は新しい「ことば」を求めるのかを、マーケティングのプロと研究者、それぞれの視点から考察することにあります。人々の潜在的な欲望をあぶり出し、世の中を構築し直す「社会記号」のダイナミズムに迫る構成となっています。
具体的な内容としては、以下の章立てで「ことば」と「欲望」の密接な関係を深掘りしています。
はじめに:社会記号が世の中を動かす
本書の導入として、社会記号が現代社会においていかに大きな影響力を持っているかを提示します。
第1章:ハリトシス・加齢臭・癒し・女子―社会記号の持つ力
「加齢臭」という言葉が資生堂によって生み出され、それまで意識されていなかった「臭い」が社会問題として顕在化し、新たな市場を創出した事例などを紹介。「フレーミング効果」という行動経済学の概念を用いて、「ことば」が人々の認識や意思決定にどう影響するかを解説します。他にも「女子アナ」から派生した「女子力」「女子会」への言葉の変遷なども考察します。
第2章:いかに社会記号は発見されるか―ことばと欲望の考察
人々の潜在的な欲望をいかに発見し、それを「ことば」として言語化するかのプロセスを考察します。ウォークマンやスターバックスの事例を挙げ、人々は「それ」を見るまで「それ」が欲しいと意識しない、というスティーブ・ジョブズの言葉や、思想家・内田樹の「欲望は自存しない。目の前にそれを満たすものが出てきてはじめて発現する」という考え方を引用し、人間は自らの欲望を言語化できない、という原則を提示します。
第3章:ことばが私たちの現実をつくる―社会記号の機能と種類
社会記号が持つ機能と種類について掘り下げます。例えば、「ファストファッション」という社会記号と「ユニクロ」といったブランドが結びつき、第一想起ブランドとして定着していくことで、市場における競争優位性が確立されることを論じます。
第4章:メディアが社会記号とブランドを結びつける―PRの現場から
PRの視点から、社会記号がいかにメディアを通じて拡散し、ブランドと結びつくことで最も効果を発揮するかを解説します。雑誌が読者の無自覚な欲望を引き出し、顕在化させる「社会記号の発生装置」としての役割を担ってきたことを指摘します。
第5章:なぜ人は社会記号を求めるのか―その社会的要請
人々が新しい社会記号を求める社会的背景や要請について考察します。社会の変化や多様化する価値観の中で、人々が自らの立ち位置やアイデンティティを確立するために、新しい「ことば」がいかに必要とされているかを分析します。
第6章:対談 誰が社会記号をつくるのか
共著者二人の対談形式で、社会記号の生成とコントロールの難しさ、マスメディアが依然として社会記号化(コンセンサス形成)に有利であること、そして「文句」や「日常の違和感」の中に隠れたインサイトを見つける重要性について語り合います。
おわりに:社会記号をクリティカルに捉える消費者になるには?
消費者が社会記号を盲目的に受け入れるだけでなく、その背後にある意図や影響をクリティカルに(批判的に)捉えることの重要性を問いかけ、賢い消費者になるための視点を提供します。
本書の要約を総括すると、『欲望する「ことば」』は、私たちの日常に溢れる「ことば」が、単なる情報伝達のツールではなく、人々の潜在的な欲望を刺激し、行動を促し、そして社会や市場そのものを再構築する強力な力を持つ「社会記号」であることを、具体的な事例と深い考察で解き明かした、マーケティング、社会学、言語学にまたがる洞察に満ちた一冊です。読者はこの本を通じて、消費行動や社会現象を見る目が変わり、より多角的な視点を得ることができるでしょう。
3. ココだけは押さえたい一文
本書『欲望する「ことば」』の核心を突き、読者の心に最も深く響く「ココだけは押さえたい一文」として、私が選んだのは、この本の主要なテーマである「社会記号」の力を端的に表すこの言葉です。
「社会記号は、世界の見え方を一変させ、マーケットを支配していく」
『欲望する「ことば」』
この一文は、本書が私たちに伝えたい最も重要なメッセージであり、普段私たちが何気なく使っている言葉、特に「女子力」「加齢臭」といった造語が、単なる流行語にとどまらない、現実を変えるほどの絶大な力を持っていることを明確に示しています。
新しい言葉が生まれることで、それまで存在しなかった課題が顕在化したり、新しい価値観が創造されたりし、その結果、私たちの消費行動や市場の構造そのものが大きく変化していく。このダイナミズムを理解することこそが、本書の最大の目的であると言えるでしょう。
モノを売るには言葉もまた売らなくてはならない
『欲望する「ことば」』
欲望というのは実在するものではなく、『それを満たすものが目の前に出現したとき』に発動するものである
『欲望する「ことば」』
人はすでに言語化した欲望に応えてくれるプレーヤーには、あまり感謝しない
『欲望する「ことば」』
クレームこそビジネスチャンスといいますが、私は人々の「何気ない文句」にこそインサイト発見のチャンスがあると思っています。
『欲望する「ことば」』
われわれは、生まれる君につけた言語の規定する線にそって自然と分割する
『欲望する「ことば」』
広報やマーケティングの担当者なら、自社の商品を語るのではなく現象を語ることができる広報パーソンを目指すべき
『欲望する「ことば」』
例外事例として見るか、新しい欲望の萌芽、予兆として見るか、そこの違いは大きい
『欲望する「ことば」』
定量は過去、定性は現在、予兆は将来
『欲望する「ことば」』
4. 感想とレビュー
普段から「どうすればお客様の心に響くか」「どうすれば商品が売れるか」を考えていますが、その根源にある「ことば」と「欲望」のメカニズムをこれほど深く、そして多角的に掘り下げた本は他に類を見ません。
まず、「社会記号」という概念に度肝を抜かれました。「女子力」「加齢臭」「インスタ映え」など、私たちが当たり前に使っている言葉の数々が、実は綿密な意図や偶然の作用によって生まれ、それが人々の意識を変え、最終的に巨大な市場を形成していくという指摘は、まさに鳥肌モノでした。
特に、「加齢臭」の事例は衝撃的で、資生堂が「ノネナール」を発見し、それを「加齢臭」という言葉でフレーミングすることで、これまで存在しなかった「悩み」が顕在化し、一気に市場が生まれたというメカニズムには、マーケターとして唸らされましたね。
本書の大きな魅力は、嶋さんのPRやブランディングの現場での肌感覚と、松井教授のマーケティング研究に基づく学術的な視点が絶妙に融合している点です。例えば、第2章で語られる「人間は自らの欲望を言語化できない」「欲望は自存しない」という哲学的な考察は、スティーブ・ジョブズや内田樹氏の言葉を引用しながら、私たちが「お客様のインサイト」を探る上で、いかに表面的なアンケート調査だけでは不十分かを示唆してくれます。
お客様が本当に欲しているものは、お客様自身も気づいていない、言語化できていない「何か」なのだと再認識させられました。
また、雑誌が「社会記号の発生装置」として重要な役割を担ってきたという指摘も非常に面白かったです。ターゲットが明確な仮想コミュニティである雑誌が、読者の無自覚な欲望を顕在化させ、新しい言葉を生み出してきたという分析は、現代のSNS時代における「コミュニティ」の重要性や、インフルエンサーマーケティングにも通じる普遍的な示唆があると感じました。
さらに、最終章の対談や「おわりに」で語られる、社会記号をクリティカルに捉える視点や、リスクについても触れられている点が、単なる成功法則を語る本ではない、本書の深みを感じさせました。「草食系男子」のように、ポジティブな意味合いで生まれた言葉が、メディアを通じてネガティブな意味に変質していく事例は、言葉の持つ力と同時に、その危うさも教えてくれます。
これは、マーケティングにおいて、常に「言葉」が社会に与える影響を意識し、倫理的な視点を持つことの重要性を再認識させてくれました。
この本は、広告やマーケティングに関わる人だけでなく、「ことば」が持つ力を理解し、世の中のトレンドや人々の行動を深く洞察したい全ての人にとって、必読の一冊だと強くお勧めします。私たちは日々、数えきれないほどの「ことば」に囲まれて生きていますが、その裏側に隠された「欲望」と「市場」のメカニズムを知ることで、世界の見え方が全く変わるでしょう。
5. まとめ
今回は、嶋浩一郎さんと松井剛さんの共著『欲望する「ことば」』について、著者の紹介、本書の要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書は、私たちの日常に溢れる「ことば」、特に「社会記号」と呼ばれる造語や流行語が、いかに人々の潜在的な欲望をあぶり出し、新たな市場や社会現象を創り出す強力な力を持つかを、実務と研究の両面から深く掘り下げた一冊です。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- 「社会記号」の定義と力:「女子力」「加齢臭」などの言葉が、人々の認識や行動を変え、マーケットを支配していくメカニズムを解説。
- 「欲望」の正体:人々は自らの欲望を言語化できないこと、欲望は「それ」を見て初めて顕在化することなど、深層心理に迫る洞察。
- メディアの役割:雑誌などのメディアが、社会記号を生み出し、ブランドと結びつける「発生装置」として機能するプロセスを詳述。
- 実践と理論の融合:広告・PRの現場で培われた嶋氏の知見と、マーケティング研究の松井教授の学術的考察が、本書の説得力を高めている。
- 社会記号のリスク:一過性の流行で終わる「泡沫社会記号化」や、意味が変質してしまう「価値の変容」といったリスクにも言及。
『欲望する「ことば」』は、単なるビジネス書ではありません。私たちが日々触れる「ことば」の裏側に隠された、人々の深層心理や社会の動きを読み解くための、洞察力とクリティカルな視点を与えてくれる、まさに知の宝庫です。マーケターはもちろん、ジャーナリスト、クリエイター、そして現代社会を生きる全ての人にとって、必読の一冊となるでしょう。
この本を読んで、あなたも「ことば」の持つ無限の可能性と、その奥深さに触れてみませんか?
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。