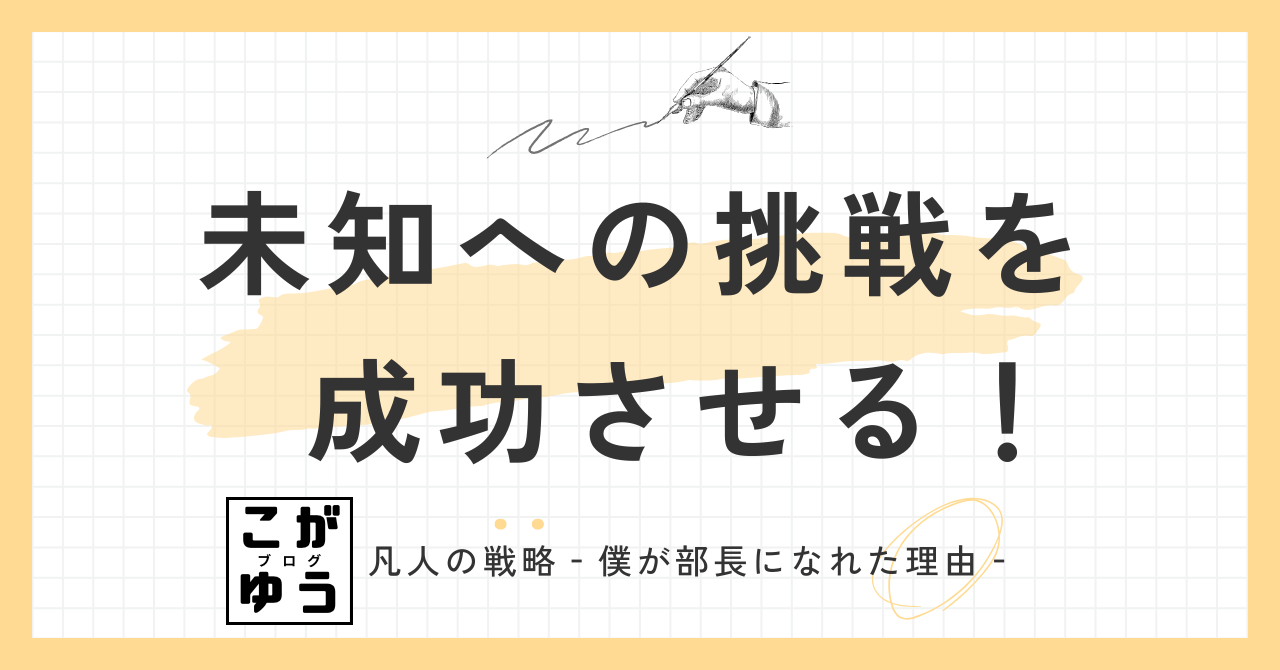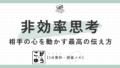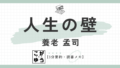皆さん、こんにちは!
これまでの日本企業は、繰り返しの多い業務を正確に、そして効率的にこなすことで、その強みを発揮してきました。素晴らしいことですよね。
でも、今の時代はどうでしょう?社会はものすごいスピードで変化し、私たちは「これまでのやり方」が通用しない、予測不可能な「プロジェクト」という取り組みに日々直面しています。
新しい技術の導入、未開拓市場への進出、前例のない社会課題への対応…。これらはまさに、答えが見えない中で進んでいく「プロジェクト」です。
そして、こうした不確実性を伴うプロジェクトを成功させるためには、これまでとは違う考え方や、新しい対応が必要とされています。
「なんだか難しそう…」「どうすればいいんだろう?」そう感じるかもしれませんね。でも、大丈夫!今日のテーマは、そんな不確実性の中でも、あなたのチームを力強く導き、プロジェクトを成功に導くための「プロジェクトマネジメントの基礎知識」です。
特別な専門知識がなくても、誰でも意識し、実践できる大切なポイントを、皆さんにわかりやすくお伝えしていきます。
この記事は、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』を参考に書かせていただきました。
プロジェクト計画についての正しい認識を持つ ~変化に対応する地図の描き方~
「プロジェクト計画」と聞くと、完璧な計画を最初に立てて、その通りに進めなければならない、と思っていませんか?もしそうだとしたら、その認識は、不確実性の高い現代のプロジェクトにおいては、少し見直す必要があるかもしれません。
これまでの繰り返し業務では、計画は一度立てたら大きく変更しないのが常識でした。しかし、プロジェクト、特に予測が難しいものにおいては、初期段階で完璧な計画を立てることは、ほとんど不可能です。なぜなら、プロジェクトが進むにつれて、新しい情報が入ってきたり、市場の状況が変わったり、予期せぬ問題が発生したりするからです。
プロジェクト計画についての正しい認識とは、「計画は生き物であり、常に変化に対応しながら更新していくもの」だということです。
- 計画は「地図」ではなく「羅針盤」:
完璧な地図を描き、その通りに進むことを目指すのではなく、プロジェクトの最終的な目標という「北極星」をしっかりと定め、そこに向かっていくための「羅針盤」だと考えましょう。時には、天候の変化で航路を変えるように、計画も柔軟に見直す必要があります。 - 初期計画は「仮説」:
プロジェクト開始時に立てる計画は、あくまでその時点での最善の「仮説」です。プロジェクトを進める中で得られる新たな情報や学びを元に、その仮説を検証し、必要に応じて修正していく前提に立ちましょう。 - 「計画すること」と「計画」:
重要なのは、完成した「計画書」そのものよりも、「計画を立てるプロセス」です。チームで議論し、目標を共有し、潜在的なリスクを洗い出す。このプロセス自体が、チームの結束力を高め、共通理解を深める貴重な時間となります。 - アジャイルな思考を取り入れる:
短い期間で計画・実行・評価・改善を繰り返す「アジャイル」の考え方も参考になります。大きな計画を一度に立てるのではなく、小さなサイクルで進捗を確認し、柔軟に方向転換していくことで、変化に強いプロジェクトを創ることができます。
不確実性の高い時代において、プロジェクト計画は「固めるもの」ではなく、「育てるもの」という認識を持つことが、成功への第一歩です。
決めるべきことを適切に決める ~意思決定の質を高める~
不確実性が高いプロジェクトでは、「何を決めるべきか」「いつ決めるべきか」という意思決定が非常に重要になります。しかし、曖昧なまま進めたり、逆にすべてを詳細に決めすぎたりすると、プロジェクトは停滞してしまいます。
プロジェクトマネジメントの基礎として重要なのは、「決めるべきことを、その時に応じて適切に決める」ことです。
- 最終目標は明確に、手段は柔軟に:
プロジェクトの最終的な目標や達成したいこと(What)は、開始時に明確に定め、チーム全体で共有しましょう。しかし、そこに到達するための具体的な手段やプロセス(How)は、プロジェクトの進捗や状況に応じて柔軟に決定していく余地を残しておくことが重要です。 - 意思決定のタイミングを見極める:
「後で決める」ことが許されることと、「今すぐ決めなければならない」ことを見極める力が必要です。例えば、初期段階で詳細な技術仕様をすべて決めてしまうと、後で新しい技術が出た際に変更が困難になります。しかし、顧客へのリリース日は早めに決定し、共有すべきでしょう。 - 決定事項の明確化と共有:
何かを決めたら、その内容、理由、決定者、決定日を明確にし、チーム全体に共有することを徹底しましょう。特に、変更点があった場合は、その経緯と理由も併せて伝えることで、認識の齟齬を防ぎます。 - 「決めないこと」も決める:
時には、「この時点では決めない」という意思決定も重要です。今は情報が不足している、あるいは状況が変化する可能性がある、と判断した場合は、その旨を明確にし、いつまでに何を揃えて決定するかを定めます。これにより、無駄な議論や手戻りを防ぎます。 - 意思決定の権限を明確に:
誰が、何を決定する権限を持っているのかを明確にしておくことも大切です。これにより、意思決定のスピードが向上し、責任の所在もはっきりします。
「決めるべきことを適切に決める」というスキルは、不確実な状況下でプロジェクトをスムーズに進めるための要となります。これは、経験と学びによって磨かれる、非常に価値のある能力です。
プロジェクトの実行チームに責任を負わせすぎない ~協働とサポートの文化~
不確実性の高いプロジェクトでは、予期せぬ問題や変更が頻繁に発生します。そんな時、「実行チームが悪い」「現場の責任だ」と、すべての責任をプロジェクトの実行チームに負わせすぎてしまうと、彼らは萎縮し、自律性や創造性を失ってしまいます。
成功するプロジェクトマネジメントでは、プロジェクトの実行チームに責任を負わせすぎず、むしろ彼らを積極的にサポートし、協働する文化を築きます。
- 「予測できない」ことを前提に:
不確実なプロジェクトでは、計画通りに進まないことが前提です。予期せぬ問題が発生した際も、「なぜそうなったのか」を冷静に分析し、誰かを責めるのではなく、解決策を見つけることに集中しましょう。 - リスクと課題を共有する:
プロジェクトの初期段階から、潜在的なリスクや課題をチーム全体で共有し、認識のズレがないように努めましょう。そして、問題が発生した際には、それを隠さずにオープンに報告できる環境を作ることが重要です。 - マネージャーの役割は「障害を取り除くこと」:
実行チームのメンバーは、目の前のタスクに集中できるよう、マネージャーは彼らの作業を妨げる障害(例:リソース不足、他部署との連携問題、意思決定の遅れなど)を積極的に取り除く役割を担いましょう。 - 成功も失敗もチームで共有:
成果が出た時はもちろん、期待通りの結果にならなかった時も、それを個人の責任とするのではなく、チーム全体の学びとして共有しましょう。失敗から何を学んだかを議論し、次の改善に繋げることが、チームの成長を促します。 - 心理的安全性を提供:
メンバーが安心して意見を言えたり、困っていることを相談できたり、失敗を恐れずに新しいことに挑戦できたりする「心理的安全性」の高い環境を創りましょう。これは、チームの創造性と生産性を最大限に引き出すために不可欠です。
プロジェクトの成功は、実行チームの頑張りだけで決まるものではありません。意思決定者やマネージャーが、彼らを信頼し、サポートし、共に困難に立ち向かう姿勢が、チーム全体の力を引き出し、不確実なプロジェクトを成功へと導くのです。
意思決定者とプロジェクト実行チームの対話を進める ~「なぜ」と「今」を繋ぐ橋~
不確実性の高いプロジェクトにおいて、最も重要なことの一つが、「意思決定者」と「プロジェクト実行チーム」間の活発な対話です。
この対話が不足すると、意思決定は現場の実情から乖離し、実行チームは「なぜこれをやっているのか」という目的を見失ってしまいます。
- 意思決定者の役割:ビジョンと方向性の共有:
意思決定者は、プロジェクトの「なぜ(Why)」、つまり最終的な目的、目標、ビジョン、そしてそれに伴うリスク許容度を明確に示し、プロジェクト実行チームに深く共有する必要があります。これにより、実行チームは、日々の業務が何に繋がっているのかを理解し、より主体的に判断できるようになります。 - 実行チームの役割:現状と課題の共有:
プロジェクト実行チームは、現場の「今(What is now)」、つまりタスクの進捗状況、直面している課題、発見された新しい情報、必要なリソースなどを、意思決定者に正確かつタイムリーに報告する責任があります。これにより、意思決定者は、リアルタイムの状況に基づいた、より適切な判断を下すことができます。 - 双方向のフィードバックループ:
一方的な指示や報告だけでなく、双方向のフィードバックループを構築することが重要です。意思決定者は、実行チームからの報告に対して具体的な質問を投げかけ、理解を深めます。実行チームは、意思決定者の意図を再確認したり、懸念点を伝えたりする機会を持ちます。 - 定期的なコミュニケーションの場:
定例会議だけでなく、必要に応じて迅速に意思決定者と実行チームが直接対話できる場を設けましょう。コーヒーブレイクやランチタイムなど、非公式な場でのコミュニケーションも、信頼関係を築き、本音を引き出す上で有効です。 - 「透明性」と「共感」:
お互いの立場や抱える制約を理解し、共感する姿勢が大切です。意思決定者は、現場の苦労に寄り添い、実行チームは、経営層の視点やプレッシャーを理解しようと努めます。透明性の高い情報共有は、この共感を育みます。
この活発な対話は、意思決定の質とスピードを高めるだけでなく、意思決定者と実行チーム間の信頼関係を深めます。これにより、プロジェクト全体が一体となって、不確実な未来に立ち向かう強靭な組織へと成長していくでしょう。
まとめ
今回のテーマ「不確実性時代のプロジェクトマネジメント基礎知識」は、これまでの「繰り返し業務」とは異なる、「プロジェクト」という未知への挑戦を成功させるための、新しい視点と具体的なアプローチについて深く探求してきました。
まず、プロジェクト計画に対する正しい認識を持つことが重要です。計画は一度きりの「地図」ではなく、常に変化に対応しながら更新していく「羅針盤」だと捉え、アジャイルな思考を取り入れましょう。これにより、予測不可能な状況にも柔軟に対応できる強さが生まれます。
次に、決めるべきことを適切に決めること。最終目標は明確にしつつも、手段は柔軟性を保ち、意思決定のタイミングを見極めることで、プロジェクトの停滞を防ぎ、質の高い判断が可能になります。
そして、プロジェクトの実行チームに責任を負わせすぎないこと。不確実な状況下では、予期せぬ問題が発生するのが当たり前です。マネージャーは、チームの障害を取り除き、成功も失敗も共に学びとして共有する「心理的安全性」の高い環境を創り、彼らを全面的にサポートする文化を築きましょう。
最後に、そして最も重要なのが、意思決定者とプロジェクト実行チーム間の活発な対話を進めること。意思決定者は「なぜ(Why)」を共有し、実行チームは「今(What is now)」を正確に伝える双方向のコミュニケーションを確立することで、現場の実情に基づいた迅速かつ適切な意思決定が可能となり、プロジェクト全体が一体となって未来を切り拓くことができるでしょう。
これらの「プロジェクトマネジメントの基礎知識」は、単なる管理手法に留まらず、不確実な時代を生き抜くために不可欠な、チームの「絆」と「知恵」を最大限に引き出すための考え方です。特別な才能や複雑なツールがなくても、これらのポイントを意識的に実践し、磨き続けることで、あなたはどんな未知のプロジェクトにも臆することなく、前向きに立ち向かえるようになるでしょう。
詳しく知りたい方は、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』を手に取ってください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。