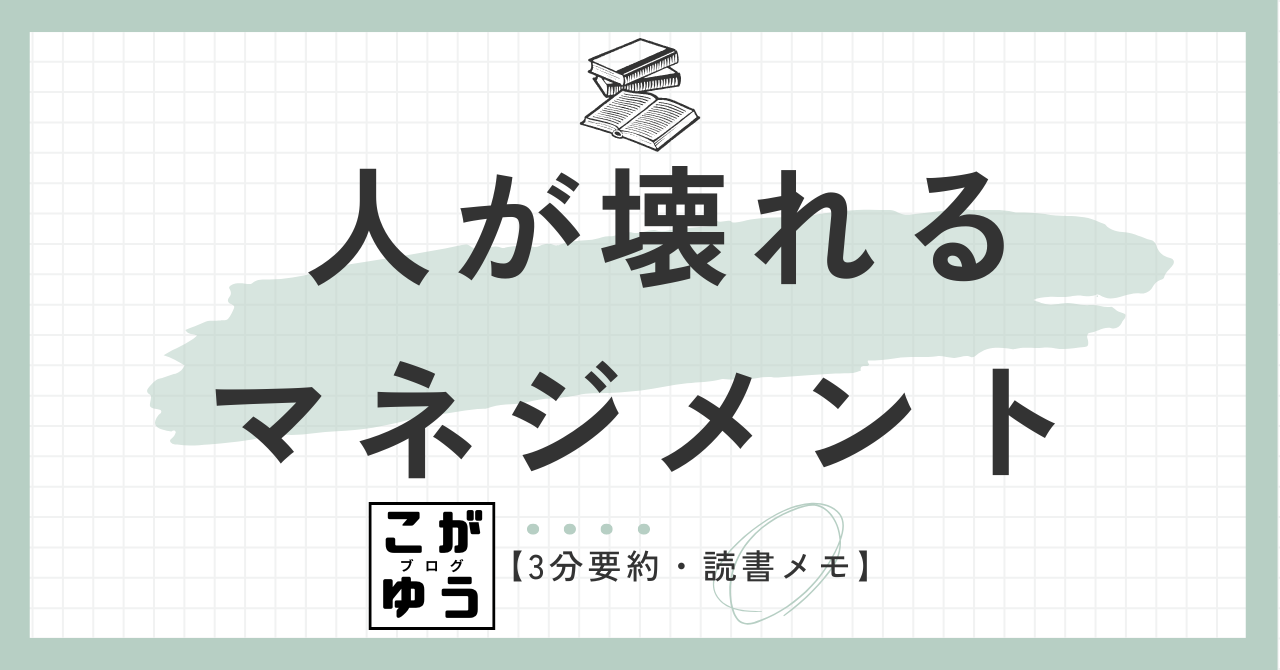プロジェクトを率いたり、チームのメンバーと関わったりする中で、「どうすればみんなが気持ちよく働けて、最大のパフォーマンスを出せるんだろう?」と常に考えています。
もしかしたら、あなたもこんな経験ありませんか?
「上司の指示が曖昧で、どう動けばいいか分からない…」
「頑張ってやった仕事が、突然キャンセルになった…」
「リモートワークで、なんだか孤独を感じる…」
もし一つでも心当たりがあるなら、今日ご紹介する一冊は、きっとあなたの心に響くはずです。それは、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』です!
この本は、「人が壊れるマネジメント」というドキッとするタイトルですが、決してネガティブな内容ではありません。プロジェクト現場でよくある「アンチパターン(失敗例)」と、それを避けて「人が輝く」ための正しいマネジメント方法を具体的に教えてくれる、まさに実践の書なんです。
今回のブログ記事では、このマネジメントの「羅針盤」とも言える一冊の魅力を、以下の構成で深掘りしていきます。
ぜひ最後までお付き合いいただき、あなたも「人が壊れない」どころか「人が育ち、成果を出す」マネジメントのヒントを見つけてみませんか?
1. 著者の紹介
本書『人が壊れるマネジメント』の著者である橋本 将功(はしもと まさよし)さんは、まさにプロジェクトマネジメントの「生き字引」とも言える方です。
早稲田大学第一文学部を卒業され、文学修士(MA)の学位をお持ちです。しかし、そのキャリアはIT業界の最前線で築かれました。IT業界歴は25年目、プロジェクトマネージャー(PM)歴は24年目、経営者歴も14年目(2025年7月現在)という、非常に長いキャリアをお持ちです。
これまでに、Webサイト、Webツール、業務システム、アプリ開発、組織改革、新規事業、DX(デジタルトランスフォーメーション)など、実に500件以上のプロジェクトのリードとサポートを実施されてきました。これほどの数のプロジェクト経験は、類まれなものです。
彼の人生のミッションは、「世界中のプロジェクトの成功率を上げて人類の幸福度を最大化すること」。この強い思いが、本書の根底にも流れています。単にプロジェクトを成功させるだけでなく、そこで働く「人」が疲弊せず、むしろ活力を得て成長できるようなマネジメントのあり方を追求されています。
2. 本書の要約
『人が壊れるマネジメント』は、プロジェクトマネージャー一筋24年、500件以上のプロジェクトを経験してきた橋本将功さんが、多くの組織やプロジェクトで頻発する「人が壊れるマネジメント」の原因を50の「アンチパターン(典型的な失敗例)」として体系化し、その具体的な回避策と「正しいマネジメントの方法」を提示する一冊です。
本書の「はじめに」で述べられているように、現代の複雑で不確実性の高いプロジェクト環境では、関係者全員が大きなストレスに晒されがちです。その中で、リーダーや上司のちょっとした言動が、部下の意欲を失わせたり、メンタルバランスを崩させたり、ひいては「人を壊してしまう」悲劇につながることがあります。
しかし、これらの多くは「悪意のない不適切なマネジメント」によって引き起こされている、と著者は指摘します。本書は、こうした悲劇を未然に防ぎ、組織に活力を与えるための知識を提供することを目的としています。
本書は、以下の5つの大きなカテゴリに分けて、50のアンチパターンとその解決策を解説しています。
■タスク編 (01–14)
この章では、メンバーが日々直面するタスク管理における失敗パターンと、その回避策が紹介されます。
- タスクを丸投げされて壊れる:詳細な説明やフォローなしに業務を割り振られることで、モチベーションやパフォーマンスが低下する問題に対し、期待する成果物の明文化と短いチェックポイントでのすり合わせを提案します。
- 長時間労働で壊れる:終わりのない残業による心身の疲弊には、工数見積もりでの「余裕率」確保と残業時間の定期レビューが重要であると説きます。
- 非現実的な締切りを設定されて壊れる:チームのキャパシティを無視した納期設定には、締切りの根拠共有とステークホルダーとの交渉・調整が求められます。
曖昧な指示はリーダーの甘え
『人が壊れるマネジメント』
人ではなくプロセスをマネジメントする
『人が壊れるマネジメント』
あまり時間をおかずに随時フィードバックを行う
『人が壊れるマネジメント』
ミスを責めても問題は解決しない
『人が壊れるマネジメント』
タスクの6W1Hを明確にする
『人が壊れるマネジメント』
■プロジェクト計画編 (15–24)
プロジェクト全体の計画段階で陥りがちな落とし穴と、その回避策が詳述されます。
- 目標の不明確さで壊れる:プロジェクトのゴールが不明確な場合、SMART(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限付き)基準での目標定義と全員での言語化・承認が鍵となります。
- 経営陣の無理解で壊れる:上層部が現場の状況を把握しないことによる疲弊に対し、課題・リスク・現場の声を「ストーリー」として経営陣に伝えることの重要性を強調します。
- 意思決定過程への非参加で壊れる:重要な決定が現場を巻き込まずに行われることによる不満には、「意思決定フレームワーク」(RACIなど)を用いた責任者と関係者の明示が有効です。
プロジェクトに優柔不断は禁物
『人が壊れるマネジメント』
プロジェクトに計画は必要だが、固執してはいけない
『人が壊れるマネジメント』
プロジェクトに不確実性はつきもの
『人が壊れるマネジメント』
■コミュニケーション編 (25–35)
人間関係や情報共有におけるトラブルが、いかに人を壊すかを解説し、その対処法を示します。
- コミュニケーションの不足で壊れる:情報共有の断片化や遅延には、毎日の短時間スタンドアップミーティング(昨日/今日/障害の共有)が効果的です。
- リモートワークの孤独感で壊れる:オンラインでの雑談不足による一体感の喪失には、週に一度のバーチャルコーヒーブレイクを提案します。
- 無駄な会議で壊れる:目的のない会議による時間浪費には、招集時に「目的」と「アウトプット」の明記が必須です。
人間関係はプロジェクト成功の鍵
『人が壊れるマネジメント』
本用の退職理由NO.1は「イヤなやつ」がいること
『人が壊れるマネジメント』
■キャリア編 (36–41)
メンバーのキャリアに関する不満や不安が、どのようにパフォーマンスに影響するかを考察し、成長を促すマネジメントを提案します。
- キャリアパスの不透明さで壊れる:将来像が描けないことによるモチベーション低下には、半年に一度のキャリア面談と具体的なスキル・経験の計画立案が有効です。
- メンターシップの欠如で壊れる:経験豊富な先輩からのフィードバック不足には、メンター制度の導入と定期的な1on1が推奨されます。
「ゆるブラック企業」からは人が逃げる
『人が壊れるマネジメント』
■組織・環境編 (42–50)
組織全体や職場環境に起因する問題が、どのように個人に影響を与えるかを分析し、改善策を提示します。
- 労働環境の不適切さ、無意味な組織変更、社内政治、ハラスメントなど、多岐にわたる問題を取り上げ、それぞれに対する具体的な対処法を提案します。
本書全体を通して、橋本将功さんは、「悪意のない不適切なマネジメント」が多くの悲劇を生むことを強調し、知っていれば避けられる「アンチパターン」を学ぶことの重要性を説いています。この「教科書」を読み解くことで、プロジェクトの炎上やメンバーの心身の疲弊を防ぎ、持続可能で生産性の高いチーム運営を実現するための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
3. ココだけは押さえたい一文
本書『人が壊れるマネジメント』の核心を突き、全てのマネージャー、リーダー、そしてビジネスパーソンが心に留めるべき「ココだけは押さえたい一文」は、間違いなくこれです。
「プロジェクトでは『悪意のない不適切なマネジメント』が発生しやすいのです。」
『人が壊れるマネジメント』
この一文は、多くのマネジメント課題の根源にある「意図しない悪影響」に光を当てています。誰もが良かれと思って、あるいは成果へのプレッシャーから、知らず知らずのうちにメンバーを追い込んでしまう可能性があるという現実を突きつけます。
この本が「人を壊す悪意のある上司を糾弾する本」ではなく、「誰もが陥りがちなマネジメントの落とし穴とその回避策を学ぶための本」であるという、本書の最も重要なメッセージが凝縮されています。この意識を持つことこそが、人が輝くチームを作る第一歩なのです。
4. 感想とレビュー
私にとって、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』は、まさに「目から鱗が落ちる」ような一冊でした。
普段からチームマネジメントに力を入れているつもりでしたが、「悪意のない不適切なマネジメント」という著者の言葉には、ドキッとさせられました。
「良かれと思ってやっていたことが、実はメンバーを追い詰めていたかもしれない…」と、自分のマネジメントを振り返る良いきっかけになりました。この本は、単なる精神論や理想論ではなく、500件以上ものプロジェクト経験を持つ橋本さんだからこそ語れる、リアルな「アンチパターン」とその回避策が満載です。
特に印象的だったのは、各アンチパターンに対して、「問題」の明確化だけでなく、必ず「回避の技術」として具体的な行動指針がセットで示されている点です。
例えば、「タスクを丸投げされて壊れる」という問題に対して、「期待する成果物の仕様を明文化し、初回は短いチェックポイントを設定してすり合わせを行う」といった具体的なアドバイスは、明日からすぐに実践できるレベルです。これは、マネージャーとして非常にありがたい情報でした。
「プロジェクト計画編」で紹介されていた「目標の不明確さで壊れる」というパターンも、まさに私が経験したことのある課題でした。漠然とした目標のままプロジェクトを進めてしまい、途中でメンバーのモチベーションが低下したり、方向性を見失ったりした経験があります。
本書のSMART基準での目標定義や、「ストーリー」として現場の声を経営陣に伝えることの重要性など、具体的な手法を知ることで、今後のプロジェクト運営に大きな自信が持てるようになりました。
また、「コミュニケーション編」の「リモートワークの孤独感で壊れる」という項目は、まさに今の時代ならではの課題だと感じました。コロナ禍以降、リモートワークが普及し、業務効率化の側面は大きいものの、メンバー間の雑談が減り、一体感が希薄になるという悩みを抱えていました。
「週に1回のバーチャルコーヒーブレイク」のような、意図的に非公式な交流の場を設けるという提案は、シンプルながら非常に効果的だと感じ、早速チームで試してみようと思っています。
この本は、プロジェクトマネージャーや管理職の方々はもちろんのこと、これからリーダーを目指す方、そして「なぜか職場がうまくいかない…」と感じている全てのビジネスパーソンに、心からお勧めしたいです。
- 部下のモチベーション維持に悩む上司の方
- プロジェクトの炎上や失敗を避けたいPMの方
- 「マネジメントって結局何?」というマネジメント初心者の方
- チームの生産性を高めたい経営者の方
- 自分自身が「壊れる」ことを防ぎたいメンバーの方
『人が壊れるマネジメント』は、単に問題を指摘するだけでなく、人が活き活きと働ける組織を作るための、具体的な「処方箋」を与えてくれます。
この一冊があれば、あなたのチームはきっと、もっと強く、もっと輝けるはずです。
ぜひ、この「アンチパターン」を知って、人が壊れない、そして人が育つマネジメントを実践してみませんか?
5. まとめ
今回は、橋本将功さんの著書『人が壊れるマネジメント』について、著者の紹介、本書の要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書は、「悪意のない不適切なマネジメント」が引き起こす様々な問題点と、それを回避して「人が壊れず、活力を発揮できる」正しいマネジメントの方法を、50の具体的な「アンチパターン」として体系的に解説する一冊です。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- プロジェクトの失敗原因を体系化:50のアンチパターンとして、タスク、計画、コミュニケーション、キャリア、組織・環境の各側面から問題点を提示。
- 実践的な回避策を提示:各アンチパターンに対し、具体的な「正しいマネジメントの方法」をセットで解説しており、即実践が可能。
- 「悪意のない不適切さ」に焦点を当てる:多くのマネジメント課題が、意図しない言動によって引き起こされることを明確にし、気づきを促す。
- 広範な読者層に役立つ:PM、管理職、経営者だけでなく、チームメンバーにとっても、自身の状況を理解し、建設的に改善を促すヒントが得られる。
- 著者の豊富な経験:500件以上のプロジェクト経験に裏打ちされた知見が、本書の説得力を高めている。
もしあなたが、今よりもっと良いチームを作りたい、あるいは職場での人間関係や業務の進め方に悩んでいるなら、ぜひこの本を手に取ってみてください。きっと、あなたのマネジメント、そしてあなたの職場が変わるきっかけになるはずですよ。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。