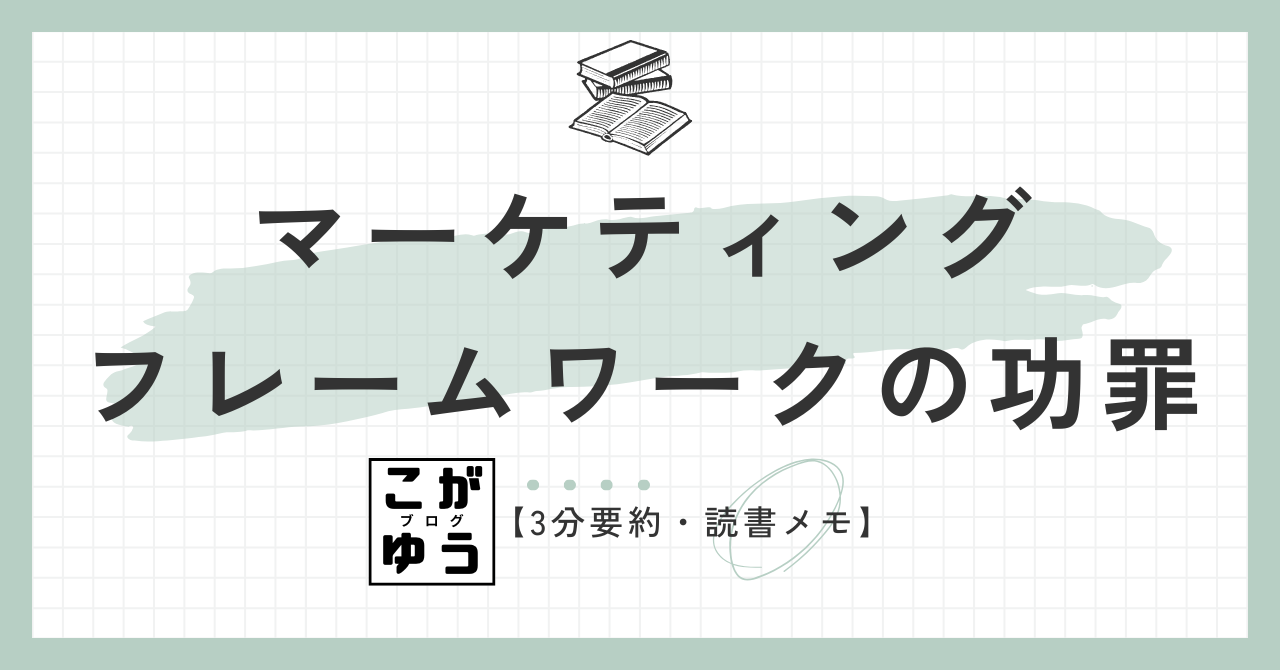今回は、マーケティングに携わる全ての方が一度は抱える疑問に答える一冊をご紹介します。
菅 恭一さんの著書『マーケティングフレームワークの功罪』です。
1. 著者の紹介
著者の菅 恭一(すが きょういち)さんは、国内外のマーケティング業界で非常に豊富な経験を持つプロフェッショナルです。
多くの企業でマーケティング戦略の策定や組織開発に深く携わってきました。
ご自身の長年の経験から、「フレームワークを導入しても成果が出ない」という企業の課題に真正面から向き合っています。
単なる理論家ではなく、企業の競争力向上と人材育成の仕組みづくりに重きを置いた実務家としての視点が魅力です。
この本は、そんな著者がたどり着いた、「形だけの取り組み」に終わらせないための実践的な思考法を提供してくれます。
2. 本書の要約
「フレームワークを導入したのに、なぜかうまくいかない…」
本書は、この「期待と失望」のギャップに焦点を当て、その原因と乗り越え方を体系的に解説しています。
フレームワークが「幻滅」に陥る3つの原因
多くの企業がフレームワークを成果に結び付けられないのには、主に3つの典型的なパターンがあります。
パターン1:自社のビジネスモデルにフィットしない誤用
フレームワークを万能薬だと信じて、無理やり自社のビジネスに当てはめようとすることが失敗の原因です。
例えば、ウェブ時代の消費者行動モデル「AISAS」は広く知られていますが、日用品のような低関与商材では「検索」や「共有」のプロセスは発生しにくいですよね。
フレームワークは、あくまで自社の実態に合わせて柔軟にアレンジすべき「思考の道具」なのです。
パターン2:難易度が高く、使いこなせない
ブランド・レゾナンス・ピラミッドのような高度なフレームワークは、その開発思想や構成要素の戦略的意図を深く理解していないと使いこなせません。
形だけ埋める作業が目的化し、成果に到達する前に「難しすぎて使えない」と諦めてしまうケースが非常に多いのです。
フレームワークは、知識と経験を積み、数年単位で習熟していくものだという認識が必要です。
パターン3:特定の部署に閉じた活用にとどまる
フレームワークが一部のチームや個人だけで使われ、全社的な「共通言語」として機能しないと、部分最適な活動に終わってしまいます。
本来、フレームワークは経営から現場まで、一貫した戦略を推進するための共通認識となるべきものです。
組織全体に浸透させるには、マネジメント層の理解と、現場を支援する体制が不可欠だと著者は指摘しています。
フレームワークを導入する前に、その開発思想を理解し、抽象的な概念についての理解を深め、概念レベルで会話ができる土壌を整えることが重要
『マーケティングフレームワークの功罪』
バカなマーケッターほど差別化したがる
『マーケティングフレームワークの功罪』
成功への道:「守」「破」「離」のプロセス
本書の核心は、フレームワークを組織の競争力に変えるための「守破離(しゅ・は・り)」のプロセスです。
フレームワークは、単なる「借り物」に依存せず、自社独自の競争力を手に入れるための指針として捉えられます。
- 「守」:まずは型(フレームワーク)を徹底的に学び、正しく理解します。
- 「破」:自社のビジネスモデルに合わせて型を検証し、より良い形を模索して改善します。
- 「離」:最終的に型から自在になり、自社独自の競争力を生み出す「プロセス」を確立します。
フレームワークを「永遠のベータ版」と捉え、使い続ける中で育てていく姿勢こそが、成果を生む組織と形だけの取り組みに終わる組織の違いを生むのです。
STPの本質は単なる細分化ではなく、顧客の潜在的な欲求と、自社が提案できる価格を行き来しながら、市場を再定義し、新たな市場を創造することにある。
『マーケティングフレームワークの功罪』
顧客が製品やサービスを選ぶ際は、単なる機能や性能ではなく、それが人文にどのような価値を提供するのか、あるいはそのブランドや商品を選ぶことでどのような自分でいられるのか、といった情緒的な要素が大きく影響します。
『マーケティングフレームワークの功罪』
フレームワークの誤用を防ぐ3つの視点
『マーケティングフレームワークの功罪』
1:顧客を理解することからはじめる
2:フレームワークの設計思想を理解する
3:結果からフレームワークを評価する
フレームワークは目的ではない。
『マーケティングフレームワークの功罪』
顧客理解を深め、戦略を磨き、成果が生み出すための道具である。
3. ココだけは押さえたい一文
私がこの本を読んで、最も心に刻まれたのはこの言葉です。
フレームワークは「永遠のベータ版」です。この前提に立ち、私たち自身がユーザーとして能動的に関与し、試行錯誤を続けることで、その力は開かれていきます。
『マーケティングフレームワークの功罪』
フレームワークは手に入れた時点で終わりではないのですね。
私たちが能動的に使い、フィードバックを加えることで初めて「生きたもの」として機能し始める、という示唆に富んだ一文です。
4. 感想とレビュー
この本を読み、私自身のマーケティングに対する考え方が大きく変わりました。
特に、多くの人が陥りがちな「フレームワークばか」という言葉にドキッとさせられました。
フレームワークを埋めること自体が目的となり、本来の目的である「顧客価値と市場の創造」を見失ってしまう現象のことです。
STPの誤用事例が示唆に富んでいる
誰もが使うSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)の誤用例の解説は、非常に具体的で学びが深いです。
STPの本質は、市場を細分化することではなく、「顧客の欲求と自社が提案できる価値を行き来しながら、市場を再定義し、新たな市場を創造するダイナミズム」にあると語られています。
製品軸ではなく、価値軸で市場を捉え直す重要性が明確になります。
例えば、RIZAPが「ダイエット」という製品カテゴリーではなく、「結果にコミットする」という価値で市場を捉えたからこそ、ゴルフや英会話にも進出できたという事例は説得力がありますよね。
また、LOVOTが単なるロボットではなく、「家庭内でのコミュニケーションによる癒やし」という価値の市場で独自のポジションを確立した話も興味深いです。
機能軸だけのポジショニングは危険
ポジショニング設計においても、機能や性能といった機能的差異だけで軸を切るのは危険だという指摘は重要です。
なぜなら、現代では機能はすぐにコモディティ化してしまうからです。
ライザップが成功したのは、ボディメイクの機能だけでなく、「コーチが伴走してくれる安心感」という顧客の情緒的な充足に訴えかけたからです。
顧客が消費を通じて「どんな自分でいられるか」という情緒的価値を前提に設計することが、強力な競争優位を築く鍵だと理解できました。
「共通言語」としてのフレームワーク
本書は、単に個人のスキルアップのための読書に留まりません。
CMOやブランドマネージャーなど、組織の競争力向上に悩むリーダー層にこそ読んでほしい内容です。
フレームワークを「共通言語化された思考法」として全社に浸透させ、組織全体で成果を生む仕組みをどう築くかというプロセスデザインが詳細に解説されています。
この本は、「フレームワークを使おう」で終わるのではなく、「フレームワークを使ってどう組織を変革するか」という高い視点を提供してくれる、まさにマーケティング組織論の教科書だと感じました。
5. まとめ
『マーケティングフレームワークの功罪』は、フレームワークに対する過度な期待と、それによる幻滅を乗り越えるための実務的なガイドブックです。
フレームワークは、正しい開発思想を理解し、自社に合わせて「守・破・離」のプロセスで磨き上げれば、非常に強力な武器になります。
フレームワークは「永遠のベータ版」であり、私たち自身がユーザーとして能動的に試行錯誤することで初めて、事業成果を生み出す「生きた道具」になるのです。
もし、あなたが今、「フレームワークを使っているのに成果が出ない」と悩んでいるなら、ぜひこの本を手に取ってみてください。
単なる「借り物」ではない、自社独自の競争プロセスを手に入れるためのヒントが必ず見つかります。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。