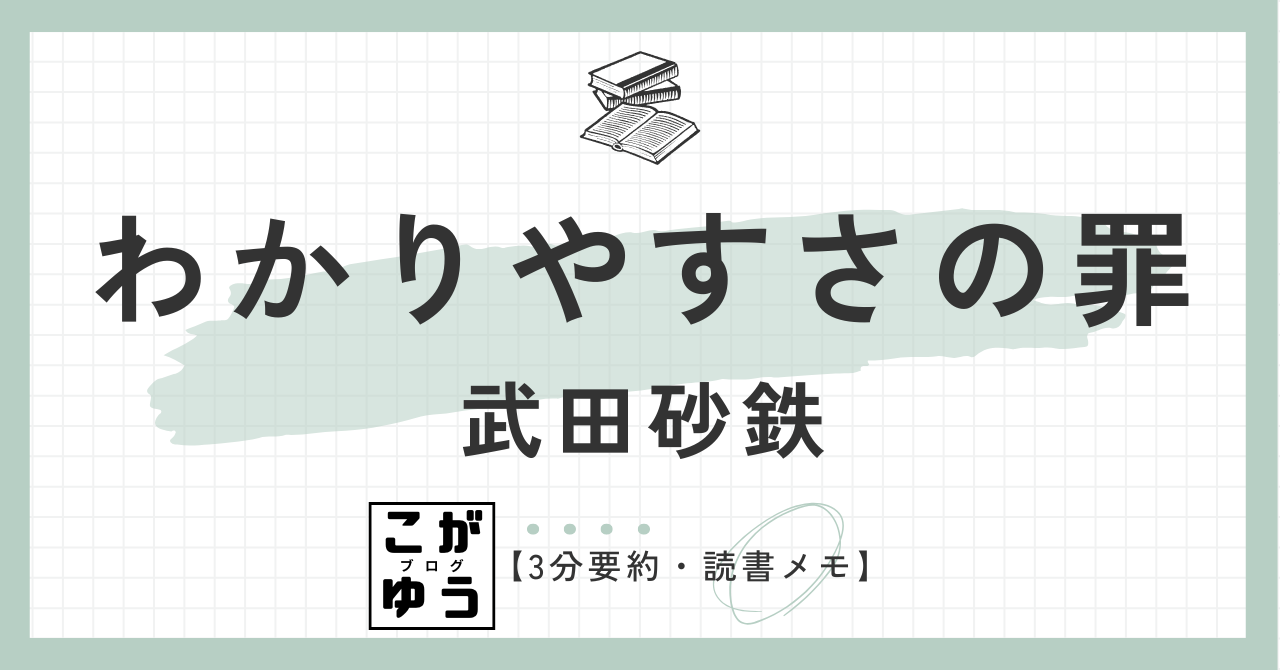武田砂鉄さんの『わかりやすさの罪』は、私たちが無意識のうちに求め、消費している「わかりやすさ」の裏に潜む、本質的な問題に切り込んだ一冊です。
「すぐにわかる!」や「要約」ばかりが尊ばれる現代において、物事の複雑さや曖昧さを切り捨てることの代償を深く掘り下げています。
この本を読み解くことで、情報の消費方法そのものを、根本から見直すきっかけになるでしょう。
1. 著者の紹介
著者の武田砂鉄(たけだ さてつ)さんは、1982年生まれのライター、編集者です。
社会や日常で感じる小さな違和感を、非常に鋭利な視点と独特の言葉選びで問い直す批評的な文章で知られています。
その視点の鋭さと、独自の言葉の選び方から、多くの読者から支持を集めています。
ラジオパーソナリティとしても活躍しており、多方面から現代の世相にメッセージを発信し続けている書き手です。
2. 本書の要約
本書は、「すぐにわかる!」「一瞬で理解できる!」といった現代の「わかりやすさ」への猛進が、社会にもたらす功罪について論じています。
「忙しい皆さんの手を煩わせません」という前提で提供される、あらゆる情報に警鐘を鳴らしているのです。
「わかりやすさの罪」とは、複雑な世界を単純化することで、私たちから深く考える機会を奪うことだと定義されています。
あなたの考えていることがちっともわからないという複雑性が、文化も政治も、個人も集団も豊かにする
『わかりやすさの罪』
他者の想像や放任や寛容は、理解し合うことだけでなく、わからないことを残すこと、分かたないことを認めることによってもたらせる
『わかりやすさの罪』
現代人が「わかりやすさ」を求める理由(功)
現代社会は情報過多であり、誰もが多忙な日々を送っています。
そのため、「忙しい読者の手を煩わせない」という前提で、情報は短く、明確に提供されるようになりました。
ビジネス書はノウハウを「一瞬で伝えたがる」ようになり、ニュースも複雑な事柄を「要約」して提供することを最優先しています。
この「わかりやすさ」は、情報処理のスピードを上げ、わかった気になれるという安心感をもたらすという点では、確かにメリットを持っています。
人は人のことをそんなに簡単には理解できない。
『わかりやすさの罪』
なにせ、自分も自分のことを理解できないのだ。
単純化によって失われるもの(罪)
しかし、このスピードとわかりやすさの追求は、物事の本来持つ複雑性や多面性を切り捨ててしまいます。
特に危険だと指摘されているのが、安易な二択を求める「どっちですか?」という単純な問いです。
「AかBか」で割り切れないはずの現実が、無理やり単純化されることで、私たちは「そもそも」を問う力を失ってしまうのです。
シンプルな選択肢は、私たちが本来持つ多様な視点や曖昧さを排除してしまいます。
感情を規定するな。
『わかりやすさの罪』
要請するな。
こういうものに慣れてはいけない。
思考を停止させる「勝手な理解」の恐怖
また、コミュニケーションの場面で起きる「勝手に理解しないでよ」という現象にも焦点を当てています。
自分の発言や行動が、相手によってすぐに「一つの意見」として処理されてしまう現象です。
例えば、著者が何かを問題視しても、相手に「おっしゃる通りだと思います」と勝手に同意されると、かえって苛立ちを感じる場合があります。
議論の余地がない「そもそも論外」の事柄が、無理やり対等な意見として俎上に載せられてしまうからです。
誰もが「いいね!」やリツイートによって、言葉を「意見化」する現代社会の弊害を鋭く分析しています。
『わからない』ことは人を不安にさせる
『わかりやすさの罪』
理解できないことに人は耐えることができない
ノイズを排除する「要約」への抵抗
現代では、すべてを短い時間で理解したいという要求が非常に強まっています。
この要求に応える「要約」は、物事のノイズやぐちゃぐちゃした部分を切り捨てます。
深い議論や真の理解には、「一気にわかる!」必要性はないと著者は訴えます。
むしろ、時間をかけて言葉にできない部分を抱え続けることが、思考の質を高める道だと指摘しています。
本書は、この「わかりにくいままでいることの重要性」を強く訴え、安易な結論に流されない思考の抵抗力を養うことを読者に求めているのです。
平坦な道に見えても地面に頬を擦り付けてよく見るといびつにぐにゃんぐにゃんに曲がっていたりする。どんな日常では楽しめる角度が確実にあるんじゃないかと思っている
僕の人生に事件は起きない ハライチ岩井勇気 わかりやすさの罪 (朝日文庫)
3. ココだけは押さえたい一文
「わかりやすさ」に抵抗し、思考の自由を守ろうとする著者の決意が詰まった一文をご紹介します。
選択肢は多ければ多いほどいい。少なければ少ないほど疑いが増える。
『わかりやすさの罪』
安易に選択肢を絞り込み、すぐに答えを出したがる現代への、強力なアンチテーゼです。
提示された選択肢の少なさに気づいたときこそ、「なぜこの二択なのだろう?」と前提を疑う姿勢が重要だと教えてくれます。
4. 感想とレビュー
この本を読んでいると、「勝手に理解しないでよ!」という武田さんの苛立ちが、読者にも直球で伝わってきます。
単なる書評ではなく、自分の思考の癖をチェックする、非常に強力なツールだと感じました。
功罪の検証:わかった気になれる代償
本書の最大の魅力は、「わかりやすさ」という快適さの裏にある代償(罪)を明確にした点です。
- 功(メリット): 複雑な事柄を素早く理解し、わかった気になれる安心感を得られます。
- 罪(デメリット): 物事の細部、ノイズ、曖昧さが消され、思考停止を招くという代償を払っています。
特に、自分の知識を「わかった気になれる文章」だけで済ませてしまい、本質的な理解から遠ざかることへの著者自身の葛藤は、多くの書き手の心に響くはずです。
「ノイズ」と「ぐちゃぐちゃ」の肯定
武田さんが徹底的に肯定するのは、「ノイズ」と「ぐちゃぐちゃ」です。
世界は常に複雑であり、簡単に要約できるものではありません。
安易な答えに飛びつかず、「わからない」という状態を抱え続けることこそが、思考を深めるための重要なプロセスだと教えてくれます。
私たちは、この本を読むことで、「わかったふり」をやめ、目の前の事柄と真摯に向き合う勇気をもらえるでしょう。
5. まとめ
『わかりやすさの罪』は、情報が流れすぎる時代に、立ち止まって「考える力」を取り戻すための必読書です。
この本は、あなたが普段接しているニュースやSNS、会話の中にある「わかりやすさ」の裏側を徹底的に暴きます。
すべてをすぐに理解しようとするのではなく、複雑さや曖昧さをそのまま受け入れる余裕を持つことが大切です。
武田砂鉄さんの鋭い批評は、あなたのものの見方をきっと変えてくれるはずです。
この本を読んだ後、あなたの周りにある「わかりやすさ」の裏側に、どんな複雑さが隠れているか、ぜひ立ち止まって考えてみてください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。