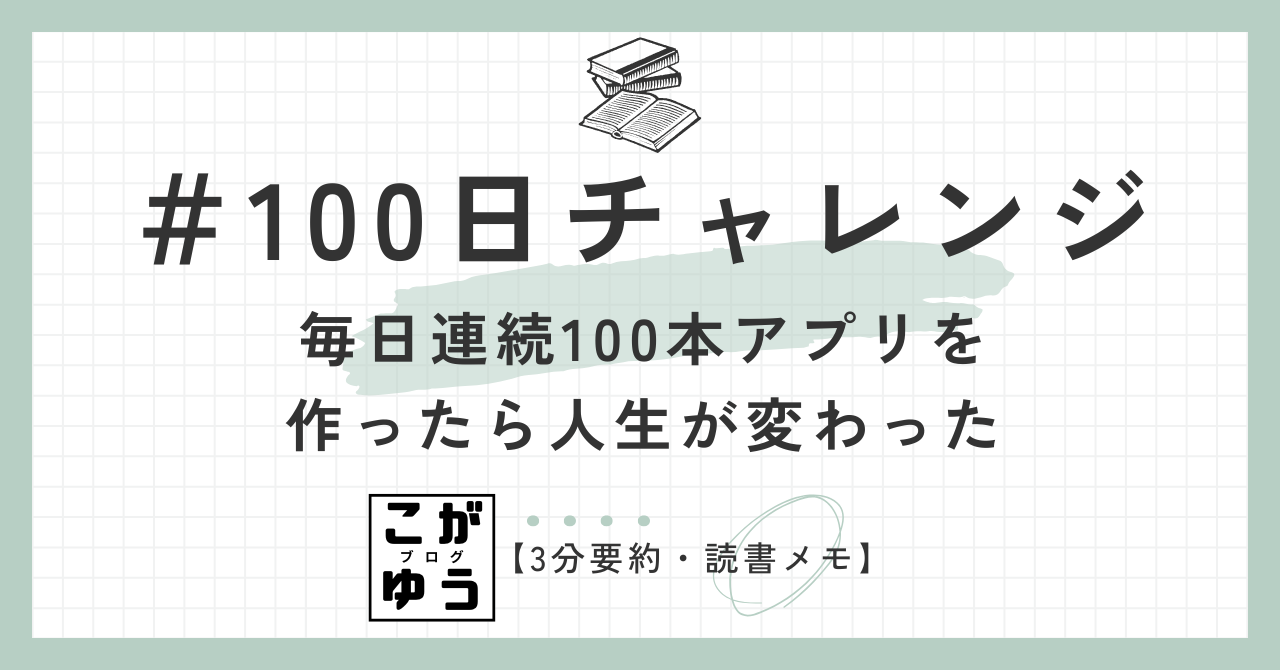「プログラミングを学びたいけど、何から手をつければいいかわからない…」
「分厚い参考書を見ると、やる気がなくなってしまう…」
そう思って、なかなか最初の一歩が踏み出せない方は多いのではないでしょうか?
今回ご紹介するのは、そんなあなたの心を動かす一冊、大塚あみさんの著書『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』です。
この記事では、『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』がどんな本なのか、その要点をまとめ、具体的なレビューをお届けします。
1. 著者の紹介:大塚あみさんってどんな人?
著者の大塚あみさんは、この本を書いた当時、普通の大学4年生でした。
彼女は自分を「手を抜くことに全力を尽くすタイプ」と語っています。
面倒な宿題をサボるため、ChatGPTというAIツールを使い始めたのが、すべての始まりだったのです。
Z世代ならではの柔軟な発想と、AIを当たり前の道具として使いこなす姿勢が、彼女のユニークな学び方を生み出しました。
この本は、プログラマーとしての特別な才能があったわけではない、ごく普通の学生が、たった100日間でどのように成長し、人生を変えていったのかをリアルに描いた物語です。
その親しみやすい語り口と、飾らない人柄が多くの読者から共感を得ています。
2. 本書の要約
なぜ「#100日チャレンジ」は始まったのか?
この挑戦は、最初から「人生を変えよう」という大きな目標があったわけではありません。
宿題を楽にするためにChatGPTを使い始め、その延長線上で「毎日1本、新しいアプリ(作品)を作ってX(旧ツイッター)に投稿する」というアイデアを思いついたのです。
それが、#100日チャレンジの始まりでした。
最初は、シンプルなオセロゲームを作ることからスタートします。
しかし、毎日続けるのは予想以上に大変でした。
エラーに直面したり、思った通りに動かなかったり、挫折しそうになる日もたくさんありました。
この本には、そんなリアルな試行錯誤の様子が、日記のように詳細に記されています。
昔は、『努力すれば成功する』って考えが当たり前だったのでしょうけど、今は違います。無理に辛いことを続けても、成功する補償なんでないんですよ。それなら、自分が興味があることや楽しいことに時間を使う方が、よほど価値があると思います
AI時代の新しいプログラミング学習法
従来のプログラミング学習は、まず分厚い参考書で文法や仕組みを学び、それからようやく簡単なアプリを作るのが一般的でした。
しかし、この本が提示する学び方は全く違います。
「作りたいものをAIに聞いて、とりあえず作ってみる」
このスタイルで、彼女は実践を通して、必要な知識をその都度学んでいきます。
たとえば、砲弾を撃つゲームを作るときには、その軌道を計算するために「数学」の重要性を痛感します。
また、複雑なアプリを作る過程で、「ライブラリ」や「クラス」、さらには「オブジェクト指向」といった、専門的な概念も自然と身につけていきます。
AIはあくまで「道具」です。
著者は、AIに言われた通りにコードをコピー&ペーストするのではなく、なぜそのコードが必要なのか、どうすればもっと効率的になるのかを常に自問自答します。
この「自分で考え、AIに適切な指示を出す」という姿勢こそが、彼女をプロとして成長させたのです。
ChatGTPは最短の解決策を教えてくれるかもしれないけれど、それが全体を見通した最適解かどうかは私しか判断できない
成長の過程と得られたもの
#100日チャレンジは、彼女に多くの変化をもたらしました。
毎日アプリを作り続けることで、彼女はプログラミングスキルだけでなく、「継続力」や「問題解決能力」も身につけました。
そして、その成果をSNSで発信することで、様々な人との繋がりが生まれ、学会での発表や、最終的にはソフトウェアエンジニアとしての就職まで実現したのです。
この物語は、単にプログラミングの技術を教えるだけでなく、行動することの重要性、そしてAIを味方につけることで人生がどう変わるかを教えてくれます。
継続とは苦行ではなく、習慣として楽しむものだ
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』
人は努力を美徳と捉えるけれど、努力と苦行という感覚ではまず続かない。それよりも「どうやって楽しく自然に習慣化していくか」が重要なのだ。
日々小さな興味を見つけて、それに没頭する———この習慣が100日続けるための秘策だったのかもしれない。
3. ココだけは押さえたい一文
この本の核心を最も表しているのは、この言葉ではないでしょうか。
「作品作りの主体は私なのだ」
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』
AIは強力なツールです。
しかし、どんなに優れたツールを使っても、それを使う人間が「何を作りたいのか」「なぜそれを作るのか」という主体性を持たなければ、何も生み出すことはできません。
この言葉は、AI時代を生きる私たちにとって、最も重要なメッセージだと感じました。
4. 感想とレビュー
素晴らしいと思ったポイント
この本は、いわゆる「技術書」ではありません。
まるで、隣にいる友達の成長を間近で見ているような、ワクワクする物語です。
著者の率直な語り口がとても魅力的で、彼女が直面した葛藤や喜び、小さな発見が、まるで自分のことのように感じられます。
特に、プログラミング初心者の方が持つ「難しそう」「挫折しそう」という不安に、一つひとつ丁寧に寄り添ってくれているのが印象的です。
きっと読み終えた後には「自分にもできるかも」と前向きな気持ちになれるでしょう。
この本は、プログラミング学習の新しい形を示しています。
まずはやってみて、必要になったときにAIに助けを求める。
このやり方は、従来の学習方法で挫折した人にとって、まさに救いとなるはずです。
どんな人におすすめ?
- プログラミングをこれから始めたい方: どんな言語を学ぶか迷っている方や、何から手をつければいいか分からない方に最適です。
- 挫折経験がある方: 過去にプログラミングを諦めてしまった経験がある方に、新しい学びの道を示してくれます。
- AI時代の働き方や学び方に興味がある方: AIをどのように活用すれば、自分のスキルアップにつながるのか、具体的なヒントが得られます。
逆に、すでにプログラマーとして活躍している方には、物足りなく感じるかもしれません。
しかし、初心を思い出したり、AI時代における「学ぶこと」の意味を再確認したりするには、とても良い一冊だと思います。
5. まとめ
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』は、単なるプログラミング学習の本ではありません。
これは、たった100日間で、人生を変えることができた一人の物語です。
本書が教えてくれるのは、以下の3つのことです。
- 継続することの大切さ: 毎日少しずつでも行動を続けることで、驚くほどの成長が手に入ります。
- AIを「道具」として使いこなす力: AIは、私たちの創造性をサポートしてくれる強力なパートナーです。
- 「主体者」としての意識: 何をするにも「自分がどうしたいか」という気持ちが、最も重要です。
もし、あなたが「何か新しいことを始めたい」「自分を変えたい」と思っているなら、ぜひこの本を読んでみてください。
「大塚あみ」さんの物語から、きっとあなたも「挑戦」への第一歩を踏み出す勇気をもらえるはずですよ。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。