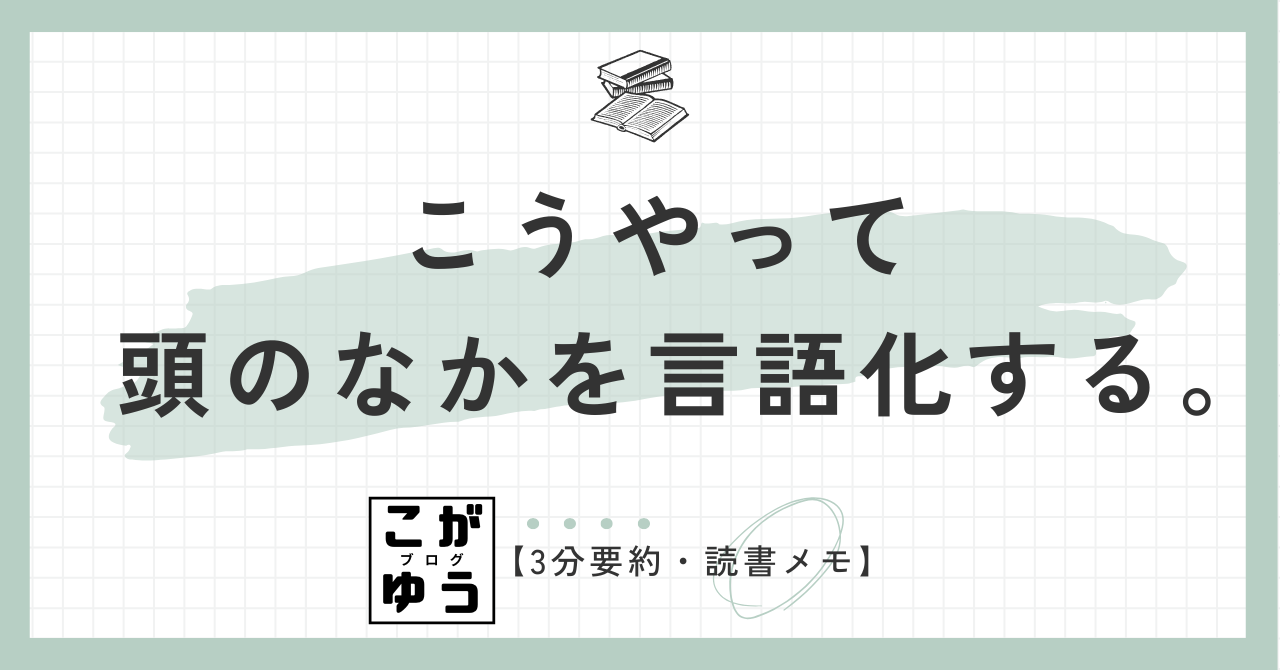「頭の中ではわかっているのに、言葉にできない…」
「なんとなくモヤモヤするけど、その原因がわからない…」
「会議で意見を求められても、うまく伝えられない…」
そんな悩み、ありませんか?
もし一つでも当てはまるなら、今回ご紹介する一冊が、きっとあなたの人生を変えるきっかけになります。
それが、荒木俊哉さんの著書『こうやって頭のなかを言語化する。』です。
この記事では、『こうやって頭のなかを言語化する。』の核心に迫り、要約とレビューを、分かりやすくたっぷりとお伝えします。
1. 著者の紹介:荒木俊哉さんってどんな人?
著者の荒木俊哉さんは、世界三大広告賞をはじめ、国内外で20以上の賞を受賞している超一流のコピーライターです。
前作のベストセラー『瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。』で、多くの読者から「言葉にできないモヤモヤが言語化できた!」と絶賛されました。
この本は、その前作のメソッドをさらに進化させたものです。
1000人以上が体験した声を元に、よりシンプルで、より確実に効果が出る新しい言語化メソッドを開発しました。
それが、本書の軸となる「言語化ノート術」なのです。
彼は、単に言葉を選ぶプロではありません。
人の心に寄り添い、その「本音」を引き出すことのプロなのです。
だからこそ、彼のメソッドは私たち一人ひとりの心に深く響きます。
2. 本書の要約
言語化とは「自分の話を聞く」こと
私たちは「言語化」と聞くと、「どう話すか?」「どう伝えるか?」という「伝え方」ばかりに意識が向きがちです。
ですが、本書はまずその前提を覆します。
本当に大切なのは、「自分の頭の中の声を聞くこと」だと著者は語ります。
自分の心に耳を傾けて、自分自身でも気づいていない本当の気持ちや小さな感情を、じっくりと引き出してあげる。
それが、言語化の第一歩なのです。
一流のコピーライターは、日常的に自分自身との対話を深めているといいます。
それが、仕事や人間関係をスムーズにし、より良いアイデアを生み出す秘訣なんですね。
言語化力のベースは「聞く力」にある
『こうやって頭のなかを言語化する。』
言語化力が高い人は、話を聞くのがうまい
『こうやって頭のなかを言語化する。』
「自分で自分の話を聞く」姿勢こそが、自分の頭の中を言語化する上では必要不可欠
『こうやって頭のなかを言語化する。』
「自分のことは、自分が一番わかっている」と無意識に思い込んでいる人が多いのですが、現実は決してそうではありません。
『こうやって頭のなかを言語化する。』
1日たった3分!誰でもできる「言語化ノート術」
この本の一番の魅力は、誰でも今日から始められる超シンプルなメソッドです。
それが、たった3つのステップからなる「言語化ノート術」。
「続けられない」という挫折を防ぐため、1日たった3分でできるように設計されています。
ステップ1:【ためる】
その日あった「できごと+感じたこと」をメモします。
例えば、「上司に褒められた」という「できごと」に対して、「嬉しかった」という「感じたこと」をセットで書き留めるのです。
良いことも、悪いことも、心が動いた出来事をそのまま書き出すことが大切です。
ステップ2:【きく】
ステップ1で書いたメモに対し、「…のはなぜか?」と自分自身に問いかけます。
「上司に褒められて、嬉しかったのはなぜか?」
このたった6文字を足すだけで、思考が一気に深まります。
「努力を認めてもらえたからだ」「もっと頑張ろうと思ったからだ」など、頭の中に隠れていた言葉がどんどん浮かび上がってきます。
ステップ3:【まとめる】
ステップ2で出てきた言葉を、最後にシンプルな「1行の結論」にまとめます。
「プレゼンで褒められたのは、相手に認めてもらえたからだ」
のように、今の自分にとって一番しっくりくる言葉を、たった一行に凝縮するのです。
このステップを実践するだけで、モヤモヤしていた感情がスッキリと整理され、自分の思考パターンや価値観が見えてくるでしょう。
結局、自分が最高の聞き手
『こうやって頭のなかを言語化する。』
言語化につながる聞き方のコツ
『こうやって頭のなかを言語化する。』
①「できごと→感じたこと」の順番で聞く
②アドバイスしようとしない
③言葉の意味を深める問いかけ
いつだって答えは、すでに、自分のなかにある。あとは、自分で自分の話を聞きながら、頭のなかを言語化して、自分のなかにある答えを見つけるだけ。
『こうやって頭のなかを言語化する。』
思考の質が高まる「具体と抽象」のトレーニング
この「言語化ノート術」は、実は実践するだけで「具体」と「抽象」の思考訓練にもなります。
ステップ1の「できごと」は「具体」。
ステップ2で「なぜ?」と問いかけることで、思考が「抽象」へと向かいます。
そして、ステップ3で「結論」を出すことで、抽象化した思考が再び具体的な言葉に落とし込まれるのです。
このメソッドを続けることで、意識せずとも思考の質が上がり、問題解決能力やアイデア発想力も自然と高まっていくでしょう。
「伝え方はレシピ、言語化は食材」
『こうやって頭のなかを言語化する。』
「何を言うか」がわかると「どう言うか」も上達する
『こうやって頭のなかを言語化する。』
3. ココだけは押さえたい一文
本書を読んで、特に心に響いた一文があります。
「言語化力はセンスではなく努力で高められるもの」
『こうやって頭のなかを言語化する。』
「自分には才能がないから…」と諦める必要は一切ありません。
言語化は、スポーツや楽器の練習と同じように、日々のトレーニングで確実に身につくスキルなのです。
この言葉は、「できない」と思っていた自分に、勇気を与えてくれました。
4. 感想とレビュー
素晴らしいと思ったポイント
『こうやって頭のなかを言語化する。』の最大の魅力は、その実践性です。
巷には言語化に関する本がたくさんありますが、その多くは抽象的な理論で終わってしまいがちです。
ですが、本書は違います。
紙とペンさえあれば、誰でもすぐに実践できる具体的な「型」を示してくれます。
「たった5日間でも確実に効果が出る」という著者の言葉に偽りはありませんでした。
実際にやってみると、本当に心がスッキリするのを実感できます。
自分でも気づかなかった感情や、ずっとモヤモヤしていたことの正体が、言葉として目の前に現れるのは感動的ですらありました。
また、文章もとても読みやすいです。
専門用語はほとんど使われておらず、難しい概念も身近な例で丁寧に解説されています。
まるで著者が隣で優しく語りかけてくれているような、そんな感覚で読み進めることができました。
どんな人におすすめ?
- 言語化に苦手意識がある人: 自分の考えをうまく伝えられず悩んでいる人に、具体的な解決策を与えてくれます。
- 思考を整理したい人: 頭の中がごちゃごちゃして、物事がなかなか決断できないという人に最適です。
- ビジネスパーソンや学生: 企画書の作成、プレゼン、面接対策など、あらゆる場面で役立つスキルが身につきます。
逆に、すでに高い言語化能力を身につけている方や、文章を書くこと自体に抵抗がある方には、少し物足りないかもしれません。
ですが、言語化の重要性を再確認したい人には、きっと新しい発見があるでしょう。
5. まとめ
『こうやって頭のなかを言語化する。』は、単なる文章術の本ではありません。
自分自身と向き合い、心を整理し、そして人生をより豊かにするための実践的なガイドブックです。
本書を読むことで、以下のような学びが得られます。
- 言語化の第一歩は、「聞く」ことにある。
- 1日3分3ステップで、誰でも思考をクリアにできる。
- 言語化力はセンスではなく、努力で確実に磨けるスキルである。
今回ご紹介したのは、この本のほんの一部に過ぎません。
ぜひ本書を手に取って、あなた自身の頭の中を「言語化」する喜びを体験してみてください。
きっと、言葉に詰まって悩む時間が減り、より自信を持って行動できる自分に出会えるはずです。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。