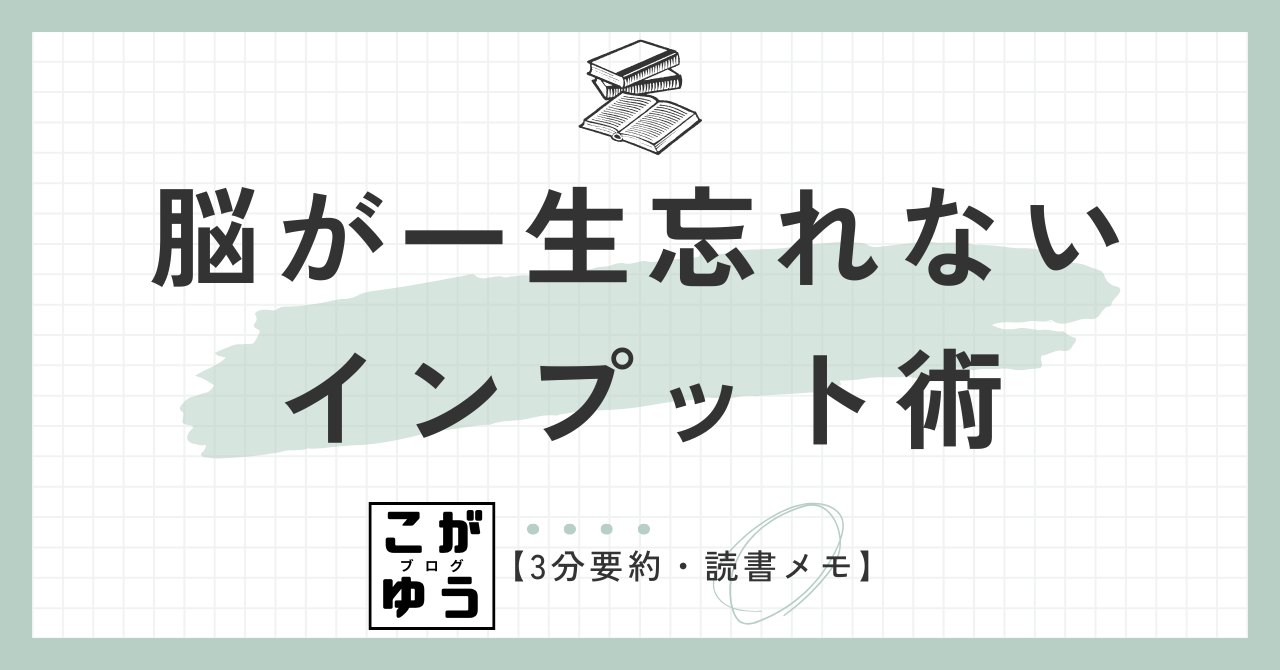ご覧頂き誠にありがとうございます。
このブログでは、日々進化するビジネスの世界で生き抜くために欠かせない、マーケティング、マネジメント、そして自己成長や効率化といったテーマについて、私の経験や読書を通じて得た学びを発信しています。特に、新しい情報をいかに効果的に吸収し、仕事に活かしていくか、というのは私自身の大きな関心事であり、皆さんの多くも同じ悩みをお持ちなのではないでしょうか?
現代は、まさに情報過多の時代です。インターネット、SNS、動画、書籍…毎日、膨大な量の情報が流れ込んできます。「学びたい」「知りたい」という気持ちはあっても、いざ本を読んだり、動画を見たりしても、すぐに内容を忘れてしまったり、覚えたはずなのに実践できなかったり…そんな経験、一度や二度ではないはずです。
「せっかく時間を使って学んだのに、身についていない…」これほど、もったいないことはありませんよね。
巷には様々な「効果的な勉強法」や「インプット術」が紹介されていますが、どれが本当に効果があるのか、迷ってしまうことも多いです。
そんな悩みを抱える中で、まさに「これだ!」と感じた一冊に出会いました。それが、今回ご紹介する『脳が一生忘れないインプット術』 星友啓 (著) です!
著者は、なんとスタンフォード大学・オンラインスクールの校長を務める星友啓氏。彼は、最先端の脳科学と心理学に基づいた、本当に効果のあるインプット方法を研究されています。本書では、その科学的な知見に裏打ちされた、誰もがすぐに実践できるインプット術が惜しみなく紹介されています。
「インプット術」に関する情報はたくさんありますが、その中には科学的な根拠が薄いものも少なくありません。本書は、そうした玉石混交の情報の中から、脳と心のメカニズムを最大限に活かせる、効果が高く実践しやすい方法を厳選して解説しています。
例えば、「はじめに」で紹介されている以下のインプット方法。
- 本を読むときは「つまみ読み」から始める
- 記憶を定着させるためには繰り返し読み直す
- YouTube動画で学ぶときは字幕付きで見る
- ポッドキャストは1.5倍速までがおすすめ
- メモやノートは手書きでとる
- 始める前に前回学んだことを思い出す
これら、多くの人が日常的に実践している方法の中に、実は科学的に「思ったほどの効果が確認されていない」ものと、効果が証明されているものが混じっている、という衝撃的な事実が提示されます。(なんと、このうち科学が明かした正解はたったの3つだとか!)
本書を読むことで、私たちは、これまで当たり前だと思っていたインプット方法が、実は非効率だったと気づかされるかもしれません。そして、科学的に証明された、本当に「脳が一生忘れない」ための効果的なインプット術を体系的に学ぶことができます。
私のように、日々大量の情報を処理し、学び続ける必要があるビジネスパーソン、そして、せっかくの努力を無駄にしたくないすべての人にとって、本書はまさに必読の一冊と言えるでしょう。
この記事では、私が『脳が一生忘れないインプット術』 を読んで特に重要だと感じたポイントを、以下の構成で詳しく解説していきます。
- 著者の紹介
- 本書の概要
- 本書の要約
- ココだけは押さえたい一文
- 感想とレビュー
- まとめ
『脳が一生忘れないインプット術』 とは一体何か? どうすればそれを実践し、学びを定着させ、仕事や人生に活かせるのか?
ぜひ、最後までお付き合いください!
1. 著者の紹介
まず、本書『脳が一生忘れないインプット術』の著者、星友啓(ほし ともひろ)氏をご紹介します。彼の経歴を知ることで、本書の信頼性が非常に高いことがお分かりいただけるでしょう。
星友啓氏は、現在の教育界、そして脳科学・心理学の分野において、非常にユニークで権威のある立場にいらっしゃいます。
彼は、アメリカのスタンフォード大学・オンラインスクール(Stanford University Online High School)の校長を務めています。スタンフォード大学オンラインハイスクールは、世界中の才能ある若い生徒たちに、質の高いオンライン教育を提供していることで知られる教育機関です。そこで校長という要職を担っていること自体が、星氏の教育に対する深い理解と実績を示しています。
星氏は、スタンフォード大学で人工知能(AI)分野の博士課程を修了されており、そのバックグラウンドから、脳科学、心理学、そしてテクノロジーといった、現代の「学習」を理解する上で欠かせない複数の領域に精通しています。彼の専門知識は、単なる教育論に留まらず、人間の認知メカニズムや学習プロセスといった、脳科学・心理学の最先端の研究に基づいています。
近年、AI技術の発展は目覚ましいものがありますが、星氏は、AI時代における「学び方」や「情報との向き合い方」についても深く洞察されています。本書の後半で、AI時代の情報の見分け方について解説されているのも、彼の専門性を反映しています。
このように、星友啓氏は、スタンフォードという世界最高峰の教育機関のトップという立場にありながら、脳科学、心理学、AIといった最先端の科学的知見を統合し、どうすれば人間は最も効果的に学べるのか?という問いを深く探求されている方です。
彼の研究や考え方は、教育関係者だけでなく、私たちのように、日々新しい情報を学び続け、知識を仕事や人生に活かしていく必要があるすべてのビジネスパーソンにとって、非常に価値の高いものです。
本書は、そんな星友啓氏が、科学的な根拠に基づき、「脳が一生忘れない」インプット術を体系的にまとめた、まさに「科学に基づいた学び方の教科書」と言えるでしょう。
2. 本書の概要
次に、本書『脳が一生忘れないインプット術』が全体としてどのような内容を扱っているのか、その概要を説明します。
本書の最大の目的は、脳科学と心理学の最新の知見に基づいた、本当に効果のあるインプット方法を読者に伝え、情報の定着と実践に繋がる学びを実現してもらうことです。
現代社会は、インターネットやSNSの普及により、情報が文字通り「洪水」のように流れ込んできます。私たちは多くの情報に触れていますが、それが本当に自分の知識やスキルとして身についているかというと、そうでないことも多いのではないでしょうか。「たくさん学んでいるのに、すぐに忘れてしまう」「知ってはいるけど、実際に行動できない」といった悩みは、多くの人に共通するものです。
本書は、こうした問題の根本原因を探り、巷に溢れる「効果があると言われているけれど、実は科学的根拠が薄い」インプット方法と、「科学的に効果が証明されている」方法を明確に区別します。そして、後者の方法の中から、特に効果が高く、日々の生活や仕事ですぐに実践できるものを厳選して紹介しています。
本書の中心的なメッセージは、効果的なインプットとは、単に情報を「読む」「聞く」「見る」といった受け身の行為ではなく、脳を「積極的に働かせる(エンゲージする)」能動的なプロセスであるということです。 AIによる文字起こしや自動要約が簡単にできるようになった現代だからこそ、単に情報を記録するだけでなく、自分の脳を使って深く処理することの重要性が増しています。
本書は以下の章立てで構成されており、インプットに関する幅広いテーマをカバーしています。
- 第1章 脳はどうやってインプットしているのか?
- 脳のインプットのメカニズム、速読の限界、人間の目の動きや理解力のリミットなど、インプットの科学的な基礎を解説。
- 第2章 脳を最大限にエンゲージする「読むインプット」術
- 本や文章を読む際に、脳の働きを最大限に引き出すための具体的な方法を紹介。多くの人がやってしまいがちな非効率な読み方と、科学的に効果のある読み方(アクティブリーディングなど)を対比して解説。
- 第3章 現代を生き抜く力! マルチメディアでの学習法
- 動画(YouTubeなど)や音声(ポッドキャストなど)といったマルチメディアからのインプットを効果的に行う方法を解説。字幕やスクショの意外な落とし穴、AI要約ツールとの賢い付き合い方など。
- 第4章 脳に焼きつく記憶メソッド
- 学んだ情報を脳にしっかりと定着させるための、科学に基づいた記憶法を紹介。繰り返しの読み直しだけでは不十分な理由、最も効果的な復習法(リトリーバルなど)など。
- 第5章 インプットの質を上げるモチベーション管理
- 学ぶ意欲、すなわちモチベーションを維持・向上させるための、脳科学に基づいた方法を解説。「やる気」のメカニズムや、心が折れにくい目標設定の仕方など。
- 第6章 スタンフォード式AI時代の情報の見分け方
- 情報過多、フェイクニュース、生成AIの時代において、信頼できる情報を見極めるための方法を紹介。インプット前に目的を設定することの重要性や、情報の信憑性を判断するチェックリストなど。
このように、本書はインプットの科学的な基礎から始まり、読書、マルチメディア学習、記憶、モチベーション、情報の見分け方といった、現代人が効果的に学ぶ上で必要なすべての要素を網羅しています。
単なる「〇〇するだけで効果アップ!」といった安易な方法論ではなく、「なぜその方法が効果があるのか」という脳科学的・心理学的な根拠まで丁寧に解説されているため、納得感を持って読み進めることができます。
「たくさん学んでいるのに、なぜか身についている気がしない」と悩んでいる方、「せっかくのインプットの時間を無駄にしたくない」と考えている方にとって、本書は、学び方を根本から見直し、「脳が一生忘れない」確かな知識とスキルを手に入れるための、強力な手引きとなるでしょう。
3. 本書の要約
それでは、本書『脳が一生忘れないインプット術』の核となる部分を、その要約としてさらに詳しく見ていきましょう。
本書の根底にあるのは、「効果的なインプットとは、脳を積極的にエンゲージ(働かせる)させるプロセスである」という考え方です。私たちは、本を読んだり、動画を見たりする際に、単に情報を受け流すだけでは、その情報は脳にしっかりと定着しないと著者は説きます。情報過多の現代において、漫然とインプットすることは、時間を浪費するだけであり、「やったつもり」になってしまう非効率な学び方に陥りがちです。
脳を最大限にエンゲージする「読むインプット」術
POINT:
・「読むインプット」時の避けるべき習慣
①目次やタイトルなどのプレビューなしで読み始める
②同じ速さで淡々と読む
③読み終わったらそのまま
・アクティブ・リーディングが鍵!
アクティブ・リーディングのコツ
①「読む前」
――目的設定:インプットの目的を設定する
―プレビュー: 読む前に目次や見出しを読む
②「読みながら」
――――自分モニタリング
・リマインドタイマー: タイマーをかけて集中力をチェックする
・こまめ休憩: こまめに休憩する
・スピード調整: 理解度などを意識して読むスピードを調整する
――手書きメモ
・キーワード定義: 重要なキーワードの定義や説明をメモする
・自分の考え:賛成、反対、理由などをメモする
・疑問:疑問点をメモする
――ストップ&ゴー
・目を閉じて思い出す: 目を閉じて内容を振り返る
目的メガネ: インプットの目的を踏まえて内容を振り返る
③「読んだ後」
――キーワードテスト: キーワードの定義や説明を思い出す
――アウトライン: 箇条書きで全体の目次をつくる
――まとめ: 目的への収穫を箇条書きでメモする
――Q&A: 周りの人に説明や質問をする
現代を生き抜く力! マルチメディアでの学習法
POINT
・インプットの質を下げずに聞くには、1.4倍速まで
・「聞く」「見る」「読む」をミックスした形でのインプットが効果的
・動画視聴で字幕はONにすると理解度が落ちる傾向がある
・リアル画像や関係ないキャラクターが出る動画は避ける
・【スクショ】や【GPT要約】より手書きメモ
【・GPT要約】は動画視聴前に
マルチメディアでの効果的なインプット習慣
ステップ1 まとめのプレビュー
ステップ2 動画の速度調整
ステップ3 ストップ&ゴー
ステップ4 視聴後のアフターケア
――キーワードテスト: キーワードの定義や説明を思い出す
――アウトライン: 箇条書きで全体の目次をつくる
――まとめ: 目的への収穫を箇条書きでメモする
――Q&A: 周りの人に説明や質問をする
脳に焼きつく記憶メソッド
POINT
・記憶の定着には【リトリーバル】が大切
・【読み返し】と【ハイライト】は【リトリーバル】とセットで行う
・【書き写し】は、【インプット&ノールック】で行う
・インプット直後に思い出して言葉にする 【ブレインダンプ】は一部を思い出すだけでも効果的
・時間を置いて【リトリーバル】をする 【スペーシング】は学びが定着しやすい
・一気に詰め込む 【短期集中】は短期間の記憶維持に強く、【スペーシング】は長期間の記憶定着に強い
復習時の効果的な【リトリーバル】方法
①ワード・リトリーバル: キーワードの定義や説明を思い出した後、正しいかチェックする
②前リトリーバル: 見出しを見てその内容を思い出した後、読み進める
③後リトリーバル: ある程度読んだら、目を閉じて内容を思い出す
インプットの質を上げるモチベーション管理
POINT
・インプットの継続にはモチベーションの維持が必要
・モチベーションは「つながり」「できる感」 「自分から感」の心の三大欲求を満たすことで維持される
・外発的なやる気は、内発的なやる気を脅かす
・SMART目標でCAR目標をどう達成するかを考える
・SMART目標に基づく短期目標とスケジュールをつくる → SMART スケジュール
・SMART スケジュールを見直して、適宜【セルフアセスメント】(自己評価)を行う
SMART目標
・Specific(具体的に): 達成度合いがわかる目標を立てる
・Measurable(測定可能な): 目標を数値化する
・Achievable (達成可能な): 到底達成できない目標は立てない
・Related (関連した): 自分や会社などと関連した目標にする
・Time-bound (時間制約がある): 達成までの時間を決める
CAR目標
・Competency(できる感): 自分の能力が上がる、新しいスキルや知識が身につく など
・Autonomy(自分から感): 自分の意思である、自分以外の何かに突き動かされていない、外発的な動機づけがない など
・Relatedness (つながり): 他の人たちとの関係性を広げて豊かになる、社会に貢献する、コラボレーションがあるなど
スタンフォード式AI時代の情報の見分け方
POINT
・【目的設定】をしてインプットする情報の質と量を最大化する
・まずは「書いた人物」「文献」 「日付」「発信元」で情報の信憑性をチェックする
・「過激表現」に要注意
・主張の根拠の出どころを確認する
・タイトルや見出しと内容が合っているかをチェックする
・他の人の評価も確認する
・意見の分布は生成AIツールを活用すると便利
生成AIツールについて
――生成AIツールへの質問は具体的にする
――賛成意見と反対意見については、「ウェブサイトやリストアップして内容を要約して」などのように聞くと良い
――生成AIツールはある時点までの情報をベースにしており、最新の情報がベースになっていない点に注意
――ツールの特性をよく理解した上で、ハルシネーションに注意する
4. ココだけは押さえたい一文
本書『脳が一生忘れないインプット術』を読んで、私がこれまでの「勉強」や「情報収集」に対する考え方が根本から変わった、最も印象深く、そして科学的な真実を突いていると感じた一文があります。
それは、本書で繰り返し重要性が説かれている、リトリーバル(記憶を呼び起こす練習)の効果について述べられている箇所で見つけた、この言葉です。
「『うーん、なんだっけ?』と頑張って思い出そうとするときに、インプットした情報の定着率が上がるのです。」
『脳が一生忘れないインプット術』
私たちは、何かを思い出せない時、「分からないな」と思ってすぐに答えを見たり、テキストを読み返したりしてしまいがちです。しかし、本書は、その「思い出そうとして、少し苦労する」というプロセスこそが、脳にとって非常に重要であり、記憶を長期的に定着させるための強力なトリガーになるのだと教えてくれます。
この一文は、受動的に情報を眺めるだけでは記憶は定着しにくいという、本書全体を貫くメッセージを最も端的に表しています。「頑張って思い出そう」という、脳を積極的に働かせる(エンゲージする)「能動的な」プロセスこそが、脳にその情報が必要だと認識させ、記憶の回路を強く太くするのです。
「ストップ&ゴー」や「読んだ後のアフターケア」といった本書で紹介されている具体的なインプット術も、まさにこの「思い出そうとする」プロセスを意図的に組み込むための方法です。
もしあなたが、「覚えたはずなのにすぐに忘れてしまう」「何度も読み返しているのに頭に入らない」と悩んでいるなら、それは「頑張り」が足りないのではなく、「思い出す練習」という、脳が最も喜ぶ「準備運動」が不足しているのかもしれません。
この一文は、インプットの質を高めるための、最も重要で、そして少しだけ「面倒」に感じるかもしれない科学的な真実を私たちに突きつけます。本書を読む際には、ぜひこの言葉を心に留めて、「頑張って思い出そう」というプロセスを、積極的にインプットのルーティンに取り入れてみてください。
メモは記録ではなく、記憶のためのとるもの
『脳が一生忘れないインプット術』
デジタル環境で理解度を下げずに「聞くインプット」をするためには、1.5倍以上の速度は避けるようにした方が賢明です。
『脳が一生忘れないインプット術』
動画の「字幕」には要注意
『脳が一生忘れないインプット術』
すべてを文字に起こした字幕は、情報量が増えすぎてワーキングメモリがパンクする
私たちの心は「つながり」「できる感」「自分から感」を欲している。これが、私たちのモチベーションの源泉になっている
『脳が一生忘れないインプット術』
5. 感想とレビュー
本書『脳が一生忘れないインプット術』は、まさに、私が長年漠然と抱えていた「学んでいるのに、なぜか身についていない」という悩みに、科学に基づいた明確な答えと具体的な解決策を与えてくれた一冊でした。
マーケティングという分野は、常に新しい情報が生まれ、トレンドが変化し続ける世界です。業界レポート、競合情報、顧客の動向、新しいテクノロジー、マーケティングツール…日々、大量の情報をインプットし、それを基に意思決定や戦略立案を行っていく必要があります。そんな中で、いかに効率的に、そして確実に情報を吸収できるかは、私のパフォーマンスに直結する喫緊の課題でした。
正直、これまで私は本書でいうところの「絶対にやってはいけない読み方」を、無意識のうちにやってしまっていたと気づき、思わず苦笑してしまいました。目的意識なく漫然と読み始めたり、同じペースで読み流したり、読み終わったらそのまま放置したり…。これでは、どんなに時間をかけても、脳に情報が定着しないのは当然です。「やったつもり」になっていただけなのだと、本書を読んで痛感しました。
本書で紹介されている「アクティブリーディング」のステップ、特に「読む前の目的設定とプレビュー」の重要性は、私の仕事にもそのまま応用できると感じています。例えば、新しい市場調査レポートを読む前に、「このレポートから、ターゲット顧客の購買決定プロセスのどこを明らかにしたいのか?」「競合の最新の動きを、具体的にどの部分で比較したいのか?」といった目的を明確に設定し、目次や見出しで全体像を把握してから読むことで、レポート全体を闇雲に読むのではなく、必要な情報に効率的にたどり着き、より深く理解できるようになるはずです。これは、会議資料やプレゼン資料を確認する際にも同じことが言えるでしょう。
また、「ストップ&ゴー」や「読んだ後のアフターケア」といったリトリーバル(思い出す練習)を意図的に組み込む方法は、最初は少し手間に感じますが、「頑張って思い出そうとするプロセスが記憶を強化する」という科学的な理由を聞くと、納得して実践する気になれます。例えば、ウェビナーやオンライン研修を受けた後に、すぐに次のタスクに移るのではなく、数分でも良いので、そこで学んだ最も重要なポイントを3つだけ自分の言葉で書き出してみる、といった形で日常に取り入れられないか考えています。これは、チームメンバーにも推奨したい「学び方」です。学んだことを単に共有するだけでなく、「どんな点が一番学びになった?」「それをどう仕事に活かせそう?」といった問いかけをして、思い出してもらう機会を作るようにしたいと感じました。
手書きでのメモが脳のエンゲージメントを高めるという点も興味深かったです。デジタルツールでのメモは便利ですが、確かに、手で書くという行為は、脳をより活性化させている感覚があります。重要な会議や、特に集中して学びたい内容の際は、意識的に手書きメモを取り入れてみようと思っています。
AI要約ツールのメリット・デメリットについての解説も、まさに現代的なテーマであり、非常に実践的でした。便利だからといって頼りすぎると、自分で考える力が衰えてしまうという警告は、AIを仕事に取り入れる上でも常に意識すべき点です。本書で提案されているように、AI要約を「読む前のプレビュー」や「目的設定」のために活用するという方法は、AIの利便性を享受しつつ、自身の学びの質も高めるという、まさにAI時代の賢い学び方だと感じました。マーケティングのトレンド情報収集などで活用できそうです。
本書は、モチベーション管理や情報の信憑性の見分け方といった、インプットを成功させるための周辺要素についても触れており、学びを「点」ではなく「線」や「面」で捉えることの重要性を教えてくれます。学ぶ意欲をどう維持するか、そして、何を学ぶべき情報として選ぶか、といった判断も、効果的なインプットには欠かせません。
私のブログテーマの一つである「ライフスタイル」という観点からも、本書のインプット術は応用範囲が広いです。例えば、新しい語学を学ぶ際や、趣味のスキルを向上させるために動画を見たり本を読んだりする際にも、本書の科学的なメソッドを取り入れることで、より効率的に、そして挫折せずに知識やスキルを身につけられるはずです。
総じて、『脳が一生忘れないインプット術』は、「学ぶとはどういうことか」「脳はどうやって覚えるのか」といった学びの根源に立ち返り、科学的なエビデンスに基づいた、具体的で実践的なインプット術を教えてくれる良書です。巷に溢れる根拠不明な情報に惑わされることなく、本当に効果のある方法で学びたいと願う、すべての人に心からお勧めしたい一冊です。
6. まとめ
今回は、星友啓氏の著書『脳が一生忘れないインプット術』について、著者の紹介、本書の概要、要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書が伝える最も重要なメッセージは、効果的なインプットとは、脳科学に基づいた正しいやり方を知り、「読む前」「読みながら」「読んだ後」の各段階で脳を積極的に働かせる「アクティブな」プロセスである、ということです。受動的な学び方では、情報過多の現代において、せっかくの努力が無駄になりやすいと警鐘を鳴らします。
本書では、多くの人がやってしまいがちな「絶対にやってはいけない3つの読み方」を指摘し、それに対比する形で、科学的に効果が証明された「アクティブリーディング」の具体的な方法を詳しく解説しています。目的設定、プレビュー、メタ認知の活用といった「読む前」の準備、ストップ&ゴー、リトリーバルといった「読みながら」の実践、そしてアフターケア、要約といった「読んだ後」の定着化プロセスは、どれも脳の記憶メカニズムを最大限に活かすための重要なステップです。
また、動画や音声といったマルチメディアからのインプット術や、AI要約ツールとの賢い付き合い方、そしてモチベーション管理や情報の見分け方といった、現代の学びにおいて不可欠な要素についても網羅的に解説されています。
私の個人的なレビューとしても、本書は「学んでいるのに身についていない」という悩みに、科学に基づいた明確な答えと実践策を与えてくれました。これまでの非効率なインプット方法を改め、本書で紹介されているアクティブなインプット術を日々のルーティンに取り入れることで、学びの質を劇的に向上させることができると確信しています。特に、「思い出そうとする努力」の重要性や、目的設定・プレビューによるメタ認知の活用は、ビジネスにおける情報収集やチームメンバーの学習サポートにも非常に役立つ視点だと感じています。
もしあなたが、
- 大量の情報に圧倒されている
- 本を読んだり、動画を見たりしても、内容をすぐに忘れてしまう
- 効率的に学び、知識やスキルを身につけたい
- 「やったつもり」ではなく、確実に学びを定着させたい
- 科学的に証明された、信頼できるインプット術を知りたい
と考えているなら、ぜひ本書『脳が一生忘れないインプット術』を手に取ってみてください。
本書は、あなたの学び方を根本から変え、情報過多の時代を力強く生き抜くための「脳が一生忘れない」確かなインプット術を授けてくれるでしょう。そして、あなたの努力が、確かな知識とスキルとして実を結ぶための強力な一助となるはずです。
この本が、皆さんの学びの質を高め、キャリアやライフスタイルをより豊かにするための一助となれば嬉しいです。