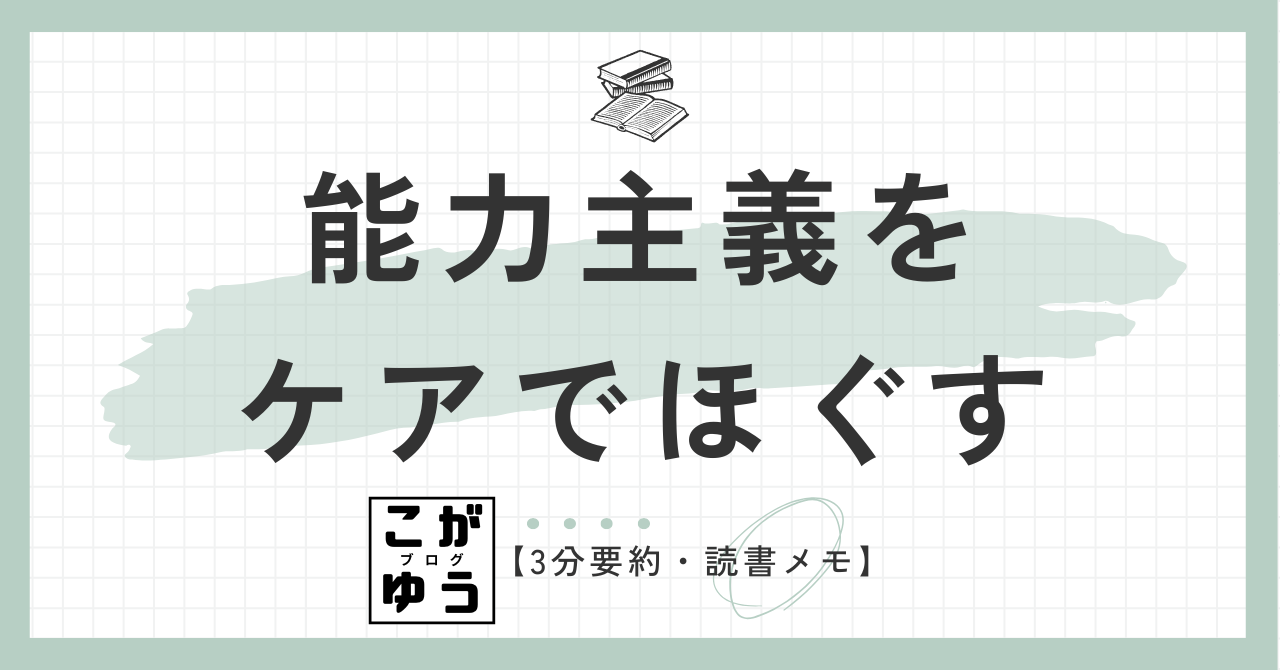「成果を出さなきゃいけない」「もっと頑張らなきゃ」…。
もしあなたが、日々の仕事や生活の中で、そんなプレッシャーを感じているなら、今日ご紹介する一冊は、きっとあなたの心を優しくほぐしてくれるはずです。
その名も、『能力主義をケアでほぐす』。
本書は、社会学者の竹端寛さんが、自らの子育て体験を通して「能力主義」の限界に気づき、「ケア」の視点から社会を見つめ直した思索エッセイです。
この記事では、本書の魅力をわかりやすく解説していきます。
ぜひ最後までお読みいただき、日々の生きづらさやプレッシャーから少し解放されるヒントを見つけてくださいね。
1. 著者の紹介
本書の著者である竹端 寛(たけはた ひろし)氏は、福祉社会学や社会福祉学を専門とする研究者です。現在は兵庫県立大学環境人間学部の准教授として教鞭を執り、理論と現場、個別支援とマクロ政策といった、さまざまな境界領域を行き来しながら精力的に研究活動を行っています。
彼は長年、成果主義や自己責任論が蔓延する社会で「仕事中毒」となり、業績を出すことに強迫観念的に縛られてきました。しかし、2017年に娘を授かって以来、その人生は一変します。
子育てや家事に明け暮れる日々の中で、「今日は何もできていない!」とため息をつく自分に気づいたとき、彼は自身の内面に深く根付いた「能力主義」の価値観を発見します。
本書は、そんな竹端さんが、子育てという「ままならない」経験を通して「ケア」の重要性に目覚め、これまで書き溜めてきたブログ記事をもとに再編集された一冊です。
様々な良書との対話や、社会で出会った人々とのエピソードを交えながら、私たちの社会に深く浸透した能力主義を問い直していきます。
2. 本書の要約
『能力主義をケアでほぐす』は、社会のあらゆる場面に存在する能力主義の呪縛を解き、誰もが生きやすい社会を築くための道筋を示した一冊です。
本書は、著者自身の個人的な経験から社会全体へと視野を広げていく構成になっています。
第1章:能力主義のなにが問題なのか?
この章では、私たちが当たり前だと思っている能力主義が、実はどれほど多くの生きづらさを生み出しているのかを問いかけます。「学歴偏重」というアディクション(中毒)から、能力主義が個人に「努力せよ」という暴力をはらんでいることを鋭く指摘。
能力は個人に備わったものではなく、他者との関係性の中で立ち上がるものであると説き、「あなたはそのままで生きていい」というメッセージを伝えます。
自分は頑張って能力を積み上げたからこそ、うまくいった。だからこそ、あなたも不努力し続けなければならない、と。それは正直、しんどい論理だよなぁ、と感じる。
『能力主義をケアでほぐす』
あなたはそのまま生きて良い
『能力主義をケアでほぐす』
結果的に貧困になった人もその価値前提の中で戦うための「制度的平等」を用意し、それでも脱落したら「自己責任」「努力不足」と問題を個人化する論理は、「努力して社長の地位に就いた(業績を伸ばした、利益率を高めた・・・)のだから、従業員の200倍の給料をもらうのも正当化される」という論理につながる
『能力主義をケアでほぐす』
中略
必要なのは、競争環境の提供(=機会の平等の保証)ではなく、安心して学べるための精神的・社会的・経済的な安定の提供(=結果の平等の保証)なのだ。
第2章:ケアについて考える
竹端さんが子育てを通して気づいた「ケア」の重要性が語られる章です。生産性や効率性とはかけ離れた、子どもの「ままならない」存在との向き合い方を通して、計画通りにいかないことの中にある喜びや、人々の「弱さ」を基盤とした強いつながりの可能性を探ります。
ここでは、「巻き込まれてなんぼ」のケアの世界や、「無力さ」を通じてつながり直す面白さが描かれています。
信頼関係の基本はただ話を聞くこと
『能力主義をケアでほぐす』
そもそも親が、「勉強しているときに『だけ』愛してくれる」という条件付き愛情を子供に注いでいる場合、その子供にとっての「努力」は苦痛でしかない場合がある。
『能力主義をケアでほぐす』
努力する「前提」は平等ではなく、千差万別
『能力主義をケアでほぐす』
虚勢を張らず、自らの脆弱性を認め、その声を聴くこと。
『能力主義をケアでほぐす』
自分の弱さを周りの人に伝えてみること。
そして、身近な他者の脆弱性をそのものとして理解しようと努めること。
そのような対話的関係性から始めるしかない。
介護は受け身。自分たちには○○がやりたい、というのがない。能動的でなく受動的な人の方が介護職は向いている
『能力主義をケアでほぐす』
第3章:家族がチームであること
家庭における「ケア」を深掘りします。仕事中毒だった著者が、家族を最優先にすることの価値を再認識する過程が描かれています。
この章では、日本社会に根強く残る「家族丸抱え」のケアの限界や、制度が家族に依存している現状を指摘。子どもを中心に据えた視点から、社会全体でケアを支え合うことの必要性を訴えます。
第一優先は家族、第二優先が仕事
『能力主義をケアでほぐす』
「私はきっと優先順位をつけるのが上手なの。第一優先は家族、第二優先は仕事。三番目が娯楽や、自分のしたいコト。この優先順位はいつも変わらない」
『能力主義をケアでほぐす』
「だから、友達に会ったりする時間はほとんどない。SNSも一切使わない。SNSを見ると、ものすごくエネルギーを消耗するから。ときどきそんな自分に罪悪感を抱くこともあるけど、でも、やっぱりそこに使う時間はないわ」
親が勝手に決めつけたり、わかった気にならず、こどもを「何とか理解したい」「少しでもわかりたい」と願うとき、子供との協力関係が始まるのだと、改めて思う。
『能力主義をケアでほぐす』
「ケアが必要な人がいるなら家族は面倒を、見るべきだ」という昭和的家族観が未だにデフォルトになっていて、家族だけで抱え込んでいる現実こそ、「社会的ネグレクト」ともいえるのかもしれない。
『能力主義をケアでほぐす』
第4章:学校・制度・資本主義
本書は、個人の内面や家族の問題で終わらず、さらに広い社会へと視点を広げます。偏差値で序列化する「学力工場」としての学校や、資本主義経済の裏で隠されている「ケア」労働の問題に切り込みます。
「平均の論理」が持つ社会的排除の側面を暴き、他者の評価に縛られる「自発的隷従」から脱却するための勇気と決意を促します。シンバル猿(機械的に動く人)にならないために、私たちがどう生きるべきかを問いかけています。
3. ココだけは押さえたい一文
『能力主義をケアでほぐす』を貫く、最も心に響く一文を選ぶなら、著者の竹端さん自身のこの言葉でしょう。
「能力は個人に備わったものではなく、他者との関係性のなかで立ち上がるもの。」
『能力主義をケアでほぐす』
私たちは日々の生活で、「自分に能力がないからダメなんだ」「もっと能力を高めなければ」と考えがちです。しかし、この一文は、その固定観念を根底から揺さぶります。
能力は、一人で努力して身につけるものではなく、誰かと関わり、支え合い、認め合う中で初めて花開くもの。この考え方を胸に刻むだけで、私たちは、日々の競争やプレッシャーから少し解放され、他者とのつながりをもっと大切にしようと思えるはずです。
4. 感想とレビュー
『能力主義をケアでほぐす』というタイトルに惹かれて本書を手に取ったのですが、これは単なる評論書ではなく、著者自身の赤裸々な「生き方」の告白であり、読書という対話を通じて、私たちが内なるモヤモヤと向き合うきっかけをくれる一冊だと感じました。
特に印象的だったのは、竹端さんが子育てを通して「仕事中毒」から解放されていく過程です。
PDCAサイクルやコストパフォーマンスといった生産性至上主義の言語が、子どもの「ままならない」存在によって「見事になぎ倒されていく」という表現は、多くの働く親にとって、心当たりがあるのではないでしょうか。完璧な計画を立てても、子どもの発熱やぐずりで全てが崩れてしまう。
しかし、その「何もできていない」ように見える時間の中にこそ、本当の豊かさや、人との深いケアの関係性があるのだと気づかされます。
また、この本は、能力主義の「暴力性」を看破しながらも、それを一方的に否定するのではなく、なぜ私たちは「努力すれば報われる」という論理に縛られてしまうのか、その社会構造まで深く考察しています。
福祉社会学の専門家である竹端さんの視点だからこそ、個人を責めることなく、社会全体の問題として能力主義を捉え直すことができ、読後には、社会の閉塞感の正体が少し見えたような気がしました。
この本は、以下のような方々に心からお勧めしたいです。
- 日々の仕事や生活で「もっと頑張らなければ」とプレッシャーを感じている方
- 子育てや介護と仕事の両立に悩んでいる方
- 教育や福祉、社会のあり方に関心がある方
- 「できること」や「成果」で自分や他人を評価しがちな価値観を問い直したい方
『能力主義をケアでほぐす』は、私たちの社会に深く根付いた能力主義の呪縛を、ケアという温かい視点でそっと解き放ってくれる、そんな優しさと力強さを持った一冊です。
5. まとめ
今回は、竹端寛氏の著書『能力主義をケアでほぐす』について、著者の紹介、要約、ココだけは押さえたい一文、感想・レビューをまとめました。
本書は、竹端寛氏の個人的な経験と学術的な知見が融合した、心に深く響く思索エッセイです。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- 能力主義の限界:仕事中毒だった著者が、子育てを通して生産性至上主義の限界に気づく。
- ケアの視点:「ままならない」ことの中にこそ、人との強いつながりや豊かさがあることを発見。
- 社会構造の問い直し:個人的な問題で終わらせず、社会全体に根付いた能力主義や制度のあり方を深く考察。
ぜひこの本を手に取って、あなたの心と社会の「能力主義」を、優しくケアでほぐしてみてください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。