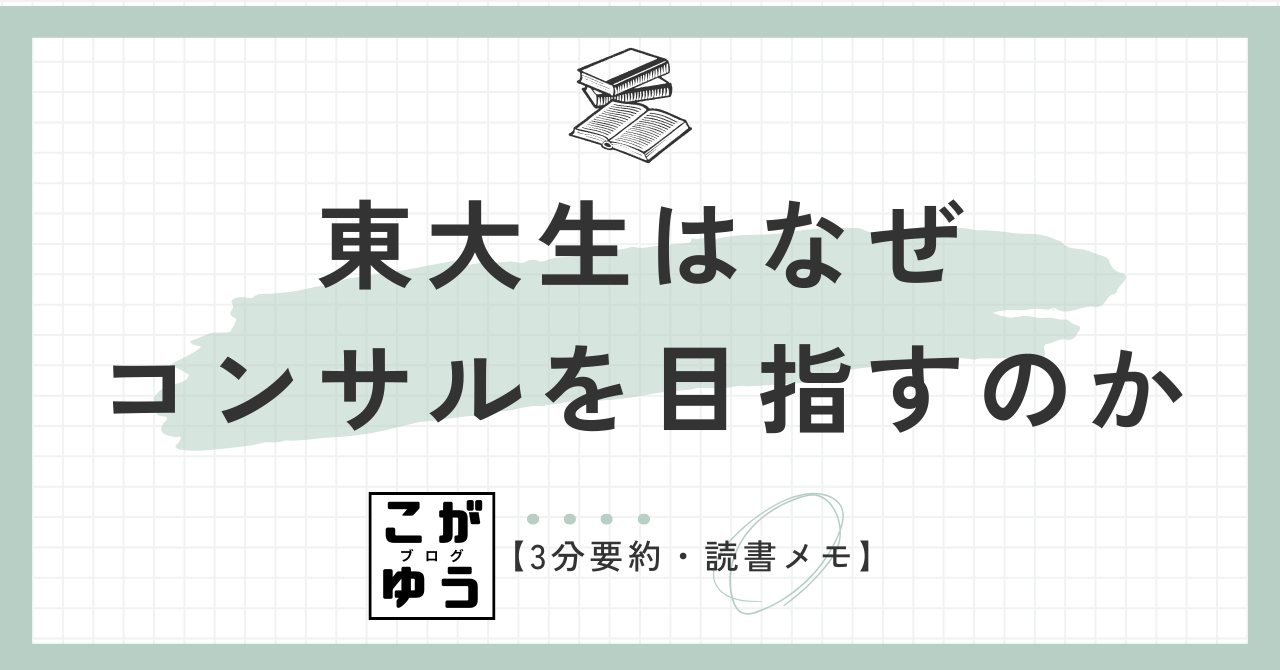最近、就職活動の話題で「東大生がコンサルを目指す」という話をよく耳にしませんか?
一昔前なら、官僚や大手メーカーが人気だったはずなのに、いつのまにかコンサルティング業界が彼らの「憧れの的」になっているなんて、ちょっと不思議に思いますよね。
「東大生はなぜコンサルを目指すのか?」
「そもそも、今の若者は何を求めているんだろう?」
「東大生 コンサルの人気って、一体どんな背景があるの?」
今日ご紹介するのは、そんな現代のキャリア事情、特に「成長」というキーワードに追い立てられるビジネスパーソンたちの心理を鋭く分析した一冊、レジーさんの『東大生はなぜコンサルを目指すのか』です!✨
この本は、単に東大生の就職事情を深掘りするだけでなく、「転職でキャリアアップ」「ポータブルスキルを身につけろ」といった現代ビジネスの「常識」が、私たちにどのような影響を与えているのか、その裏側まで鮮やかに描き出しています。
今回のブログ記事では、この示唆に富んだ一冊の魅力を、以下の構成で深掘りしていきます。
ぜひ最後までお付き合いいただき、あなたも「成長」という言葉と、これからのキャリアについて一緒に考えてみませんか?
1. 著者の紹介
本書『東大生はなぜコンサルを目指すのか』の著者であるレジーさんは、批評家、コラムニスト、編集者として多岐にわたる活動を展開している人物です。
1986年生まれ。東京大学文学部を卒業されており、まさに本書のテーマである「東大生」を内部から見つめ、その背景を分析するのにふさわしい経歴をお持ちです。
レジーさんは、現代社会の現象を鋭い視点で分析し、その本質を浮き彫りにする著作で知られています。特に、ベストセラーとなった前著『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』では、情報過多の時代に「手軽に知識を得たい」という人々の欲求と、それがもたらす弊害について考察し、大きな反響を呼びました。
彼の文章は、単なる表面的な事象の解説に留まらず、社会の構造や人々の心理の奥深くにある「なぜ?」を掘り下げ、読者に新たな気づきを与えます。今回のテーマである「東大生とコンサル」という一見アカデミックなテーマも、彼の手にかかれば、現代を生きる誰もが直面する「仕事」「成長」「キャリア」といった普遍的なテーマへと繋がっていきます。
幅広い教養と、独自の視点から現代社会を読み解く力は、多くの読者から支持を集めています。レジーさんは、固定観念にとらわれず、常に問いを立て、その答えを探求する姿勢で、私たちに思考のヒントを与え続けてくれる存在です。
2. 本書の要約
レジーさんの著書『東大生はなぜコンサルを目指すのか』は、近年、東京大学の学生たちの間でコンサルティング業界への就職人気が急上昇している現象を入り口に、現代社会を覆う「成長」という価値観の光と影を深く掘り下げた一冊です。この本は、単なる就職トレンドの分析に終わらず、ビジネスパーソンが「仕事で成長すること」を求められ、ときに不安に駆られる現代のキャリア観の本質を問いかけます。
本書は、以下の7つの章で構成され、「成長」と「コンサル」というキーワードを軸に、多角的に現代社会を読み解きます。
はじめに:就活ランキングを埋め尽くす「コンサル」
本書の導入として、東大生の就職人気ランキングでコンサルティング業界が上位を占めるようになった現状を提示します。そして、その背景には、「転職でキャリアアップ」「ポータブルスキルを身につけろ」といった、現代のビジネスパーソンが「成長」を強く求められている状況があることを示唆します。
第一章:成長に魅せられ、振り回される人たち
この章では、現代に蔓延する「成長教」とも呼べる風潮が、人々の人生にどのような影響を与えているかを考察します。常に成長を追い求め、立ち止まることを許さない社会の圧力が、人々の心に不安や焦りを生み出し、仕事と人生のバランスを崩している現状を指摘します。また、「会社に頼るな」という言葉の裏にある社会構造についても言及します。
「成長教」で人生のバランスが崩れる
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
会社は、成長させたがる
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
会社都合で成長を「成長を目指すことが正しいことだ」という価値観を押しつける
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
結局、「成長したい」の裏側にあるのは「安定したい」なのである
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
第二章:成長に囚われた時代のカラクリ
「若者はなぜ3年で辞めるのか?」といった過去の議論を再検証しながら、現代の「成長」を求める風潮がどのように形成されてきたかを分析します。企業や社会が、社員を「働かせる」ための手段として「キャリア教育」や「自己成長」を打ち出している側面や、個人の「やりたいこと」と「サバイブ(生き残り)」という二つの欲求が複雑に絡み合っている状況を解き明かします。
安定のために成長を目指さざるを得ない、安定のために成長したいと思わされている。
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
生き残りたい気持ちが「成長」というポジティブなラベルで覆われていて、当人もその切迫感に気づかない。
第三章:「成長」と「コンサル」 東大生はなぜコンサルを目指すのか?
本書の核心部分であり、東大生がコンサルティング業界を目指す具体的な理由を探ります。著者は、彼らがコンサルに魅力を感じるのは、単に高収入やエリート志向だけでなく、以下の点にあると分析します。
- 知的好奇心と問題解決への探求:複雑な課題を論理的に解き明かす知的刺激と、それを究極のスキルとして磨く場を求めている。
- 経験の幅と成長機会:短期間で多様な業界や企業の課題に触れ、汎用性の高いポータブルスキルを身につけ、若いうちから圧倒的に成長できる環境。
- キャリアパスの多様性:コンサルを「キャリアの通過点」と捉え、その後の事業会社への転職、起業、投資家転身など、多様な選択肢を広げるための訓練期間として活用する戦略。
また、コンサル業界で用いられる「MECE」「結論から話せ」「3つあります」といったロジカルシンキングのフレームワークが、彼らにとっての「共通言語」となり、効率的な思考法として魅力的に映ることも指摘しています。
第四章:コンサルタントたちの本音
現役のコンサルタントへのインタビューを通して、彼らが実際に何を考え、なぜこの仕事を選んだのか、その「本音」に迫ります。20代の新卒コンサルタントは「安定のための努力」「モラトリアム期間で武器を身につけるため」と語り、30代の中途コンサルタントは「フレキシブルさ」を強調するなど、彼らのキャリア観や仕事への価値観を浮き彫りにします。
なにになるかより、何をやるかの方が大事
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
第五章:「成長」文脈で読み解くポップカルチャー
一見コンサルとは関係ないように見えるタワマン文学や人気お笑いコンビ「令和ロマン」、元AKB48の宮脇咲良といったポップカルチャーの事例を挙げ、それらがどのように「成長」という現代の価値観を反映しているかを分析します。これは、社会の空気感や人々の願望が、エンターテインメントにも色濃く表れていることを示唆しています。
第六章:成長をめぐる不都合な真実
「働き方改革」がもたらす「ゆるい職場」問題や、イチロー選手の発言から見える「生存者バイアス」など、「成長」という言葉の裏に隠された不都合な真実を暴きます。勤勉さが必ずしも報われるわけではない現代社会の厳しさや、情報に流されず本質を見抜くことの重要性を問いかけます。
第七章:成長に囚われずに、成長と生きる
最終章では、著者が考える「成長」との健全な向き合い方を提示します。「怠惰のウソ」と戦いながらも、過度な成長志向によってキャリア迷子にならないためのヒントが語られます。「ジョブ・クラフティング」など、自己満足を得ながら仕事の意義を見出す方法を提案し、私たちは「成長」に振り回されるのではなく、それを人生の豊かさにつなげていくべきだと締めくくっています。
「優秀な人材」としてスキルと年収を高めるのは、あくまでもビジネスパーソンの成長における一つの側面に過ぎない。
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
無駄だとは言わないが、すべてではない。
怠惰のウソ
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
「あくせく働くことは、のんびりするより道徳的に優れている」「生産性の高い人は生産性が低い人より価値がある」という考え方で、「人の価値は生産性で測られる」「自分の限界を疑え」「もっとできることがあるはずだ」という3つの原則で構成されている
キャリアをコントロールできると思いすぎない
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
3. ココだけは押さえたい一文
本書『東大生はなぜコンサルを目指すのか』の、現代社会の「成長」という価値観と、それに囚われる人々の心理を最も的確に表している「ココだけは押さえたい一文」は、これです。
「『転職でキャリアアップ』『ポータブルスキルを身につけろ』そんな勇ましい言葉の裏側に見えてきたのは、『仕事で成長』を課せられて不安を募らせるビジネスパーソンたちの姿だった。」
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』
この一文は、現代のビジネスパーソンが「成長」という至上命題にいかに追い立てられ、それが新たな不安や生きづらさを生み出しているのかを鮮やかに描き出しています。
東大生がコンサルを目指す背景にある、「成長したい」というポジティブな動機と、「成長しなければ生き残れない」というネガティブな不安が混在する、現代社会の複雑なキャリア観の本質を突いていると言えるでしょう。
4. 感想とレビュー
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』は、まさに現代のキャリアと社会の空気を読むための必読書だと感じました。
著者が東大生のコンサル志向を単なる「エリート志向」や「高収入志向」で片付けず、「知的好奇心」「経験の幅」「成長機会」「多様なキャリアパス」といった多角的な視点から分析している点に感銘を受けました。
特に、コンサルを「キャリアの選択肢を広げるための訓練期間」と捉える現代の戦略的なキャリア観は、私自身の若手時代にはなかった視点で、非常に新鮮でした。彼らは、会社を「一生働く場所」ではなく「通過点」と捉え、自身の市場価値を最大化しようとしている。これは、これからの人材戦略を考える上で、経営層が理解すべき重要な変化だと痛感しました。
「成長に魅せられ、振り回される人たち」という第一章のタイトルは、まさに今の社会を言い表していると感じました。SNSやメディアで「自己成長」「スキルアップ」といった言葉が溢れる中で、私たちは常に「もっと成長しなければ」というプレッシャーを感じています。本書は、そのプレッシャーが、時に人々の心を蝕み、疲弊させているという「不都合な真実」を突きつけてきます。
ポップカルチャーの分析も非常に面白かったです。タワマン文学や令和ロマン、宮脇咲良さんのキャリアなどを通して、「成長」というテーマが社会全体に浸透している様子が具体的に描かれており、読み物としても大変引き込まれました。一見、ビジネス書とは関係なさそうな切り口から、社会の深層を読み解く著者の洞察力は、さすがだと唸らされました。
そして、最終章の「成長に囚われずに、成長と生きる」というメッセージは、まさに現代のビジネスパーソンが目指すべき理想の姿だと感じました。無理に「成長」を追い求めるのではなく、自分らしいペースで、自己満足や仕事の意義を見出しながら、結果的に成長していく。「ジョブ・クラフティング」のように、自らの手で仕事の質を高めていく考え方は、部下たちにもぜひ伝えていきたいと思いました。
この本は、以下のような方々に心からお勧めしたいです。
- 東大生の就職トレンドや、現代のキャリア観に関心がある方
- 「成長しなければ」というプレッシャーを感じているビジネスパーソン
- コンサルティング業界のリアルな姿を知りたい学生や若手社会人
- 若手社員のモチベーションやキャリア形成について悩むマネジメント層
- 現代社会の空気感を鋭く分析する視点に触れたい方
『東大生はなぜコンサルを目指すのか』は、単なる就職ガイドやキャリア論ではありません。それは、私たちが「成長」という言葉といかに向き合い、より豊かに生きるかを深く考えさせてくれる、現代社会の必読書です。ぜひ、この本を読んで、あなた自身の「成長」とキャリアについて、改めて問い直してみませんか?
5. まとめ
今回は、レジーさんの著書『東大生はなぜコンサルを目指すのか』について、著者の紹介、本書の要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書は、東大生のコンサル志向という現象を入り口に、現代社会を覆う「成長」という価値観が、私たちのキャリアや人生に与える影響を深く考察した一冊です。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- 東大生がコンサルを目指す多角的な理由:高収入だけでなく、知的好奇心、幅広い経験、圧倒的な成長機会、そしてその後の多様なキャリアパスを求めている。
- 「成長教」という社会現象:現代のビジネスパーソンは常に「成長」を求められ、それが不安や疲弊の原因となっている側面もある。
- 「成長」をめぐる不都合な真実:表面的な「成長」や効率性追求の裏に隠された、社会の構造的な問題や個人が抱える生きづらさ。
- 「成長」との健全な向き合い方:過度な「成長」の追求に囚われず、自己満足や仕事の意義を見出しながら、自分らしくキャリアを築いていくことの重要性。
- 社会の空気を読む力:ポップカルチャーなどを通して、社会全体の価値観や人々の願望がどのように形成されているかを鋭く分析。
もしあなたが、今、「成長」という言葉に漠然とした不安を感じていたり、これからのキャリアについて深く考えたいと思っているなら、ぜひこの本を手に取ってみてください。
きっと、あなたの心に新たな視点と、自分らしいキャリアを築くヒントを与えてくれるはずですよ。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。