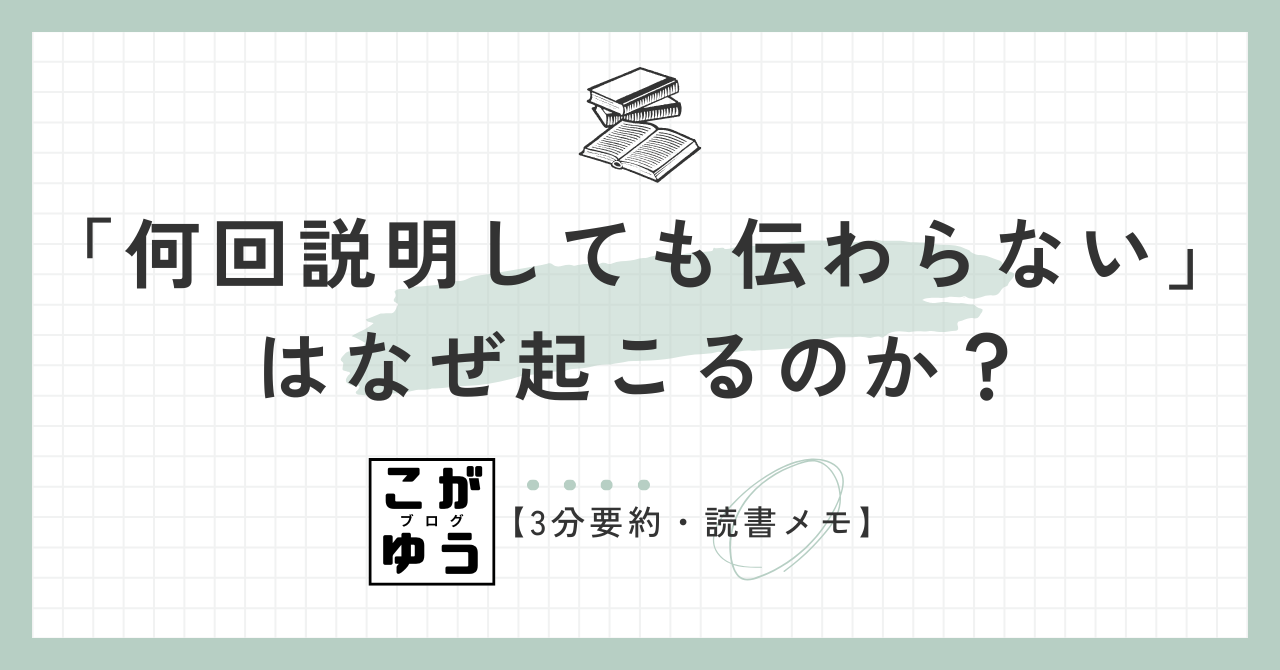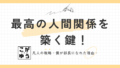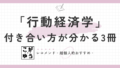あなたは、仕事で部下や同僚に、あるいは家庭でパートナーや子どもに、「何回説明してもなぜか伝わらない…」「言ったはずなのに、理解してもらえていない…」とモヤモヤした経験はありませんか?
「もっと言い方を工夫しなきゃ」「何度も繰り返して説明するしかないのかな」なんて、試行錯誤している方もいるかもしれませんね。
今日ご紹介するのは、そんな「伝わらない」という悩みを抱えるあなたに、根本的な解決策を提示してくれる一冊、認知科学者である今井むつみさんが書かれた『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』です!
この本は、「話せばわかる」という一見当たり前の常識に疑問を投げかけ、「伝わらない」のは「言い方」の問題ではなく、「心の読み方」や「人の認知メカニズム」にあると教えてくれます。私たちは皆、それぞれ異なる「心のフィルター(スキーマ)」を持っていて、同じ言葉を聞いても違う景色を見ているんです。だからこそ、「言ったのに伝わらない」「言っても理解されない」という現象が起こるんですね。
今回のブログ記事では、この目からウロコの一冊の魅力を、以下の構成で深掘りしていきます。
ぜひ最後までお付き合いいただき、あなたも「伝わる」コミュニケーションの達人を目指しませんか?
1. 著者の紹介
本書『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』の著者である今井 むつみ(いまい むつみ)さんは、慶應義塾大学環境情報学部教授であり、認知科学、発達心理学の第一線でご活躍されている研究者です。
今井さんは、言葉の獲得と学習、概念形成に関する研究で世界的に知られており、私たちがどのように言葉を学び、意味を理解し、世界を認識しているのかを科学的に探求しています。学術的な知見を一般向けに分かりやすく解説することにも力を入れており、本書以外にも『学びとは何か』など数々のベストセラーを執筆されています。
難解な認知科学の知見を、私たちの日常生活における「コミュニケーションのすれ違い」や「誤解」の解消に結びつけ、実践的な解決策を提示してくれるのが今井さんの大きな特徴です。その専門性と洞察力が、本書の温かさと説得力に繋がっています。
2. 本書の要約
今井むつみさんの著書『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』は、ビジネスや日常生活における「伝わらない」「わかり合えない」というコミュニケーションの悩みを、認知科学の視点から根本的に解き明かし、その解決策を提示する画期的な一冊です。
著者は、「言い方を変えましょう」「何度も説明しましょう」といった表面的な対策では、真のコミュニケーション問題は解決しないと指摘します。なぜなら、人はそれぞれ異なる「スキーマ」(個々人が持つバックグラウンド、経験、知識、価値観などに基づく心のフィルター)を持っているため、同じ言葉を聞いても、それぞれが都合の良いように解釈し、誤解してしまう「認知の偏り」が起こるからです。
本書は、以下の章立てで、コミュニケーションの本質と、それを改善するための具体的な方法論を提示しています。
はじめに:認知科学者が教えるコミュニケーションの本質と解決策
「伝わらない」問題は、言い方だけでなく「心の読み方」にあると述べ、本書が「伝えること」「わかり合うこと」を真剣に考える人への解決策を提供することを示唆します。
第1章:「話せばわかる」はもしかしたら「幻想」かもしれない
「人と人は、話せばわかり合える」という一般的な認識に疑問を投げかけます。人間の記憶は非常に曖昧であり、話した内容が正確に記憶され、伝わるわけではないという現実を指摘。私たちは、自分の都合のいいように記憶を書き換えたり、解釈したりする生き物であることを解説します。
私たち人間は、相手の話した内容をそのまま脳にインプットするわけではない。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
言葉をつくして説明しても、相手に100%理解されるわけではない。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
ウソをつくつもりがなくても、「相手が、そして自分が、事実をして正しいことを言っているとは限らない。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
第2章:「話してもわからない」「言っても伝わらない」とき、いったい何が起きているのか?
「言っても伝わらない」現象が起こる具体的な理由を、認知科学の視点から深掘りします。
- 「理解」についての2つの勘違い:私たちは「相手が自分と同じように理解する」と思い込みがちですが、実際には「猫」という言葉一つとっても、人によって思い浮かべるイメージは全く異なることなどを例に挙げ、それぞれの「スキーマ」の違いが誤解を生むことを解説。
- 視点の偏り:「まんべんなく公平に見渡す」ことは不可能であり、人は自分の興味関心や専門性によって、見るべき情報が偏ることを指摘。特に「専門性」が高い人ほど、その専門知識が視野を歪ませ、非専門家への説明が難しくなる現象を説明します。
- 記憶の曖昧さと書き換え:人間は「記憶マシーン」ではなく、感情や願望、その時の状況によって記憶がどんどん書き換えられてしまう特性を持つことを解説。言った側は重要だと思っても、言われた側にとってはそうでない場合、記憶に残らない、あるいはすり替わってしまうことが多々あると示します。
- 「認知バイアス」による思考停止:代表性バイアス、過剰一般化、エコーチェンバー現象、信念バイアス、流暢性バイアスなど、様々な認知バイアスが私たちの思考をいかに歪ませ、コミュニケーションの妨げになるかを具体的に解説します。特に、生成AIの普及が、根拠のない情報でも「流暢性バイアス」によって信じられやすくなり、人間の直観力を鈍らせる危険性についても警鐘を鳴らします。
私たちの視点は、つねに偏っている
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
仕事ができる人というのは、「相手も自分も忘れる可能性がある」ということを分かっています。そして、それを回避する方法をあらかじめ見つけています。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
私たちの記憶容量は「1GB」ほどしかない。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
一度記憶しても、ちょっとしたことでその記憶が書き換わってしまう。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
第3章:「言えば→伝わる」「言われれば→理解できる」を実現するには?
認知科学の知見をビジネスや日常生活に落とし込み、「伝わる」コミュニケーションを実現するための具体的な方法を提示します。
- 「相手の立場」で考える:「心の理論」や「メタ認知」の概念を用いて、相手の知識レベル、感情、目的を想像し、相手の「スキーマ」に合わせた伝え方をすることの重要性を説きます。
- 「感情」に気を配る:人の意思決定は感情に左右されることが多いため、感情を味方につけ、ポジティブな関係性を築くことの重要性を解説。
- 「具体と抽象」の使い分け:「伝わる説明」のためには、具体的な事例と抽象的な概念を行き来しながら説明することの有効性を提示。
- 「意図」を読む:言葉の表面だけでなく、相手の真の意図を汲み取ることの大切さ。
選択や意思決定の多くの場合、人は、最初に感情で、端的に言えば「好きか嫌い」で物事を判断し、その後、「論理的な理由」を後づけしているに過ぎない。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
感情を味方につけるコミュニケーションのコツ
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
・理由を伝える
・相手の感情に寄り添う
・悩みを共有する
・感情をぶつけても、問題は解決しない
「なんでできないんですか?」と言うことほど、ラクなことはない。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
第4章:「伝わらない」「わかり合えない」を越えるコミュニケーションのとり方
「いいコミュニケーション」のあり方、そして「コミュニケーションの達人」が持つ特徴について解説します。
- 失敗を成長の糧にする:達人は失敗を分析し、改善に繋げることで、より熟達したコミュニケーションスキルを身につけている。
- 説明の手間を惜しまない:相手のフィルターの違いを受け入れ、暗黙の了解に頼らず、丁寧に説明することの重要性。
- コントロールしようと思わない:相手を操作しようとするのではなく、良い関係性を築き、相手の成長を支援するコーチングのような姿勢が大切。
- 「聞く耳」をいつも持つ:耳が痛い話やネガティブな報告にも真摯に耳を傾け、感謝することで、ポジティブなコミュニケーションサイクルを生み出す。
「相手を思い通りに動かそう」と考えている限りは、真のコミュニケーションは成り立ちません。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
「イヤな報告を受けたときこそ、相手を褒める・感謝する」くらいの心づもりが必要です。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
終章:コミュニケーションを通してビジネスの熟達者になるために
ビジネスにおける熟達者は、コミュニケーションを通して直観を磨き、より複雑な問題解決に対応できるようになることを示唆します。
本書の要約を総括すると、『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』は、コミュニケーションの「なぜ?」を認知科学で解き明かし、単なるテクニックではない、人の心の奥深さを理解することで、真に「伝わる」関係性を築くための羅針盤となる一冊です。
3. ココだけは押さえたい一文
本書『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』の核となるメッセージを凝縮し、読者の認識を大きく変える「ココだけは押さえたい一文」は、間違いなくこれです。
「人は、自分の都合がいいように、いかようにも誤解する生き物です。」
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』
この一文は、私たちがコミュニケーションにおいて直面する「伝わらない」問題の根源を、非常にシンプルかつ的確に表現しています。相手が「理解してくれない」のではなく、人間が持つ本質的な「認知の偏り」によって誤解が生じるという事実を突きつけ、私たち自身の認識を変えることの重要性を示唆しています。この前提を理解することこそが、より良いコミュニケーションへの第一歩となるでしょう。
4. 感想とレビュー
今井むつみさんの『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』は、日々の業務におけるコミュニケーションの悩みに、まさに「腑に落ちる」答えをくれた一冊でした。これまで漠然と感じていた「なんで何度言っても伝わらないんだろう?」という疑問が、認知科学の視点からスッキリと解明され、目から鱗が落ちるような体験でした。
特に印象に残ったのは、「人はそれぞれ違う景色を持っている」という考え方です。この例えは非常に分かりやすく、私たちが普段、いかに「自分が見ているものが、相手も同じように見えているはずだ」という無意識の思い込みをしているかを痛感させられました。部下やチームメンバーに指示を出す際も、私が当たり前だと思っている前提が、彼らにとっては全くそうではない可能性があるのだと、改めて認識させられました。
本書で詳細に解説されている「認知バイアス」の章も、非常に学びが多かったです。私たちが無意識に陥りがちな思考の偏りを知ることで、自分のコミュニケーションを客観的に見つめ直すきっかけになりました。特に、生成AIの普及が、人間の「正しさ」の判断を鈍らせる危険性について警鐘を鳴らしている部分は、マーケティングという情報過多な分野に身を置く私にとって、非常に示唆に富んでいました。
そして、最も実践的だと感じたのは、「相手の立場」で考えるための具体的なアプローチです。会議での説明や、部下へのフィードバックの際に、「相手は今、何を理解していて、何を疑問に思っているだろうか?」と一歩引いて考える癖がついたことで、以前よりも格段に「伝わる」コミュニケーションが取れるようになったと実感しています。
この本は、単なるコミュニケーションスキルアップのテクニック集ではなく、人間の心の奥深さを知り、本当の意味で「わかり合う」ための、深い洞察と実践的な知恵を与えてくれる、人生を変える一冊となるでしょう。
5. まとめ
今回は、認知科学者の今井むつみさんの著書『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』について、著者の紹介、本書の要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書は、「伝わらない」というコミュニケーションの悩みを、人間の「認知のメカニズム」という視点から解き明かし、根本的な解決策を提示する画期的な一冊です。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- 「伝わらない」のは「言い方」でなく「心の読み方」:人はそれぞれ異なる「スキーマ」を持ち、都合よく誤解する生き物であるという前提を理解することが重要。
- 認知の偏りを理解する:記憶の曖昧さ、視点の偏り、専門性、そして様々な認知バイアスが、コミュニケーションのすれ違いを生む原因となる。
- 「相手の立場」で考える:相手の知識レベルや感情を想像する「心の理論」や「メタ認知」を活用し、相手に合わせた伝え方を意識する。
- 「感情」と「具体・抽象」の活用:人の意思決定に感情が大きく関わることを理解し、具体的な事例と抽象的な概念を組み合わせた説明で、より伝わるコミュニケーションを目指す。
- コミュニケーションの達人の特徴:失敗を成長の糧とし、説明の手間を惜しまず、相手をコントロールせず、常に「聞く耳」を持つこと。
『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?』は、「何回説明しても伝わらない」と悩むあなたに、その原因と解決策を明確に示し、より良い人間関係を築くための強力な武器を与えてくれるでしょう。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。