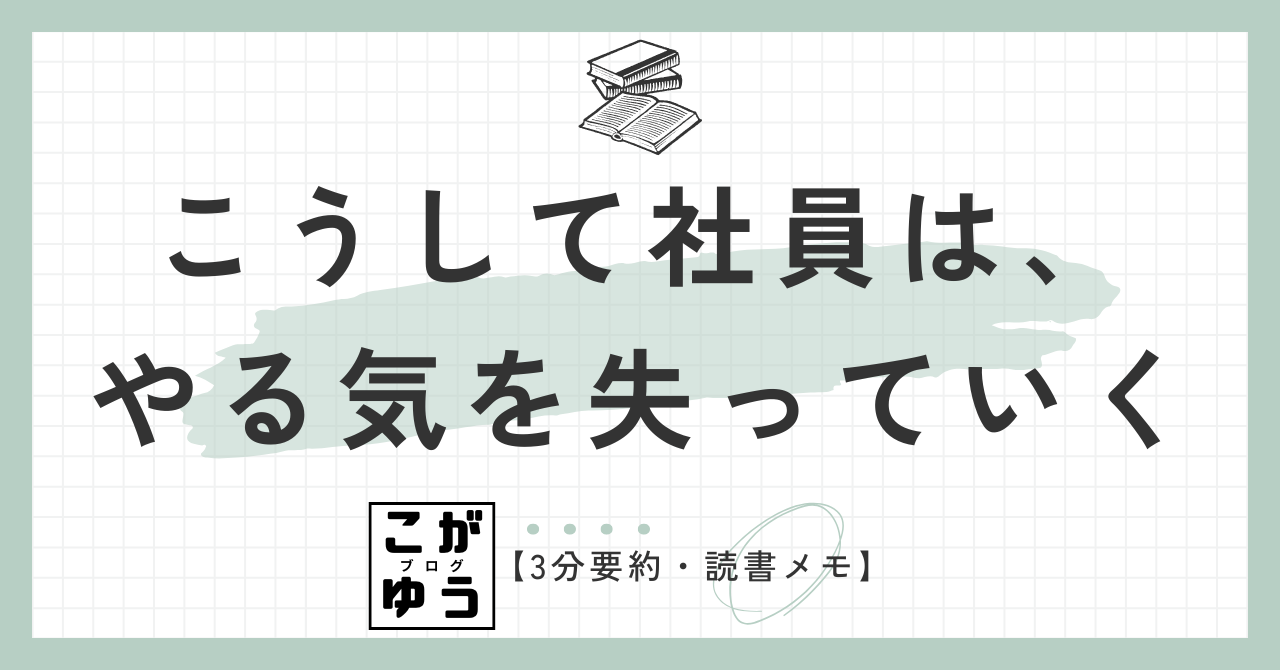ご覧頂き誠にありがとうございます。
このブログでは、マーケティング、マネジメント、そして日々の仕事や生活をより良くするためのヒントを、私の経験を交えながら発信しています。
「どうすれば社員のやる気を引き出せるか?」これは、マネージャーやリーダーなら誰もが悩む永遠のテーマかもしれません。研修を受けたり、様々な施策を企画したり、と皆さん色々と工夫されているのではないでしょうか。
私ももちろんその一人です。チームメンバーが生き生きと働ける環境を作りたい、最高のパフォーマンスを発揮してほしい、と常に考えています。
そんな時に出会ったのが、今回ご紹介する『こうして社員は、やる気を失っていく』という、なんともドキリとさせられるタイトルの一冊です。
著者は、長年様々な企業の組織変革に関わってこられた方。その豊富な経験から、「社員のやる気を高めることよりも、まず優先すべきは『やる気を下げる要因を取り除くことだ』」と喝破しています。
確かに言われてみれば、どんなに良い施策を打っても、日常的に「やる気を削がれること」が起こっていたら、モチベーションは砂が水を吸うように失われていってしまいますよね。
この本は、「こうすればモチベーションが上がる!」という話ではなく、「これをやると、残念ながら社員はやる気を失っていきますよ…」という、耳の痛い現実を「あるある事例」として突きつけ、その上でどう改善すべきかを教えてくれる本です。
私自身も、この本を読んで「うわっ、うちの部署でも、いや、私自身もやってしまっているかもしれない…」と、思わず背筋が凍るような瞬間が何度もありました(苦笑)。
この記事では、私が『こうして社員は、やる気を失っていく』を読んで感じたことを詳しくお伝えしていきます。
ぜひ最後までお付き合いください!
1. 著者の紹介
まず、本書『こうして社員は、やる気を失っていく』の著者である松岡 保昌(まつおか やすまさ)氏をご紹介します。
松岡氏は、株式会社モチベーションジャパンの代表取締役社長であり、経営・人事・マーケティングのコンサルタントとして、多くの企業の組織変革や人材育成を支援されています。
そのキャリアが非常にユニークで、コンサルタントとして活躍される前には、様々な分野でトップに近いポジションを歴任されています。
具体的には、まずリクルートで『就職ジャーナル』や『Works』といったメディアの編集、そして組織人事コンサルタントとしてご活躍されました。ここで、組織と人間の組織心理について深く学ばれた経験が、本書の根幹にも活きています。
その後、ファーストリテイリングやソフトバンクといった、日本を代表するグローバル企業で、人事やマーケティング関連の幹部として手腕を振るわれました。特にソフトバンク時代には、福岡ソフトバンクホークスの取締役として、球団の立ち上げや経営にも深く関わられたという経歴もお持ちです。
このように、松岡氏はコンサルタントとして多くの企業を外から見てきた経験と、リクルート、ファーストリテイリング、ソフトバンクという最前線の企業で実際に組織や人を動かしてきた経験、その両方を兼ね備えています。
本書で語られる内容は、単なる理論や理想論ではなく、ご自身の豊富な実体験と、長年培ってこられた組織心理への深い洞察に基づいています。社員のモチベーションが自然に高まる仕組みや、金銭的なものだけでなく「見えない報酬」を大切にする仕組みを実際に作り、運用してきた経験があるからこそ、本書の内容は非常に説得力があるのです。
まさに、机上の空論ではない、「現場を知るプロフェッショナル」が書いた一冊と言えるでしょう。
2. 本書の概要
次に、本書『こうして社員は、やる気を失っていく』が全体としてどのような内容を扱っているのか、その概要を説明します。
本書の最大のテーマは、「社員のモチベーションは、高めることよりも、まず『下げない』ようにすることが重要である」という、一見逆説的とも思えるメッセージです。
多くの会社やマネージャーは、社員のやる気を引き出すための研修やイベント、表彰制度といった「モチベーション向上施策」に力を入れがちです。もちろんこれらも大切ですが、本書は、それ以前に日常的に行われている「社員のやる気を削いでしまう言動や組織のあり方」にこそ、まず目を向けるべきだと強く主張します。
特に現代の若手社員は、無理に鼓舞しなくても、やる気をそぐようなことをされなければ、自然と前向きに仕事に取り組むポテンシャルを持っている、というのが著者の見方です。だからこそ、そのポテンシャルを潰さないこと、つまり「社員のやる気を削いでしまう言動や組織のあり方」というモチベーションを下げる要因を徹底的に排除することが、最優先の課題となるのです。
本書は、この「モチベーションを下げる要因」に焦点を当て、疲弊する組織や離職率の高い会社で頻繁に見られる「あるあるケース」を、「やってはいけないこと」として具体的に列挙し、その問題点と改善策をセットで解説しています。
いわば、「反面教師」として、これらの「残念な上司」や「ガッカリな職場」の事例から学び、自身のマネジメントや組織の課題に気づき、改善を促すことを目的とした本です。
本書は以下の章立てで構成されており、非常に分かりやすい流れになっています。
- 第1章 企業の格差は「モチベーション」に起因する
- なぜ、社員のモチベーションが重要なのか? 下がると何が問題なのか? その導入部分です。
- 第2章 社員がやる気を失っていく上司に共通する10の問題と改善策
- マネージャーやリーダー個人の言動が、部下のやる気をどう削ぐのか?具体的な「あるある」と、それぞれの対策が示されます。
- 第3章 「組織が疲弊していく」会社に共通する15の問題と改善策
- 組織全体の仕組みや文化、風土が、社員のやる気をどう奪うのか? 会社レベルの「あるある」と、その対策が示されます。
- 第4章 こうして社員が変わり、会社も変わっていく〜「組織心理」に基づいたマネジメント
- モチベーションダウンを防ぐための具体的な施策や心構えを、組織心理に基づいた理論(心理的安全性、内発的動機づけなど)とともにまとめて提示しています。
本書の構成はシンプルで、特に第2章と第3章が本書の中心と言えます。各問題点が具体的にリストアップされ、それぞれに対してすぐに実践できる改善策が添えられています。この「問題提起 → 解決策」という対になった構成が、非常に読みやすく、自分の職場に引きつけて考えやすい工夫だと感じました。
長年のコンサルタント経験と、実際の大企業での組織マネジメント経験に基づいているため、挙げられている事例はリアルで、説得力があります。なかには「え、今の時代にこんなこと本当に?」と思うような極端な例も含まれているそうですが、それらはすべて「やる気を引き下げる要因となりうるもの」として、反面教師として受け止めるべきだと著者は述べています。
本書を読むことで、あなたは知らず知らずのうちにやってしまっているかもしれない「やる気を削ぐ言動」に気づき、それをやめるための具体的な方法を学ぶことができます。また、自社の組織が抱える、社員のモチベーションを低下させている構造的な問題点に気づき、改善の糸口を見つけることができるでしょう。
「やる気を失わせない」というネガティブな要因排除のアプローチから組織とマネジメントを見つめ直すための、非常に実践的な一冊と言えます。
3. 本書の要約
それでは、本書『こうして社員は、やる気を失っていく』の主要なポイントを、要約として詳しく見ていきましょう。
本書の最も重要な主張は、繰り返しますが、「社員のモチベーションを高めることばかりに注力するのではなく、まずモチベーションを下げる要因、すなわち『やってはいけないこと』を特定し、それを取り除くことから始めよ」ということです。
著者は、多くの組織がこの逆を行っている現状に警鐘を鳴らします。バケツに穴が開いているのに、いくら水を注いでも溜まらないのと同じように、モチベーションを下げる要因が存在する限り、どんな向上施策も効果は限定的になってしまうのです。特に、前述の通り、最近の若手社員は外からの刺激で無理やりモチベーションを上げなくても、変にやる気を削がれなければ、自然と前向きに取り組む傾向が強いと指摘しています。
では、具体的にどのようなことが社員のやる気を失わせてしまうのでしょうか? 本書では、これを「上司に共通する問題」と「組織が疲弊する会社に共通する問題」として、多数の「あるあるケース」を挙げています。
社員がやる気を失っていく上司に共通する問題(一部抜粋):
- 理由や背景を説明しない / 一方通行の指示をするだけ:
- 指示だけがポンと飛んできて、その仕事の目的や、会社全体の目標とどう繋がるのかが見えないと、社員は単なる作業者になったように感じ、主体性や納得感が失われます。「何のためにこれをするのだろう?」という疑問がやる気を削ぎます。
- コントロールできる部分を与えない:
- 任された仕事に対して、進め方や裁量の余地が全くないと、社員は自分の力を発揮する機会がないと感じます。これは自己効力感(「自分にはできる」という感覚)を低下させ、「どうせ自分がやっても変わらない」という無力感につながります。
- 話を聞かずに結論を出す / 意見も提案も受け入れない:
- 部下が考えや意見を持っていても、聞く耳を持たなかったり、頭ごなしに否定したりすると、社員は「自分の存在や貢献が認められていない」と感じます。これは心理的安全性を著しく損ない、委縮して何も言わなくなり、新しいアイデアも生まれなくなります。
- 言うことに一貫性がない:
- 日によって言うことが変わったり、以前の指示を覆したりすると、部下は何を信じれば良いか分からなくなります。上司への不信感が募り、指示に対して懐疑的になり、安心して仕事に取り組めなくなります。
- 感覚だけで評価する:
- 明確な基準がなく、上司の好き嫌いやその時の印象だけで評価が決まると、社員は「どう頑張れば評価されるのか分からない」と感じます。これは評価への納得感を失わせ、「頑張っても無駄だ」という諦めにつながります。
- 失敗を部下のせいにする / 部下の仕事を横取りする:
- これは論外ですが、部下は安心して挑戦できなくなり、上司への信頼は完全に失われます。
組織が疲弊していく会社に共通する問題(一部抜粋):
- いつもピリピリしている:
- 職場の雰囲気が悪く、皆が顔色をうかがっていたり、小さなミスにも過剰に反応したりする環境では、社員はリラックスして働くことができません。これも心理的安全性の欠如であり、社員は発言や行動を控えるようになります。
- 個人が仕事を抱えすぎている / 仕事を押しつけ合う:
- 業務分担が不明確だったり、特定の人に負荷が集中したり、逆に責任の押し付け合いがあったりすると、社員は疲弊し、不公平感を感じます。適切なワークロードとサポート体制の欠如は、持続的なモチベーションを損ないます。
- 前例ありき、過去の成功体験から抜けられない:
- 変化を嫌い、新しい挑戦を受け入れない組織では、社員は新しいアイデアを出したり、改善提案をしたりすることに意味を見出せなくなります。「どうせ言っても無駄だ」「変化は認められない」という感覚が、創造性や挑戦意欲を奪います。
- 管理職が逆ロールモデル:
- 本来手本となるべき管理職が、指示待ちだったり、愚痴ばかり言っていたり、非効率な働き方をしていたりすると、社員は「ああはなりたくない」と感じ、組織の将来に希望を持てなくなります。
- 長期的な展望を描けない / 理念が言葉だけ:
- 会社として目指す方向性が見えなかったり、掲げている理念と実際の行動が乖離していたりすると、社員は何のために働いているのかを見失いがちです。自分の仕事が社会や会社の未来にどう貢献するのかが見えないと、内発的動機づけが働きにくくなります。
- 物事を決められない:
- 意思決定が遅く、いつまで経っても物事が進まない組織では、社員はフラストレーションを感じ、停滞感からやる気を失います。
本書は、これらの「あるあるケース」を挙げた上で、それぞれに対する具体的な改善策を提示しています。その根底にあるのは、組織心理の知見です。
特に、第4章で詳しく解説される「心理的安全性」と「ブラックボックス化」の概念は非常に重要です。
心理的安全性 (Psychological Safety):
これは、「チームの中で、自分の考えや気持ちを、誰に対してでも安心して発言できる状態」を指します。「こんなことを言ったら馬鹿にされるかな」「失敗したら責められるかな」といった不安なく、自由に意見交換や質問、挑戦ができる環境のことです。 著者は、特に創造性や変化対応力が求められる現代において、心理的安全性が不可欠だと説きます。なぜなら、複雑な課題に対して一人で答えを出すのは難しく、多様な他者の知恵や経験を借りるためには、安心して発言できる場が必要だからです。
心理的安全性が低い職場では、社員は「波風を立てたくない」「無難にやりたい」と考え、発言を控えるようになります。質問が減り、新しいアイデアが出なくなり、組織は硬直し、やがて衰退していくのです。 ブレインストーミングが良い例で、心理的安全性が確保されていないと、参加者は自由に発言できず、ブレストは失敗します。「批判しない」「自由に発言する」といったブレストの原則は、まさに心理的安全性を確保するためのルールなのです。
ブラックボックス化 (Black Boxification):
心理的安全性が低い、特に「失敗すると評価が下がる」「正当に評価されないかもしれない」といった恐怖感がある環境では、社員は自分の立場を守ろうとします。その結果、自分の担当業務を、他の人には分からないように囲い込んでしまう「ブラックボックス化」が起こり得ます。 これは、その人がいないと業務が回らなくなる状況を作り出すことで、自分の存在価値を示し、クビにならないようにするという、ある種の自己防衛です。「このままでは評価が下がるかも…自分にしかできない仕事を持っていれば安心だ」といった「評価への恐怖」や「職場への不安」といった心理が働きます。
しかし、ブラックボックス化された業務は、組織にとってはリスクであり、情報共有や業務改善の妨げになります。マネジメントも困難になります。 本書では、ブラックボックス化してしまった社員との信頼関係を時間をかけて再構築し、安全な環境だと伝えることで、社員が再びオープンになっていったという具体的なエピソードが紹介されており、安全で安心な環境の重要性を浮き彫りにしています。そして、このような事態を防ぐためには、日頃からの信頼関係の構築と、社員が正当に評価されていると感じられるような評価の仕組みが不可欠です。
その他にも、本書では「見えない報酬」(金銭以外での承認、成長機会、貢献実感など)を重視すること、内発的動機づけを引き出すコミュニケーション、部下の行動原理や不満・満足感を理解する方法、納得感のある人事評価のあり方など、社員のモチベーションダウンを防ぐための実践的なノウハウが多数紹介されています。
マネジメントは勘や経験だけでなく、組織心理に基づいた、「スキル」として学び、身につけるべきものだ、という著者の主張は、本書全体を通じて貫かれています。
本書の要約を締めくくるならば、社員のやる気を失わせる「あるある」な言動や組織の構造を徹底的に知り、それを「やらない」こと。そして、心理的安全性のような、社員が安心して意欲的に働ける土壌を作ること。これが、組織の活性化とパフォーマンス向上のための、最も現実的で効果的な第一歩である、ということです。
4. ココだけは押さえたい一文
本書『こうして社員は、やる気を失っていく』の中で、私が最も強く印象に残り、「これこそがこの本の、いや、マネジメントの本質ではないか!」と感じた一文があります。
それは、本書の冒頭部分で示されている、この言葉です。
「社員のモチベーションを高めるためにすべきは、まず『下げる要因』を取り除くことである。」
『こうして社員は、やる気を失っていく』
多くの書籍や研修では、「どうすれば社員のモチベーションを上げられるか?」という点に焦点が当てられがちです。もちろんそれは重要なのですが、この一文は、その前という、より根本的な問いに向き合うことの重要性を私たちに教えてくれます。
どんなに素晴らしい「モチベーション向上施策」も、やる気を削ぐ要因が放置されていれば、効果は薄れてしまいます。これは、水漏れしているバケツに一生懸命水を注ぎ続けるようなものです。まずはバケツの穴を塞ぐこと、つまりモチベーションを下げる「やってはいけないこと」をやめることが、何よりも優先されるべきなのです。
特に、日々マネジメントに携わる中で、「どうもうまくいかないな…」「メンバーの反応が鈍いな…」と感じることがあるならば、それはもしかしたら、あなたの言動や組織の仕組みの中に、意図せず社員のやる気を削いでしまっている「穴」があるのかもしれません。
この一文は、私たちマネージャーやリーダーに対し、「良いことを加える」ことよりも前に、「悪いことをやめる」ことの緊急性と重要性を再認識させてくれる、非常にパワフルな言葉だと感じました。
本書を読む際には、ぜひこの一文を常に頭に置いて、自分の職場や自身の言動を振り返ってみてください。この視点を持つだけで、見えてくる課題や取り組むべきことが大きく変わってくるはずです。
「やる気」は個人の問題ではなく、職場の問題
『こうして社員は、やる気を失っていく』
「会社のニーズ」と「個人のニーズ」が重なる時、人は自ら動く
『こうして社員は、やる気を失っていく』
傾聴のスキル
『こうして社員は、やる気を失っていく』
①話を聞く姿勢
②共感的理解
③無条件の受容
④自分が理解したことを、理解できたことを伝える
⑤会話を深める質問
人は感情の生き物
『こうして社員は、やる気を失っていく』
3つほめて、1つ叱り、1つ励ます
『こうして社員は、やる気を失っていく』
人に言いにくいことを伝える時は、「I(アイ)メッセージ」
『こうして社員は、やる気を失っていく』
自分が主語になる「わたしは」でじはじめる
モチベーションを高めるためにやるべきことは、まずはモチベーションを下げない
『こうして社員は、やる気を失っていく』
5. 感想とレビュー
本書を読んで一番に感じたのは、「そうそう!これ、あるあるなんだよ!」という強い共感でした。著者が挙げる「社員がやる気を失っていく上司の問題」や「組織が疲弊していく会社の問題」は、私自身がこれまで経験してきた組織や、今現在見聞きする職場でも、まさに「あるある」として存在する光景ばかりだったからです。
特に「理由や背景を説明しない一方通行の指示」や「話を聞かずに結論を出す」といった上司の問題は、残念ながら今でも色々な現場で目にします。私自身も、忙しさにかまけてつい説明が不足してしまったり、結論を急いで相手の話を十分に聞けていなかったりする場面があったかもしれない、と本書を読んで深く反省しました。「自分がやっていることは大丈夫か?」と自問自答しながら読み進める良い機会になりました。
また、「個人が仕事を抱えすぎている」「前例と成功体験から抜けられない」といった組織の問題も、耳が痛い話です。変化の激しいマーケティングの世界では、過去の成功体験に囚われているとあっという間に置いていかれます。新しい手法や技術を取り入れようとしても、組織全体に停滞感があると、チームメンバーの挑戦意欲も削がれてしまいます。
本書で特に学びが深かったのは、「心理的安全性」と「ブラックボックス化」のメカニズムについてです。これらの概念は近年よく耳にするようになりましたが、本書はそれが「なぜ重要なのか」、そして「それがないとどうなるのか」を、「あるある」事例を通じて非常に分かりやすく説明してくれています。
例えば、私のチームでも、新しいマーケティング施策についてブレインストーミングをすることがあります。以前は、どうも活発な意見交換にならないな、と感じることもありました。本書を読んで、それは単に「発想力がない」のではなく、もしかしたら「心理的安全性が十分に確保されていなかったのかもしれない」と気づかされました。「こんなアイデア、言ったら笑われるかな」「的外れなことを言って、評価が下がるのは嫌だな」といった不安が、メンバーの発言を躊躇させていた可能性を真剣に考えるようになりました。
これからは、ブレストの際には本書で推奨されている「批判しない」といったルールを徹底するだけでなく、日頃からチーム内で「何を言っても大丈夫」という安心感を醸成することにもっと意識を向けようと思っています。メンバーが安心して率直な意見や懸念を表明できる環境こそが、新しいアイデアを生み出し、変化に強いチームを作る土台になると確信しました。
また、「ブラックボックス化」の話も非常にリアルでした。特に専門性の高い業務を担当しているメンバーがいるチームでは、その人しか業務内容を完全に理解していない、という状況が起こり得ます。本書を読んで、それが単なる「属人化」の問題だけでなく、その根底に「評価への恐怖」や「職場への不安」といった心理が隠れている可能性があることを理解しました。マネージャーとしては、単に「情報共有してね」と伝えるだけでなく、メンバーが「自分の知識やスキルを共有しても、自分の立場は脅かされない」と安心できるような、信頼関係と評価の仕組みを作ることが重要なのだと痛感しました。
本書は、「こうすればやる気が上がる!」という派手な特効薬を期待する人には物足りないかもしれません。しかし、地に足をつけて、組織やマネジメントの根本的な課題に向き合いたいと考えている人にとっては、非常に価値のある一冊です。
「マネジメントは勘と経験だけでなく、スキルとして学ぶべきものだ」という著者のメッセージも、私には強く響きました。マネージャーになった途端、急に部下を持たされ、どうすれば良いか手探り…という人も多いと思います。本書は、そんな手探りの状態から抜け出し、心理学に基づいた確かな知識とエビデンスをもって、自信を持ってマネジメントに取り組むための強力な羅針盤となるでしょう。
私のブログのもう一つのテーマである「ライフスタイル」という観点からも、本書は多くの示唆を与えてくれました。例えば、新しい習慣を身につけたいと思っても、三日坊主で終わってしまうことってありますよね。これも人間は楽な方に流れやすいという弱さ(性弱説)と、本書でいうところの「やる気を失う=行動を阻害する要因」が関係しているのではないでしょうか。運動しようと思っても、「準備が面倒くさい」「疲れている」といった「やる気を失わせる要因」があるから続かない。健康的な食事をしようと思っても、「目の前にお菓子がある」といった「誘惑要因」があるから挫折する。
本書で学んだ「モチベーションを高めるより、下げる要因を取り除く」という考え方を、自分の習慣づくりにも応用できないかと思っています。例えば、運動するハードルを下げるために、運動着をすぐに手の届く場所に置く。お菓子を無駄に買わない。このように、「望ましい行動を阻害する要因を物理的・心理的に取り除く仕組み」を作ることで、意志力に頼らずとも習慣が継続しやすくなるのかもしれません。
総じて、『こうして社員は、やる気を失っていく』は、マネジメントに携わるすべての人にとって、「やる気を失わせない」という視点から組織と人を見つめ直すための必読書です。挙げられている「あるある」に、きっとあなたの職場やあなた自身が重なる瞬間があるはずです。耳の痛い話も含まれますが、それこそが現状を変えるための第一歩となるでしょう。
小手先のテクニックではなく、組織心理に基づいた本質的なアプローチを学びたい方には、心からお勧めしたい一冊です。
6. まとめ
今回は、松岡 保昌氏の著書『こうして社員は、やる気を失っていく』について、家電メーカーのマーケティング部長である私の視点から、著者の紹介、本書の概要、要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書の最も重要なメッセージは、「社員のモチベーションを高めるためには、まず『下げる要因』を取り除くことが最優先である」ということです。多くのマネージャーや組織が陥りがちな、「やる気を削いでいることに気づかないまま、モチベーションアップ施策ばかりに注力する」という状態からの脱却を強く促す一冊です。
本書では、社員のやる気を失わせる「上司の10の問題」と「組織の15の問題」が、「あるあるケース」として具体的に挙げられ、それぞれに対する改善策が丁寧に解説されています。これらは、あなたの職場にもきっと当てはまる点があるはずです。
特に、「心理的安全性」の重要性とその欠如がもたらす弊害(発言の抑制、組織の硬直)、そして、「ブラックボックス化」という、社員が不安から自分の業務を囲い込んでしまう現象とその背景にある心理についての解説は、多くのマネージャーにとって目から鱗の内容でしょう。
本書で学ぶべきは、小難しい理論ではなく、組織心理に基づいた、人が意欲的に働くための土壌づくりの重要性です。そして、それを実現するためには、まず「やってはいけないこと」をやめることから始める、という極めて実践的なアプローチです。
私自身も、この本を読んで自身のマネジメントを深く反省するとともに、チームの心理的安全性を高めるための具体的な行動や、メンバーが安心して業務に取り組めるような信頼関係の構築、そして「見えない報酬」をもっと意識して提供することの重要性を改めて認識しました。
もしあなたが、
- 社員のモチベーション低下に悩んでいる
- 組織の停滞感や非効率性を感じている
- 部下とのコミュニケーションに課題がある
- マネジメントを体系的に学びたい
- 「あるある」から学び、自分の言動や職場を改善したい
と考えているなら、ぜひ本書『こうして社員は、やる気を失っていく』を手に取ってみてください。
耳の痛い「あるある」のシャワーを浴びることになるかもしれませんが(笑)、それは間違いなく、あなたのマネジメントや組織を変えるための、そして社員のやる気を再び引き出すための、非常に価値ある一歩となるはずです。
この本が、皆さんの職場がより良い環境になり、社員一人ひとりが持つポテンシャルを十分に発揮できるための一助となれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。