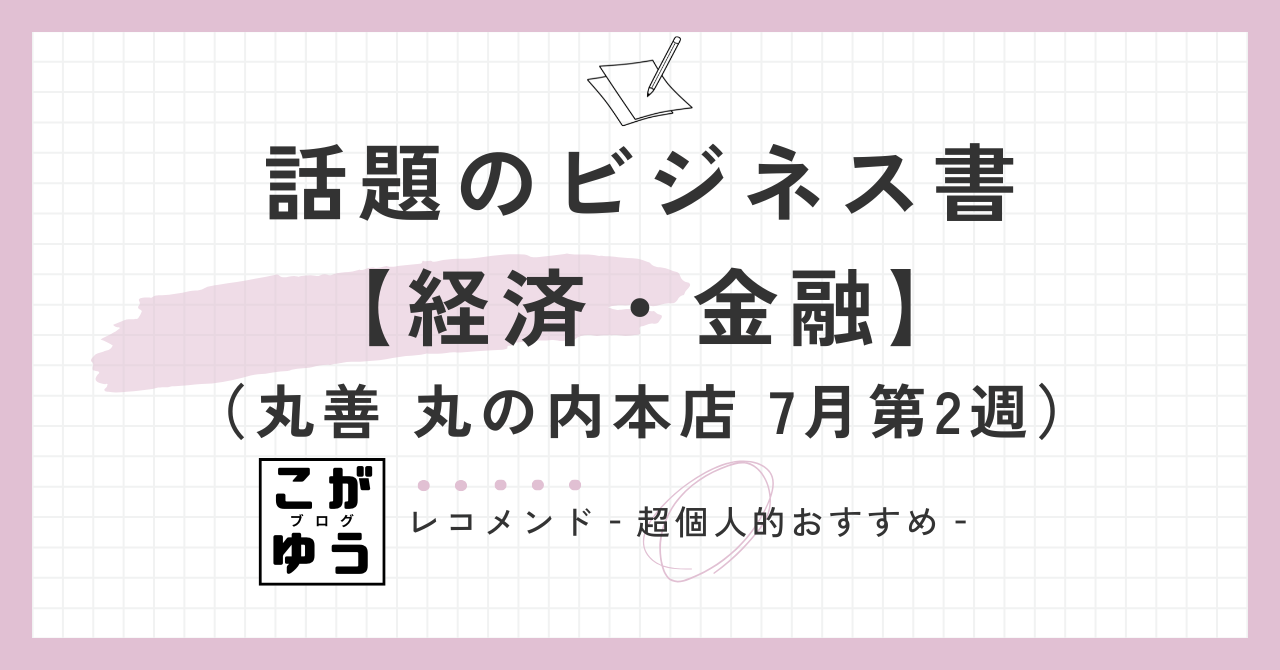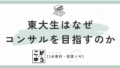2025年7月18日の日経BOOKPLUSに、話題の本 書店別・週間ランキング(2025年7月第2週)が特集されていた。
サイトでは、丸善 丸の内本店、丸善 日本橋店、紀伊國屋書店 新宿本店の3書店で、ビジネス書、ノンフィクション、フィクション、新書、文庫など様々なカテゴリーランキングが紹介されている。
本ブログでは、丸の内で働く40~50代の会社員が多いと思われる丸善 丸の内本店の経済・金融のランキングを紹介する。
【経済・金融ビジネス書ランキング】
1. 『新富裕層のための本質的不動産投資』
杉山 浩一 著、明日香出版社
本書は、単なる不動産投資のテクニックに留まらず、「新富裕層」と呼ばれる層が実践する本質的な不動産投資の考え方を深く掘り下げた一冊です。著者の杉山浩一氏は、豊富な経験と実績を持つ不動産投資の専門家であり、表面的な利回りやキャピタルゲインだけでなく、不動産が持つ本来の価値を見抜き、長期的な視点で資産を築くための戦略を詳細に解説しています。物件選定の基準、リスクマネジメント、出口戦略、さらには税務対策といった具体的なノウハウに加え、不動産を通じて社会に貢献するという視点も提示。インフレ対策や安定した資産運用を求める個人投資家にとって、従来の不動産投資の常識を覆し、真の富を築くための羅針盤となる必読書です。
2. 『50万円を50億円に増やした投資家の父から娘への教え』
たーちゃん 著、ダイヤモンド社
わずか50万円の元手を50億円にまで増やしたという驚異的な実績を持つ投資家の父親が、その成功の秘訣を娘に語りかける形式で書かれた、実践的な株式投資の指南書です。本書は、単なる投資手法の解説に終わらず、市場の本質、リスクとの向き合い方、そして投資家として必要なマインドセットを、親子間の温かい対話を通じて分かりやすく伝えています。具体的な銘柄選定の考え方、市場のサイクルを読む洞察力、そして感情に流されない冷静な判断力など、成功する投資家が持つべき資質を具体的なエピソードと共に解説。投資初心者でも理解しやすい言葉で書かれており、株式投資の基本から応用までを段階的に学ぶことができます。少額からでも大きな資産形成を目指したいと考える個人投資家にとって、実践的な知恵と勇気を与えてくれる一冊となるでしょう。
3. 『新・ドル覇権の崩壊 金はまだまだ上がる』
副島 隆彦 著、徳間書店
著者の副島隆彦氏が、世界の基軸通貨である「ドル」の覇権が終焉を迎えつつあるという衝撃的な見解を提示し、それに伴い「金(ゴールド)」の価値が今後も上昇し続けると大胆に予測する一冊です。本書は、国際政治、金融政策、そして地政学的リスクといったマクロな視点から、ドルの信頼性低下の要因を多角的に分析。米国の財政赤字問題、中国やロシアの台頭、そしてデジタル通貨の台頭など、世界の経済秩序の変動を鋭く読み解きます。単なる経済予測に留まらず、歴史的な文脈を踏まえながら、金が安全資産として果たす役割の重要性を強調し、来るべき金融システムの変革期に個人がどのように資産を守るべきかを提言。金融市場の大きな転換点を見据え、資産防衛と投資戦略を再考したいと考える投資家やビジネスパーソンにとって、非常に刺激的で示唆に富む一冊となるでしょう。
4. 『トレーディング・ゲーム』
ギャリー・スティーヴンソン 著、早川書房
金融市場で成功を収めるための「トレーディングの本質」を、ゲーム理論の視点から深く掘り下げた一冊です。著者のギャリー・スティーヴンソンは、長年のトレーディング経験を持つプロフェッショナルであり、市場を単なる数値の変動としてではなく、プレイヤー間の心理戦や戦略的相互作用が絡み合う「ゲーム」として捉えることで、勝つための思考法を提示しています。市場参加者の行動原理、情報の非対称性、そしてリスクマネジメントといった要素をゲーム理論のレンズを通して分析し、感情に流されない冷静な意思決定の重要性を強調。チャート分析やテクニカル指標といった表面的な手法に囚われず、市場の背後にある「人間心理」と「戦略」を理解することで、トレーディングにおける優位性を確立するためのヒントが満載です。株式、FX、仮想通貨など、あらゆる金融市場で利益を追求したいトレーダーや投資家にとって、必読の戦略書となるでしょう。
5. 『戦後日本経済史』
野口 悠紀雄 著、東洋経済新報社
著者の野口悠紀雄氏が、終戦から現在に至るまでの日本経済の変遷を体系的に分析し、その構造的変化と特徴を明らかにする一冊です。高度経済成長期の奇跡、バブル経済とその崩壊、「失われた30年」と呼ばれる低迷期、そして現代の課題に至るまで、各時代の経済政策、産業構造の変化、技術革新、そして国際情勢が日本経済に与えた影響を深く考察しています。単なる歴史的事実の羅列に終わらず、それぞれの時代に日本経済が直面した課題と、それに対する政策や企業の対応を詳細に分析。経済学の視点から、なぜ日本経済が特定の軌跡をたどったのか、そしてそこから現在への教訓として何を学ぶべきかを提示しています。過去を知ることで未来を予測し、現代の経済問題を多角的に理解したいビジネスパーソンや学生にとって、日本経済の全体像を捉えるための最良の教科書となるでしょう。
6. 『スティグリッツ 資本主義と自由』
ジョセフ・E・スティグリッツ 著、東洋経済新報社
ノーベル経済学賞受賞者であるジョセフ・E・スティグリッツ氏が、現代における「資本主義」と「自由」の関係性について深く考察した一冊です。グローバル化、技術革新、格差の拡大といった現代社会が直面する複雑な課題に対し、市場経済の光と影、政府の役割、そしてより公正で持続可能な社会を実現するための制度設計について、経済学者の視点から鋭い分析を展開しています。単なる理論的な解説に終わらず、現実の経済問題に焦点を当て、所得格差の是正、金融市場の規制、気候変動対策など、多岐にわたる政策提言を行っています。新自由主義的な市場原理主義の限界を指摘しつつ、より人間中心の経済システムの可能性を探る本書は、経済学の専門家だけでなく、現代社会の課題に関心を持つすべての人にとって、資本主義の未来を考える上での重要な視点を提供してくれるでしょう。
7. 『5年で1億円貯める株式投資』
kenmo(湘南投資勉強会) 著、ダイヤモンド社
「湘南投資勉強会」を主宰するkenmo氏が、わずか5年で1億円の資産形成を目指すための具体的な株式投資戦略を提示する一冊です。本書は、単なる投資手法の羅列ではなく、明確な目標設定、徹底したリスク管理、そして長期的な視点での銘柄選定といった、再現性の高い投資哲学に基づいています。デイトレードのような短期的な売買に依存せず、企業の成長性やファンダメンタルズを重視した堅実な投資アプローチを提案。具体的なポートフォリオの組み方、情報収集の方法、そして市場の変動に一喜一憂しないためのメンタルコントロール術まで、実践的なノウハウが満載です。初心者から中級者まで、誰もが具体的な目標に向かって資産形成を進めるためのロードマップを提供。着実に資産を増やし、経済的自由を目指したいと考えるすべての人にとって、「億り人」への具体的な道筋を示してくれるでしょう。
8. 『経済は地理から学べ! 全面改訂版』
宮路 秀作 著、ダイヤモンド社
ベストセラー『経済は地理から学べ!』の全面改訂版である本書は、経済学と地理学という一見異なる分野を結びつけ、世界の経済動向をより深く理解するための新たな視点を提供する一冊です。著者の宮路秀作氏は、地理的条件が資源の分布、産業の発展、貿易の形態、そして国際関係に与える影響を詳細に分析。なぜ特定の地域で特定の産業が栄えるのか、なぜ国家間で経済格差が生じるのかといった疑問に対し、地理的な要因から論理的に解説しています。気候変動、地政学的リスク、資源問題といった現代の喫緊の課題も地理的視点から考察することで、読者は複雑な世界経済の構造を多角的に捉えることができるでしょう。ビジネスパーソン、投資家、学生など、世界の経済ニュースをより深く理解し、未来を予測するための知見を深めたいすべての人にとって、必読の教養書です。
9. 『行動経済学BEST100』
橋本 之克 著、総合法令出版
近年注目を集める「行動経済学」の主要な概念を100項目に厳選し、分かりやすく解説した一冊です。行動経済学は、従来の経済学が前提としてきた「合理的な人間」というモデルに対し、人間の心理的なバイアスや非合理的な意思決定プロセスを組み込むことで、より現実の経済行動を説明しようとする学問です。本書では、「プロスペクト理論」「アンカリング効果」「フレーミング効果」「損失回避性」といった重要な概念を、身近な事例や実験結果を交えながら簡潔に解説。なぜ私たちは非合理な選択をしてしまうのか、その心理的なメカニズムを理解することで、自身の意思決定を改善し、ビジネスやマーケティングに活かすためのヒントが満載です。行動経済学の全体像を手軽に把握し、日常生活やビジネスに応用したいと考えるすべての人にとって、行動経済学の入門書として最適な一冊となるでしょう。
10. 『詳説 バーゼル規制の実務 第2版』
一般社団法人 金融財政事情研究会
著、金融財政事情研究会 国際的な金融規制の枠組みである「バーゼル規制」について、その詳細と実務への影響を深く解説した専門書です。特に、バーゼルⅢやその後の改訂版が銀行などの金融機関に与える影響について、具体的な規制内容、資本要件、リスク管理の枠組みなどを網羅的に解説しています。金融機関の健全性を確保し、金融システムの安定性を維持するために不可欠なバーゼル規制の目的と、それが金融機関の業務、リスク管理体制、そして経営戦略にどのように影響するかを詳述。信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクといった各リスクカテゴリーに対する規制の詳細に加え、ストレステストや自己資本比率の計算方法など、実務担当者が直面する具体的な課題にも焦点を当てています。金融機関の実務担当者、金融規制当局関係者、そして金融業界に関わるすべてのビジネスパーソンにとって、バーゼル規制を深く理解するための必携の参考書となるでしょう。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。