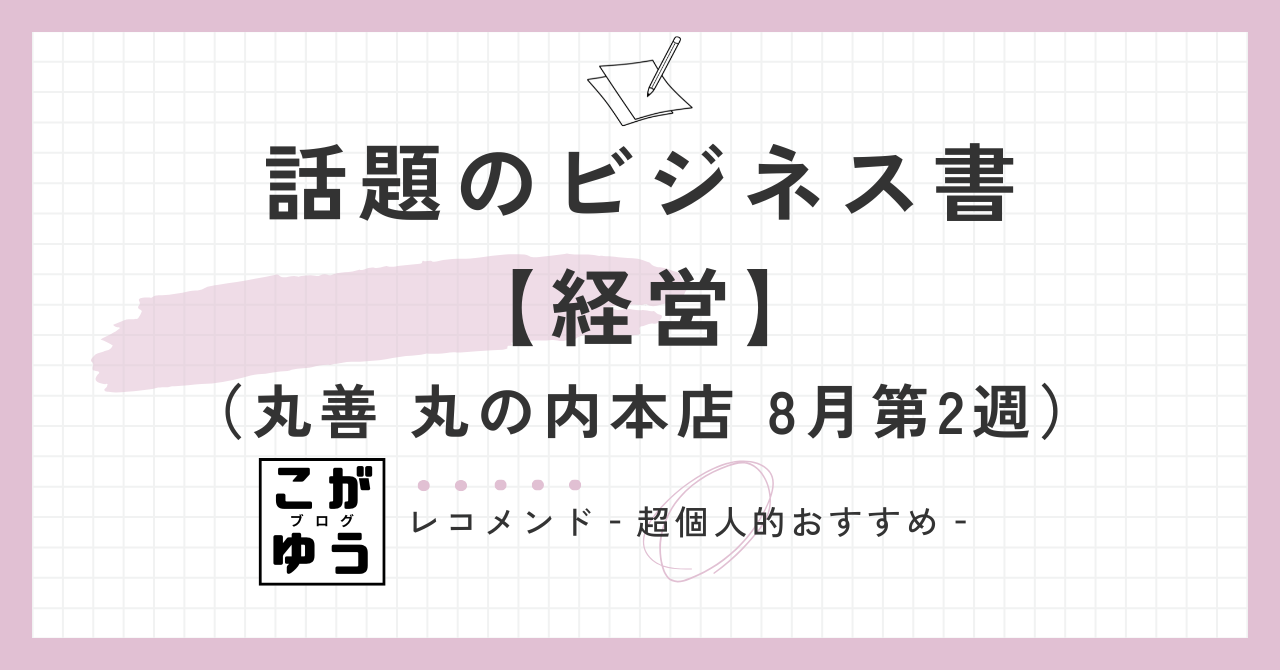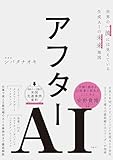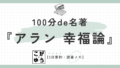2025年8月22日の日経BOOKPLUSに、話題の本 書店別・週間ランキング(2025年8月第2週)が特集されていた。
サイトでは、丸善 丸の内本店、丸善 日本橋店、紀伊國屋書店 新宿本店の3書店で、ビジネス書、ノンフィクション、フィクション、新書、文庫など様々なカテゴリーランキングが紹介されている。
本ブログでは、丸の内で働く40~50代の会社員が多いと思われる丸善 丸の内本店のビジネス(経営)のランキングを紹介する。
【ビジネス(経営)ランキング】
1. 『アフターAI』
シバタナオキ/尾原和啓 著、日経BP
AIが社会のあらゆる領域に浸透した「アフターAI」の時代を生き抜くための、新たなビジネス戦略と個人のあり方を提示する一冊です。本書は、単なるAIツールの使い方解説ではなく、生成AIがコモディティ化する未来において、人間がどのような知的活動に価値を見出し、どのような役割を担うべきかを深く考察します。著者のシバタナオキ氏と尾原和啓氏は、技術の進化がもたらすビジネスモデルの破壊と創造を多角的に分析し、AIを「ツール」としてだけでなく、「共創するパートナー」として捉え直す視点を提案。企業がAI時代に競争優位性を築くための組織変革、個人がAIに代替されないためのスキルセット、そして「人間ならではの強み」を活かす方法を具体的に解説しています。AI時代を乗り越え、未来を自ら創造したいと願う経営者、ビジネスリーダー、そしてすべてのビジネスパーソンにとって、必読の羅針盤となるでしょう。
2. 『生成AI活用の最前線』
バーナード・マー 著、東洋経済新報社
AI分野の世界的権威であるバーナード・マー氏が、生成AIの最新動向と、ビジネスにおける具体的な活用事例を網羅的に解説した一冊です。本書は、ChatGPTやMidjourneyといった生成AIが、企業のマーケティング、製品開発、顧客サービス、そして経営戦略にどのような変革をもたらしているかを、グローバルな視点から多角的に分析します。単なる技術解説に留まらず、生成AIを導入する際の倫理的課題、データセキュリティ、そして組織内での学習文化の醸成といった、経営者が直面する現実的な課題に対する解決策も提示。具体的な成功事例や失敗事例を豊富に紹介することで、読者は自社のビジネスに生成AIをどのように組み込むべきか、具体的なイメージを持つことができます。AIをビジネスに本格的に活用し、競争優位性を確立したいと考える経営者やイノベーション担当者にとって、実践的なガイドブックとなるでしょう。
3. 『もうけの仕組み』
会社四季報業界地図編集部/井上進彦 著、東洋経済新報社
日本の主要な産業の「もうけの仕組み」を、分かりやすい図解と解説で解き明かす一冊です。東洋経済新報社の『会社四季報業界地図』編集部が、長年培ってきた業界分析のノウハウを結集し、各業界の収益構造や競争環境、そしてビジネスモデルの鍵となる要素を丁寧に解説しています。本書は、単に業界のトレンドを追うだけでなく、「なぜこの会社は儲かっているのか?」「なぜこの業界は厳しいのか?」といった、ビジネスの本質的な問いに対する答えを提供。製造業からサービス業、IT産業、そして伝統的な産業まで、幅広い業界の事例が網羅されており、読者は自分の業界以外のビジネスモデルについても深く理解することができます。新規事業の立ち上げ、転職、投資といった様々な場面で、ビジネスの本質を見抜く力を養いたいと考えるすべての人にとって、知的刺激に満ちた必携書です。
4. 『資本コスト経営のすすめ』
野口真人 著、日本経済新聞出版
企業価値を最大化するための重要な概念である「資本コスト経営」について、その本質と実践的な方法論を解説した一冊です。著者の野口真人氏は、多くの経営者が直面する「資本コストを意識した経営」の難しさを乗り越えるため、分かりやすい言葉で理論と実践を結びつけます。本書は、株主から見た企業価値、負債のコスト、そして事業投資の意思決定において、資本コストがいかに重要な判断基準となるかを詳細に解説。単なる財務分析に留まらず、資本コストを意識した経営が、企業の成長戦略や組織文化にどのような影響を与えるかについても深く考察しています。経営者、財務担当者、投資家だけでなく、企業の持続的な成長に関心を持つすべての人々にとって、企業価値を向上させるための新たな視点を与えてくれる必読書です。
5. 『日清食品をぶっつぶせ』
安藤徳隆/竹居智久 著、日経BP
日清食品の創業者である安藤百福の孫である安藤徳隆氏が、日清食品という巨大ブランドを「ぶっつぶす」という常識破りの挑戦を通して、いかにして新たなイノベーションを生み出してきたかを綴ったノンフィクションです。本書は、伝統と革新の狭間で葛藤しながらも、既存の成功体験に安住せず、大胆なマーケティング戦略や斬新な製品開発に挑んできた舞台裏を赤裸々に描きます。安藤氏が掲げた「ぶっつぶせ」というスローガンは、単なる破壊ではなく、自己変革と創造的な破壊を意味しており、読者は、既成概念を打ち破るリーダーシップと、組織を動かす情熱を感じることができます。イノベーションのジレンマ、ブランドの再生、そして挑戦することの意義について深く考えたい経営者やマーケティング担当者にとって、刺激と学びに満ちた一冊となるでしょう。
6. 『両利きのプロジェクトマネジメント』
米山知宏 著、翔泳社
「両利き経営(Ambidextrous Management)」の概念を、プロジェクトマネジメントの視点から解説した一冊です。両利き経営とは、既存事業の効率化(深化)と、新規事業の探索(探索)という、一見矛盾する二つの活動を同時に追求する経営手法を指します。著者の米山知宏氏は、本書で、いかにして一つのプロジェクトチーム内でこの二つの側面を両立させるか、具体的な方法論を提示します。既存のプロジェクトを安定的に運営しながら、同時に未来の成長の種を探索するための、組織構造、人材配置、コミュニケーション、そして評価のあり方について詳細に解説。変化の激しい現代において、既存事業の収益を守りながら、持続的なイノベーションを生み出したいと考えるプロジェクトマネジャー、チームリーダー、そして経営者にとって、実践的な戦略とツールを提供する必読書です。
7. 『ルポ M&A仲介の翼』
藤田知也 著、朝日新聞出版
M&A仲介という、日本経済のダイナミズムを象徴する業界に焦点を当て、その知られざる舞台裏と、M&Aの最前線で働く人々の物語を描いた一冊です。著者の藤田知也氏は、単なるM&Aの手法や理論を解説するのではなく、中小企業の事業承継や、ベンチャー企業の成長戦略において、M&Aがいかに重要な役割を果たしているかを、実際の事例を通して描き出します。本書は、売り手と買い手の双方の想いや葛藤、そしてそれを結びつけるM&A仲介者の情熱と苦悩をリアルに描写。M&Aが、単なる企業の買収・合併ではなく、人々の人生や企業の未来を繋ぐ「物語」であることを伝えます。M&A業界に関心がある人、事業承継に悩む経営者、そして現代ビジネスのダイナミズムを深く知りたいと考えるすべての人にとって、感動と学びに満ちたノンフィクションとなるでしょう。
8. 『AIエージェント革命「知能」を覆う時代へ』
シグマクシス 著、日経BP
AI技術の次なるフロンティアである「AIエージェント」の概念を提示し、それが社会とビジネスにどのような革命をもたらすかを予測した一冊です。AIエージェントとは、単に与えられたタスクをこなすだけでなく、自律的に思考し、複数のタスクを連携させながら、複雑な目標を達成するAIを指します。本書は、AIが人間のような思考力や判断力を持つようになる未来を「知能を覆う時代」と呼び、その変革の波に備えるための企業戦略と個人のあり方を解説。個人の働き方や組織構造、そして産業のあり方が、AIエージェントの進化によっていかに根本的に変わっていくかを、具体的な事例や未来シナリオを交えながら提示します。AIの最先端技術に関心がある人、未来のビジネスを構想したい経営者、そしてAIと共存する社会のあり方を深く考察したいすべての人にとって、刺激的な未来予測書となるでしょう。
9. 『ガバナンスを語る』
中村直人 著、商事法務
企業経営において、ますます重要性が増している「ガバナンス」の概念について、その本質と実践を深く掘り下げた一冊です。著者のナカムラ・ナオト氏は、企業の不正や不祥事が後を絶たない現代において、なぜ強固なガバナンスが必要なのか、そしてそれが企業価値の向上にどのように寄与するのかを、法務、経営、倫理といった多角的な視点から解説します。本書は、単なる法令遵守の枠を超え、取締役会の機能、監査体制の強化、企業文化の変革といった、実効性のあるガバナンスを築くための具体的な方法論を提示。また、コーポレートガバナンス・コードの改訂など、最新の動向も踏まえ、企業が持続的な成長を実現するための「理想のガバナンス」像を描き出します。経営者、役員、法務担当者、そして企業の透明性や健全性に興味を持つすべての人にとって、ガバナンスの本質を理解するための必携書です。
10. 『図解&ストーリー「資本コスト」入門 第3版』
岡 俊子 著、中央経済社
企業経営や投資の意思決定において不可欠な概念である「資本コスト」について、専門知識がない人でも一から学べる入門書です。本書は、難解な専門用語を避け、分かりやすい図解と物語形式で、資本コストの基本的な考え方、計算方法、そしてそれが経営戦略にどう活かされるかを丁寧に解説します。著者の岡俊子氏は、企業の成長性やリスクを評価する上で、資本コストを理解することがいかに重要であるかを、実際の企業の事例を交えながら具体的に示しています。特に、株主が企業に求めるリターンと、企業が投資から生み出すリターンを比較する「資本コスト」の概念が、M&Aや設備投資の判断において重要な役割を果たすことを分かりやすく解説。経営者や財務担当者、そして株式投資に関心があるすべての人にとって、財務の基本を楽しく学べる必携の一冊です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。