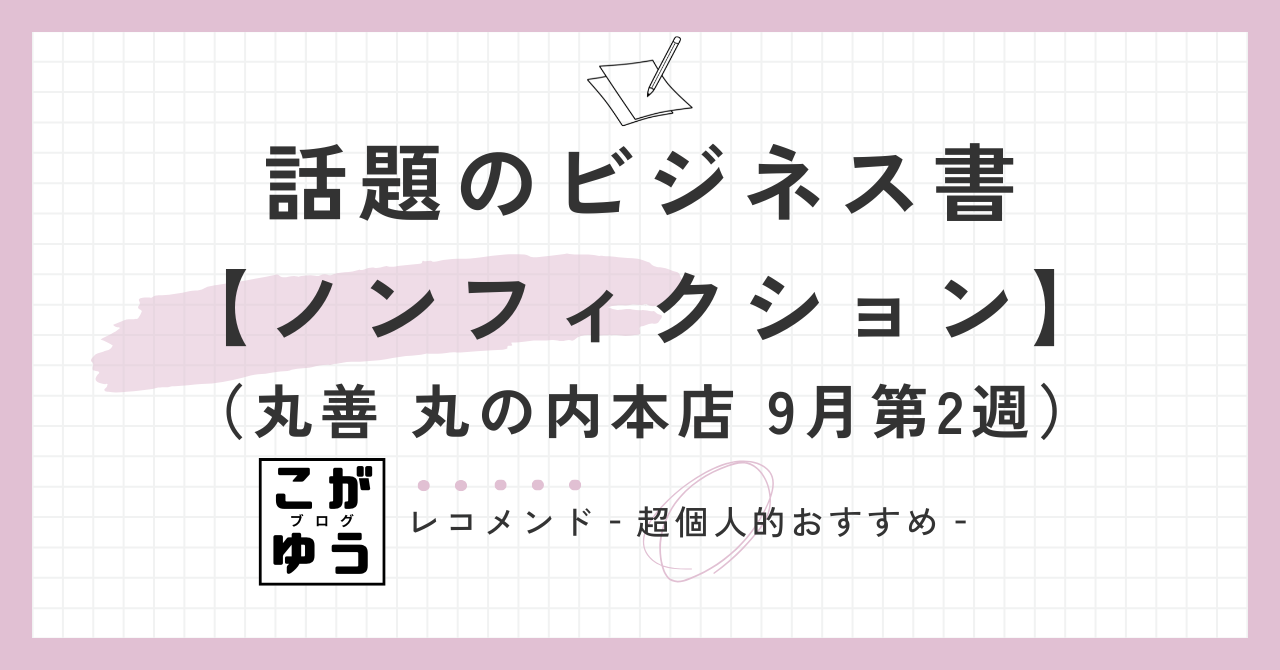2025年9月19日の日経BOOKPLUSに、話題の本 書店別・週間ランキング(2025年9月第2週)が特集されていた。
サイトでは、丸善 丸の内本店、丸善 日本橋店、紀伊國屋書店 新宿本店の3書店で、ビジネス書、ノンフィクション、フィクション、新書、文庫など様々なカテゴリーランキングが紹介されている。
本ブログでは、丸の内で働く40~50代の会社員が多いと思われる丸善 丸の内本店のノンフィクションのランキングを紹介します。
【ノンフィクションランキング】
1. 『地球の歩き方 オルカン』
地球の歩き方編集室 著、Gakken
この本は、長年にわたり旅のガイドブックとして愛されてきた『地球の歩き方』シリーズが、投資信託の「オルカン(オール・カントリー)」という全く新しい世界を案内するものです。単なる投資の解説書ではなく、まるで世界中を旅するかのように、各国の経済状況や市場の特性を、分かりやすい図解やユニークな視点で解説しています。投資初心者でも、複雑なグローバル経済の仕組みが直感的に理解できるでしょう。この本を読むと、投資が単なる資産運用ではなく、世界各国の文化や歴史、そして未来に触れる知的探求になると気づかされます。世界の経済を「歩く」ように学びたい人、そして投資という旅の第一歩を踏み出したいすべての人にとって、知的興奮に満ちた必携のガイドブックです。
2. 『「風の谷」という希望』
安宅 和人 著、英治出版
テクノロジーと社会の未来を洞察する著者が、宮崎駿監督の『風の谷のナウシカ』に登場する「風の谷」を、現代社会が目指すべき理想郷として考察したユニークな一冊です。本書は、環境問題、テクノロジーの進化、そして人間社会のあり方といった複雑なテーマを、作品の世界観を借りて分かりやすく解説。安宅氏は、「風の谷」が示す自然との共生、コミュニティのあり方、そしてリーダーシップの理想像を現代に引きつけ、私たちがこれから目指すべき社会のビジョンを描き出します。単なる映画評論ではなく、未来に対する深い洞察と、私たち一人ひとりができることについて深く考えさせてくれる、示唆に富んだノンフィクションです。
3. 『現場で活用するための AIエージェント実践入門』
太田 真人/宮脇 峻平/西見 公宏 他 著、講談社
この本は、ChatGPTのような単なるAIツールではなく、自律的にタスクをこなし、人間を補佐する「AIエージェント」を、現場でどう活用するかを解説した実践的なガイドブックです。企画立案、データ分析、顧客対応といった具体的なビジネスシーンで、AIエージェントがどのように機能し、人間の業務を効率化するのかを、豊富なコード例や図解と共に示しています。この本を読むと、AIが単なる「答えを出す機械」ではなく、まるで「知能を持った同僚」のように協働する未来が、すぐそこまで来ていることがわかります。AI技術を実際のビジネスに活かしたいと考えているエンジニアやビジネスパーソンにとって、必読の一冊です。
4. 『いちばんやさしいAIエージェントの教本』
古川 渉一 著、インプレス
「AIエージェント」という新しい技術について、全くの初心者でも無理なく理解できるよう、基礎から丁寧に解説した入門書です。この本は、AIエージェントがどのような仕組みで動いているのか、そしてそれを活用することで何ができるのかを、平易な言葉で分かりやすく説明しています。プログラミングの知識がなくても、AIエージェントの基本原理や、その可能性を理解できるような工夫が凝らされています。また、実際にAIエージェントを試すためのステップも紹介しており、読者は知識をインプットするだけでなく、実際に手を動かして学ぶことができます。AIエージェントという新しい技術に興味はあるけれど、何から始めたらいいか分からない人に最適な、最初の一歩となる一冊です。
5. 『会話の0.2秒を言語学する』
水野 太貴 著、新潮社
この本は、私たちが普段意識しない「会話」の中に隠された、驚くべき言語学的メカニズムを解き明かしたものです。著者の水野太貴氏は、会話の「間(ま)」や「0.2秒」といった微妙な時間のズレが、コミュニケーションにどんな影響を与えているのかを、科学的な視点から分析。なぜ私たちは相手の言葉が途切れる前に話し始めてしまうのか。そして、その行動が示す心理的な意味とは何か。その謎を、豊富な事例と共に解説しています。この本を読むと、日常の何気ない会話が、まるで新しい研究テーマのように面白く感じられるでしょう。人とのコミュニケーションをより深く理解したい人、そして言語学という学問の面白さに触れたい人に、必読の一冊です。
6. 『13歳からの哲学的思考』
星 友啓 著、ソシム
この本は、哲学を「難解な学問」ではなく、「生きるためのツール」として、中学生にも理解できるように解説したものです。著者の星友啓氏は、人生の根本的な問いである「自分とは何か」「幸福とは何か」について、哲学の歴史や偉人たちの言葉を引用しながら、分かりやすく提示しています。単に哲学者の思想を紹介するだけでなく、読者自身が答えを探すための「思考のヒント」を与えてくれるのが特徴です。この本を読むと、哲学が、自分の人生をより深く考え、生きる指針を見つけるための強力な武器になると気づくでしょう。哲学を学び直したい大人、そして考える力を身につけたいすべての人にとって、必携の書です。
7. 『頭がいい人のChatGPT&Copilotの使い方』
橋本 大也 著、かんき出版
AI活用コンサルタントである著者が、「頭がいい人」がどのようにChatGPTやCopilotを使いこなしているかを解説した一冊です。本書は、単なるAIツールの操作方法に留まらず、AIを「思考のパートナー」として最大限に活用するための本質的な考え方を提示します。著者は、AIに良い回答を引き出すための「問いの立て方」や、AIが生成した文章をどのように人間が編集し、付加価値を加えるかといった、より高度な活用術を詳細に解説。ビジネスにおける企画書作成、プログラミング、資料作成など、具体的な業務シーンでの活用事例を豊富に紹介することで、読者はAIを単なるツールとしてではなく、自身の能力を拡張するための強力な武器として捉え直すことができます。AI時代を生き抜くために、人間とAIの最適な協働のあり方を学びたいと考えるすべての人にとって、知的刺激に満ちた必携書です。
8. 『サイコパスから見た世界』
デイヴィッド・ギレスピー 著、東洋経済新報社
この本は、「サイコパス」という言葉の持つイメージを覆し、彼らが世界をどのように認識し、感じているのかを、当事者の視点から描いたものです。著者のデイヴィッド・ギレスピー氏は、自身のサイコパスという特性を明かし、その特徴である「感情の欠如」や「共感性の低さ」が、日常生活や社会生活にどのような影響を与えるかを赤裸々に語っています。この本を読むと、サイコパスが持つ能力(論理的な思考力、冷静な判断力など)が、特定の分野でいかに強みとなり得るかがわかります。一方で、彼らが社会のルールや他者との関係で直面する困難も描かれています。人間の多様な心のあり方について、深く考えさせられる一冊です。
9. 『数理モデルはなぜ現実世界を語れないのか』
エリカ・トンプソン 著、白揚社
この本は、経済学や社会学、科学の分野で広く使われる「数理モデル」の限界と、その本質を問い直したものです。著者のエリカ・トンプソン氏は、複雑な現実世界を単純化して分析する数理モデルが、しばしば「予測を外す」理由を、哲学的な視点から深く考察。モデルの前提条件や、人間の非合理的な行動といった、モデルでは捉えきれない要素の重要性を説きます。この本を読むと、データや数理モデルを盲信することの危険性に気づくでしょう。科学的な思考法を身につけたい人、そして、不確実な世界をどう捉えるべきか模索しているすべての人にとって、知的刺激に満ちた必読書です。
10. 『「いきり」の構造』
武田 砂鉄 著、朝日新聞出版
社会批評家である著者が、現代社会に蔓延する「いきり(自分を大きく見せる行為)」という現象を、鋭い洞察とユーモアを交えて分析した一冊です。SNSの過剰な自己アピールから、ビジネス界の誇大な成功談、そして社会の規範まで、様々な「いきり」の事例を取り上げて、その背後にある心理や社会構造を解き明かします。武田氏は、この「いきり」という行為が、いかに私たち自身の心を不自由にしているかを問いかけます。この本を読むと、現代社会の空気感や、自分自身の振る舞いを客観的に見つめ直すことができるでしょう。生きづらさを感じている人、そして社会の当たり前を疑いたいすべての人にとって、鋭い視点と、どこか温かいユーモアが心地よい、必読の社会批評です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。