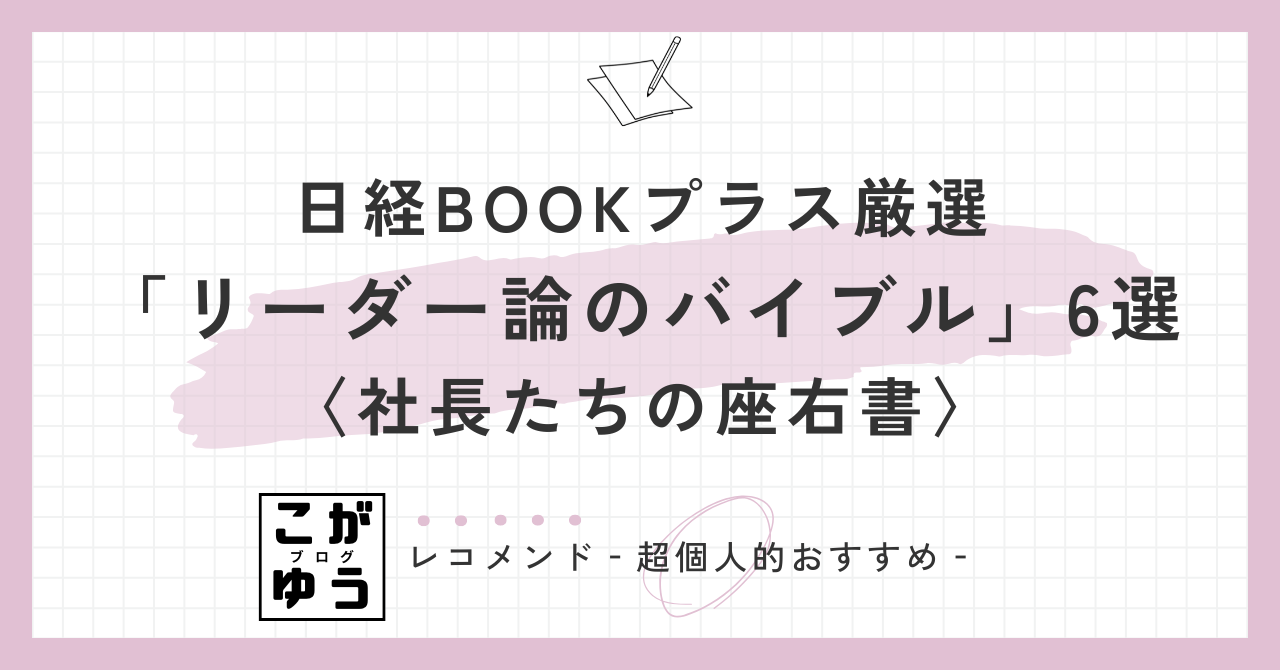「時間を無駄にせず、確実に良書と出会いたい」
日経BOOKプラスのアンケートで、企業のトップたちが感銘を受け、座右の書としているリーダー論の名著6冊です。
これらの本は、日々の意思決定や組織運営、そして自己成長に行き詰まった際に、立ち返るべき指針を与えてくれます。
社員を動かし、組織に変革をもたらすために、トップリーダーたちが何を学び、自身の視点をどう磨いてきたのか。その秘密がこのラインナップに詰まっています。
詳しくはこちら→『経営者が選ぶ「リーダー論のバイブル」〈社長たちの座右書〉』
1. 『人を動かす』
D・カーネギー 著、創元社
この本は、人間関係の原理原則を説いた、時代を超えた自己啓発の古典です。
三菱UFJニコス社長の角田典彦氏も、「行き詰まったときに参考になる良書」として推薦しています。
カーネギーは、人を動かすための三原則、九つの方法、十二の原則などを具体的な事例と共に提示しています。
単なるテクニックではなく、相手を尊重し、心から興味を持ち、相手の立場に立って考えるという、普遍的な人間愛に基づく原則です。
特に、人を批判せず、誠実に評価することの重要性が説かれています。リーダーが部下の能力を最大限に引き出すためには、叱るのではなく、自信を持たせ、成長を促す肯定的関わりが不可欠です。
この本を読むと、リーダーシップが「権力」や「地位」によって発揮されるものではなく、「人間的な魅力」と「共感力」によって生まれることがわかります。
組織内のコミュニケーションを円滑にし、チームの活力を高めたいすべてのリーダーにとって、人間関係の本質を学ぶための永遠のバイブルです。
2. 『完訳 7つの習慣』
スティーブン・R・コヴィー 著、キングベアー出版
この本は、自己啓発の分野で世界的な影響を与え続けている名著です。
沢井製薬社長の木村元彦氏が「自分が変わり、自己成長につながった貴重な一冊」と語るように、個人の効果性(エフェクティブネス)を高めるための原則が体系化されています。
コヴィー博士は、習慣を身につけることが、成功への鍵だと説き、私的成功(インサイド・アウト)から公的成功へと至る7つのステップを提示しています。
まず、自らの人生の責任を引き受ける「主体的である」こと。次に、人生の目的を明確にする「終わりを思い描くことから始める」こと。
そして、最も重要なことに集中する「最優先事項を優先する」ことが、私的成功の基盤です。この私的成功を経て、他者との相互依存の関係を築く「公的成功」へと進みます。
この本を読むと、リーダーシップが組織を導く前に、まず自分自身の内面と向き合い、原則に基づいた人格を磨くことから始まることがわかります。
組織のトップとして、自己変革と人間的な成長を志すすべての人にとって、普遍的な価値観を再認識させてくれる座右の書です。
3. 『叱らない、ほめない、命じない。 あたらしいリーダー論』
岸見 一郎 著、日経BP
この本は、アドラー心理学の第一人者である岸見一郎氏が、現代の組織に合った新しいリーダーシップのあり方を提示したものです。
古河電気工業社長の森平英也氏が推薦するように、従来の「上意下達」や「アメとムチ」によるマネジメントから脱却し、「勇気づけ」を核とした人間関係を築くことを推奨しています。
著者は、リーダーが部下を叱ったり、褒めたり、命令したりすることが、かえって部下の自律性や主体性を損なうと指摘します。
真のリーダーの役割は、部下を評価することではなく、彼らが困難に立ち向かう「勇気」を与えることです。
それは、横の関係(対等な関係)を築き、課題を共有し、共に解決策を考えるという姿勢から生まれます。
この本を読むと、リーダーシップが「支配」ではなく「支援」であり、「権威」ではなく「信頼」に基づくものだとわかります。
部下が自ら考え、行動する自律的な組織を築きたいと願うリーダーにとって、アドラー心理学に基づいた人間理解と組織運営の哲学を授けてくれる一冊です。
4. 『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』
安斎 勇樹、塩瀬 隆之 著、学芸出版社
この本は、NTTドコモ・ベンチャーズ社長の笹原優子氏が「問いの投げ方次第で、組織を活性化できる」と推薦するように、対話を通じて組織にイノベーションと変革をもたらすための「問い」の設計図を解説したものです。
現代の複雑な課題は、トップダウンの指示だけでは解決できません。多様な知恵を引き出し、共創的な解決策を生み出すファシリテーションの重要性が高まっています。
本書は、単なる会議術ではありません。対話の場において、参加者の思考を深め、行動を促すような「良質な問い」をいかに生み出すか、そのための具体的なフレームワークと技術を紹介しています。
例えば、「現状の課題を問い直す」「未来の可能性を探索する」など、目的に応じた問いの類型が示されています。
良質な問いは、組織のメンバーが既存の枠組みを超えて考え、主体的に議論に参加するきっかけとなります。
組織の停滞を打破し、新しいアイデアを生み出したいと考えるリーダーにとって、対話を通じて組織の潜在能力を引き出すための実践的な手引きとなる一冊です。
5. 『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』
マーシャル・ゴールドスミス、マーク・ライター 著、日経ビジネス人文庫
この本は、日本M&Aセンターホールディングス社長の三宅卓氏が「成功するリーダーが陥りがちなことから、自分を見直せる」と推薦するように、成功者がさらに高いレベルへ成長するために乗り越えるべき「成功の罠」を解説したものです。
多くのリーダーは、過去の成功体験から得た「良い習慣」によって、かえって次の成長が妨げられるというパラドックスに直面します。
著者のゴールドスミス氏は、「成功者がより成功するためにやめるべきこと」を明確に提示しています。
それは、「勝ちすぎる」「助言をしすぎる」「ネガティブな発言をする」といった、リーダーシップを発揮する上での無意識の悪癖です。
これらの悪癖を認識し、謙虚さ、感謝、そして傾聴といった人間的な資質を意識的に強化することの重要性を説きます。
成功体験に固執せず、常に自己を客観的に評価し、周囲からのフィードバックを真摯に受け止める姿勢こそが、持続的な成長の鍵となります。
キャリアの壁に直面しているリーダーや、成功を収めた後も成長を続けたいと願うすべての人にとって、自分自身のリーダーシップを見つめ直すための鏡となる一冊です。
6. 『EQ こころの知能指数』
ダニエル・ゴールマン 著、講談社+α文庫
この本は、が「IQよりEQ(こころの知能指数)が重要と教えてくれた」と推薦するように、感情の認識、理解、そして管理能コメ兵ホールディングス社長の石原卓児氏力である「EQ(Emotional Intelligence)」が、成功とリーダーシップに不可欠であることを証明した画期的な著作です。
従来の知能指数(IQ)偏重の考え方に対し、ゴールマン氏は、自己認識、自己制御、モチベーション、共感、そして社会性という5つの要素からなるEQが、人生やビジネスの成功を決定づける重要な要素であると説きます。
特にリーダーシップにおいては、他者の感情を理解し、共感する能力、すなわち「共感力」が組織をまとめ、変革を推進するために不可欠です。
EQが高いリーダーは、メンバーのモチベーションや不安を察知し、適切なコミュニケーションをとることで、チームのパフォーマンスを最大化できます。この本を読むと、感情はコントロールすべき障害ではなく、活用すべき情報源であるとわかります。
感情的な知性を高め、人間関係とリーダーシップの質を向上させたいと考えるすべての人にとって、科学的根拠に基づいた行動指針を与えてくれる必読書です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。