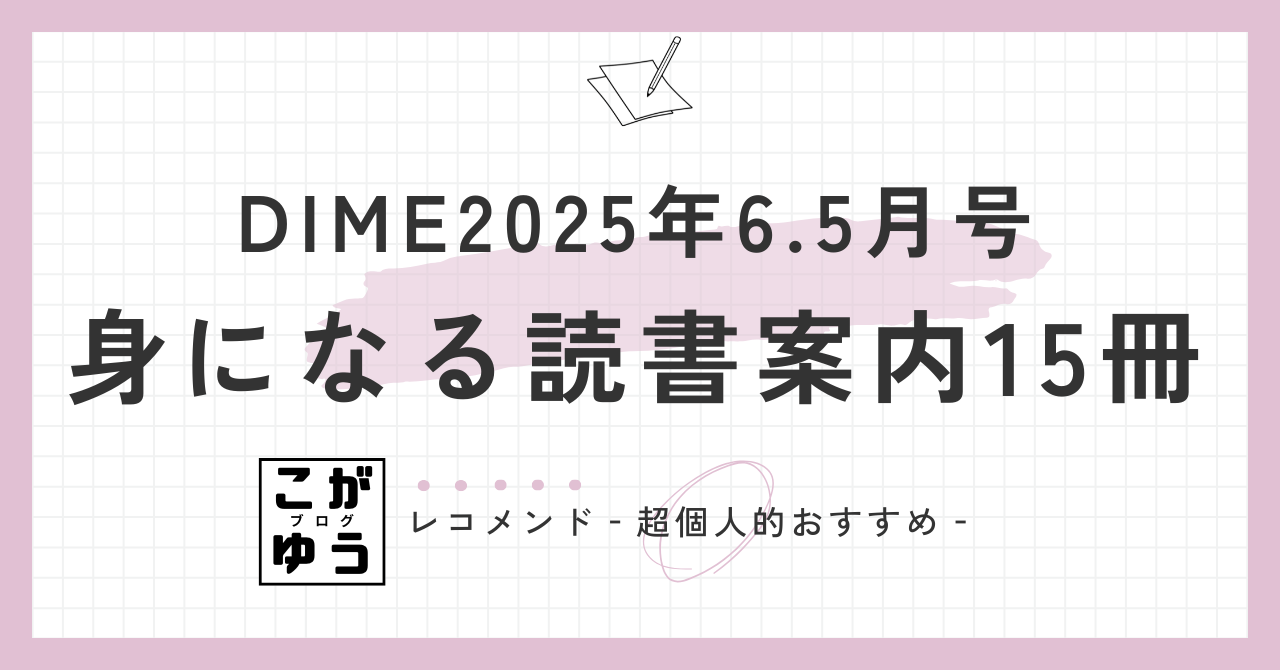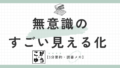「時間を無駄にせず、確実に良書と出会いたい」
DIME2025年6.5月号に掲載されていた「身になる読書案内15冊」を紹介します。
DIME2025年6.5月号は語りたくなるストーリーを持つ逸品が大集合! あなたのこだわりを満たし、思わず自慢したくなるようなマスターピースとの出会いを約束する特集です。
「身になる読書案内15冊」は日常に新鮮な風を送ります。異分野の本は、眠っていた好奇心を呼び覚まし、新たな知見をさ付けてくれる。そこから得た学びは、あなたの成長の糧となるはず!
1. 音楽が未来を連れてくる 時代を創った音楽ビジネス百年の革新者たち (榎本幹朗 著)
レコードの誕生からストリーミングサービスの隆盛まで、激動の100年間を駆け抜けた音楽ビジネスの革新者たちの物語を描き出します。トーマス・エジソンによる蓄音機の発明、ラジオの登場、レコード盤の進化、CDの普及、そしてインターネットによる音楽配信の革命。それぞれの時代において、既存の常識を打ち破り、新たな音楽の聴き方、届け方を創造したパイオニアたちの情熱と戦略に迫ります。彼らは、技術革新の波を乗りこなし、時には逆らいながら、音楽を人々の生活に不可欠な存在へと進化させてきました。本書は、単なる音楽史に留まらず、ビジネスにおけるイノベーションの本質、変化への適応力、そして創造性の重要性を教えてくれます。音楽業界の変遷を知ることは、他の産業における未来予測やビジネス戦略を考える上でも貴重な示唆を与えてくれるでしょう。音楽ファンはもちろん、ビジネスに関わるすべての人にとって、刺激的な読書体験となるはずです。
2. 高鳴る心の歌 ヒット曲の伴走者として (朝妻一郎 著)
数々のミリオンヒットを世に送り出してきた音楽プロデューサー、朝妻一郎氏による回顧録です。山口百恵、松田聖子、中森明菜など、昭和の歌謡史を彩るトップスターたちと歩んだ軌跡を、当時のエピソードを交えながら赤裸々に語ります。ヒット曲誕生の裏側、スターたちの才能と苦悩、そしてプロデューサーとしての信念と情熱。華やかな音楽業界の舞台裏で、いかにして人々の心に響く歌が作られ、届けられてきたのか。そのプロセスは、創造的な仕事に関わるすべての人にとって、示唆に富んでいます。朝妻氏の言葉は、時代を超えて人々の心を捉える普遍的な魅力を持つ音楽の本質、そしてそれを支える人々の情熱と努力を伝えてくれます。単なる音楽業界の裏話に留まらず、人を惹きつけるコンテンツを生み出すためのヒントが詰まった一冊です。
3. アメリカ音楽の新しい地図 (大和田 俊之 著)
ロック、ジャズ、ブルース、ヒップホップなど、多様なジャンルを生み出し、世界中の音楽シーンに影響を与え続けてきたアメリカ音楽の「今」を、新たな視点で捉え直す試みです。21世紀に入り、音楽を取り巻く環境が激変する中で、アメリカの音楽シーンはどのように変化し、新たな潮流を生み出しているのか。気鋭の音楽研究者である著者が、現代の音楽家たちの活動、インディペンデントシーンの隆盛、そして社会的なメッセージを込めた音楽の台頭などを詳細に分析します。過去の偉大な音楽遺産を受け継ぎながら、常に新しい表現を模索し続けるアメリカ音楽のダイナミズムを描き出し、その創造性の源泉を探ります。アメリカ音楽のファンはもちろん、現代の音楽シーンの動向に関心のあるすべての人にとって、新たな発見と刺激に満ちた一冊となるでしょう。
4. 鉄道路線に翻弄される地域社会 – 「あの計画」はどうなったのか? – (鐵坊主 著)
日本の各地で計画されながらも実現に至らなかった鉄道路線計画に焦点を当て、その背景にある地域社会の期待と落胆、そして計画中止に至るまでの複雑な経緯を追います。地方創生の切り札として期待されながらも、経済状況の変化、政治的な駆け引き、住民の反対など、様々な要因によって頓挫した「幻の路線」たち。著者は、膨大な資料と現地取材に基づき、それぞれの計画に関わった人々の証言を丹念に拾い上げ、その光と影を描き出します。単なる鉄道史に留まらず、地域開発の難しさ、公共事業の意思決定プロセス、そして地域社会の変容を考える上で貴重な事例を提供します。鉄道ファンだけでなく、地域社会のあり方に関心のあるすべての人にとって、深く考えさせられる一冊となるでしょう。
5. スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場”140ヶ所の魅力と歴史を全紹介 (江上 英樹, 栗原 景 著/編集)
鉄道ファン垂涎のテーマである「スイッチバック」に特化した、前代未聞のガイドブックです。全国に残る約140ヶ所のスイッチバックの魅力を、豊富な写真と詳細な解説で徹底的に紹介します。急勾配を克服するための独特な線形、列車が進行方向を変えるダイナミックな動き、そしてそれぞれの場所に刻まれた歴史と物語。著者は、長年の研究と情熱に基づき、スイッチバックの構造、運行方法、そして沿線の風景まで、その奥深い魅力を余すところなく伝えます。単なる鉄道技術の紹介に留まらず、地形との闘い、人々の知恵と工夫、そして鉄道が地域社会に果たしてきた役割を垣間見ることができます。鉄道ファンはもちろん、旅好き、歴史好きにとっても、新たな発見と感動を与えてくれる一冊となるでしょう。
6. JR東日本 脱・鉄道の成長戦略 (枝久保 達也 著)
少子高齢化や人口減少といった厳しい経営環境に直面するJR東日本が、鉄道事業だけに依存しない新たな成長戦略をどのように描いているのかを分析します。駅ナカビジネスの展開、不動産開発、Suicaを活用した多角化、そして新たなモビリティサービスへの挑戦。著者は、JR東日本の現状と課題を詳細に分析し、その将来に向けた戦略の可能性とリスクを検証します。鉄道事業の未来を考えることは、他のインフラ産業や地方経済の活性化策を検討する上でも重要な視点を提供します。鉄道ファンだけでなく、企業経営、地域経済に関心のあるすべての人にとって、示唆に富む一冊となるでしょう。
7. 「感動体験」で外食を変える 丸亀製麺を成功させたトリドールの挑戦 (粟田貴也 著)
セルフうどんチェーン「丸亀製麺」を一代で築き上げたトリドールホールディングスの創業者、粟田貴也氏の経営哲学と挑戦の軌跡を描きます。徹底的な現場主義、顧客に「感動体験」を提供するという信念、そして常識にとらわれない大胆な戦略。著者は、丸亀製麺がどのようにして競争の激しい外食業界で独自の地位を確立し、国内外へと事業を拡大してきたのか、その成功の要因を詳細に分析します。単なる飲食店の成功物語に留まらず、ベンチャー企業の成長戦略、リーダーシップのあり方、そして顧客満足を追求する姿勢の重要性を教えてくれます。外食業界に関わる人はもちろん、起業家精神を持つすべての人にとって、多くの学びと刺激を与えてくれる一冊となるでしょう。
8. アットコスメのつぶれない話 困難を乗り越え成長を続けるベンチャー経営の要諦 (吉松 徹郎 著)
日本最大級のコスメ・美容の総合サイト「@cosme」を運営するアイスタイル創業者、吉松徹郎氏による経営論です。創業以来、数々の困難を乗り越え、成長を続けてきたベンチャー企業の経営者として、その経験から得た独自の経営哲学と、組織運営、事業戦略の要諦を語ります。変化の激しいインターネット業界において、いかにして競争優位性を確立し、持続的な成長を実現してきたのか。その過程で培われた、顧客視点の徹底、コミュニティの重視、そして変化への柔軟な対応力は、あらゆるビジネスに通じる普遍的な教訓を含んでいます。ベンチャー企業の経営者だけでなく、事業を成長させたいと願うすべての人にとって、貴重な指針となる一冊でしょう。
9. 名前のない仕事 ── UUUMで得た全知見 (鎌田和樹 著)
数多くの人気YouTuberを輩出し、インフルエンサーマーケティングの最前線を走るUUUM(ウーム)の立ち上げに深く関わった著者が、その黎明期から成長期にかけて得た貴重な経験と知見をまとめたものです。まだ「YouTuber」という言葉も一般的ではなかった時代から、新しい才能を発掘し、育成し、マネジメントしていく過程で直面した課題、それを乗り越えるための試行錯誤、そしてそこで培われた組織論、ビジネスモデル、そして人材育成のノウハウが赤裸々に語られます。「名前のない仕事」を創り上げ、新たな市場を開拓してきた著者の言葉は、変化の激しい現代において、新しい価値を生み出すためのヒントに満ちています。新規事業開発、メディア運営、人材マネジメントに関心のあるすべての人にとって、刺激的な一冊となるでしょう。
10. 2050年の世界 見えない未来の考え方 (ヘイミシュ・マクレイ 著, 遠藤真美 翻訳)
著名な経済ジャーナリストである著者が、気候変動、テクノロジーの進化、人口動態の変化、地政学的なリスクなど、現代社会が抱える様々な課題を踏まえ、2050年の世界がどのような姿になっているのかを予測する試みです。単なる未来予測に留まらず、不確実な未来をどのように考え、備えるべきかという視点を提示します。様々な分野の専門家の意見や最新の研究データを基に、多角的な視点から未来の可能性を探り、読者自身の未来に対する思考を深めることを促します。ビジネスリーダー、政策立案者、そして未来に関心のあるすべての人にとって、長期的な視点を持つための重要な一冊となるでしょう。
11. 世界から青空がなくなる日:自然を操作するテクノロジーと人新世の未来 (エリザベス・コルバート 著, 梅田智世 翻訳)
ピューリッツァー賞受賞作家である著者が、気候変動によって深刻な危機に瀕している地球の現状と、それを食い止めようとする人類の試みを克明に描きます。地球工学(ジオエンジニアリング)と呼ばれる、自然を大規模に操作するテクノロジーの可能性とリスクを探りながら、人類が引き起こした「人新世」と呼ばれる新たな地質年代における、自然と人間の関係性の未来について深く考察します。科学的な知見に基づきながらも、文学的な筆致で綴られた本書は、地球環境問題の深刻さを改めて認識させるとともに、持続可能な未来のために私たち一人ひとりが何をすべきかを考えさせられる一冊です。
12. 「働き手不足1100万人」の衝撃 (古屋星斗 著, リクルートワークス研究所 著)
リクルートワークス研究所が推計した「2030年に日本で1100万人の働き手が不足する」という衝撃的な予測に基づき、その現状、背景にある構造的な問題、そして企業や社会が取るべき対策について多角的に分析します。少子高齢化、労働人口の減少、産業構造の変化など、働き手不足を引き起こす要因を詳細に解説し、人材確保、生産性向上、働き方改革といった具体的な解決策を提示します。企業経営者、人事担当者、そして日本経済の未来に関心のあるすべての人にとって、喫緊の課題である働き手不足問題に対する理解を深め、具体的な行動を起こすための指針となる一冊です。
13. パズルで解く世界の言語: 言語学オリンピックへの招待 (風間 伸次郎 監修, 国際言語学オリンピック日本委員会 著)
言語学の奥深さと面白さを、パズルという親しみやすい形式を通して体験できるユニークな一冊です。世界各地の様々な言語にまつわる論理パズルを解きながら、言語の構造、歴史、文化、そして思考方法の多様性に触れることができます。言語学オリンピックの実際の問題をベースにしたパズルは、論理的思考力、分析力、そして異文化理解力を養うのに最適です。言語学に興味がある人はもちろん、パズル好き、論理思考力を鍛えたい人、そして異文化理解を深めたい人にとって、知的探求心を刺激する魅力的な一冊となるでしょう。
14. 絶対に解けない受験世界史4: 悪問・難問・奇問・出題ミス集 (稲田義智 著)
長年にわたり受験世界史の問題を研究してきた著者が、大学入試で出題された数々の「絶対に解けない」悪問、難問、奇問、そして出題ミスを集めた異色の問題集です。正答が存在しない、知識だけでは対応できない、出題意図が不明瞭など、受験生を惑わせ、苦しめてきた問題たちの実態を明らかにし、受験世界史の裏側をユーモラスに、そして批判的に描き出します。単なる問題集としてだけでなく、受験教育の問題点、そして知識偏重の教育に対する痛烈なメッセージが込められています。受験生はもちろん、教育関係者、そしてかつて受験を経験したすべての人にとって、考えさせられる一冊となるでしょう。
15. パズルで鍛えるアルゴリズム力 (大槻 兼資 著)
本書は、プログラミングの基礎となるアルゴリズムの考え方を、パズルを解くという楽しいアプローチを通して身につけることができる一冊です。迷路探索、数独、グラフ理論など、様々な種類のパズルに挑戦しながら、効率的な問題解決のための思考法、データ構造の扱い方、そしてアルゴリズムの設計 কৌশল を自然に習得できます。プログラミング初心者だけでなく、論理的思考力を鍛えたい人、パズル好きの人にとっても、知的挑戦と学習の喜びを同時に味わえる魅力的な一冊となるでしょう。Kindle版で手軽に始められるのも魅力です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。