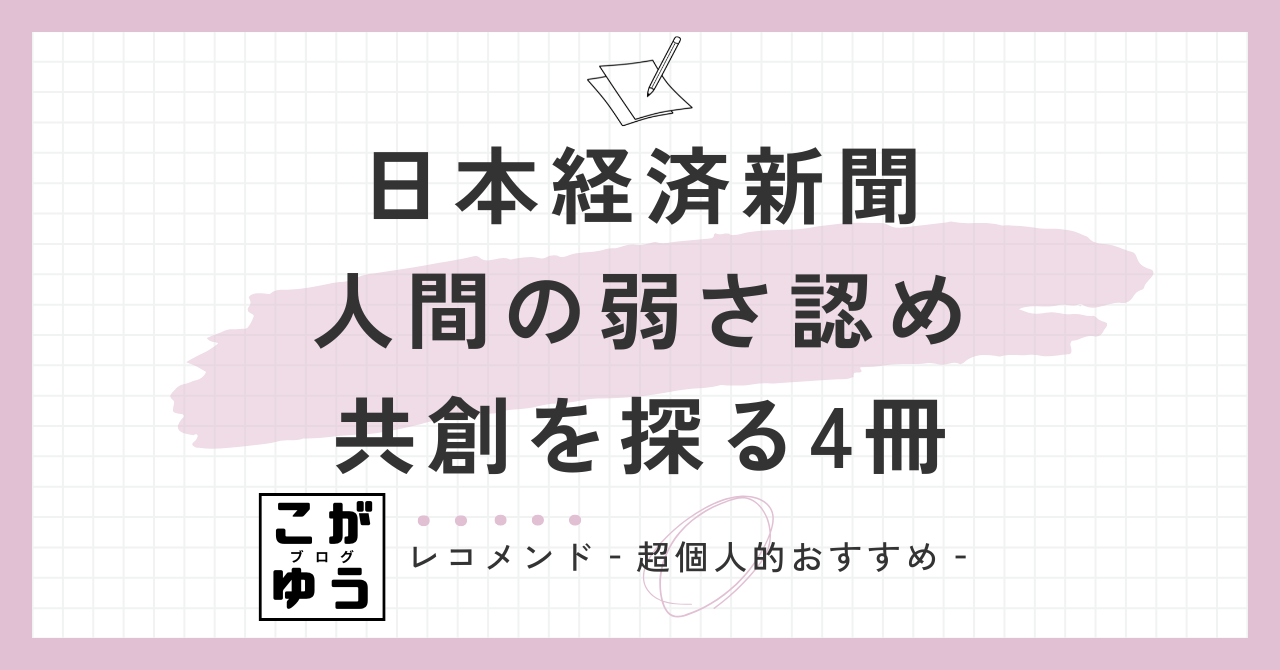「時間を無駄にせず、確実に良書と出会いたい」
日本経済新聞(今を読み解く)に掲載されていた「人間の弱さ認め共創を探る4冊」を紹介します。(2025年7月12日)
日本経済新聞の「今を読み解く」で紹介された4冊は、現代の能力主義社会に対する建設的な「批判」の視点を提供し、「強い個人」を前提とする既存のビジネスモデルや社会構造の再考を促しています。
これらの書籍は、「強い個人」という既存の枠組みから脱却し、「弱い個人」の多様性を認め、相互に「共創」することが、これからの社会やビジネスにおいて重要であるという共通のメッセージを投げかけています。
1. 井上慎平著『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考』
(ダイヤモンド社・2025年)
本書は、社会が求める「強いビジネスパーソン」像に適合しようと奮闘した結果、精神的な限界を迎え、鬱病を発症した著者自身の赤裸々な経験を通して、現代社会における「弱さ」の本質と、そこから生まれる新たな可能性を深く考察する一冊です。
著者は、自身のどん底からの回復プロセスを通じて、「強い個人」という固定されたアイデンティティへの執着が、かえって人間関係やパフォーマンスを阻害する要因となり得ると指摘します。
そして、人間は状況や他者との関係性によって常に変化する「弱い個人」であるという認識こそが、むしろ相互扶助や共創を促し、結果として組織全体の生産性を向上させる鍵であると論じます。
個人の内面的な葛藤を乗り越え、自己受容へと至る過程が丁寧に描かれており、読者は自身の経験と重ね合わせながら、現代社会における「強さ」と「弱さ」の再定義を迫られるでしょう。
働き方やキャリアに悩むすべての人、特に「頑張りすぎ」てしまうビジネスパーソンにとって、自己肯定感を高め、新たな働き方を見つけるための示唆に富む必読書です。
2. 勅使川原真衣著『学歴社会は誰のため』
(PHP新書・25年)
学歴社会の根底に潜む「語られざる前提構造」を鋭く喝破し、その真の受益者が誰であるのかを問い直す衝撃の一冊です。
著者の勅使川原真衣氏は、私たちが当然と受け入れている学歴主義が、いかに個人の多様な能力や可能性を限定し、画一的な評価軸で「出来の良さ」を測ろうとするのかを、具体的な事例やデータに基づいて分析します。
本書は、学歴が個人の価値や将来の成功を決定づけるという神話が、実際には競争を煽り、社会全体の創造性や生産性を損なっている可能性を指摘。特に、ビジネスの現場において求められるのは、個人の「強さ」だけでなく、チームとしての協調性や、異なる「弱さ」を補い合う「共創」の力であると強調します。
学歴社会の欺瞞を暴き、本来あるべき社会の姿を提示することで、読者は自己の評価基準やキャリア選択に対する新たな視点を得るでしょう。
教育関係者、企業の人事担当者、そして学歴に縛られず真の価値を追求したいと願うすべての人にとって、既存の社会システムを問い直すための必読書です。
3. 田中将人著『平等とは何か』
(中公新書・25年)
現代社会が抱える複雑な不平等の問題を、「差別」「格差」「差異」という三つの概念に明確に区別し、それぞれの本質と是正の方向性を深く掘り下げた一冊です。
著者の田中将人氏は、私たちが日常的に使う「不平等」という言葉の裏に隠された多層的な意味合いを解き明かし、特に「強い個人」を前提とする社会が容認してきた「格差」の自己責任論や、個人の「差異」を認めない画一的な評価の問題点を鋭く指摘します。
本書は、真の平等とは、単に形式的な機会均等ではなく、一人ひとりのユニークな違いを承認し、多様な価値観が尊重される「関係の平等主義」にあると提唱。
さらに、差別や過度な格差を是正した上で、人々が自身の存在に誇りを持てる「自尊の社会」を築くことの必要性を訴えます。
現代社会における公正さや多様性について深く考察したい人、そしてより良い社会のあり方を模索するすべての人にとって、複雑な不平等の構造を理解し、具体的な解決策を考えるための羅針盤となるでしょう。
4. 最首悟著『能力で人を分けなくなる日』
(創元社・24年)
重度知的障害を持つ娘・星子さんとの暮らし、そして「相模原障害者施設殺傷事件」の加害者との対話という、著者の壮絶な体験を通して、「能力主義」という現代社会の根幹にある思想を徹底的に問い直す一冊です。
東京大学助手や和光大学教授を務めた「能力主義の勝ち組」である著者が、障害を持つ娘の存在を通して、社会が「役に立つ」「有能である」という一元的な基準で人間を評価し、区別することの危険性を痛感。
特に、加害者から投げかけられた「なぜ役に立たない娘を殺さないのか」という問いに対し、著者は「頼り頼られるはひとつのこと」というシンプルな真理に辿り着きます。
本書は、人間関係の根底にある「相互依存性」の重要性を強調し、能力や成果が個人の「あいだ」で生まれるという「弱い個人」の思想を提示。異なる「差異」を持つ人々が対話を通じて互いを理解し、共に機能する「共創」の社会の必要性を訴えかけます。
人間存在の尊厳、多様性、そして真の豊かさとは何かを深く考えさせられる、魂を揺さぶる必読書です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。