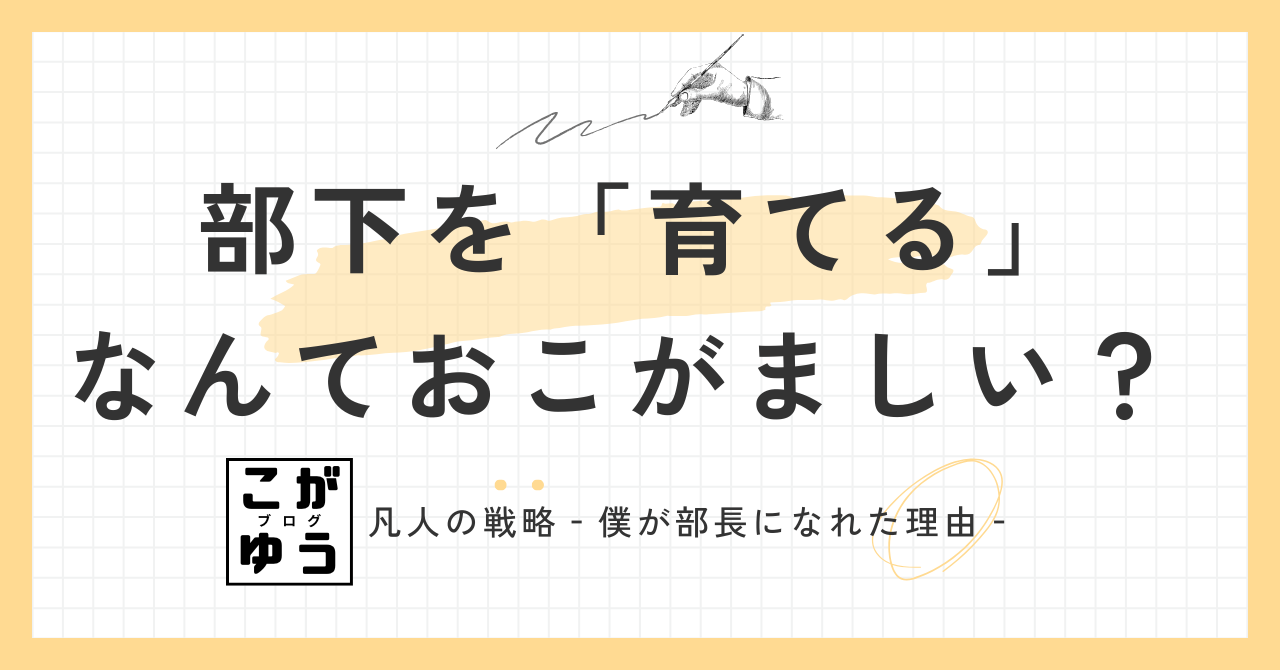皆さん、こんにちは!日々、部下育成に奮闘されているリーダーの皆さん、本当にお疲れ様です。でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。「部下を育てる」って、一体どういうことなのでしょうか?
今回のテーマは、ちょっと衝撃的なタイトルかもしれませんが、「部下を育てることはできない」です。これは、決して部下育成を否定するものではありません。むしろ、従来の「育てる」という概念から解放され、より本質的なリーダーシップについて考えてみませんか?という提案です。
この記事を通して、あなたが部下育成における固定観念から解放され、より自由で、そして何より部下と共に成長できる、新しいリーダーシップのカタチを見つけるヒントを得ていただければ幸いです。
この記事は、『誰にも何にも期待しない』長倉顕太 (著)を参考に書かせていただきました。
「部下を育てる」という幻想 ~上司ができること、できないこと~
私たちは、いつの間にか「上司は部下を育てるもの」という固定観念にとらわれてしまっています。まるで、植物に水や肥料を与えるように、知識やスキルを与えれば、部下は成長すると思い込んでいるのではないでしょうか?
しかし、現実はそうではありません。部下は、上司の所有物でも、操り人形でもありません。一人ひとりが異なる個性、経験、価値観を持った、独立した人間です。
上司ができることは、部下が自ら成長したいと思えるような環境を作ることだけです。知識やスキルを与えることはできても、それをどのように活かすかは、部下自身が決めることなのです。
上司の「当たり前」は、部下の「当たり前」ではない ~多様性を理解する~
上司は、自分の経験や価値観を基準に物事を判断する傾向があります。しかし、部下一人ひとりが異なる背景、経験、価値観を持っていることを忘れてはいけません。
上司にとって「当たり前」のことが、部下にとっては「当たり前」ではないかもしれません。上司が良かれと思ってしたことが、部下にとっては逆効果になることもあるでしょう。
部下は上司のコピーではありません。上司が部下を本当の意味で理解することは、非常に難しいと言わざるを得ません。
だからこそ、上司は自分の価値観を押し付けるのではなく、部下の多様性を理解し、尊重することが重要です。
上司がすべきは、心理的安全性の確保 ~部下は自ら成長する~
では、上司は何をすれば良いのでしょうか?それは、チームメンバーの心理的安全性を確保することです。
心理的安全性とは、チーム内で安心して発言したり、質問したり、新しいアイデアを提案したり、あるいは失敗を認めたりできる環境のことです。
心理的安全性が確保されれば、部下は安心して自分の能力を発揮し、積極的に新しいことに挑戦するようになります。失敗を恐れずに挑戦し、そこから学ぶことで、部下は自然と成長していくのです。
上司も部下から学び、成長する ~共に成長するリーダーシップ~
部下育成は、決して一方通行ではありません。上司も部下から学び、成長することができます。
部下は、上司とは異なる視点やアイデアを持っています。部下との対話を通して、上司は新しい知識やスキル、考え方を学ぶことができます。
また、部下の成長を支援する過程で、上司自身のリーダーシップスキルも向上します。部下と共に成長することで、上司はより高いレベルのリーダーシップを発揮できるようになるのです。
上司自身のストレス低減とメンタルヘルス ~無理のないリーダーシップ~
部下を「育てよう」と必死になることは、上司自身のストレスにも繋がります。完璧なリーダーであろうとすればするほど、理想と現実のギャップに苦しむことになるでしょう。
しかし、「育てる」という幻想から解放され、部下の自主性を尊重し、心理的安全性を確保することに注力すれば、上司自身のストレスも低減します。
無理のないリーダーシップは、上司自身のメンタルヘルスを保つ上でも非常に重要なのです。
新しいリーダーシップのカタチ ~共に成長するパートナーシップ~
これからのリーダーシップは、従来の「上司が部下を育てる」という一方通行の関係ではなく、「上司と部下が共に成長する」というパートナーシップの関係に変わっていくでしょう。
上司は、部下の自主性を尊重し、心理的安全性を確保するファシリテーターとしての役割を担います。部下は、自ら学び、成長し、上司と共にチームの目標達成に貢献します。
このような新しいリーダーシップのカタチこそが、変化の激しい現代社会において、組織の成長を牽引する力となるのです。
具体例
例1:部下の自主性を尊重する上司
- Aさんは、部下に新しいプロジェクトを任せる際、細かな指示は出しませんでした。代わりに、プロジェクトの目的とゴールを明確に伝え、部下が自由にアイデアを出し、実行できる環境を整えました。部下は、自分のアイデアが採用されたことに喜びを感じ、主体的にプロジェクトに取り組み、素晴らしい成果を上げました。
例2:心理的安全性を確保する上司
- Bさんは、チームミーティングで、メンバーが自由に意見を言える雰囲気を作ることを心がけました。たとえ反対意見が出ても、頭ごなしに否定するのではなく、「そういう考え方もあるね」と受け止め、議論を深めるようにしました。メンバーは、Bさんの姿勢を見て、安心して自分の意見を言えるようになり、チーム全体のコミュニケーションが活発になりました。
例3:部下から学ぶ上司
- Cさんは、若い世代の部下から、最新のITツールやSNSの使い方を教わりました。最初は戸惑いましたが、部下の指導を受けながら、積極的に新しいツールを使いこなすようにしました。その結果、Cさんは業務効率を大幅に改善することができました。
まとめ
「部下を育てることはできない」というテーマは、従来のリーダーシップの概念を覆すものです。私たちは、上司が部下を「育てる」ものだと考えがちですが、実際には、部下は自ら成長する存在であり、上司はそれを支援する環境を作る役割を担います。
上司の経験や価値観は、部下とは異なることを理解する必要があります。部下は上司のコピーではなく、多様な背景を持つ個人です。上司がすべきは、自分の価値観を押し付けるのではなく、部下の多様性を尊重し、心理的安全性を確保することです。
心理的安全性が確保された環境では、部下は安心して意見を述べ、挑戦し、失敗から学ぶことができます。上司もまた、部下から学び、共に成長するパートナーとしての役割を果たすことができます。
部下を「育てよう」とすることによる上司のストレスを軽減し、メンタルヘルスを保つためにも、この視点の転換は重要です。上司は完璧である必要はなく、部下の自主性を尊重し、共に成長する姿勢が求められます。
これからのリーダーシップは、上司と部下が共に成長するパートナーシップです。上司はファシリテーターとして、部下の成長を支援し、チーム全体の目標達成に貢献します。
詳しく知りたい方は、『誰にも何にも期待しない』長倉顕太 (著)を手に取ってください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。