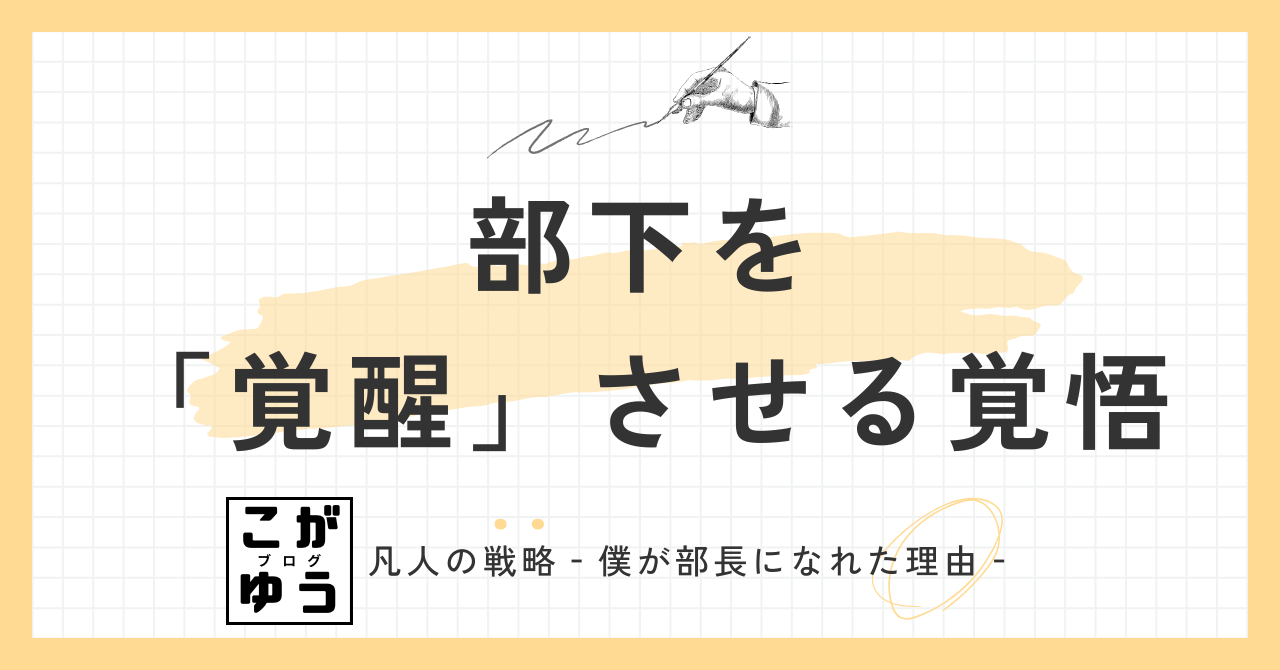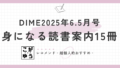今日のテーマは、リーダーにとって非常に重要な「部下に任せる覚悟」について深く掘り下げていきます。
この記事は、『できるリーダーは、「これ」しかやらない』 伊庭 正康 (著) を参考に書かせていただきました。
「部下に任せる」というと、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか?簡単な雑務を頼むこと?それとも、ある程度の手順が決まった業務を委ねることでしょうか?
確かに、それらも「任せる」ことの一部かもしれません。しかし、今日の話は、そんな表面的な「任せる」ではありません。真に部下の可能性を開花させ、眠っていた力を呼び覚ます、「覚醒」を促すための「任せる覚悟」についてです。
そのためには、リーダーである私たち自身が、いくつかの「覚悟」を持つ必要があるのです。それは、時に私たちを不安にさせるかもしれない、でも、その先に大きな成長と信頼が待っている、「覚悟」です。
簡単な業務を任せるだけでは見えない景色 ~「覚醒」への挑戦~
簡単な業務を任せることは、業務効率化の第一歩としては重要です。しかし、それだけでは、部下の成長を真に促すことはできません。なぜなら、それは、部下にとって「できること」の範囲内であり、挑戦や学びの機会が少ないからです。
真の「任せ上手」なリーダーは、部下の現状の能力だけでなく、その奥底に眠る可能性を見抜き、あえて少しストレッチした、責任のある仕事を任せます。それは、部下にとって「ちょっと難しいかもしれない」「本当に自分にできるだろうか」と感じるような挑戦です。
しかし、その挑戦こそが、部下の眠っていた力を呼び覚まし、新たな能力を開花させる「覚醒」の瞬間を生み出すのです。プレッシャーの中で試行錯誤し、壁を乗り越える経験を通して、部下は自信を深め、自己成長を加速させていきます。
「裏切られても、かまわない」と腹をくくる覚悟 ~信頼という名の投資~
部下に責任のある仕事を任せるということは、当然、失敗のリスクを伴います。期待通りに事が運ばないこともあるでしょう。もしかしたら、「こんなはずじゃなかった」という結果に終わることもあるかもしれません。
そんな時、リーダーに必要なのは、「裏切られても、かまわない」と腹をくくる覚悟です。
ここでいう「裏切られる」とは、文字通りの意味ではありません。期待した結果が出なかったり、自分の意図とは違う方向に進んでしまったりすることを指します。
しかし、部下を信頼し、大胆に任せることは、未来への 投資です。たとえ最初はうまくいかなくても、その経験は部下にとって貴重な学びとなり、必ず次の成長へと繋がります。
リーダーが「失敗しても大丈夫だ」というメッセージを態度で示すことで、部下は安心して挑戦することができます。そして、その挑戦の中からこそ、真の成長が生まれるのです。
「人は必ず変わる」と信じてみる覚悟 ~可能性への希望~
「この部下は、なかなか成長してくれない」「以前にも同じようなミスをしたから、今回も期待できないだろう」
リーダーとして、そう感じてしまう瞬間もあるかもしれません。しかし、そこで諦めてしまうのは、部下の可能性を閉ざしてしまうことと同じです。
真の「任せ上手」なリーダーは、「人は必ず変わる」と信じる覚悟を持っています。
人は、様々な経験を通して、少しずつ、でも確実に変化し、成長していきます。過去の失敗や現状の能力だけで判断するのではなく、その人が持つ可能性を信じ、成長を温かく見守ることが、リーダーの重要な役割です。
「きっと、この経験を活かして、次はやってくれるはずだ」「この人には、まだ眠っている大きな力がある」と信じる希望を持つことが、部下の成長を後押しする力となるのです。
期待すべきは、スグの結果ではなく、その人のノビシロ ~未来への潜在能力~
部下に仕事を任せた時、私たちはどうしても「すぐに結果を出してほしい」と期待してしまいがちです。しかし、特に新しい挑戦の場合、すぐに期待通りの結果が出るとは限りません。
真の「任せ上手」なリーダーが期待すべきは、スグの結果ではなく、その人のノビシロ、つまり、潜在的な成長力です。
最初は戸惑いながらも、試行錯誤を繰り返す中で見せる小さな進歩。壁にぶつかりながらも、諦めずに解決策を探そうとする粘り強さ。そういった過程の中にこそ、その人の未来への大きな潜在能力が隠されています。
リーダーは、短期的な結果に一喜一憂するのではなく、部下の長期的な成長を見据え、その過程を辛抱強くサポートしていく必要があります。「今回の結果は残念だったけれど、〇〇さんの粘り強さは素晴らしい」「この経験を通して、〇〇さんは大きく成長するだろう」といったフィードバックは、部下のモチベーションを高め、更なる成長へと繋がるでしょう。
「任せる覚悟」がリーダー自身を成長させる ~信頼が生む好循環~
部下に任せる覚悟を持つことは、部下を成長させるだけでなく、リーダー自身をも大きく成長させる力となります。
部下に任せるためには、リーダーは自分の業務を手放し、チーム全体の状況を俯瞰的に把握する必要があります。また、部下の能力を最大限に引き出すために、効果的なコミュニケーションやフィードバックのスキルを磨く必要も出てくるでしょう。
そして何より、部下を信頼し、任せることで、リーダーはより多くの時間を戦略的な思考や新たな挑戦に費やすことができるようになります。
部下の成長は、チーム全体の成果へと繋がり、それはリーダーの評価を高めることにも繋がります。
「任せる覚悟」は、部下とリーダー双方にとって、成長と信頼を生む好循環を生み出すのです。
具体例
例1:新人に大きなプロジェクトを任せたリーダー
経験の浅い新人のAさんに、思い切って重要なプロジェクトの一部を任せたリーダーのBさん。周囲からは「まだ早いのではないか」という声もありましたが、BさんはAさんの潜在能力を信じていました。最初は戸惑うことも多かったAさんでしたが、Bさんの温かいサポートと励ましを受けながら、試行錯誤を繰り返し、最終的に見事プロジェクトを成功させました。この経験を通して、Aさんは自信をつけ、その後の成長も目覚ましいものとなりました。
例2:「裏切られてもいい」と腹をくくったリーダー
チームのメンバーCさんに、新しい業務プロセス改革の担当を任せたリーダーのDさん。Cさんは意欲的に取り組みましたが、結果として、期待していたほどの効果は得られませんでした。しかし、DさんはCさんを責めることなく、「今回の経験から多くのことを学べたはずだ。次は、この経験を活かして、別の形でチームに貢献してほしい」と伝えました。CさんはDさんの言葉に励まされ、その後、持ち前の粘り強さを活かして、別のプロジェクトで大きな成果を上げました。
例3:すぐに結果を求めなかったリーダー
Eさんに新しいチームの立ち上げを任せたリーダーのFさん。立ち上げ当初は、なかなか成果が出ず、Fさん自身も焦りを感じることもありました。しかし、FさんはEさんの努力を認め、「今は結果が出なくても、Eさんのリーダーシップは着実にチームを成長させている。焦らず、じっくりとチームを育てていこう」と伝えました。Fさんの信頼に応えるように、Eさんは粘り強くチームをまとめ、数ヶ月後には目覚ましい成果を出すようになりました。
まとめ
今回のテーマ「部下に任せる覚悟」は、単なる業務分担の話ではありません。それは、部下の可能性を信じ、その成長を心から願う、リーダーの深い覚悟についてです。
簡単な業務を任せるだけでは、部下の眠った力は目覚めません。真の「任せ上手」なリーダーは、部下を「覚醒」させるために、あえて挑戦的な仕事を任せる勇気を持ちます。
そのためには、「裏切られても、かまわない」と腹をくくる覚悟が必要です。失敗は成長の糧であり、信頼という 投資は、必ず未来へと繋がります。
また、「人は必ず変わる」と信じる希望を持つことも重要です。過去の失敗や現状の能力だけで判断するのではなく、部下の持つ無限の潜在能力を信じ、温かく見守りましょう。
そして、期待すべきは、スグの結果ではなく、その人のノビシロです。短期的な結果に一喜一憂するのではなく、部下の長期的な成長を見据え、その過程を辛抱強くサポートしていくことが、リーダーの重要な役割です。
「任せる覚悟」は、部下だけでなく、リーダー自身をも成長させる力となります。信頼が生む好循環の中で、リーダーと部下は共に成長し、より大きな成果を生み出すことができるのです。
さあ、あなたも今日から、「部下に任せる覚悟」を持って、チームの可能性を最大限に引き出してみませんか?信じる勇気が、きっと素晴らしい未来を拓くはずです。
詳しく知りたい方は、『できるリーダーは、「これ」しかやらない』 伊庭 正康 (著)を手に取ってください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。