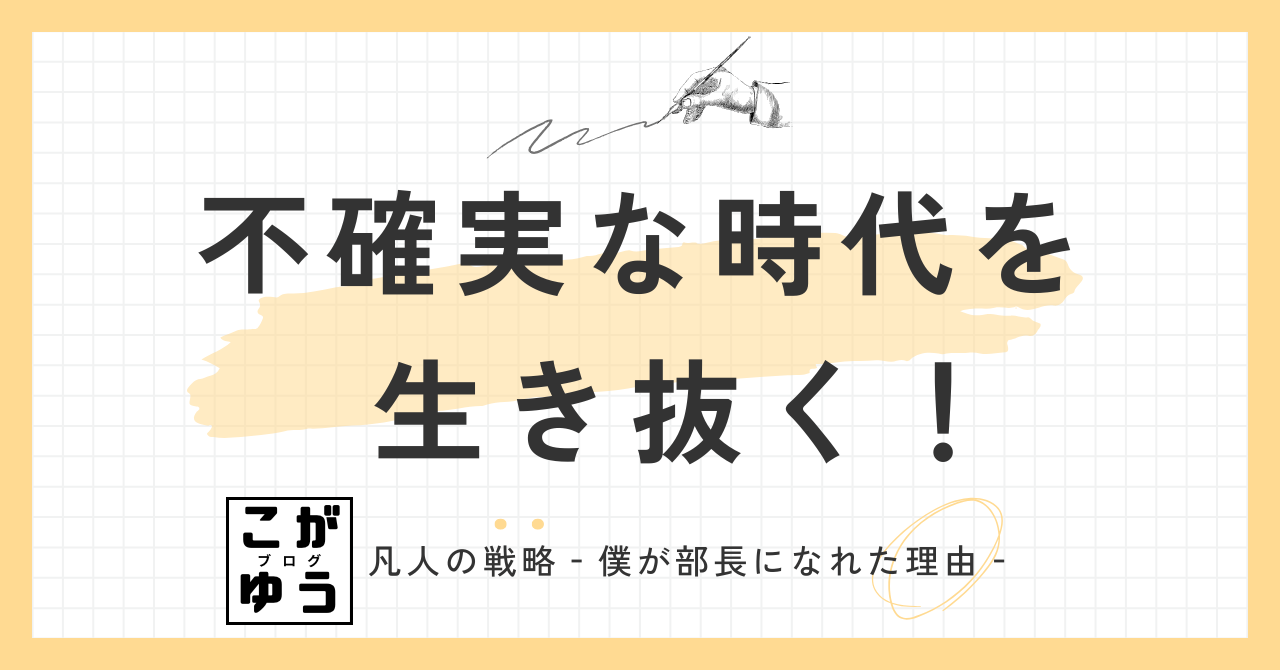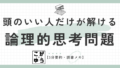人生の大きな割合を占める「仕事」。皆さんのキャリアは、どんな風に描かれていますか?昔は「一つの会社で定年まで」が当たり前でしたが、今は違いますよね。大企業でも将来が危ぶまれたり、転職や独立・起業が当たり前になったり…まさに「変化の時代」!
そんな中で、会社が社員にどんなキャリアをサポートできるのか、社員一人ひとりがどう自分の未来をデザインしていくのかが、すごく大切になっています。
「でも、どうすればいいんだろう?」
「会社はちゃんと見てくれているのかな?」
そんな不安を感じる人もいるかもしれませんね。でも、ご安心ください!今日のテーマは、この不確実な時代に、最高のキャリアを築いていくための「プロジェクトマネジメントの視点」について、大切なポイントを厳選してお伝えしていきます。
これは、会社側が社員のためにできることだけでなく、私たち自身が自分のキャリアを「プロジェクト」として捉え、能動的に動いていくためのヒントでもあります。
この記事は、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』を参考に書かせていただきました。
ジョブディスクリプション(職務記述書)を明確にする ~自分の「地図」を手に入れよう~
皆さんの会社には、「ジョブディスクリプション(職務記述書)」が明確にありますか?
「そんなの見たことない」「あっても曖昧だよ」という人もいるかもしれませんね。でも、キャリアを考える上で、このジョブディスクリプションは、まるで自分の役割と責任が書かれた「地図」のようなものなんです。
なぜジョブディスクリプションが重要なのでしょうか?
- 役割と責任の明確化:
自分が何を求められているのか、どんな責任を負っているのかが明確になります。これにより、日々の業務に迷いがなくなり、生産性が向上します。
会社側から見ると: 採用時に必要な人材像が明確になり、ミスマッチを防げます。また、人事評価の基準も明確になります。
社員側から見ると: 自分の仕事の範囲や期待値を理解し、目標設定やスキルアップの方向性を定めることができます。 - 成長のロードマップ:
現在のジョブディスクリプションが明確であれば、次に目指すべき上位のポジションや、別の職務のジョブディスクリプションと比較することで、自分に不足しているスキルや経験が明確になります。これが、自身のキャリアアップのための具体的なロードマップになるのです。 - 公平な評価:
曖昧な職務内容では、評価も主観的になりがちです。明確なジョブディスクリプションがあれば、客観的な基準で評価が行われるため、評価への納得感が高まり、モチベーション維持にも繋がります。 - キャリア対話の基盤:
上司とのキャリア面談や目標設定の際に、「自分のジョブディスクリプションでは、このスキルが求められているので、それを強化したいです」「将来的に〇〇の職務に就きたいので、そのジョブディスクリプションにある△△の経験を積ませてほしいです」といった具体的な会話ができるようになります。
もし皆さんの会社に明確なジョブディスクリプションがない場合でも、悲観することはありません。自分自身で、自分の現在の職務内容や責任、期待されていること、そして将来目指したい職務の内容を具体的に言語化してみることから始めてみましょう。
それは、あなたのキャリアをプロジェクトとして捉え、具体的な計画を立てるための最初の一歩となります。
人材育成プログラムを導入する ~未来を創る「投資」~
企業にとって、社員はかけがえのない財産です。そして、社員の成長こそが、企業の成長に直結します。不確実性の高い時代だからこそ、企業は「人を育てる」こと、つまり「人材育成プログラム」を導入することに惜しみなく投資する必要があります。
単に「研修を受けさせればいい」というわけではありません。社員一人ひとりが、自分のキャリアパスと会社のビジョンを結びつけながら、必要なスキルを習得し、成長できるようなプログラムが求められます。
- 体系的なスキルアップ研修:
ロジカルシンキング、リーダーシップ、ITスキル、語学など、ビジネスパーソンとして普遍的に求められるスキルから、特定の業務に必要な専門スキルまで、体系的に学べる機会を提供しましょう。社内研修だけでなく、外部研修やeラーニングなども積極的に活用します。 - OJT(On-the-Job Training)の質の向上:
実務を通して学ぶOJTは非常に重要です。OJTが「見て覚えろ」になっていないか、指導する側のマネージャー層へのトレーニングやサポートも不可欠です。適切なフィードバックやコーチングを通じて、メンバーの成長を促す仕組みが必要です。 - 自己啓発支援:
資格取得支援、書籍購入補助、外部セミナー参加費補助など、社員が自律的に学習する意欲をサポートする制度も効果的です。社員自身の「学びたい」という気持ちを尊重し、後押しすることで、主体的な成長が促されます。 - 「学び」を評価に組み込む:
単に業務成果だけでなく、新しいスキル習得への意欲や、研修への積極的な参加など、「学び」そのものも評価対象に組み込むことで、社員の成長意欲をさらに高めることができます。 - メンター制度・コーチング制度:
経験豊富な先輩社員や外部の専門家が、個々の社員のキャリアや悩みに寄り添い、アドバイスをするメンター・コーチング制度は、社員の成長を力強く後押しします。
人材育成プログラムは、短期的なコストではなく、未来の企業を支えるための「投資」です。社員が「この会社にいれば、自分は成長できる」と感じられる環境こそが、優秀な人材を引きつけ、定着させる最大の要因となるでしょう。
多様なキャリアパスを設計する ~未来を「選択」する自由~
かつては「管理職コース」が唯一の出世コースでしたが、現代のキャリアはもっと多様です。企業は、社員がそれぞれの個性や強みを活かし、多様なキャリアパスを選択できるような設計を考える必要があります。
これは、社員一人ひとりの「人生設計」に会社が寄り添う、という視点です。
- 専門職コースの確立:
管理職だけでなく、特定の専門分野を深く掘り下げていく「専門職コース」を明確に設けることで、マネジメント志向ではないけれど、技術や知識で貢献したい社員のモチベーションを高めます。例えば、エンジニア、研究職、マーケティングスペシャリストなど、それぞれの分野で専門性を極める道を提示します。 - ジョブローテーション・部署間異動の促進:
様々な部署や業務を経験できるジョブローテーション制度を活性化することで、社員は多角的な視点を養い、自身の適性や興味を発見する機会を得られます。部署間の壁を低くし、異動希望を出しやすい環境を整えることも重要です。 - 社内公募制度・FA制度:
社員が自らの意思で、社内の別のポジションに挑戦できる「社内公募制度」や、一定の条件を満たせば希望する部署に異動できる「FA制度(フリーエージェント制度)」は、社員のキャリア自律を促します。 - 副業・兼業の推奨:
本業以外の活動を通してスキルアップを図ったり、新たな知見を得たりすることを推奨する企業も増えています。これは、社員のキャリアの選択肢を広げるだけでなく、企業にとっても外部の知見を取り入れるメリットがあります。 - ワークライフバランスへの配慮:
多様なキャリアパスは、多様なライフスタイルと密接に関わっています。時短勤務、リモートワーク、フレックスタイム制度など、柔軟な働き方を導入し、社員が仕事と私生活を両立しながらキャリアを築ける環境を提供することも、多様なキャリアパスの設計に繋がります。
社員が「自分の未来は自分で選択できる」と感じられる多様なキャリアパスを提示することは、社員のエンゲージメントを高め、企業全体の活性化に繋がります。企業は、社員のキャリアを「管理する」のではなく、「共に創造する」パートナーとしての役割を果たすことが求められます。
対話とサポートを行う ~「伴走者」としての企業~
ジョブディスクリプションや育成プログラム、多様なキャリアパスを整備しても、それだけでは十分ではありません。最も重要なのは、社員一人ひとりに寄り添い、「対話」と「サポート」を継続的に行うことです。企業は、社員のキャリアの「伴走者」であるべきです。
- 定期的なキャリア面談の実施:
年に一度の評価面談だけでなく、半年に一度、あるいは四半期に一度など、定期的に上司や人事担当者とのキャリア面談の機会を設けましょう。ここでは、業務の進捗だけでなく、社員のキャリアプラン、身につけたいスキル、将来の希望などについて、じっくりと対話する時間を設けます。 - 傾聴と共感の姿勢:
面談では、上司が一方的に指導するのではなく、社員の言葉に真剣に耳を傾け、共感する姿勢が大切です。社員が抱える悩みや不安、あるいは秘めている夢や希望を、安心して話せる雰囲気を作りましょう。 - 具体的なアドバイスと機会提供:
対話を通じて社員のニーズを理解したら、それに基づいて具体的なアドバイスを提供したり、必要なスキルを習得できる研修や、新しい経験を積めるプロジェクトへの参加機会などを積極的に提供したりしましょう。 - 「コーチング」の導入:
上司が単なる「管理者」ではなく、「コーチ」として、社員の潜在能力を引き出し、自律的な成長を促すコーチングスキルを身につけることも非常に有効です。答えを与えるのではなく、社員自身が答えを見つけられるようサポートします。 - 失敗を恐れない文化の醸成:
新しいキャリアに挑戦する際には、失敗がつきものです。失敗を非難するのではなく、それを学びの機会と捉え、再挑戦を応援する文化を醸成することで、社員は安心してキャリアの幅を広げることができます。
企業が社員のキャリアに真剣に向き合い、対話とサポートを継続的に行うことで、社員は「この会社は自分を大切にしてくれている」「自分の成長を応援してくれている」と感じることができます。これは、社員の会社へのエンゲージメントを劇的に高め、結果として企業の持続的な成長へと繋がる、最強の「人材戦略」となるでしょう。
まとめ
今回のテーマ「不確実な時代を生き抜く!~最高のキャリアを築くプロジェクトマネジメントの視点~」は、終身雇用が当たり前ではなくなった現代において、企業が社員のキャリアをどのようにサポートし、社員自身がどのようにキャリアを築いていくべきかについて深く探求してきました。
まず、ジョブディスクリプション(職務記述書)を明確にすることが、社員自身の役割と責任を明確にし、キャリアアップのための具体的な「地図」となることを学びました。これは、会社と社員双方にとって、公平な評価と成長の基盤を提供します。
次に、企業は、未来を創るための「投資」として、人材育成プログラムを導入することの重要性です。体系的なスキルアップ研修、質の高いOJT、自己啓発支援、そして「学び」を評価に組み込むことで、社員の継続的な成長を力強く後押しします。
さらに、社員がそれぞれの個性や強みを活かし、多様なキャリアパスを設計すること。管理職コースだけでなく、専門職コースの確立、ジョブローテーションの促進、社内公募制度の活用、さらには副業推奨や柔軟な働き方の導入など、社員が未来を「選択」する自由を提供することが、エンゲージメントを高める鍵となります。
そして、最も重要なのが、企業が社員のキャリアの「伴走者」として、継続的な「対話とサポート」を行うことです。定期的なキャリア面談、傾聴と共感の姿勢、具体的なアドバイスと機会提供、コーチングの導入、失敗を恐れない文化の醸成を通じて、社員は「この会社で成長できる」と実感し、会社への信頼と貢献意欲を深めることができます。
これらの視点は、単なる人事制度の話ではありません。不確実な時代に、企業が優秀な人材を惹きつけ、定着させ、そして共に成長していくための、戦略的な「プロジェクトマネジメント」そのものです。
さあ、今日からあなたの会社で、そしてあなた自身のキャリアにおいて、これらのポイントを意識し、実践してみませんか?きっと、社員一人ひとりのキャリアが輝き、それが企業の未来を力強く照らしていくことでしょう。
詳しく知りたい方は、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』を手に取ってください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。