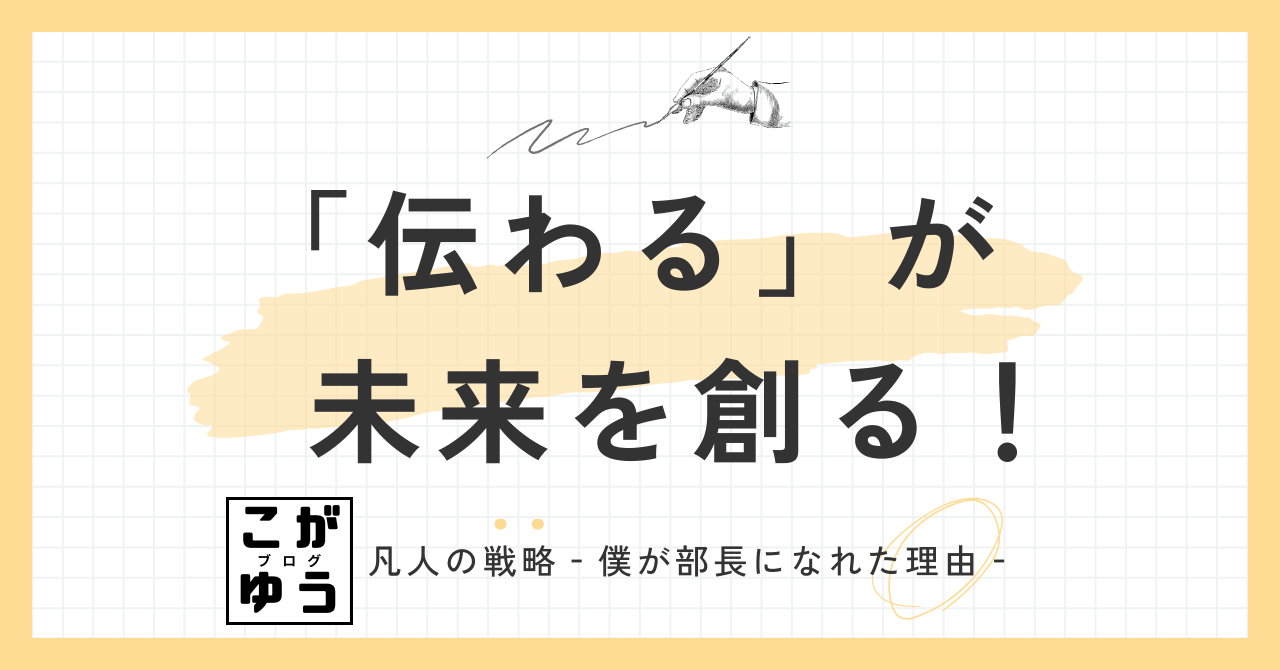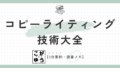皆さん、こんにちは!
今の時代、私たちは「これまでのやり方」が通用しない、前例のないプロジェクトに日々挑戦していますよね。新しい技術、変化する市場、多様な働き方…。こうした不確実な状況で、プロジェクトを成功させるには何が一番大切だと思いますか?
それは、ずばり「コミュニケーション」です!
「仕事なんだからやれ!」という一方的な指示や、人を単なる「ビジネスの歯車」として見るようなコミュニケーションでは、新しい挑戦はうまくいきません。だって、私たちは感情を持った人間だし、未知のことに挑むには、お互いの信頼と協力が不可欠だからです。
「でも、どうすれば良いコミュニケーションが取れるんだろう…」
「忙しい中で、そんなに時間をかけられないよ」
そう感じるかもしれませんね。でも、ご安心ください!今日のテーマは、そんな不確実な時代でも、あなたのチームを一つにし、プロジェクトを成功に導くための「コミュニケーションの極意」について、大切なポイントを厳選してお伝えしていきます。
この記事は、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』を参考に書かせていただきました。
コミュニケーションの質を確保する ~「伝わる」を追求する丁寧な対話~
プロジェクトにおけるコミュニケーションは、ただ情報を伝えるだけでは不十分です。特に前例のない不確実な物事を扱う際には、「コミュニケーションの質」を徹底的に確保することが成功の鍵となります。
「質が高い」とはどういうことでしょう?それは、単に「話した」「聞いた」で終わらせず、「確実に伝わり、理解され、行動に繋がる」レベルを目指すということです。
- 「なぜ」を伝える:
単に「これをやってください」と指示するだけでなく、「なぜこのタスクが必要なのか?」「このタスクがプロジェクト全体のどの目標に貢献するのか?」という背景や目的を明確に伝えましょう。人は、自分の仕事に意味を見出すと、主体性とモチベーションが格段に上がります。
NG例:「この資料、今日中に作っといて。」
OK例:「この資料は、来週の重要な顧客提案で使うから、顧客の〇〇という課題解決に繋がるように、今日中にまとめてほしいんだ。」 - 相手の理解度を確認する:
一方的に話し終えるのではなく、相手がどこまで理解したかを必ず確認しましょう。「何か不明な点はないですか?」だけでなく、「今の話、〇〇さんはどう理解しましたか?」「具体的にどんなアクションを取ろうと思いますか?」など、具体的な言葉でフィードバックを促す質問を投げかけます。
NG例:「わかった?じゃあよろしく。」
OK例:「いくつかポイントをお伝えしましたが、特に重要だと感じた点はどこですか?」「この後、具体的にどんな手順で進めるか、教えてもらえますか?」 - 言葉だけでなく、非言語情報も活用する:
対面やオンライン会議では、表情、声のトーン、ジェスチャーなども重要なコミュニケーションツールです。熱意を伝えたい時には、声に感情を込める、相手の目をしっかり見て話す、といった工夫も必要です。また、文章でのコミュニケーションでは、箇条書きや太字、図などを使って視覚的に分かりやすくする工夫が、理解度を高めます。 - 「I(私)」メッセージを使う:
相手の行動を指摘する際に、「You(あなた)メッセージ」(例:「君はいつも遅い」)を使うと、相手は責められていると感じ、反発心を抱きがちです。代わりに、「I(私)メッセージ」(例:「私は〇〇の状況を見て、少し心配しています」)を使うことで、自分の感情や懸念を伝えつつ、相手に建設的な対話を促すことができます。 - フィードバックは具体的かつ未来志向で:
改善を促すフィードバックは、抽象的な批判ではなく、具体的な行動に焦点を当て、未来の行動改善に繋がるように伝えましょう。「もっと頑張って」ではなく、「〇〇のプロセスを△△のように変えると、さらに良くなると思う」のように伝えます。
コミュニケーションの質を高めることは、一見すると手間がかかるように思えるかもしれません。しかし、これにより誤解や手戻りが減り、プロジェクトの進行がスムーズになり、結果として時間とコストの節約に繋がります。
そして何より、質の高いコミュニケーションは、チームメンバー間の信頼を深め、心理的安全性の高い協力関係を築き上げる基盤となります。
コミュニケーションの量を確保する ~「頻度」がもたらす安心感とスピード~
「忙しいのに、そんなに話す時間はないよ!」と思うかもしれません。しかし、特に前例のない不確実なプロジェクトでは、「コミュニケーションの量」を意識的に確保することが、プロジェクトを成功に導く上で非常に重要です。
なぜなら、不確実な状況では、新しい情報や変化が頻繁に発生します。情報が共有されなければ、認識のズレが生じ、手戻りや意思決定の遅れ、そして何よりもチームの不安に繋がってしまいます。
- 定期的なチェックイン(日次・週次):
毎日数分間の朝会や、週に一度の短時間の進捗会議など、定期的に顔を合わせ、短い情報共有を行う場を設けましょう。ここで話すのは、細かな報告ではなく、各自の「今日の最重要タスク」「困っていること」「チームに共有したいこと」など、簡潔な情報で構いません。
これにより、小さな問題が大きくなる前に気づけたり、メンバー間の連携がスムーズになったりします。 - 非公式なコミュニケーションを奨励する:
プロジェクトの進捗に関するフォーマルな会議だけでなく、ランチタイムや休憩時間、あるいはチャットツールでの気軽なやり取りなど、非公式なコミュニケーションの機会を大切にしましょう。雑談の中から、思わぬアイデアが生まれたり、メンバーの隠れた悩みに気づけたりすることもあります。 - 情報のオープン化と透明性:
プロジェクトの目標、進捗状況、課題、意思決定のプロセスなどを、チーム全体でオープンに共有できるツール(プロジェクト管理ツール、共有ドライブ、社内SNSなど)を活用しましょう。これにより、メンバーはいつでも必要な情報にアクセスでき、認識のズレを防ぎます。 - 「報・連・相」の文化を浸透させる:
「報告・連絡・相談」は、コミュニケーションの基本です。特に不確実なプロジェクトでは、「少しでもおかしいと感じたらすぐに報告・相談する」という文化を浸透させることが重要です。マネージャーは、悪いニュースほど早く報告してくれたことを褒め、決して責めない姿勢を見せましょう。 - 目的を明確にした会議設計:
会議の数を増やすだけでなく、一つ一つの会議の目的を明確にし、効率的に進行することを心がけましょう。ダラダラとした会議は、時間の無駄であり、コミュニケーションの質を低下させます。アジェンダを事前に共有し、時間厳守で進めることで、密度の高いコミュニケーションが可能になります。
コミュニケーションの量を確保することは、チームに「安心感」をもたらします。「自分は孤立していない」「困った時に助けてもらえる」という感覚は、不確実な状況下でこそ、メンバーの心理的な支えとなります。
そして、情報の鮮度と共有スピードが上がり、結果としてプロジェクトの進行を加速させるのです。
価値観の多様性に留意する ~違いを力に変える共感力~
「仕事なんだから、みんな同じ方向を向いて当然」そう思っていませんか?しかし、現代のプロジェクトでは、年齢、性別、国籍、経験、働き方、そして「価値観」など、非常に多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まることがほとんどです。
プロジェクトを成功に導くには、この「価値観の多様性」に留意し、それを理解し、尊重するコミュニケーションが不可欠です。強権的なコミュニケーションでは、この多様性は分断を生み、新しい取り組みを阻害する要因となってしまいます。
- 異なる視点を受け入れる姿勢:
自分とは異なる意見や考え方が出てきた時、すぐに否定するのではなく、まずは「なぜそう思うのだろう?」と相手の背景を理解しようと努めましょう。その人の経験や価値観から生まれた意見は、プロジェクトに新しい視点や解決策をもたらす可能性があります。
例:「〇〇さんは、その点について違う意見を持っていますね。どのような経験や考えから、そうお考えになったか、もう少し詳しく聞かせてもらえますか?」 - それぞれの「動機」を理解する:
同じ目標に向かっていても、メンバー一人ひとりの「動機」や「仕事に求めるもの」は異なります。ある人は「キャリアアップ」、ある人は「社会貢献」、ある人は「ワークライフバランス」かもしれません。個々の動機を理解し、その動機とプロジェクトの目標を結びつけるようなコミュニケーションを心がけましょう。
例:「このタスクは、〇〇さんが将来目指すスキル習得にも繋がると思うんだけど、どうかな?」 - 「べき論」を押し付けない:
「こうあるべきだ」「こうするのが当然だ」といった自分の価値観を相手に押し付けないように注意しましょう。特に、世代間ギャップや文化の違いがある場合、これが衝突の原因となることがあります。
NG例:「社会人なら、残業するのは当たり前だ。
OK例:「このタスクは、今日の定時までに完了が難しいかもしれない。もし残業が必要な場合、〇〇さんのご都合はどうですか?」 - 心理的安全性を最優先する:
価値観の多様性を受け入れ、活かすためには、メンバーが「自分らしくいられる」「率直な意見を言っても大丈夫」「失敗を恐れずに挑戦できる」と感じられる心理的安全性が非常に重要です。相手の意見を尊重し、批判ではなく対話を促す姿勢が不可欠です。 - 共感と共通点を見出す努力:
違いばかりに目を向けるのではなく、共通の目標や、共感できる点を見出す努力をしましょう。たとえ価値観が異なっても、「プロジェクトを成功させたい」という共通の願いや、「より良いものを作りたい」という情熱は、多くの人が持っているはずです。
価値観の多様性を理解し、それを力に変えるコミュニケーションは、単に人間関係を円滑にするだけでなく、プロジェクトに革新的なアイデアと、変化に対応できる強靭なチームをもたらします。
「仕事なんだからやれ」という強権的な姿勢ではなく、一人ひとりの価値観を尊重し、対話を通じて共に未来を創っていく姿勢こそが、不確実な時代を生き抜くプロジェクトマネジメントの真髄です。
まとめ
今回のテーマ「不確実な時代を乗りこなすプロジェクトコミュニケーションの極意」は、前例のないプロジェクトを成功させ、事業を継続的に発展させるために不可欠な、「人と人との繋がり」を深めるコミュニケーションの重要性について深く探求してきました。
私たちは、単に情報を伝えるだけでなく、「コミュニケーションの質を確保する」ことが何よりも大切だと学びました。具体的には、「なぜ」を伝え、相手の理解度を確認し、非言語情報も活用し、「Iメッセージ」で建設的にフィードバックを行うことです。これにより、誤解を減らし、信頼関係を築き、確実に「伝わる」コミュニケーションを実現できます。
次に、「コミュニケーションの量を確保する」ことの重要性です。定期的なチェックインや非公式な会話を奨励し、情報のオープン化を図ることで、不確実な状況における「安心感」をチームにもたらし、情報の鮮度と共有スピードを高めることができます。
そして、最も重要なのが、「価値観の多様性に留意する」姿勢です。異なる視点や動機を受け入れ、「べき論」を押し付けず、心理的安全性を確保することで、多様なメンバーの知恵と力を最大限に引き出し、それをプロジェクトの成功へと繋げることができます。
これらのコミュニケーションの極意は、決して「仕事なんだからやれ」という強権的なスタンスでは成し得ません。むしろ、一人ひとりの人間を尊重し、対話を通じて共に未来を創っていく「人間中心」のアプローチが、不確実な時代におけるプロジェクトマネジメントの成功を確かなものにします。
さあ、今日からあなたのプロジェクトにおけるコミュニケーションを、これらの視点で見直してみませんか?きっと、チームメンバーとの絆が深まり、どんな未知の課題にも、自信を持って立ち向かえる、最高のプロジェクトへと進化していくことでしょう。
あなたのコミュニケーションが、未来を創る原動力となります!
詳しく知りたい方は、橋本将功さんの『人が壊れるマネジメント』を手に取ってください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。