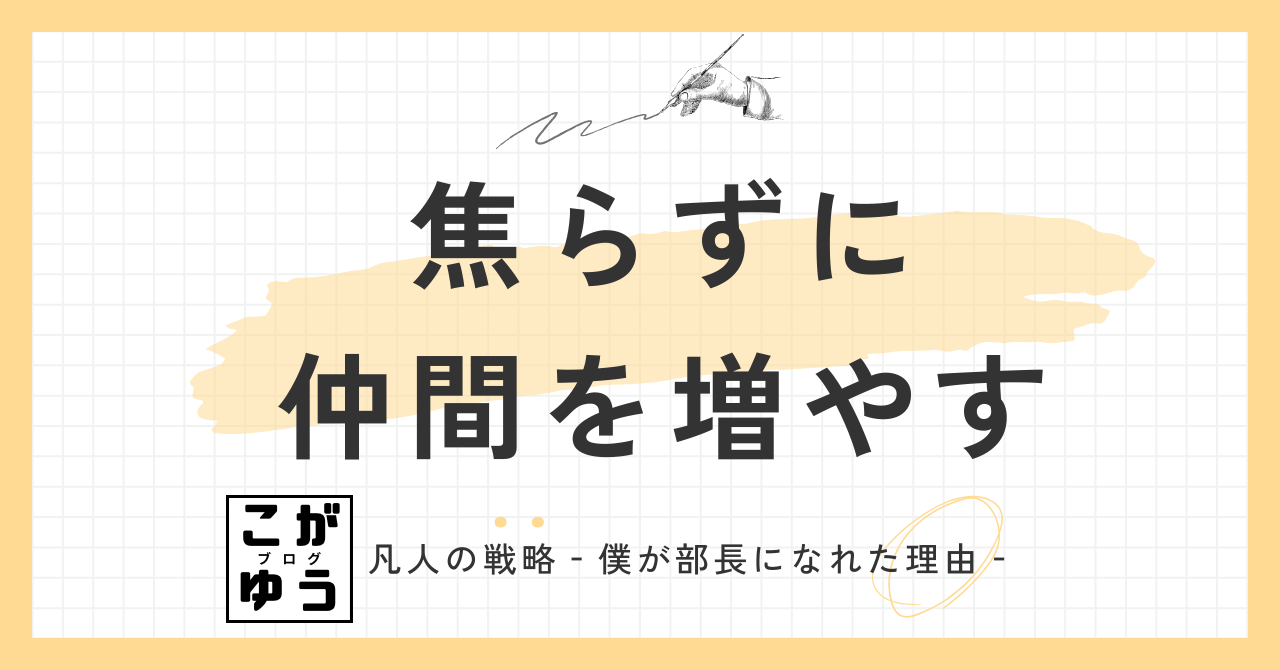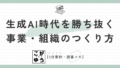いくら頑張っても認められなかった20~30代を過ごした凡人の自分が、どのように42歳で上場企業の部長になったのか、年収1000万を目指すビジネスパーソンに向けて、等身大の経験と知恵を発信したいと思います。
凡人の戦略<組織改革>
焦らずに仲間を増やす
皆さん、こんにちは!日々、組織の中で、チームの中で、様々な目標に向かって奮闘されていることと思います。新しいプロジェクトの推進、業務の改善、チームの活性化…何かを変えようとするとき、私たちはどうしても「早く結果を出したい」「多くの人に賛同してもらいたい」と焦ってしまいがちです。
今回のテーマは、そんな焦りを鎮め、持続的な変化を生み出すための大切な考え方、「焦らずに仲間を増やす」です。これは、組織変革の道のりはマラソンのようなものであり、短距離走のように一気にゴールを目指すのではなく、着実に、そして穏やかに進んでいくことが重要であることを教えてくれます。この記事を通して、この考え方を深く理解し、実践することで、より効果的に、そして無理なく仲間を増やし、組織を変えていくことができるようになることを願っています。
小さなことから始めて、小さな成功例を作る ~変化の種をまく~
何か大きなことを成し遂げようとするとき、私たちはどうしても大きな計画を立て、一気に状況を変えようとしがちです。しかし、組織のような複雑なシステムにおいては、急激な変化は反発を生みやすく、かえって物事がうまくいかなくなることがあります。
そこで重要なのが、「小さいことからはじめて小さな成功例を作る」というアプローチです。これは、変化の種をまくようなもので、最初は目に見える効果は小さいかもしれませんが、着実に根を張り、やがて大きな木へと成長していくのです。
例えば、チームのコミュニケーションを改善したいと考えているとします。いきなり大規模な研修を企画したり、新しいコミュニケーションツールを導入したりするのではなく、まずは朝礼で一言ずつポジティブなことを共有する、ランチタイムに雑談の時間を設けるなど、小さなことから始めてみましょう。
このような小さな取り組みが成功すれば、チームの雰囲気が少しずつ良くなり、メンバー間の関係も深まります。そして、この小さな成功体験が、他のメンバーにも伝わり、「自分たちもやってみよう」という気持ちを育むのです。
社内で小さな成功のコツを広め、同士の輪を増やす ~共感のネットワークを築く~
小さな成功例ができたら、それを社内に広めることが重要です。これは、共感のネットワークを築くようなもので、成功体験を共有することで、同じように課題を感じている人たちと繋がり、同士の輪を広げることができます。
例えば、朝礼でのポジティブ共有がチーム内で好評であれば、他のチームにも紹介してみたり、社内ブログで紹介してみたりするのも良いでしょう。成功のコツや工夫した点を共有することで、他のチームでも同じように取り組むことができ、社内全体に良い影響が広がっていきます。
この過程で、自然と「同士」が増えていきます。同じ目標を持ち、同じように行動する仲間が増えることで、変化の波はさらに大きくなり、組織全体を巻き込む力を持つようになるのです。
組織には、いろんな人がいて健全である ~多様性を力に変える~
組織は、様々な個性を持つ人々が集まって構成されています。変化に対して積極的に行動する人もいれば、様子を見ている人もいますし、変化に対して抵抗を感じる人もいます。これは自然なことであり、むしろ組織の健全性を示すものです。
変化を起こそうとするとき、私たちはどうしても賛同者ばかりを求めがちです。しかし、組織には様々な人がいて、それぞれの役割を果たしていることを理解することが重要です。
- 積極派: 変化に対して積極的に行動し、率先して新しいことに取り組む人たち。
- 様子見派: 変化の様子を見て、メリットを感じれば賛同する人たち。
- 消極派: 変化に対して抵抗を感じ、現状維持を望む人たち。
大切なのは、どのタイプの人も否定しないことです。それぞれの立場を理解し、尊重することで、組織全体のバランスを保ちながら、変化を進めていくことができるのです。
ガンジーも一気に全体を変えようとせず、農民一人ひとりと対話し続けた ~粘り強い対話の力~
インド独立の父、マハトマ・ガンジーは、非暴力抵抗の指導者として知られています。彼は、イギリスからの独立という大きな目標を掲げながらも、一気にインド全体を変えようとはしませんでした。
ガンジーは、農民一人ひとりと対話し、彼らの生活や苦しみに耳を傾けました。そして、彼らが自ら立ち上がり、変化を起こすように、辛抱強く働きかけました。
ガンジーの活動は、一見地味で時間がかかるように見えましたが、最終的にはインドの独立という大きな成果に繋がりました。これは、粘り強い対話と、人々の内なる力を信じることの大切さを教えてくれます。
組織変革においても、ガンジーのように、目の前の仲間一人ひとりと丁寧に対話することが重要です。相手の立場や考えを理解し、共感することで、信頼関係を築き、変化への抵抗を和らげることができます。
ティッピングポイントはきっと訪れる ~変化が雪崩のように広がる瞬間~
「ティッピングポイント」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、マルコム・グラッドウェルが著書『ティッピング・ポイント』で提唱した概念で、アイディアや社会的行動が閾値を超えると、野火のように広がっていく、劇的な瞬間のことを指します。
組織変革においても、ティッピングポイントは必ず訪れます。最初は小さな変化だったものが、徐々に周囲に広がり、ある時点を超えると、雪崩のように組織全体に広がっていくのです。
このティッピングポイントを迎えるためには、焦らずに、着実に仲間を増やしていくことが重要です。小さな成功例を作り、それを共有し、共感の輪を広げていくことで、賛同者の数は徐々に増えていきます。
賛同者の数がティッピングポイントを超えれば、「多数派の様子見だった人達」が次々と仲間になる ~雪だるま式に増える共感の輪~
賛同者の数がティッピングポイントを超えると、これまで様子見をしていた人たちが、次々と仲間に加わってきます。これは、人間が社会的な生き物であり、周囲の行動に影響を受けやすいという性質によるものです。
多くの人が賛同しているのを見ると、「自分も参加してみよう」「これは良いことかもしれない」と感じるようになり、これまで様子見をしていた人たちも、積極的に行動するようになるのです。
この段階になると、変化は自己増殖的に進んでいきます。まるで雪だるまが転がるように、共感の輪はどんどん大きくなり、組織全体を巻き込む大きな流れとなるのです。
目の前で働く仲間一人ひとりと、一期一会の気持ちで対話する ~心の繋がりを大切にする~
組織変革の過程で、最も大切なのは、目の前で働く仲間一人ひとりと、一期一会の気持ちで対話することです。これは、単に業務連絡をするだけでなく、相手の立場や考えを理解し、共感する、心のこもったコミュニケーションを意味します。
相手の名前を呼び、目を見て話し、相手の話に真剣に耳を傾ける。たったこれだけのことで、相手との間に心の繋がりが生まれ、信頼関係が深まります。そして、この信頼関係こそが、変化を推進する上で最も重要な基盤となるのです。
大河の流れも一滴のしずくから ~継続は力なり~
「大河の流れも一滴のしずくから」という言葉があります。これは、大きなことも、最初は小さなことから始まるということを意味しています。
組織変革も同じです。最初は小さな変化かもしれませんが、それを継続することで、やがて大きな流れとなり、組織全体を変えていく力となるのです。
焦らずに、着実に、仲間を増やしていく。目の前の仲間との繋がりを大切にし、一期一会の気持ちで対話する。そして、小さな成功を積み重ねていく。
これらのことを意識することで、あなたは組織の中に穏やかな革命を起こし、より良い未来を創造していくことができるでしょう。
具体例で見てみよう ~チームの会議改革~
例えば、チームの会議が長くて非効率だと感じているとします。
- 小さいことからはじめる: まずは自分の発言を簡潔にする、会議前にアジェンダを確認する、などの小さなことから始めます。
- 成功例を広める: 会議がスムーズに進んだ場合は、その要因をチームメンバーに共有します。「アジェンダのおかげで議論がスムーズになったね」など、具体的な効果を伝えることで、他のメンバーも同じように行動するようになります。
- 様々なタイプのメンバーへの対応: 積極的に改善を提案するメンバーもいれば、様子を見ているメンバーもいます。それぞれの意見に耳を傾け、丁寧に説明することで、徐々に賛同者を増やしていきます。
- 粘り強い対話: 会議後には、メンバー一人ひとりと個別に話をし、会議の感想や改善点などを聞くようにします。
- ティッピングポイント: 徐々に会議の効率が改善していくと、これまで様子見をしていたメンバーも「確かに会議が短くなった」「以前より有意義な時間になった」と感じるようになります。そして、彼らも積極的に会議の改善に協力するようになり、ティッピングポイントを迎えます。
まとめ ~焦らず、着実に、共感の輪を広げよう~
今回のテーマ、「焦らずに仲間を増やす」は、組織変革における重要な心構えを教えてくれます。それは、焦らずに、着実に、共感の輪を広げていくことで、持続的な変化を生み出すことができるということです。組織を変える、チームを動かす、プロジェクトを成功させる。これらの目標を達成するためには、短距離走のようなスピード勝負ではなく、マラソンのような持久力とペース配分が求められます。一気にすべてを変えようとするのではなく、小さな一歩を踏み出し、その小さな成功を丁寧に積み重ねていくこと。これが、周囲の共感を呼び、仲間を増やし、最終的には大きな変化へと繋がる道筋なのです。
この考え方を実践する上で、特に重要なポイントを改めて整理してみましょう。
- 小さなことから始めることの重要性
- 成功体験の共有と共感の輪
- 多様性の受容と尊重
- 粘り強い対話の力
- ティッピングポイントの認識
- 継続の力
組織を変える、というのは、簡単なことではありません。しかし、「焦らずに仲間を増やす」という視点を持ち、上記のポイントを意識することで、より着実に、そして持続的な変化を生み出すことができるはずです。目の前の仲間との繋がりを大切にし、共感の輪を広げながら、より良い組織、より良い未来を創造していきましょう。この考え方が、皆さんの組織変革の道のりを照らす灯台となることを心から願っています。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。