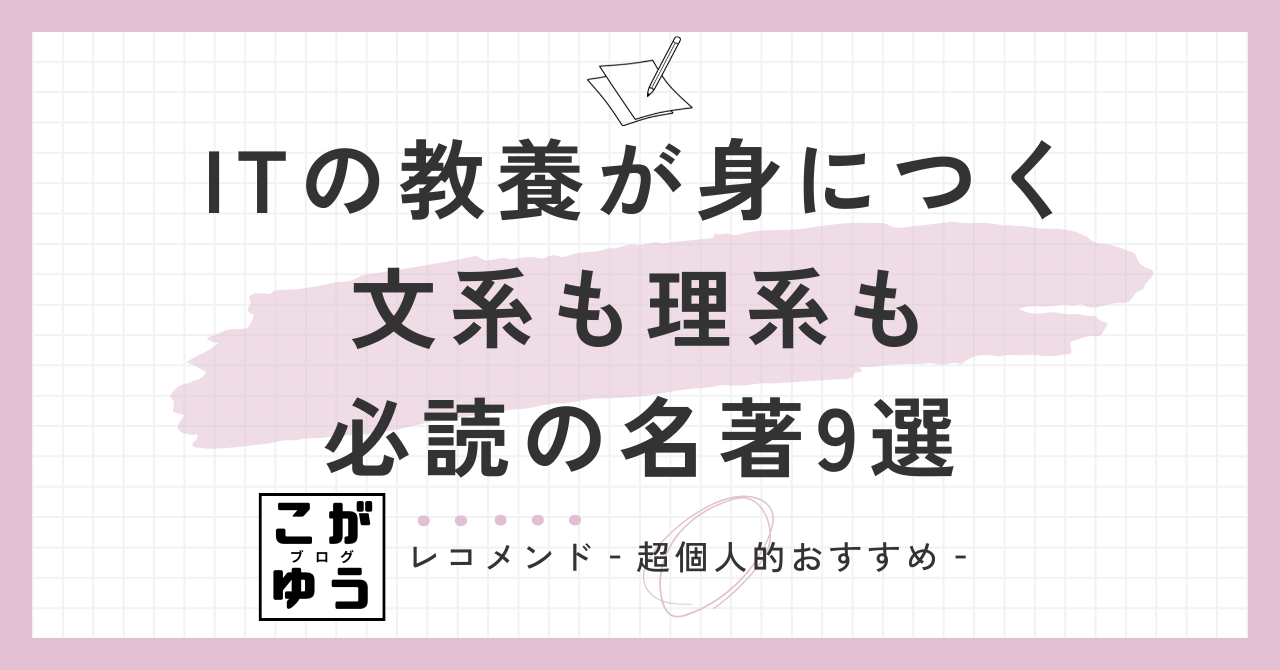日経BOOKプラスが2025年9月11日に公開した『「ITの教養」が身につく良書 文系も理系も必読の名著9冊』企画。
IT系のヒット書籍を手掛けてきた編集者が、「仕組みの基本と全体像の輪郭」が身につく本を9冊厳選した書籍を紹介します。
日経BOOKプラスの特集で厳選された9冊は、ITが苦手な人にも、得意な人にもおすすめです。
これらの本は、コンピューターの仕組みから、プログラミング、ネットワーク、そしてAIの基礎までを体系的に学ぶことができます。
ITの全体像を理解し、現代社会を生き抜くための教養を身につけましょう。
詳しくはこちら→『「ITの教養」が身につく良書 文系も理系も必読の名著9冊』
1.『教養としてのコンピューターサイエンス講義 第2版』
ブライアン・カーニハン 著、酒匂 寛 訳、坂村 健 解説、日経BP
この本は、コンピューターサイエンスの基礎を、専門家ではない人にも分かりやすく解説したものです。コンピューターがどのように情報を処理し、アルゴリズムがどのように機能するのか。その本質的な仕組みを、豊富な例と図解で解き明かしています。
著者のブライアン・カーニハンは、プログラミング言語「C言語」の生みの親の一人です。彼の簡潔で明快な語り口は、読者を飽きさせません。
この本を読むことで、IT技術の表面的な知識ではなく、その根幹にある普遍的な原理を理解できます。IT時代を生きるすべての人にとって、知的基盤を築くための必読書です。
2.『コンピュータはなぜ動くのか 第2版』
矢沢 久雄 著、日経BP
この本は、私たちが当たり前のように使っているコンピューターが、内部でどう動いているのかを、初歩から丁寧に解説しています。CPUやメモリ、ハードディスクといった部品が、どのように連携して情報を処理しているのか。その全体像を、分かりやすい図解で示しています。
専門知識がなくても、コンピューターの起動から、ソフトウェアの実行、データの保存まで、一連の流れが理解できるでしょう。
この本を読むと、コンピューターが単なる「黒い箱」ではなくなります。IT技術の背景にある仕組みを深く理解したい人にとって、この上ない入門書です。
3.『プログラムはなぜ動くのか 第3版』
矢沢 久雄 著、日経BP
この本は、「プログラム」の仕組みに焦点を当てて、その基本原理を解説したものです。私たちが普段使っているアプリケーションは、どのようにして動いているのか。その謎を解き明かします。
著者は、プログラミング言語が、どのようにしてコンピューターが理解できる機械語に変換されるのか。そして、メモリー上でどのように実行されるのかを、具体的な例を交えながら説明しています。
プログラミングをこれから学ぶ人にとって、挫折しないための心強い味方になるでしょう。プログラマーを目指す人だけでなく、ITサービスを使うすべての人に役立つ教養書です。
4.『データベースをなぜつくるのか』
矢沢 久雄 著、日経BP
この本は、私たちの生活を支える「データベース」の役割と仕組みを解説したものです。インターネットサービス、銀行のシステム、企業の顧客管理など、あらゆる場面でデータベースは使われています。
著者は、データベースが「なぜ必要なのか」という根本的な問いから始めます。データの効率的な管理、検索、そしてセキュリティが、どのようにして実現されているのかを、分かりやすい図解で示しています。
この本を読むと、普段は意識しないデータベースの重要性がよくわかるでしょう。ITシステムの本質を理解したい人にとって、必読の一冊です。
5.『ネットワークはなぜつながるのか 第2版』
戸根 勤 著、日経NETWORK 監修・著、日経BP
この本は、私たちが毎日使っているインターネットが、どのようにして成り立っているのかを解き明かしたものです。メールを送ったり、ウェブサイトを見たりする際、裏側では複雑な通信の仕組みが動いています。
著者は、通信のルールである「プロトコル」や、データを運ぶ「パケット」の仕組みを、図解で丁寧に解説。ネットワークの全体像を、まるで旅をするように理解できます。
この本を読むと、インターネットがなぜ安全につながるのか、トラブルが起きたときにどう対処すべきかといった知識が身につきます。現代社会に不可欠なインフラの仕組みを学びたい人におすすめです。
6.『教養としてのAI講義』
メラニー・ミッチェル 著、松原 仁 解説、尼丁 千津子 訳、日経BP
この本は、AIを「教養」として理解することを目指したものです。AIとは何か。そして、その進化が社会にどんな影響を与えるのか。その本質を、歴史的背景から最新技術まで、幅広く解説しています。
著者は、AI研究の最前線にいる専門家です。AIが何を得意とし、何を苦手としているのかを客観的に示しています。また、AIがもたらす倫理的な問題についても深く考察しています。
この本を読むと、AIに対する漠然とした不安が解消されるでしょう。AI時代を生きるすべての人にとって、AIを正しく理解するための羅針盤となる一冊です。
7.『ディープラーニングAIはどのように学習し、推論しているのか』
立山 秀利 著、日経ソフトウェア 編、日経BP
この本は、AIの中核技術である「ディープラーニング」の仕組みを、豊富な図解で分かりやすく解説したものです。AIは、どのようにして大量のデータからパターンを学習し、未知の情報を推論しているのか。その謎を解き明かします。
著者は、プログラミングや数学の知識がなくても理解できるよう、丁寧な解説を心がけています。AIが、まるで人間の脳のように機能する様子が、視覚的に理解できるでしょう。
この本を読むと、AI技術の背景にある原理がよくわかります。AIの可能性をビジネスに活かしたい人、そしてAI技術をより深く理解したい人に、ぜひ読んでほしい一冊です。
8.『ソフトウェアファースト 第2版』
及川 卓也 著、日経BP
この本は、「ソフトウェア」が、いかに現代のビジネスを支えているかを解説したものです。著者の及川卓也氏は、IT業界の第一人者です。
彼は、「ソフトウェアを制する企業が、未来を制する」と説きます。単なる技術論ではなく、ビジネス戦略、組織文化、そしてリーダーシップまで、幅広い視点から「ソフトウェアファースト」という考え方を提示しています。
この本を読むと、すべての企業が「ソフトウェア企業」になるべき時代が来ていると気づくでしょう。ビジネスパーソンが、ITを経営戦略の中心に置くためのヒントが満載です。
9.『CODE 第2版』
チャールズ・ペゾルド 著、酒匂 寛 訳、日経BP
この本は、コンピューターの仕組みを「論理」の観点から徹底的に解き明かした古典的名著です。著者チャールズ・ペゾルドは、IT技術を構成するすべての要素を「符号(CODE)」として捉えています。
電気回路のON/OFFから、二進法、そして複雑なソフトウェアがどのようにして生まれるのか。その壮大なつながりを、まるでミステリーを解くように解説しています。
この本を読むと、IT技術が魔法ではなく、普遍的な論理の積み重ねであると理解できます。ITの基礎を究めたい人、そしてコンピューターの真の姿を知りたいと願うすべての人にとって、時間をかけて読む価値のある一冊です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。