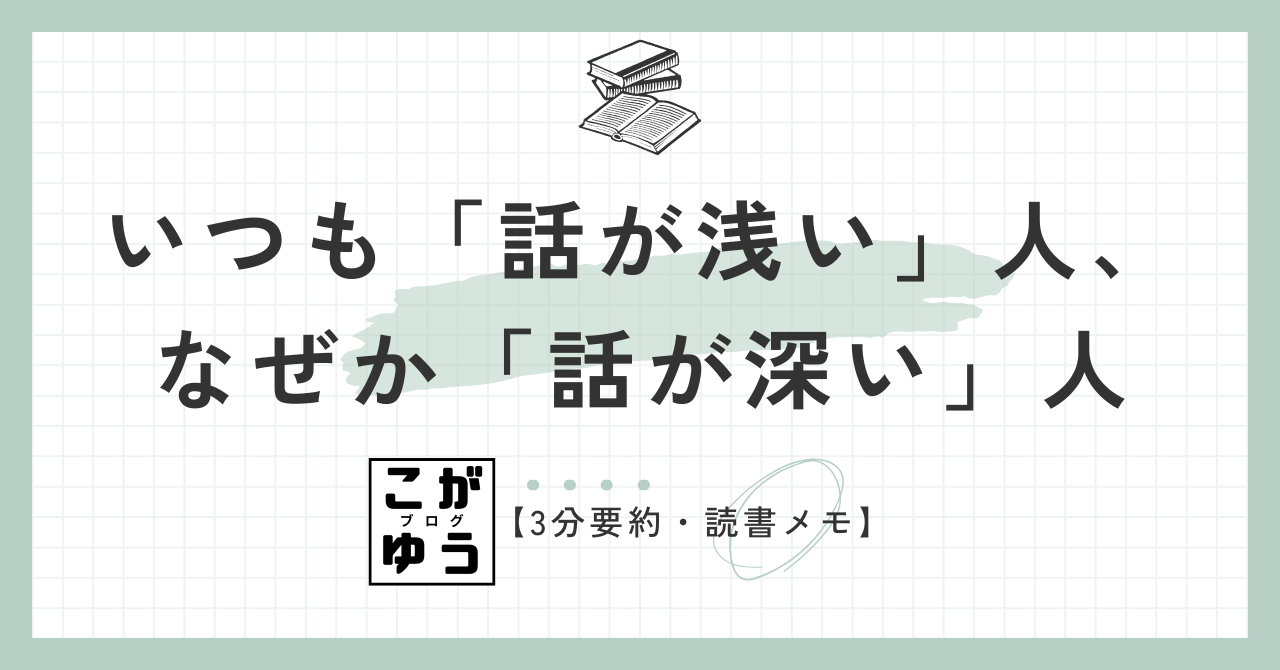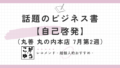あなたは、誰かの話を聞いていて、「うーん、話が浅いな…」と感じたことはありませんか?
逆に、「この人の話はなぜか深い!」「ハッとさせられる」と感銘を受けた経験はありませんか?
今日ご紹介するのは、そんな私たちの日常に潜む「話の浅さ」と「話の深さ」の正体を解き明かす、齋藤孝先生の著書『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』です!
この本は、単なる話し方のテクニック集ではありません。話の「深さ」が、その人自身の「人間としての深さ」に直結するという、本質的なメッセージを投げかけてきます。読み終える頃には、あなたの話す力だけでなく、考える力、そして何より「聞く力」もぐっと深まっていることでしょう。
今回のブログ記事では、この魅力的な一冊の秘密を、以下の構成でじっくりと探っていきます。
ぜひ最後までお付き合いいただき、あなたも「深い話」ができる人への第一歩を踏み出してみませんか?
1. 著者の紹介
本書『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』の著者である齋藤孝先生は、日本の教育学を牽引する第一人者であり、多方面で活躍されている著名な教育学者です。
齋藤 孝(さいとう たかし)氏
1960年、静岡県静岡市生まれ。東京大学法学部を卒業後、同大学大学院教育学研究科博士課程を経て、現在は明治大学文学部教授を務めていらっしゃいます。
専門は教育学、身体論、そしてコミュニケーション論。特に、身体感覚を取り戻すことや、日本語の豊かな表現力を重視した教育スタイルを提唱されており、その知見は多岐にわたります。
齋藤先生の名前を一躍有名にしたのは、2001年に出版されたベストセラー『声に出して読みたい日本語』でしょう。この本はシリーズ累計260万部を超える大ヒットとなり、日本中に「音読ブーム」を巻き起こし、第56回毎日出版文化賞特別賞を受賞しました。他にも、『身体感覚を取り戻す』で新潮学芸賞を受賞されるなど、数々の著書が多くの読者に支持されています。著書累計出版部数は1000万部を超えるというから驚きですね。
また、NHK Eテレの「にほんごであそぼ」の総合指導をはじめ、「世界一受けたい授業」「情報7days ニュースキャスター」「東大王」など、テレビ番組にも多数出演されており、その明快な解説と温かい人柄で幅広い層から人気を集めています。
齋藤先生は、コミュニケーションの重要性を長年説き続けており、『雑談力が上がる話し方』『大人の語彙力ノート』など、話し方や言葉に関するベストセラーも多数執筆されています。教育学という確かな基盤を持ちながら、現代社会に必要とされるコミュニケーション能力を実践的に、かつ分かりやすく指南してくれる点が、多くの読者に支持される理由でしょう。
本書においても、その豊富な知識と洞察力に基づき、「話の深さ」が単なるテクニックではなく、その人自身の「知性」や「人間性」に根ざしていることを、具体的な視点から解き明かしてくれています。
2. 本書の要約
齋藤孝先生の著書『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』は、私たちの日常会話やビジネスシーン、さらにはメディアに溢れる発言まで、あらゆるコミュニケーションにおける「話の浅さ」と「話の深さ」の正体を具体的に解き明かし、聞き手の心を動かす「深い話」をするための能力とその磨き方を解説する一冊です。
本書の冒頭では、「話が浅い人」の特徴が具体的に挙げられます。
- 当たり前のことばかり述べる話
- ポイントがずれていて掘り下げが甘い話
- 具体性がなく漠然とした話
- 思い込みが強く視野の狭い話
- 知識に乏しい話
- 思いつきだけで思考の形跡がない話
- 人生観や普遍的視点がない話
これらは、聞き手に「浅い」という印象を与え、最終的にはその人自身が「底の浅い人」と評価されてしまうと警鐘を鳴らします。一方で、「深い話」ができる人は、周囲から「示唆に富んでいる」「思慮深い」と一目置かれる存在となると述べます。
では、私たちは話のどこに「浅さ」や「深さ」を感じるのでしょうか?本書は、この問いに対し、具体例を交えながらその本質に迫ります。そして、「浅い人」から「深みのある人」へと変わるための44の戦略を提示しています。
本書は、以下の4つの章で構成され、「深い話」をするための具体的な道筋を示してくれます。
まえがき:あなたのまわりの「浅い人」
身近にいる「話が浅い人」の特徴を挙げ、読者に共感を促しながら、本書で扱うテーマの重要性を提示します。
第1章:話の「浅い人」、「深い人」の違いはここだ
「深い話」をするために特に重要な3つの能力を提示します。
- 展開力:単なる情報の羅列ではなく、話を広げ、異なる視点から発展させる力。自分の知識や経験を元に、相手の関心を惹きつけながら話を広げることが重要です。
- 本質把握力:物事の表面的な事柄にとどまらず、その背景にある重要なポイントや意味を掴み、明確に伝える力。問題の核心を見抜き、簡潔に表現する力が求められます。
- 具体化力:抽象的な話に終始せず、具体的な事例やエピソードを織り交ぜて説明する力。相手が話をより深く理解し、心に響くようにするために不可欠です。 この章では、「練られたものが深さである」ことや、「感覚の変容」体験の重要性、受け売りの情報に飛びつく「浅さ」なども解説します。
第2章:本質がわかっている人は、やっぱり深い
「本質把握力」をさらに深掘りします。普遍的な視点を持つことの重要性や、「具体と本質」の両面から物事を捉える大切さを説きます。深さとは、斬新なものの中にではなく、「一見、平凡なもの」の中にある本質を見抜く力だという視点も示されます。細部に着目することで本質が見えてくる「深さの感覚」を養う練習方法も紹介されます。
第3章:深い人は「エピソード」をもっている
「具体化力」に焦点を当て、話を深くする上でエピソードがいかに重要かを解説します。誰もが実は深いエピソードを持っていること、そしてそれらを「判断力」をキーワードに見つけ出す方法を提示。見えないところで思考を重ね、具体化する力が深さを生み出すと述べます。
第4章:「あの人は深い」と言われる話し方の技術
具体的な話し方のテクニックが紹介されます。「なぜか深い人」の口癖や、「スリーステップ論法」といった効果的な論理展開の方法、会議や面接試験で一目置かれる発言のコツ、そして「逆質問」の活用法など、すぐに実践できる技術が満載です。
本書は、単に話し方の上手・下手ではなく、いかに深く物事を考え、それを的確な言葉で表現できるかという、人間としての知的体力、知性を鍛えることの重要性を説いています。情報過多な現代において、「深い話」ができる人になるための指針を与えてくれる一冊と言えるでしょう。
3. ココだけは押さえたい一文
本書『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』の核となるメッセージを最も的確に捉え、深く印象に残る「ココだけは押さえたい一文」は、この言葉に尽きるでしょう。
「話の『深さ』は、人間の『深さ』である。」
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
この一文は、単なるコミュニケーションスキルを超え、話の質がその人の内面的な知性や人間性、つまり「深み」を反映しているという、本書の最も重要な主張を明確に示しています。表面的なテクニックに走るのではなく、いかに物事を深く思考し、本質を捉え、それを具体的な言葉で表現できるか。
その根底には、日々の学びや経験、そして物事を多角的に見る姿勢が不可欠であることを示唆しています。この言葉を知ることで、私たちは自分の話し方だけでなく、生き方そのものを見つめ直すきっかけを得られるはずです。
情報収集の際には、角度をつけて、別の視線からの意見や情報を意識的に集めることが、深い話をするためには重要
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
人は、「具体的かつ本質的」なものに、「深さ」を感じる
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
「本質」とは、斬新なものより「一見、平凡なもの」にある
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
深い話、深い意見というのは、極論ではなく、中庸の感覚がもたらすもの
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
まず第一に、別の視点から見たらどうだろうか、という点を意識して、そこから思考を深める。
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
第二に、「なぜだろう?」という疑問を原動力にして、思考を展開する。
第三に、シミュレーションをしたり、予測をしたりすることで思考を展開する。
具体化力とは、エピソード力、提案力
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
常に、具体的なものを提案するということを、自分のミッションとして生活していると、思考力が深まっていく
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
「本質的には・・・・」「具体的には・・・・」という言葉をセットで口癖にする
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
「実はこう」「さらにこう」「そのまた奥がこう」とテンポよく短時間にまとめて話すことがポイント
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』
4. 感想とレビュー
齋藤孝先生の『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』は、まさに「目から鱗が落ちる」ような、非常に学びの多い一冊でした。日頃から社内外でのコミュニケーション、特に部下や他部署との連携において「いかに本質を伝え、相手を動かすか」という課題に直面している私にとって、この本は具体的なヒントと深い示唆を与えてくれました。
まず、「話の『深さ』は、人間の『深さ』である」という冒頭のメッセージに強く共感しました。これまで「話し方」というと、どうしても「伝え方」や「表現方法」といった表面的なテクニックに意識が向きがちでした。しかし、この本は、話の質がその人の思考力や知識、そして人生観といった内面的な「深さ」に根ざしていることを明確に指摘しており、私自身の学びの姿勢や思考プロセスを見直すきっかけとなりました。
特に印象的だったのは、「深い話をするために必要な3つの能力」として挙げられている「展開力」「本質把握力」「具体化力」です。これらは、日々のビジネスシーンで求められる能力そのものだと感じました。
- 展開力:会議で意見を述べたり、プレゼンテーションをしたりする際、単に事実を並べるだけでなく、多角的な視点から話を広げ、聞き手の興味を引きつけることの重要性を再認識しました。私の部署でも、新商品のコンセプトを説明する際に、市場データだけでなく、顧客の潜在的なニーズやライフスタイルにまで話を広げることで、より深い共感を得られると確信しました。
- 本質把握力:これは、マーケターにとって最も重要な能力の一つだと常々感じています。表面的な売上減少の原因ではなく、その背後にある顧客行動の変化や競合の動向といった「本質」を見抜く力。齋藤先生は、「本質は斬新なものより一見、平凡なものにある」と述べており、日々の業務の中で見過ごしがちな細部にこそ、重要なインサイトが隠されていることを示唆してくれました。
- 具体化力:抽象的な概念や理論だけでは、なかなか人の心を動かすことはできません。本書が強調するように、具体的なエピソードや事例を交えることで、話は格段に「深く」なり、聞き手の心に響きます。私自身も、部下へのフィードバックや指導の際に、抽象的な指示だけでなく、具体的な行動例や成功体験を共有することで、より理解を深めてもらえると感じました。
また、第4章で紹介される「あの人は深い」と言われる話し方の技術は、非常に実践的です。「スリーステップ論法」や「逆質問に深さが出る」といったテクニックは、すぐにでも試したくなるものばかり。特に「逆質問」は、相手の思考を促し、対話の深みを増す上で非常に有効だと感じました。
この本は、単に「話し方が上手になりたい」という人だけでなく、「もっと本質的な話ができるようになりたい」「思考力を深めたい」「人間として成長したい」と願う全ての人に読んでほしい一冊です。特に、私のようにビジネスの現場で「伝える」ことの重要性を日々感じている方にとっては、コミュニケーションの質を根本から見直すための、かけがえのない羅針盤となるでしょう。
5. まとめ
今回は、齋藤孝先生の著書『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』について、著者の紹介、本書の要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書は、単なる話し方の技術論にとどまらず、話の「深さ」がその人の「人間としての深さ」に直結するという、コミュニケーションの本質を深く掘り下げた一冊です。
この本の重要なポイントを改めてまとめると、以下のようになります。
- 「浅い話」と「深い話」の明確な違い:具体性の欠如、本質を見抜けない思考、普遍的視点の欠如などが「浅さ」を生み出す。
- 「深い話」をするための3つの能力:展開力、本質把握力、具体化力という、知性を鍛えるための核となる要素。
- 「本質」の捉え方:一見平凡なものの中にこそ本質があり、細部に着目することで深さが生まれる。
- 「エピソード」の重要性:具体的な経験や事例を交えることで、話は格段に深みを増し、聞き手の心に響く。
- 実践的な話し方の技術:「スリーステップ論法」や「逆質問」など、すぐに試せる具体的なテクニック。
『いつも「話が浅い」人、なぜか「話が深い」人』は、「いつも話が浅い人」とレッテルを貼られたくない人、そして、「なぜか話が深い」と一目置かれる存在になりたいと願うすべての人にとって、必読の書です。この本を読むことで、あなたの話し方はもちろんのこと、物事を深く考える力、そして何より人間としての「深み」が培われることでしょう。
ぜひ、この本を手に取り、あなたのコミュニケーションと人生をより豊かなものに変えるきっかけにしてみてください。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。