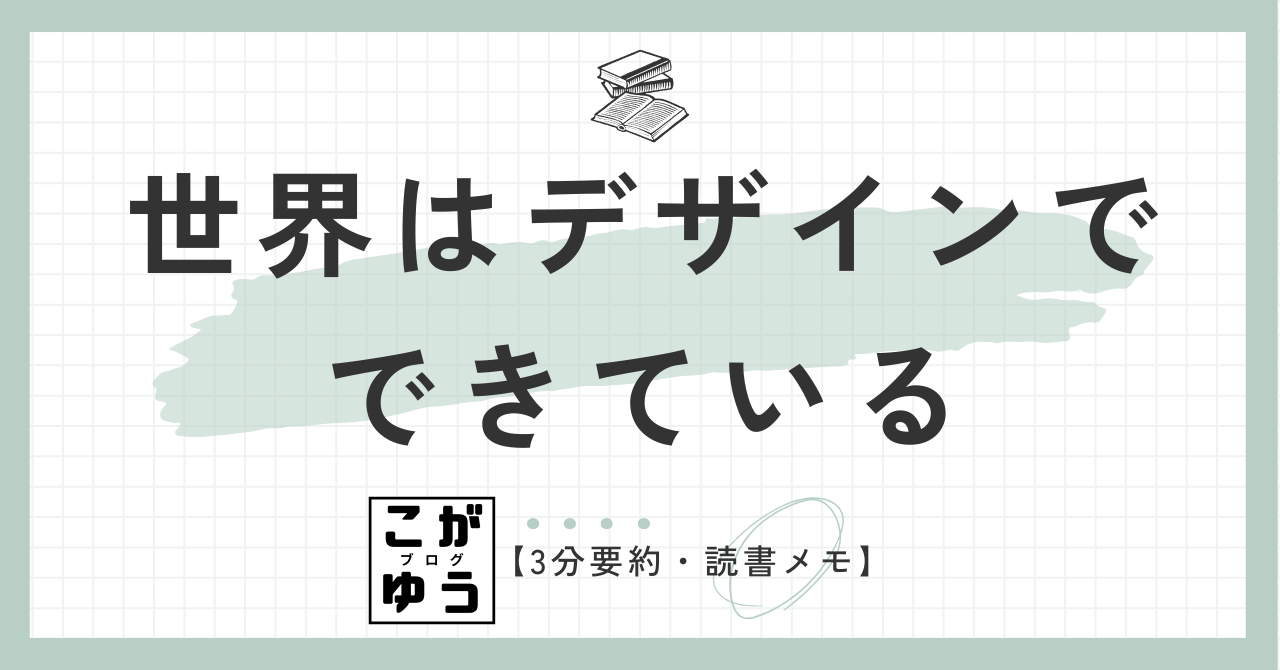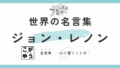ご覧頂き誠にありがとうございます。
今回は『世界はデザインでできている』についてレビューと要約の記事となります。
『世界はデザインでできている』徹底解説:身の回りのデザインから世界の仕組みまで読み解く
1. 著者の紹介
秋山具義(あきやま ぐぎ)氏は、1966年東京都千代田区(秋葉原出身とすることが多い)生まれのアートディレクターです。日本大学藝術学部卒業後、広告代理店を経て1999年に独立し、デイリーフレッシュ株式会社を設立。広告、パッケージ、装丁、CDジャケット、キャラクターデザインなど、ジャンルを限定せず多岐にわたるクリエイティブ活動を展開しています。特に、広告キャンペーン、商品のパッケージデザイン、ロゴ制作などで広く知られており、その作品は常に時代の先端を走り、多くの人々の記憶に残るものとなっています。
秋山具義氏の代表的な作品や活動実績:
- 東洋水産「マルちゃん正麺」の広告・パッケージデザイン: 大ヒット商品となった「マルちゃん正麺」の印象的なパッケージデザインは、秋山氏の代表作の一つです。
- トヨタ自動車「もっとよくしよう。」キャンペーン: トヨタの企業広告キャンペーンのアートディレクションを担当し、企業イメージの向上に貢献しました。
- AKB48「さよならクロール」CDジャケットデザイン: 人気アイドルグループAKB48のCDジャケットデザインを手がけ、話題を集めました。
- NHK BSプレミアム「ワラッチャオ!」キャラクターデザイン: 子供向け番組のキャラクターデザインを担当し、子供たちに親しまれるキャラクターを生み出しました。
- パルコ「PARCO CARD」キャンペーン: パルコのクレジットカードキャンペーンのアートディレクションを担当し、若者を中心に支持を集めました。
- SHARP「エコロジークラスでいきましょう。」: SHARPの環境キャンペーンのアートディレクションを担当。
- エンジャパン「転職は慎重に。」: エンジャパンの転職サイト広告のアートディレクションを担当。
- キリン「麒麟ZERO」: キリンビールのノンアルコールビール広告のアートディレクションを担当。
これらの実績からもわかるように、秋山氏は広告業界のみならず、様々な分野でその才能を発揮し、日本のデザイン界に大きな影響を与えている人物です。
2. 本書の概要
『世界はデザインでできている』は、私たちの身の回りにあるあらゆるものがデザインによって形作られているという視点から、デザインとは何か、どのように機能しているのかを解説する一冊です。商品パッケージやポスター、広告、CMなど、日常的に目にするデザインを通して、その意図や効果、そして未来のデザインのあり方までを考察しています。著者が実際に手がけた事例も豊富に紹介されており、デザインの裏側を垣間見ることができるのも魅力です。デザインに関わる人はもちろん、そうでない人にとっても、世界の見方を変えるきっかけとなるでしょう。
3. 本書の要約
本書は、デザインと人との距離感、スマートフォンがもたらしたデザインの変化、デザインの作戦、AIとデザインの未来など、多角的な視点からデザインを考察しています。以下、主要なポイントを要約します。
- デザインの距離: 私たちの周りには、商品パッケージ、ポスター、広告、CMなど、様々なデザインが溢れています。これらのデザインには、「商品を買ってほしい」「メッセージを読み取ってほしい」など、様々な目的があり、必ず「デザインの意図」が存在します。広告は、見る人との距離によってデザインが変えられています。遠くから目にするビルボードは大きい文字やロゴを使ったシンプルなデザインに、歩きながら見ることの多い駅貼りポスターは写真などビジュアルに訴えるデザインになっています。逆に、電車の中吊り広告は乗車中にある程度時間をかけて読むものなので、文字数が多くても問題ありません。このように、デザインは受け手との距離感によって最適な表現方法を選択しているのです。
- スマートフォンがもたらしたもの: スマートフォンの登場は、デザインに大きな影響を与えました。特に、消費行動に直結するスマートフォン広告のデザインは、他の広告とは戦略が異なります。「その場で買う」という行動を促すことができるため、広告とユーザーの距離感や見え方が大きく変わり、「つい買ってしまう」ことが起きやすくなりました。そのため、スマホの広告デザインには「タップされやすいデザイン」が意識されています。また、インスタグラムの普及による写真の正方形化や、アプリのアイコンデザインなど、スマホが持ち込んだ文化は確実にデザインの世界に変化を与えています。
- デザインの作戦: デザインに「正解」はありませんが、「正解をつくる」ための様々な方法があります。例えば、デザインを説明しやすいポイントやストーリーをデザインの中に入れ込み、説得力を高めたり、既存のデザインをうまく利用してデザインに信頼感をもたせたりといったことです。著者は、立命館大学のコミュニケーションマーク(ロゴ)を作成する際、古来から使われている美観を与える比率である「黄金比」を用いたことで、提案の際に顧客から納得感を得やすくなったという事例を紹介しています。デザインを決定する会議の場には最終決裁者がいないケースも多いため、後から担当者が最終決裁者に伝える際、説明しやすいストーリーをデザインの中に入れ込んでおくことも大切です。
- AIとデザインの未来: AIは過去の作品の組み合わせで「それらしい」デザインは作れるかもしれませんが、真に新しいものを生み出すことはできません。これからのデザインには、デザイナー自身の「自分らしさ」や「個性」がこれまで以上に重要になります。AIに代替されない、人間ならではの感性や創造性が求められる時代になるでしょう。
- デザインと人との距離感: 広告は、見る人との距離によってデザインが変えられています。
- 伝えやすいデザインで納得感を与える: デザインの中に「誰かに伝えたくなる」要素を入れることは重要です。「伝えやすい形」でつくると、説明しやすくなり、納得感のあるデザインになります。
- 他者のレビューにあったポイント: デザインには正解がなく、デザイナーの数だけデザインがあるという点も重要な視点です。
4. ココだけは押さえたい一文
「人間がつくったものには、すべてデザインがある。つまり、世界はデザインでできているのだと言える。」
『世界はデザインでできている』
この一文は、本書の根幹をなす考え方を示しています。私たちが普段意識することなく目にしているもの、手に取っているもの、使っているもの、そのすべてにデザインが存在し、私たちの生活や行動に影響を与えているのです。
5. 感想とレビュー
『世界はデザインでできている』は、デザインの専門家だけでなく、一般の人々にとっても非常に興味深く、学びの多い一冊です。著者の秋山具義氏が、自身の経験や具体的な事例を交えながら、デザインの奥深さと魅力を分かりやすく解説しているため、デザインの知識がない人でも無理なく読み進めることができます。
良かった点:
- 分かりやすい解説: 専門用語を多用することなく、平易な言葉で解説されているため、デザインの知識がない人でも理解しやすいです。
- 豊富な事例: 著者が実際に手がけた事例が豊富に紹介されており、具体的なイメージを持ちながら読み進めることができます。特に、誰もが知る商品のデザインの裏側を知れるのは非常に興味深いです。
- 多角的な視点: デザインと人との距離感、スマートフォンがもたらした変化、AIとデザインの未来など、多角的な視点からデザインを考察しているため、多角的にデザインを捉えることができます。
- デザインの本質に迫る考察: 単なるテクニック論ではなく、デザインの本質や役割について深く考察している点が素晴らしいです。
- デザインへの興味を喚起する内容: 日常生活で目にするデザインを通して、デザインへの興味を喚起する内容となっており、読者は周りのデザインに意識を向けるようになるでしょう。
- 秋山氏の視点: 著名なアートディレクターである秋山氏の視点からデザインを語っているため、非常に貴重な情報が得られます。
- デザインの意図を理解することの重要性: デザインには必ず意図があり、その意図を理解することで、デザインをより深く理解できるということを教えてくれます。
6. まとめ
『世界はデザインでできている』は、デザインとは何か、どのように機能しているのか、そして私たちの生活にどのような影響を与えているのかを、分かりやすく解説した良書です。デザインに関わる人はもちろん、そうでない人にとっても、世界の見方を変えるきっかけとなるでしょう。この本を読むことで、あなたは街で見かける看板、手に取る商品のパッケージ、日常的に使うアプリのインターフェースなど、あらゆるデザインに隠された意図や工夫に気づき、これまでとは違った視点で世界を見ることができるようになるはずです。
特に以下のような方におすすめです。
- デザインに関わる仕事をしている人(デザイナー、アートディレクター、マーケターなど)
- デザインに興味がある人
- 広告やCM、商品パッケージなどに興味がある人
- クリエイティブな仕事に就きたいと思っている人
- 普段何気なく見ているものに隠された意図を知りたい人
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。