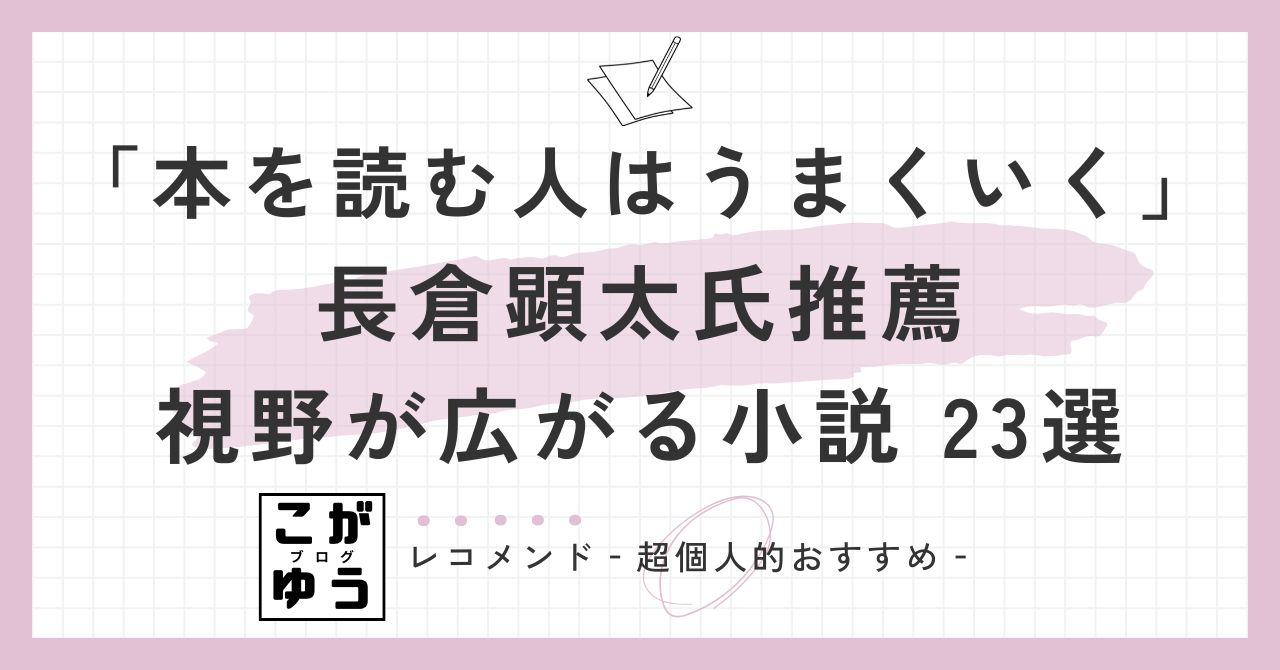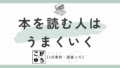「時間を無駄にせず、確実に良書と出会いたい」
長倉 顕太さんの「本を読む人はうまくいく」に掲載されていた「人生が好転し、視野が広がる「おすすめ本101冊」リスト」から小説ジャンルの23冊を紹介します。
長倉 顕太氏は、「読みやすい」という点を重視して選定しています。
まずは読みやすい本を読んで本を好きになってもらい、読書を習慣化してもらいたいという思いが詰まったリストです。
読んだらどんどんアウトプットしていくと人生が好転し視野が広がります。
「本を読む人はうまくいく」に関して詳しく知りたい方は、こちら↓

1. 『一九八四年』
(ジョージ・オーウェル、高橋和久訳/早川書房)
全体主義国家による監視と、思想統制に抗おうとする男の物語です。
自由と真実が持つ、根源的な意味を問いかけるディストピア小説です。
読みやすい作品から入って、現代社会のあり方を考えるきっかけにしてください。
2. 『レディ・ジョーカー』
(高村薫/新潮社)
企業を標的とした計画的な恐喝事件を背景に、物語が進みます。
日本社会の深い闇と、巨大組織の腐敗をリアルに描いた社会派サスペンスです。
事件の裏側から、人間関係と権力の構造を読み解きましょう。
3. 『舟を編む』
(三浦しをん/光文社)
新しい辞書づくりに情熱を注ぐ、編集者たちの姿が描かれた感動作です。
言葉と人間の深いつながりを丁寧に描き出しています。
読み終わった後には、普段使う言葉の重みを再認識できます。
4. 『汝、星のごとく』
(凪良ゆう/講談社)
複雑な家庭環境に生きる少年少女の成長と、運命に翻弄される恋を描いた小説です。
ヤングケアラーなどの現代的な問題にも触れています。
彼らの切実な生き方から、共感力を深めてみてください。
5. 『そして、バトンは渡された』
(瀬尾まいこ/文藝春秋)
親が何度も変わる中で、愛情を受けながら育った少女の心温まる成長ストーリーです。
3人の父と2人の母に育てられた少女と、その周りの人々の物語です。
家族の形を考えさせられる、優しさに満ちた一冊です。
6. 『人質の朗読会』
(小川洋子/中央公論新社)
人質となった男女が、最後に自らの人生を語り合う短編集です。
美しくも哀しい言葉で綴られた、人間の生と死が描かれています。
命の尊厳について、深く思索する時間を持てます。
7. 『夜のピクニック』
(恩田陸/新潮社)
高校最後のイベント「歩行祭」で、夜通し約80キロを歩く高校生が主人公です。
交わることのない人間との会話や出会いから、内面の成長が描かれています。
青春の切なさと一歩踏み出す勇気をもらえるでしょう。
8. 『スロウハイツの神様』
(辻村深月/講談社)
クリエイターたちが集まるシェアハウスを舞台にした群像劇です。
夢と挫折、そして希望が交錯する、若者たちの姿が描かれています。
才能とは何か、創造とは何かを問いかける作品です。
9. 『クライマーズ・ハイ』
(横山秀夫/文藝春秋)
日航機墜落事故を取材する新聞記者たちの葛藤と使命感を描いた人間ドラマです。
極限状況下での組織の論理と個人の正義がぶつかります。
プロフェッショナルとしての仕事の重みを感じられるでしょう。
10. 『羊と鋼の森』
(宮下奈都/文藝春秋)
ピアノ調律師を目指す青年が、音と静けさに包まれながら成長していく物語です。
仕事への真摯な姿勢と、感覚を磨くことの尊さが描かれています。
五感の繊細さに気づきを与えてくれる、美しい作品です。
11. 『死神の精度』
(伊坂幸太郎/文藝春秋)
死神が対象者を指定し、生死を決定するという奇妙なルールを描いた連作短編です。
シニカルでありながら、人間の温かさを感じさせる物語です。
軽妙な語り口で、人生の深さに触れることができます。
12. 『十角館の殺人』
(綾辻行人/講談社)
孤島の館で次々と起こる連続殺人を描くミステリです。
叙述トリックが鮮やかな、日本ミステリ史に残る名作として知られています。
思考をフル回転させ、物語の仕掛けをぜひ楽しんでください。
13. 『52ヘルツのクジラたち』
(町田そのこ/中央公論新社)
誰にも届かない孤独な叫びを抱えた人々の出会いと再生を描く、心揺さぶる小説です。
心の傷と他者とのつながりが、生きる希望へと変わります。
共感の力が、いかに人を救うかを教えてくれます。
14. 『沈まぬ太陽』
(山崎豊子/新潮社)
巨大組織と闘う男の苦悩と正義が描かれた長編大作です。
アフリカ編、中近東編、会長編の三部作からなる骨太な作品です。
組織の腐敗と、正義を貫くことの難しさを教えてくれます。
15. 『天国への階段』
(白川道/幻冬舎)
男たちの希望と絶望を描いた長編小説です。
挫折と再起を繰り返しながらも、人生を諦めない人間たちの熱い生き様が力強く綴られています。
熱量をもって、生きることの力を感じてください。
16. 『麻雀放浪記』
(阿佐田哲也/文藝春秋)
戦後の混乱期、麻雀だけを頼りに生きる青年坊や哲の放浪と成長を描きます。
勝負に生き、数えにも美学を見出す、孤高の青春小説です。
時代背景から、生きることのリアリティを読み取れます。
17. 『町でいちばんの美女』
(チャールズ・ブコウスキー、青野駅/新潮社)
酒と暴力、孤独にまみれた人生を生きた男たちの物語です。
澱んだ日常の中に、湿り気とユーモアを独特の乾いた筆致で描いた短編集です。
アウトローの生き様から、人間の本質が見えてきます。
18. 『いねむり先生』
(伊集院静/集英社)
アルコール依存と孤独を抱えた作家が、無口な師との交流を通じて再生していく自伝的小説です。
苦悩と、そこからの立ち直りが感動的に描かれています。
人間的な温かさに触れることができるでしょう。
19. 『金閣寺』
(三島由紀夫/新潮社)
美への異常な執着にとらわれた青年が、金閣を焼き払うまでの内面の葛藤を描く心理小説です。
「美」と「破壊」というテーマが、深く掘り下げられています。
感情の機微を追体験し、人間の深層を探ってください。
20. 『人間失格』
(太宰治/KADOKAWA)
自己喪失と孤独に苦しみながら墜ちていく男の半生を、絶望とユーモアを交えて描いた代表作です。
人間の弱さや不安が赤裸々に綴られています。
自己と向き合うための、内省的な一冊です。
21. 『こころ』
(夏目漱石/KADOKAWA)
近代化の波に揺れる明治期を背景に、「先生」と「私」の交流と、秘められた罪と孤独を描いた金字塔です。
友情、裏切り、そして孤独という普遍的なテーマが扱われています。
日本文学の根幹を理解するための必読書です。
22. 『わたしを離さないで』
(カズオ・イシグロ、土屋政雄訳/早川書房)
生まれながらにして運命づけられた子どもたちの、切ない成長と愛を描く静かな衝撃作です。
命の尊厳と、人間の愛の形を問いかける作品です。
深い感動と倫理的な問いを心に残すでしょう。
23. 『モモ』
(ミヒャエル・エンデ、大島かおり/岩波書店)
時間に追われる現代社会で、本当に大切なものを守ろうとする少女モモの物語です。
時間とは何か、豊かさとは何かという哲学的な問いを投げかけます。
子供から大人まで楽しめる、ファンタジーの傑作です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。