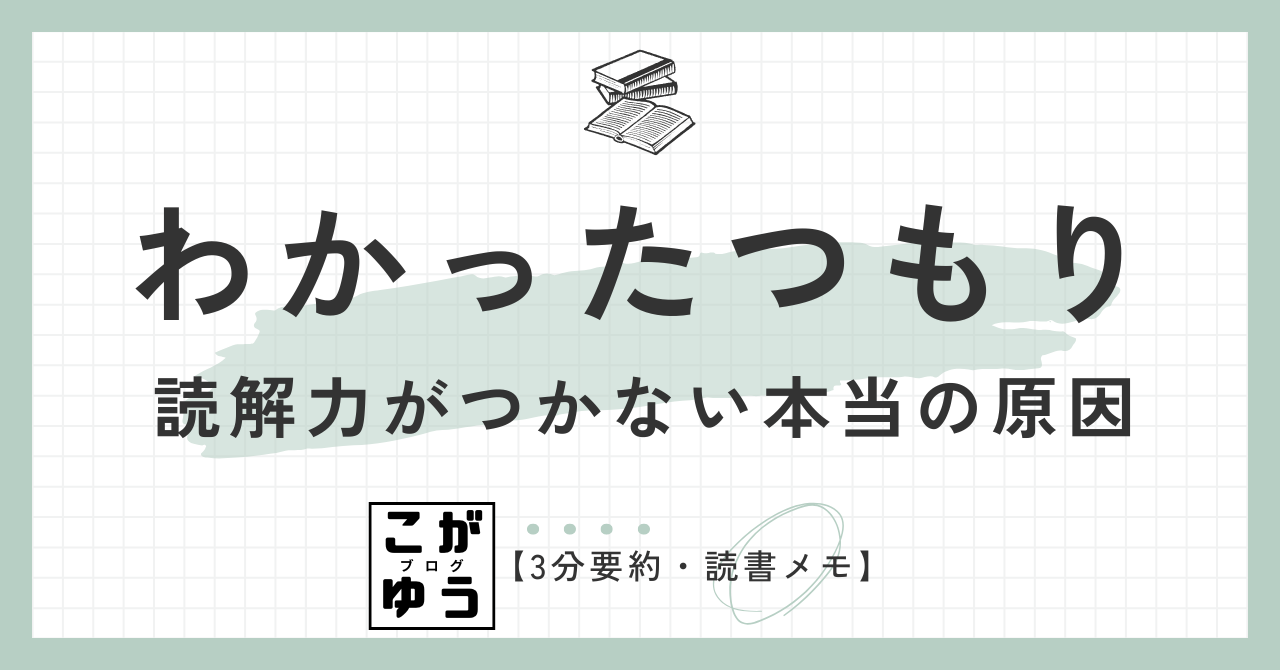ご覧頂き誠にありがとうございます。
このブログでは、ビジネスの現場で役立つ知識や、効果的な働き方、そして自身の能力を高めるためのヒント、さらにはコミュニケーションや思考法といったライフスタイルに関わるテーマまで幅広く発信しています。
皆さんは、本や記事を読んだり、誰かの話を聞いたりした時に、「うん、わかったぞ!」と思ったのに、後から振り返ってみると、実はちゃんと理解できていなかった… という経験はありませんか? あるいは、相手が「分かった」と言っているのに、話がどうも噛み合わない、という経験は?
その、分かっているようで、実は分かっていなかった…という状態。まさに「わかったつもり」です。
この「わかったつもり」こそが、読解力がつかない、さらにはコミュニケーションのズレや意思決定のミスにつながる、非常に厄介な問題なのだと言います。そして、「分からない」より、たちが悪い場合があるのです。
今回ご紹介する一冊は、この「わかったつもり」という、多くの人が陥りがちな落とし穴の正体を徹底的に解き明かし、そこから抜け出すための本当の原因と具体的な方法を教えてくれる本です。
それが、『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 西林 克彦 (著) です!
著者の西林克彦氏は、私たちが物事をどう理解し、どう考えているのか、その思考のメカニズムを深く探求されている方です。本書は、彼の専門的な知見に基づき、「わかったつもり」がなぜ生まれるのか、そしてどうすれば真に「深くわかる」ことができるのかを、分かりやすく解説してくれます。
この「わかったつもり」の問題は、単に本を読むときだけでなく、日々の仕事での情報収集、上司や部下とのコミュニケーション、企画や戦略の立案、そしてプライベートでの学びや人間関係まで、あらゆる場面に影響します。
この記事では、私が『わかったつもり』を読んで、これはビジネスパーソンにとって読解力だけでなく、思考力やコミュニケーション能力を高める上で、あまりにも重要だ!と感じたポイントを、以下の構成で、コンパクトにまとめてお伝えします。
なぜ私たちは「わかったつもり」になってしまうのか? その本当の原因を知り、「深くわかる」ための思考法とは? ぜひ、最後までお付き合いください!
『わかったつもり』西林克彦著を解説!読解力がつかない本当の原因は「思考停止」にあった【要約/レビュー】
1. 著者の紹介
1944年、台湾高雄市生まれ。東京工業大学理工学部卒業。東京大学大学院教育学研究科博士課程中退。現在、宮城教育大学教育学部教授。「知識のありよう」をベースに、学習や学習指導をより細かく考えることを実践している。著書に、『間違いだらけの学習論』『「わかる」のしくみ』『親子でみつける「わかる」のしくみ(共編)』(以上、新曜社)、『わかったつもり』(光文社新書)などがある。
2. 本書の概要
次に、本書『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 が全体としてどのような内容を扱っているのか、その概要を説明します。
本書の中心的なテーマは、多くの人が陥りがちな「わかったつもり」という状態の危険性を指摘し、その「本当の原因」を明らかにした上で、真に「深くわかる」ための思考法と具体的なアプローチを提示することです。
著者の西林克彦氏は、「分からない」状態はもちろん問題だが、それ以上に「わかったつもり」の状態は、それ以上の思考や学びを止めてしまうため、より重大な問題であると警鐘を鳴らします。
本書は、主に文章を読むときの「わかったつもり」に焦点を当てていますが、その原理は日常会話、他者の話の理解、問題分析、意思決定など、情報を理解し、それに基づいて判断するあらゆる場面に応用できる普遍的なものです。
本書では、私たちが文章を理解する過程を、「わからない」→「わかる」→「よりわかる」という段階で捉え、「わかったつもり」がこの「わかる」の段階で立ち止まってしまい、「よりわかる」に進めなくなる状態であることを明確にします。そして、「わかったつもり」には、理解が不十分な場合と、間違った理解をしてしまっている場合があることを指摘します。
なぜ私たちは「わかった」と感じた瞬間に思考を止めてしまうのか? 私たちの脳の効率化の癖、無意識に使う知識や前提(スキーマ)、文章全体の「雰囲気」に流されてしまうこと、あるいは結果や冒頭だけで判断してしまうといった思考の落とし穴や認知バイアスが、「わかったつもり」を生む原因として深く掘り下げられます。
本書の目的は、単に速く読めるようになることや、表面的な情報を把握することではなく、物事の本質や背景、論理の繋がりを真に「深く理解する」ための思考力や視点を身につけることにあります。
そのために、「わかったつもり」から脱却するための具体的な方法として、常に「もっとわかりたい」という探求心を持つこと、人間が持つ「認知バイアス」について知ること、そして多様な「異なる視点」を活用することといったヒントが提示されます。
読解力だけでなく、思考力やコミュニケーション力を高めたい方、そして自分が「分かったつもり」になっていないか、自身の理解の精度を見直したいすべての人にとって、本書は目から鱗が落ちるような、非常に刺激的で実践的な一冊となるでしょう。
3. 本書の要約
それでは、本書『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 の核となる部分を、その要約としてさらに詳しく見ていきましょう。
本書の核心は、多くの人が陥る「わかったつもり」という状態の危険性を指摘し、その原因と克服法を示すことです。著者は、「わかったつもり」は、単に「分からない」よりもたちが悪い場合があると言います。なぜなら、「分からない」自覚があれば調べたり質問したりしますが、「わかったつもり」になると、それ以上の思考や確認が止まってしまい、誤った理解や判断に基づいて行動してしまうからです。
本書は、私たちが何かを理解するプロセスを、「わからない」→「わかる」→「よりわかる」の段階で説明します。「わからない」は意味が掴めない状態。「わかる」は単語の意味や文の繋がりがある程度理解できた状態。そして、「よりわかる」は、その背景や論理、他の要素との関連性まで深く理解できた状態です。「わかったつもり」は、この「わかる」の段階で思考が止まり、「よりわかる」に進めなくなる状態であり、理解が不十分か間違っているかのどちらかだと指摘します。
では、なぜ私たちは「わかったつもり」になってしまうのでしょうか?本書は、その原因を多角的に分析します。
- 「わかる」ことによる思考停止: 人は「わかった」と感じると安心し、それ以上考えようとしなくなる傾向があります。「もっとわかりたい」という探求心が失われてしまうのです。
- 文脈の罠: 文章の文脈は理解に不可欠ですが、文脈だけで判断すると、筆者の真意と異なる解釈をしてしまうことがあります。特に、限られた情報から都合の良い文脈を補完してしまうと危険です。
- 無意識の「補完」と「捏造された理解」: 私たちは、文章に書かれていない部分を、これまでの経験や知識(スキーマ)を使って無意識に補って読みます。この「補完」が誤っている場合、「捏造された理解」となり、間違った「わかったつもり」になります。知識が豊富な人ほど、この罠に陥りやすい場合があります。
- 思考の近道(認知バイアス、雰囲気、ステレオタイプ): 脳は効率を求めるため、「認知バイアス」といった思考の癖に頼りがちです。文章全体の「雰囲気」で内容を判断したり、冒頭や結論だけで全てを理解したと思ったり、特定のタイプに当てはめて考えたり(ステレオタイプ)すると、詳細や異なる可能性を見落とし、「わかったつもり」になります。「いろいろあるんだなあ」と済ませてしまうのも思考停止の一種です。
本書は、これらの「わかったつもり」から脱却し、真に「深くわかる」ための具体的なステップを提示します。
- 常に「もっとわかりたい」という探求心を持つ: 「わかった!」と感じた時ほど立ち止まり、「本当にそうか?」「矛盾はないか?」と疑う意識を持つこと。
- 「人間にはどんな認知バイアスがあるのか」を知る: 認知バイアスの存在を知ることで、自分の思考の癖に気づき、客観的に物事を捉える助けになります。(例:確証バイアス、利用可能性ヒューリスティックなど)
- 「異なる視点」を利用する: 自分一人の視点には限界があります。フレームワーク(例:3C, 4P)を使ったり、他者の意見を聞くこと(組織における多様性の重要性にもつながる)で、多角的に物事を理解できます。
本書の要約をまとめると、『わかったつもり』は、私たちが日常的に経験する「わかったつもり」という状態が、いかに危険で、思考停止や誤解を招くかを、人間の認知の仕組みや思考の癖から深く掘り下げて解き明かします。
そして、「より深くわかる」ための、常に探求心を持つこと、自身の認知の偏りを知ること、多様な視点を取り入れることといった、読解力だけでなく、思考力やコミュニケーション力をも高めるための具体的な方法論を提供してくれる一冊です。単なる表面的なテクニックではなく、「理解すること」の本質に迫る内容です。
4. ココだけは押さえたい一文
本書『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 の中で、著者がこの本の執筆動機とも言える、「わかったつもり」という問題の重大性を最も端的に示していると感じた一文があります。それは、本書の冒頭部分で提示される、この言葉です。
「『わからない』より『わかったつもり』をどう克服するか」
『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』
この一文は、私たちがこれまで漫然と捉えてきた「わかったつもり」という状態が、実は「分からない」という状態よりも、はるかに厄介で、対処が難しい問題である可能性を示唆しています。
「分からない」という自覚があれば、「これは分からないな」と立ち止まり、質問したり、調べたり、詳しい人に聞いたりといった「分からないを解消するための行動」を起こすことができます。しかし、「わかったつもり」になっていると、「自分は理解できた」と錯覚しているため、そこで思考や確認が止まってしまいます。その結果、間違った情報に基づいて行動してしまったり、真に重要なことを見落としてしまったりするリスクが高まるのです。
この一文は、私たち読者に対し、「あなたは大丈夫か?もしかしたら、一番危険な『わかったつもり』になっているのではないか?」と問いかけ、「わかったつもり」という問題の存在とその深刻さに気づかせてくれます。そして、この重大な問題をどうすれば克服できるのか、その答えが本書にあるのだと示唆することで、読者の知的好奇心と危機感を同時に刺激します。
本書を読む際には、ぜひこの言葉を心に留めて、「自分が今『わかったつもり』になっているのではないか?」「この『わかったつもり』という重大な問題に、どう向き合えばいいのだろうか?」という視点を持って読み進めてみてください。
5. 感想とレビュー
本書『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 は、まさに「わかったつもり」になっている自分自身の姿を、痛いほどリアルに突きつけられる、非常に刺激的で、そして根本的な思考の癖を見直すきっかけをくれた一冊でした。
特に、「『わかる』ことによる思考停止」という指摘は、私の経験からも「ああ、確かに!」と膝を打ちました。ある程度情報が集まり、「これで全体像は掴めた」と感じた瞬間に、それ以上の深掘りを止めたり、異なる可能性を検討するのをやめてしまったりすることが、自分にもあったなと反省させられます。「もっとわかりたい」という探求心を持ち続けることの重要性を改めて痛感しました。
「無意識の『補完』と『捏造された理解』」、そして「認知バイアス」に関する解説も、非常に興味深かったです。自分がこれまで蓄積してきた知識や経験(スキーマ)が、新しい情報を理解する際に、良い方向に働くこともあれば、逆に「こうだろう」という先入観を生み出し、誤った解釈(捏造された理解)に繋がる危険性がある。特に、ある分野に専門性がある人ほど、この罠に陥りやすいという指摘は、私自身も含め、多くのベテランビジネスパーソンにとって耳が痛い話かもしれません。自分の「わかったつもり」が、実は長年の経験からくる偏見や思い込みに基づいていた…なんてこともあるのだろうと、身が引き締まる思いです。
本書で提示される、「わかったつもり」から脱却するための具体的なステップ、特に「常に『もっとわかりたい』と意識すること」「異なる視点を利用すること」は、非常に実践的です。仕事で企画を練る際にも、自分の視点だけでなく、お客様、競合、現場といった様々な視点から多角的に考えることの重要性は常々感じていますが、本書はそれがなぜ「わかったつもり」を防ぐために重要なのか、その思考のメカニズムから説明してくれます。フレームワークを活用したり、意識的に多様な意見に耳を傾けたりすることの重要性を再認識しました。
総じて、『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 は、単なる読解力の向上というレベルを超え、人間の思考の癖、情報との向き合い方、そして真に理解するための姿勢といった、ビジネスパーソンにとって、そして人生において不可欠な「知性」を高めるための、根本的な「思考の教科書」と言えるでしょう。読むことで、自分が普段いかに「わかったつもり」で済ませてしまっているか、ということに気づき、日々の情報との向き合い方が変わるはずです。
6. まとめ
今回は、西林 克彦氏の著書『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 について、著者の紹介、本書の概要、要約、ココだけは押さえたい一文、そして感想・レビューをお伝えしました。
本書の核となるメッセージは、多くの人が無意識に陥る「わかったつもり」という状態が、それ以上の思考や学びを止めてしまうため、「分からない」よりも重大な問題であるということです。著者は、「わかったつもり」が生まれる原因を、「わかる」ことによる思考停止、文脈やスキーマの罠、認知バイアスといった、人間の認知の仕組みから深く分析します。
本書では、「わからない」→「わかる」→「よりわかる」という理解の段階を示し、「わかったつもり」は「わかる」で止まる状態であると定義。雰囲気に流される、結果や冒頭だけで判断する、ステレオタイプで考えるといった具体的な「わかったつもり」のパターンも解説します。
そして、「わかったつもり」から脱却し、真に「深くわかる」ための方法として、「常に『もっとわかりたい』と探求心を持つこと」「認知バイアスについて知ること」「フレームワーク活用や他者の意見を聞くなど『異なる視点』を持つこと」といった実践的なステップが提示されます。
私の個人的なレビューとしても、本書は、ビジネスにおける情報の正確な理解や、人間関係におけるコミュニケーションのズレといった、日々の課題に直結する「わかったつもり」の問題を、根本原因から理解する助けとなりました。思考停止のメカニズムや認知バイアスの話は特に興味深く、自身の思考の癖を見直すきっかけとなりました。「異なる視点」の重要性など、仕事にもすぐに活かせる学びが多かったです。
もしあなたが、
- 本や文章を読んでも、ちゃんと理解できているか不安だ
- 誰かの話を聞いても、後から「わかったつもり」だったと気づくことが多い
- コミュニケーションのズレが多いと感じる
- 自分の思考力を高め、より深く物事を理解したい
- 認知バイアスや思考の癖について知りたい
と考えているなら、ぜひ本書『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』 を手に取ってみてください。
本書は、あなたが普段いかに無意識に「わかったつもり」になっているかに気づかせ、真に「深くわかる」ための思考の武器を与えてくれる、知的な刺激に満ちた、そしてあなたの「理解する」という能力を根本から変える可能性を秘めた一冊となるでしょう。
この本が、皆さんの読解力、そして思考力を高め、より正確な理解に基づいた、より良い仕事やより豊かな人生を送るための一助となれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
背伸びしない等身大の経験とアイディアのコラムも書いています。
日々の仕事やライフスタイルのヒントになればうれしいです。
X(Twitter)、Threads、instagram、Blueskyもやっているので、もしよかったら覗いてください。